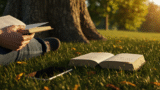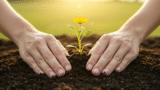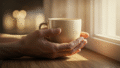「私、このままでいいのかな…」
大きな不満はないはずなのに、ふと心が渇いてしまう。
そんな日はありませんか?
「幸福論」なんて聞くと、少し難しそうに感じますよね。
でも、安心してください。
この記事では、人生の先輩たちの知恵を借りながら、あなたの日常に“小さな光”を見つけるための、具体的で優しい「5つの習慣」だけをお伝えします。
読み終える頃には、「幸せって、自分で作っていけるんだ」と、少しだけ前を向けるはず。
さあ、あなただけの「ご機見な自分」を取り戻す知識を、一緒に見つけにいきましょう。
はじめに なぜ、心は渇いてしまうのか?
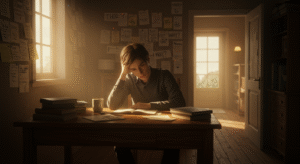
朝起きて、仕事へ向かい、やるべきことをきちんとこなす。
大きな不満があるわけじゃない。
それなりに平和な毎日。
でも、ふとした瞬間に、胸の中にぽっかりと穴が開いたような、そんな感覚になることはありませんか?
仕事帰りの電車の中、窓に映る自分の顔がなんだか疲れて見えたり。
ベッドに入って何気なく開いたSNSで、友人たちの充実した投稿に、ちくりと胸が痛んだり。
かく言う私も、かつては「いいね」の数に一喜一憂しては、眠れない夜を過ごした一人です。
「私、このままでいいのかな…」
そんな、言葉にならないモヤモヤとした気持ち。
この記事は、そんな風に日々を懸命に生きる、あなたのためのもの。
「いいね」の数では埋まらない。現代の私たちが抱える「見えない息苦しさ」
そのモヤモヤの正体、それは決して、あなたの心が弱いからではありません。
むしろ、今の時代を真面目に生きている証拠なのだと、私は思います。
私たちは今、知らず知らずのうちに、心をすり減らしやすい環境にいるのかもしれませんね。
-
常時接続による「比較の疲れ」
スマートフォンを開けば、いつでも他人の「一番輝いている瞬間」が見えてしまう。すると、自分の日常がなんだか色褪せたものに感じられて、落ち込んでしまうんですよね。比べるつもりがなくても、無意識に比べてしまうのが、本当にしんどいところです。 -
情報過多による「選択の疲れ」
世の中には「これが正しい」「こうすれば幸せになれる」という情報が溢れすぎていて。どれを選べばいいのか分からなくなって、結局何も選べず、ただただ疲れてしまう。そんな経験、ありませんか? -
未来への「漠然とした不安」
社会の変化はどんどん速くなる一方で、確かなものが何なのか見えにくい。そんな中で、「自分の心の置き場所」をどこにすればいいのか、分からなくなってしまうのも、無理はないのだと思います。
もし、あなたが今、こんな息苦しさを感じているのだとしたら。
それは、あなたが
「もっと自分らしく、豊かに生きたい!」
と、心の奥で強く願っているからに他なりません。
その息苦しさは、決して悪いものではないんです。
むしろ、あなたの人生をより良い方向へ導くための、大切なサインなのかもしれませんね。
【本質】「快楽」と「幸福」は別物。目指すは長続きする“心の安らぎ”
私たちはつい、幸せを何か特別なイベントで測ってしまいがちです。
欲しかった服を買った時の高揚感。SNSでたくさんの「いいね!」がついた時の嬉しさ。
もちろん、それらも素敵な心の動きです。
でも、不思議なくらい、その喜びって長続きしないな、と感じたことはありませんか?
ここで少し、言葉を整理させてください。
実は、この二つは似ているようで、心の満たされ方が少し違います。
| 種類 | 特徴 | 例えるなら… |
| 快楽 |
刺激的で、瞬間的に気分が高まる。 でも、すぐに消えて、もっと強い刺激が欲しくなる。 |
ジェットコースター |
| 幸福 |
穏やかで、じんわりと心が満たされる。 静かだけれど、長く続く温かさ。 |
あたたかい陽だまり |
少し専門的な話をすると、前者は興奮を司る「ドーパミン」、後者は心の安定に関わる「セロトニン」という脳内物質の働きに例えられます。
ドーパミン 「達成感や快楽、意欲に関わる脳内物質で、もっと欲しい!というモチベーションの源になります。ゲームでハイスコアを出したり、欲しいものを手に入れたりした時に多く分泌されます。」
セロトニン 「心の安定や幸福感、安らぎに関わる脳内物質で、心のバランスを保つ働きがあります。日光を浴びたり、リズム運動をすることで分泌が促されます。」
ジェットコースターのスリルも楽しいけれど、そればかりを追い求めていると、心はだんだん疲れてしまいます。
この記事で私がお伝えしたいのは、ジェットコースターの乗り方ではありません。
あなたの日常の中に、
「陽だまり」のような温かい場所を、あなた自身の手で育んでいくための具体的な方法です。
刹那的な楽しさではなく、じんわりと心を満たしてくれる、本質的な安らぎ。
それを一緒に見つけていきませんか。
【朗報!】幸福は「技術」。40%は「日々の実践」で変えられるという科学的事実
「でも結局、幸せかどうかは、もって生まれた性格や、お金みたいな環境で決まるんでしょ?」
そんな風に、心のどこかで諦めてしまっている部分も、あるかもしれません。
でも、これは朗報なのですが、近年の心理学の研究で、非常に希望の持てる事実が分かってきたんです。
ポジティブ心理学の権威であるソニア・リュボミアスキー教授らの研究によると、私たちの幸福を決める要因は、だいたいこんな割合なのだそうです。
(Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005)
-
遺伝(生まれ持った設定値):約50%
-
環境(収入、健康、地位など):約10%
-
私たちの意図的な行動:約40%
これ、すごいことだと思いませんか?
遺伝や環境も確かに関係はしますが、
私たちの幸福度の実に40%もの部分は、日々の「意図的な行動」…つまり、私たちの心がけや習慣によって変えることができる、
というのです。
これは、私たちの手の中に、人生を豊かにするための、広大な「余白」が残されていることを意味しています。
そう、幸福は、一部の人だけが持つ「才能」や「運」ではありません。
練習すれば誰でも少しずつ上手になる、「技術(スキル)」なんです。
ちょうど、自転車に乗る練習に似ているかもしれません。
最初は誰だって、ふらついたり、転んだりします。
でも、諦めずにペダルを漕ぐ練習を続けるうちに、いつの間にか自然と、気持ちの良い風を切って走れるようになる。
この記事では、
その40%の可能性を最大限に引き出すための、具体的な「ペダルの漕ぎ方」=「習慣」を、これから一つひとつ、丁寧にお伝えしていきますね。
【この章のポイント】
現代の「息苦しさ」の正体は、比較や情報過多による疲れであり、あなたのせいではない。
私たちが目指すのは、一時的な「快楽」ではなく、長く続く穏やかな「幸福(心の安らぎ)」。
幸福度の40%は日々の行動で変えられる。幸せは、練習すれば上達する「技術」である。
幸福論は難しくない!アランとラッセルに学ぶ、気持ちが楽になる考え方

「哲学」とか「幸福論」なんて聞くと、なんだかすごく難しくて、自分とは縁遠い世界の話のように感じてしまいますよね。
私だって、分厚い本に書いてある、昔の偉い人の難しいお説教、
みたいに思っていましたから。
でも、実際に彼らの言葉に触れてみると、驚くほどシンプルで、温かくて。
100年も前の言葉なのに、「そうそう、それが知りたかったんだよ」と膝を打ちたくなるような、現代の私たちの心に寄り添ってくれるヒントに満ち溢れているんです。
ここでは、そんな幸福論の中でも特に有名な二人の哲学者の考え方に、少しだけ触れてみたいと思います。
難しく考えなくて大丈夫です。
「人生を少しだけ上手に生きるための、考え方の道具箱」を覗いてみるような、そんな気軽な気持ちで読み進めてみてください。
アランの幸福論「ご機嫌」は自分の意志で選べる
雨が降ると、なんとなく気分が沈んだり。
誰かに褒められると、一日中気分が良かったり。
私たちはつい、「気分」というものは、天気や周りの出来事によって決まる、自分ではどうしようもないものだ、と思いがちです。
でも、著書『幸福論』で知られるフランスの哲学者アランは、それとは全く逆のことを言いました。
幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ。
…ほう?
なるほど?
私たちは普通、「嬉しいから、笑う」と考えますよね。
でもアランは、
「まず、笑ってみなさい。そうすれば、幸福な気持ちが後からついてくるよ」
と言っているのです。
つまり、「感情」が「行動」を決めるのではなく、
「行動」が「感情」を導くことができる、というわけです。
これ、実は私たちの日常にもよくあることなんです。
例えば、面倒な部屋の片づけ。
「やる気が出ないな…」と思っていても、とりあえず机の上の一つを片付け始めると、だんだん集中してきて、気づいたら部屋中ピカピカになっていた、なんて経験。
あれと似ています。
この考え方は、単なる精神論ではありません。
私たちの脳は、身体の状態から感情を判断するクセがあるようで、意識的に口角を上げて笑顔を作るだけでも、
「あ、今、楽しいんだな」
と感じて、気持ちが少し明るくなることが分かっているんです。
つまり、アランは100年も前に、こんな力強いエールを私たちに送ってくれているんですね。
「あなたの機嫌のハンドルは、いつだって、あなたが握っているんだよ」と。
気分という名の乗り物に、ただ揺られるがままになるのではなく、自分の意志で行き先を選んでいく。
そう考えると、なんだか少し、心が強くなれるような気がしませんか?
ラッセルの幸福論 不幸の原因は「自分への関心の向けすぎ」にあった
悩んでいる時や、気分が落ち込んでいる時って、私たちの意識はどんな状態になっているでしょう。
おそらく、頭の中は「自分」のことで、いっぱいになっているはずです。
自分の欠点、過去の失敗、未来への不安…。
気づけば、思考がぐるぐると自分を中心に回り続けて、出口が見えなくなってしまう。
同じく『幸福論』を著したイギリスの哲学者バートランド・ラッセルは、そんな状態を鋭く見抜き、こう指摘しました。
不幸の最大の原因の一つは、自己への没頭である。
「自己への没頭」。
少しドキッとする言葉ですが、これは決して「自分を大切にするな」という意味ではありません。
むしろ逆で、
「自分」という小さな檻の中に、自分自身を閉じ込めてしまっている状態が、心を苦しくさせるのだ、
とラッセルは考えたのです。
私はこれを、心の「自撮りモード」みたいに呼んでいます。
スマートフォンのカメラを、ずっとインカメラにして自分の顔(悩み)ばかりをアップで見つめていては、周りに広がる美しい景色(世界の面白さ)に気づくことができませんよね。
では、どうすれば、その自撮りモードを解除できるのか。
ラッセルの答えは、とてもシンプルです。
あなたの興味をできるかぎり幅広くせよ。
つまり、意識のカメラを、外側に向けてみよう、ということです。
例えば、
-
普段は聴かないジャンルの音楽を、試しに聴いてみる。
-
通勤途中に、道端に咲いている花の名前を調べてみる。
-
誰かのために、見返りを求めない小さな親切をしてみる。
そんな風に、自分の悩みから少しだけ意識を逸らして、外の世界に心を向ける時間を作ってあげる。
そうすると、凝り固まっていた自分の悩みが、ほんの少しだけ、相対的に小さなものに感じられてくるから不思議です。
自分の悩みでいっぱいになった心の部屋から、ほんの少しだけ顔を上げて、外の世界という窓を開けてみる。
ラッセルは、その窓の先に、気持ちが楽になるための爽やかな風が吹いていることを、教えてくれているのですね。
【この章のポイント】
アランの教え 気分は「起きること」ではなく「起こすこと」。行動が感情を導くので、自分の機嫌は自分の意志で選べる。
ラッセルの教え 不幸の原因は「自分」にばかり関心を向けすぎること。意識を外の世界に向けることで、心は楽になる。
幸福論は、難しいお説教ではなく、日常で使える「気持ちが楽になる考え方の道具」である。
【幸福論の実践】今日からあなたの日常が変わり始める5つの具体的習慣
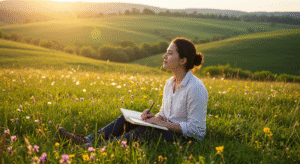
さて、前の章では、アランとラッセルの知恵を借りて、気持ちが少し楽になる「考え方の道具」を手に入れましたね。
この章では、いよいよこの記事の心臓部です。
その道具を、あなたの毎日の生活の中で実際に使っていくための、5つの具体的な「習慣」をご紹介します。
どれも、難しいことや特別な準備が必要なことではありません。
「これなら、私にもできるかも」
そう思えるものから、気軽な気持ちで試してみてくださいね。
一つでもあなたの生活に加わったなら、昨日とは少しだけ、見える景色が変わってくるはずです。
習慣1「光を探す」練習|ネガティブ思考の回路を書き換える
一日が終わってベッドに入ると、今日できなかったことや、誰かに言われた些細な一言、小さな失敗ばかりを思い出してしまう…。
そんな夜、ありますよね。
私たちの脳は、どうやら放っておくと、良かったことよりも悪かったことの方を記憶しやすいめんどくさい性質があるようです。
でも、大丈夫。
その「思考のクセ」は、簡単な練習で少しずつ変えていくことができます。
そのための具体的な実践が、「3つの良いこと日記」です。
これは、ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマン博士も推奨している、科学的にも効果が認められた方法なんですよ。
【具体的なやり方】
-
寝る前に、ノートやスマートフォンのメモを開きます。
-
今日あった「良かったこと」を、3つだけ書き出します。
-
本当に、どんなに些細なことで構いません。
【書き出すことの例】
-
ランチで食べたパスタが、すごく美味しかった。
-
朝、駅まで急いでいたら、信号が青に変わってラッキーだった。
-
コンビニの店員さんの笑顔が、素敵だった。
-
道端に咲いていた花の色が、綺麗だった。
-
帰りの電車で、タイミングよく座れた。
…ほら、なんだか自分にもできそうな気がしてきませんか?
私自身、始めたての頃は「書くことがない…」と3分も悩んだ日がありましたが、それでも「温かいお茶が飲めた」と絞り出すことから始めました。
私たちの脳は、「意識を向けたものを見つけ出す」のが得意です。
今まで「悪いこと探し」が上手だったのは、無意識にその練習をずっとしてきたから。
これからは、この日記を通して、「良いこと探しの練習」をしてみるのです。
この習慣を続けていくと、
「今日も色々あったけど、悪いことばかりじゃなかったな」
と、一日を穏やかな気持ちで締めくくれるようになります。
世界は何も変わっていないのに、世界の「光」の部分に気づく力が、あなたの中に育っていくのですね。
習慣2「今を味わう」練習 頭の中のおしゃべりを止めて不安を手放す
静かな部屋に一人でいるはずなのに、頭の中では仕事の心配や、人間関係の悩み事が、ずっとおしゃべりを続けている…。
まるで、落ち着きのないお猿さんが、頭の中で飛び回っているような感覚。
心理学の世界では、これを「モンキーマインド」なんて呼んだりします。
このお猿さんを、少しだけ静かにさせてあげるための、最もシンプルで強力な方法。
それが、「1分間マインドフルネス呼吸法」です。
【具体的なやり方】
-
椅子に座るか、楽な姿勢で立ち、背筋を軽く伸ばします。
-
目を閉じるか、難しければ、床の一点をぼんやりと眺めます。
-
そして、ただ、自分の「吸う息」と「吐く息」だけに、全ての注意を向けます。
-
(吸う時に、お腹が膨らむ感覚…)
-
(吐く時に、空気が鼻先を通る感覚…)
-
-
きっとすぐに、他の考え事が浮かんできます。それは自然なこと。「あ、考えたな」と、それに気づいてあげて、またそっと、意識を呼吸に戻します。
たったこれだけです。
これを、まずは1分間。
慣れてきたら3分間と、少しずつ伸ばしてみてください。
私たちの不安や悩みのほとんどは、「過去」への後悔か、「未来」への心配事から生まれています。
つまり、「今、ここ」にはない、「思考」が生み出しているものなんですね。
呼吸法は、さまよいがちな意識を、「思考」の世界から、「今、この瞬間の身体感覚」へと、優しく連れ戻してくれるアンカー(錨)のようなもの。
不安で押しつぶされそうになった時、いつでも自分を落ち着かせられる「心の安全基地」を、あなた自身の中に作ってあげることができる、一生もののスキルになりますよ。
習慣3「自分と仲直りする」練習|不完全さを受け入れ自己肯定感を育む
「100点満点じゃなければ、まるで0点だ」
「もっと頑張らないと、自分には価値がない」
そんな風に、自分に厳しくなりすぎて、自分で自分の心を苦しめてしまうこと、ありませんか?
真面目で、頑張り屋さんな人ほど、そうなりがちかもしれませんね。
でも、私たちは神様ではないので、いつでも完璧でいることなんてできません。
そんな不完全な自分を、まるごと「よくやっているよ」と認めてあげるための、温かい習慣を始めてみませんか。
① 小さな「できた!」を可視化する
大きな成功体験は、必要ありません。
日常の当たり前の中に隠れている、小さな「できた!」に光を当ててあげるのです。
手帳や付箋に、今日完了したタスクを書き出してみましょう。
ポイントは、「目標」ではなく「完了したこと」「できたこと」を書くこと。
-
朝、時間通りに起きられた。
-
面倒だったメールを1件、返信した。
-
夜ご飯の食器を洗った。
そして、終わったら線で消していく。
この「消す」という行為が、小さな達成感を生み、「私、ちゃんとできているじゃん」という感覚(自己効力感)を、少しずつ育ててくれます。
② アラン流「形から入るご機嫌とり」
気分が沈んでいる時こそ、前の章で学んだアランの知恵を実践してみましょう。
だまされたと思って、あえて、口角をきゅっと上げてみてください。
そして、猫背になりがちな背筋を、すっと伸ばしてみる。
最初は、心と身体がちぐはぐで、違和感があるかもしれません。
でも、その身体の「形」が、少しずつ心に影響を与え、「まあ、なんとかなるか」という気持ちを連れてきてくれることがあります。
この二つの習慣を通して、どんな自分であっても、まずは自分が一番の味方でいてあげる。
気分の浮き沈みに振り回されるのではなく、自分で自分の機嫌をとってあげる。
そんな、しなやかで自立した心のあり方を、育んでいくことができるはずです。
習慣4「外に心を開く」練習|良質な「繋がり」の中で孤独を溶かす
ラッセルが教えてくれたように、不幸の原因は、自分の内側にばかり関心が向いてしまうことにあるのかもしれません。
自分の悩みでいっぱいになった心に、外の新鮮な空気を取り込んであげる時間を作りましょう。
① 1日1回の「小さな親切」をしてみる
誰かのために、何かをしてみる。
といっても、そんなに大げさなことではありません。
-
家族のために、一杯のコーヒーを淹れてあげる。
-
コンビニのレジ横にある募金箱に、おつりを入れてみる。
-
会社の共有スペースを、さっと拭いてみる。
誰かに褒められたり、気づかれたりしなくてもいいんです。
心理学の研究では、親切な行いは、された側よりも、した側の幸福感を高める、という面白い結果が出ています。
見返りを求めない小さな親切は、自己中心的な思考から心を解放し、自分が世界と繋がっているという温かい感覚を思い出させてくれます。
② 「感謝」を言葉にして伝えてみる
心の中で「ありがたいな」と思っていること、たくさんありますよね。
でも、意外とそれを、言葉にして相手に伝える機会は少ないかもしれません。
「ありがとう」の一言に、ほんの少しだけ、具体的な言葉を添えてみてください。
「さっきは手伝ってくれて、”本当に助かったよ。”ありがとう」
「いつも美味しいご飯を作ってくれて、”元気が出るよ。”ありがとう」
感謝の言葉は、相手の心を温めるだけでなく、実は、言った本人の心をも、じんわりと満たしてくれる不思議な力を持っています。
これらの習慣は、自分の悩みという小さな部屋から出て、他者や社会という広い世界との繋がりを、改めて感じさせてくれます。
そうすると、あれほど大きく感じていた自分の悩みが、ほんの少しだけ、ちっぽけに思えてくるから不思議ですね。
与えることが幸福につながるんです。
習慣5「自分の物差しを育てる」練習|他人の評価から自由になる
「みんなが良いと言っているから、良いものなんだろう」
「SNSで『いいね』がたくさんつく生き方が、幸せな生き方なんだろう」
私たちは知らず知らずのうちに、「他人」や「世間」という物差しで、自分の価値を測ってしまいがちです。
でも、あなたにとっての心地よさと、他の人にとっての心地よさは、違っていて当たり前。
ここでの最後の習慣は、他人の物差しから自由になり、「自分だけの、オーダーメイドの物差し」を育てていくための練習です。
① 「心が動いた瞬間」をメモする
あなたの心が、
「嬉しい!」
「楽しい!」
「心地よい!」
と感じた瞬間を、簡単な言葉でいいので、メモしておきましょう。
-
(カフェで)このコーヒーの香り、すごく落ち着くなあ。
-
(音楽を聴いて)この曲のメロディー、なんだか泣きそうになるくらい好きだな。
-
(友人と話して)こういう、何でもないおしゃべりの時間が一番楽しいな。
ポイントは、
「モヤっとした」「これは嫌だな」というネガティブな感情も、大切なサインとして書き留めておくこと。
それらは、あなたが「何を大切にしたくないか」を教えてくれる、貴重なヒントだからです。
このメモを時々見返すことで、あなただけの「好き」と「嫌い」の輪郭が、だんだんと、はっきりと見えてきます。
② 勇気を出して「やらないこと」を決めてみる
幸せになるためには、何かを「足し算」するだけでなく、不要なものを「引き算」する勇気も、時には必要です。
-
本当は気乗りしない飲み会の誘いを、勇気を出して断ってみる。
-
寝る前のスマホ時間を、15分だけ減らしてみる。
あなたの貴重な時間とエネルギーを、本当に大切なこと
…つまり、あなたの心が「好き」だと教えてくれたことのために、使ってあげる。
その選択の一つひとつが、ブレない「自分軸」となり、あなただけの「心の指針」を形作っていきます。
この物差しが育てば、もう情報や他人の意見に、むやみに振り回されることはありません。
自分の人生を、自分で選んでいる
という、静かで、しかし確かな満足感に、あなたの心は満たされていくはずです。
【この章のポイント】
習慣1 光を探す → 「3つの良いこと日記」で、ポジティブな側面に気づく練習をする。
習慣2 今を味わう → 「1分間呼吸法」で、思考の渦から抜け出し、心を「今」に戻す。
習慣3 自分と仲直りする → 「できたことリスト」で、不完全な自分を認め、自己肯定感を育む。
習慣4 外に心を開く → 「小さな親切」と「感謝」で、自己への執着から解放され、繋がりを感じる。
習慣5 自分の物差しを育てる → 「心の動きのメモ」で、自分軸を見つけ、他人の評価から自由になる。
【応用編】日常がさらに豊かに。幸福度を加速させる2つの追加エッセンス

基本の5つの習慣に少し慣れてきたら、あるいは、もう少し違う角度からのアプローチも知りたいなと感じたら。
ここでは、あなたの幸福感をさらに高めてくれる、いわば「幸福度のブースター」となるような、2つの追加エッセンスをご紹介します。
5つの基本習慣が、心の「土台」を整えるためのものだとしたら。
この応用編は、その整った土の上に、より彩り豊かな花を咲かせるためのヒント、といったところでしょうか。
「へえ、そんな視点もあったんだ」
そんな風に、新しい発見を楽しんでもらえたら嬉しいです。
追加エッセンス① 自然に触れる|空を見上げるだけで悩みが小さくなる理由
最後に、ゆっくりと空の色が変わるのを眺めたのは、いつでしたか?
一日中パソコンやスマートフォンの画面と向き合っていると、私たちの視野はどんどん狭くなり、首や肩も凝り固まってしまいますよね。
大自然豊かな場所へ出かけるのも素晴らしいことですが、もっと手軽に、私たちの心を解放してくれるものがあります。
それが、「日常の中の小さな自然」に、意識的に触れる習慣です。
-
通勤の途中、少しだけ遠回りして公園の木々を眺めてみる。
-
ベランダに置いた小さな観葉植物に、丁寧に水をやる。
-
ランチの時に5分だけ外に出て、ただ、空を見上げてみる。
たったそれだけのことなのに、不思議と心がすーっと、穏やかになるのを感じませんか?
実はこの感覚、最近の研究で、そのメカニズムが少しずつ解明されてきているんです。
カリフォルニア大学の研究者たちは、雄大な自然などに触れた時に私たちが感じる、
「畏敬(いけい)の念」
…つまり、
「うわあ、すごい…」と、ただただ圧倒されるような感覚が、私たちの心に素晴らしい効果をもたらすことを発見しました。
この「畏敬の念」は、
私たちの「自己(エゴ)」…つまり、「自分、自分」と考える意識を、一時的に小さくしてくれる働きがあるのだそうです。
大きな夕焼け空を見つめていると、さっきまでくよくよ悩んでいた自分の悩みが、なんだか、ちっぽけなことに思えてくる。
あの感覚には、ちゃんと科学的な裏付けがあったのですね。
これは、ラッセルが教えてくれた「自己への没頭からの脱却」とも、深く繋がっています。
自分の内側ばかりに向いていた意識を、自分よりもはるかに大きな存在である「自然」へと向けてみる。
まずは、この文章を読み終えたら、騙されたと思って、窓の外をぼーっと見てみてください。
そこに広がる空が、知らず知らずのうちに狭くなっていたあなたの心を、少しだけ、広くしてくれるはずですよ。
追加エッセンス② 何かに没頭する|時間を忘れるほどの「フロー体験」のすすめ
「気づいたら、もうこんな時間!」
何かに夢中になって、食事や時間の経過すら忘れてしまうほど、深く集中した経験はありませんか?
それは、読書かもしれないし、料理や、趣味の編み物、あるいは仕事の作業かもしれません。
その、最高の集中状態のことを、心理学者のミハイ・チクセントミハイは
「フロー体験」と名付けました。
彼はこれを、人生における「最高の経験」と呼び、幸福感を構成する非常に大切な要素だと考えたのです。
フロー状態にある時、私たちは自分の存在すら忘れて、その活動と一体化しています。
そこには、未来への不安や、他人からの評価を気にする意識は、一切ありません。
これはまさに、ラッセルの言う「自己への没頭」とは真逆の、「自己を忘れる(没我)」という状態です。
自分の悩みから完全に解放される、この上なく豊かで、充実した時間だと言えるでしょう。
このフロー体験は、ただ偶然に訪れるのを待つだけでなく、ある程度、意図的に作り出すことができます。
そのための、簡単な3つの条件をご紹介しますね。
-
明確な目的があること
(例:「この1時間で、本のこの章を読み終える」) -
すぐに手応え(フィードバック)があること
(例:パズルをはめれば、絵が完成に近づいていく) -
自分の「能力」と、その活動の「難易度」のバランスが、ちょうど良いこと
(簡単すぎて退屈でもなく、難しすぎて不安でもない、ちょっとだけ難しい絶妙なレベル)・(挑戦的集中状態)
あなたにとって、この3つの条件が揃う活動は、一体何でしょうか?
私の場合はテトリスとかがちょうどいいですね。
もし、あなたが子供の頃、時間を忘れて熱中していたことがあるとしたら、それは何でしたか?
その中に、あなたの「フローの種」が隠れているかもしれません。
特別なことである必要は、全くありません。
あなたの日常に、そんな「時間を忘れるほどの宝物」を、ぜひ見つけて、大切に育ててみてくださいね。
楽しいですよ!
【この章のポイント】
自然に触れる → 「畏敬の念」が自己中心的な悩みを小さくし、心を解放してくれる。まずは空を見上げることから。
何かに没頭する → 「フロー体験」は、自己を忘れるほどの最高の充実感をもたらす。能力と難易度のバランスが鍵。
応用編は、心の土台を整えた上で、日常をさらに彩り豊かにするためのブースターとなる。
まとめ 幸福論の実践とは、幸せな「目的地」を探すのではなく、豊かな「道のり」を歩む技術

最後に、この記事でお伝えしてきた、一番大切なことをお話しさせてください。
それは、
幸福とは、いつかたどり着くべき「目的地」ではなく、日々の実践を通して、一歩一歩豊かにしていく「道のり」そのものである
ということです。
「いつかお金持ちになったら」
「理想のパートナーが見つかったら」…
私たちはつい、幸せに「条件」をつけて、未来のどこかにあるはずのゴールを探してしまいます。
でも、アランやラッセル、そして現代の心理学が教えてくれるのは、そうではありません。
幸福とは、今、この瞬間から始められる、ささやかな実践の積み重ねの中にこそ、宿っているのです。
いつでも立ち返れる、7つの習慣
あなたの心が道に迷ってしまった時、いつでもここに帰ってこられるように。
これまでご紹介してきた習慣を、「心の指針」として、もう一度リストアップしておきますね。
【基本の5つの習慣】
| 習慣 | やること(一例) | 得られるもの |
| 1. 光を探す | 3つの良いこと日記 | ポジティブな側面に気づく力 |
| 2. 今を味わう | 1分間呼吸法 | 不安を手放し、心を今に戻す力 |
| 3. 自分と仲直りする | できたことリスト | 不完全さを受け入れる自己肯定感 |
| 4. 外に心を開く | 小さな親切と感謝 | 繋がりを感じ、孤独を溶かす力 |
| 5. 自分の物差しを育てる | 心の動きをメモする | 他人の評価から自由になる自分軸 |
【応用編の2つのエッセンス】
| エッセンス | やること(一例) | 得られるもの |
| ① 自然に触れる | 空を見上げる | 小さな悩みをリセットする解放感 |
| ② 何かに没頭する | フロー体験を探す | 自己を忘れるほどの充実感 |
…どうか、これら全てを、明日から完璧にやろう、なんて思わないでくださいね。
それは、この記事が一番伝えたかったこととは、正反対のことですから。
もし忘れてしまっても、三日坊主で終わってしまっても、全く問題ありません。
またふと思い出した時に、ここに戻ってきて、一つだけ、試してみる。
その小さな試みこそが、あなたの人生が、あなた自身の力で、豊かさへと向かい始めた、何よりの証拠なのです。
あなたの新しい日常への、最初の一歩
この記事を読み終えたら、スマートフォンをそっと置いて、一度だけ、目を閉じてみてください。
そして、ゆっくりと、深く息を吸い込み、
ゆっくりと、吐き出します。
…ただ、それだけでいいのです。
その一呼吸が、他人や過去や未来ではなく、「今、ここにいる自分」に、あなたの意識を優しく戻してくれるための、小さくても、そして、とても偉大な第一歩です。
普段私たちは「前に!」「前に!」と意識を向けがちです。
でもたまには
「今」にゆっくりと意識を向けてじっくりと味わってみるのも素敵な日々につながります。
あなたの新しい日常は、いつだって、その一呼吸から始まります。
幸福は、味わうもの。
この記事が、あなたの毎日を、昨日より少しだけ色鮮やかにする、ささやかなきっかけとなれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
【この記事のポイント】
幸福は「目的地」ではなく、日々の実践で育んでいく「道のり」そのものである。
完璧を目指す必要はない。一つでも試してみようと思う気持ちが、何よりも尊い。
新しい日常への第一歩は、いつでも「今、ここ」での深い一呼吸から始まる。
【さらに深く知りたい方へ|参考文献】
-
アラン『幸福論』
-
バートランド・ラッセル『幸福論』
-
ソニア・リュボミアスキー『幸せがずっと続く12の行動習慣』
-
ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』
- Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9(2), 111-131.
このブログでは、この記事でご紹介したような「考え方」のヒントを通して、あなたが自分にとっての「豊かさ」や「幸せ」とは何かを探求していくお手伝いができればと考えています。
もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。
きっと、あなたの日常を少しだけ豊かにする、新しい発見があるはずです。
【こちらの記事も読まれています】