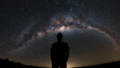「最近、何も楽しくない…」
その感情、実はあなたの脳の仕組みが関係しているかもしれません。
この記事を読めば、
脳の性質をうまく利用し、わくわくする気持ちを“意図的に”生み出す方法がわかります。
ドーパミンの本当の役割から、
わくわくを持続させるための「仕組みづくり」までを具体的なステップで解説。
感情論ではない、科学的根拠に基づいたアプローチです。
あなたの脳を味方につけて、明日を少しだけ変えてみましょう。
※この記事でいう『わくわく』は、単なる興奮だけでなく、『未来への期待感』や『内側から湧き上がる好奇心』を指します。
机の上に置かれたままの本が、教えてくれる「幸福」の正体

最近、心から「わくわく」したことって、ありましたか。
なんだか、毎日が同じことの繰り返しのように感じてしまう。
仕事や日々のやるべきことに追われ、気がつけば一日が終わり、また新しい朝が来る。
大きな不満があるわけじゃない。
でも、子どもの頃のように、未来のことを考えると胸が高鳴るような、あの体の芯から湧き上がってくるような感覚は、一体どこへ行ってしまったんだろう…。
そんな風に感じていませんか?
実は先日、本屋さんでずっと気になっていた一冊の本を手に入れました。
家に帰って、すぐにでも読みたい気持ちをぐっとこらえ、いつも目につく机の上に、そっと置いてみたんです。
それから数日間、コーヒーを淹れるたびに、その本の背表紙が目に入ります。
「このページの中には、どんな世界が広がっているんだろう」
「読み終えた時、私はどんなことを感じているんだろう」
不思議なことに、まだ一行も読んでいないのに、その本が「そこにある」というだけで、日常が少しだけ彩り豊かになった気がする。
この、ページをめくる前の「期待に満ちた時間」そのものに、なんとも言えない幸福感を感じている自分に、ふと気づいたんです。
もしかしたら、私たちが失くしてしまったと思っている「わくわく」の正体は、これにとても近いのかもしれません。
未来への「わくわく」は、どこか遠くにある特別な出来事の中にだけ存在するのではなく、
むしろ、これから起こるかもしれない小さな出来事への「期待」そのものの中に、静かに隠れているのではないでしょうか。
そして、その「期待」は、誰かに与えられるものではなく、自分自身の手で、日々の生活の中にそっと仕込み、育てていくことができる「技術」だとしたら…?
この記事では、
「脳科学」が解き明かす私たちの心の仕組みや、
「心理学」が示す感情の育み方、
そして時には「古代の哲学」が教えてくれる、時代を超えた幸福の本質。
そういった確かな知見を借りながら、あなたの毎日が少しでも楽しみになるような、具体的な方法を一つひとつ、丁寧にお伝えしていきますね。
もしよろしければ、温かい飲み物でも片手に、ゆっくりとこのまま読み進めてみてください。
なぜ、大人になると「未来へのわくわく」は消えてしまうのか?

子どもの頃の夏休み・冬休み前のあの胸が高鳴るような感覚を、今でも覚えていますか。
あるいは、誕生日やクリスマスを指折り数えて待っていた、あの頃のどうしようもない高揚感を。
いつからでしょう。
同じ虹を見ても「ああ、綺麗だな」と思うくらいで、
カレンダーの記念日も、ただの「やらなければいけないことが多い日」に感じてしまうようになったのは。
「昔はもっと感受性が豊かだったのに、自分がつまらない人間になってしまったのかな…」
大人になると「わくわく」を感じにくくなるのには、ちゃんとした理由があるんです。
それは決して、あなたの心が色褪せてしまったからではないんですよ。
理由1:脳が賢くなったから – 世界の「未知」が「既知」に変わる
私たちの脳は、非常に優秀な「予測マシン」のようなものなんです。
子どもの頃は、見るもの聞くもの全てが新鮮で、「未知」の情報で溢れていました。
だから脳はフル回転で世界を学び、その度に驚きや発見という「わくわく」を感じていたのです。
しかし、様々な経験を重ねるにつれて、脳はどんどん賢くなっていきます。
「こういう時は、こうなるだろう」
「この道を行けば、あの角を曲がれば、いつもの景色が待っている」
そんな風に、未来を高い精度で予測できるようになる。
これは、無駄なエネルギーを使わずに効率よく生きるための、脳が身につけた素晴らしい「省エネ術」なんですね。
ただ、その副作用として、予測できることが増えれば増えるほど、新鮮な驚きは減っていきます。
つまり、わくわくが減ったように感じるのは、あなたの感性が鈍ったのではなく、
あなたの脳がこの世界に順応し、賢くなった証拠とも言えるのです。
理由2 心の声が聞こえないから「やるべきこと」が「やりたいこと」を覆い隠す
もう一つの理由は、私たちの日常にあります。
いつの間にか、あなたのスケジュール帳は「やるべきこと」でいっぱいになっていませんか?
仕事の締め切り、誰かとの約束、日々の家事…。
社会的な役割や責任が増えるにつれて、私たちは
「~すべき」
「~しなければならない」
「~をやっといたほうがいい」
という思考に多くの時間を使うようになります。
もちろん、それらは生きていく上でとても大切なことです。
でも、その「べきべき思考」の声が大きくなりすぎると、心の奥底でささやいている
「~してみたい」
「なんだか、これが気になる」
という、自分自身の純粋な好奇心の声が、どんどん聞こえにくくなってしまう。
本当は寄り道してみたいカフェがあるけれど、夕飯の準備の時間があるからと諦める。
なんとなく手に取ってみたい本があるけれど、「それより先に読むべき本があるから」と我慢する。
そんな風に、小さな「やりたい」という気持ちに気づかないふりをし続けることで、私たちの心は少しずつ、ときめき方を忘れていってしまうのかもしれませんね。
【本質】それは喪失ではない。大人のわくわくは「育てる」ものへ
脳が賢くなり、やるべきことが増える。
これが、私たちが感じていた「わくわくの喪失」の正体です。
だとしたら、子どもの頃と全く同じ感覚を「取り戻そう」とするのは、少しだけ方向が違うのかもしれません。
子どもの頃のわくわくが、偶然見つける虹のような「発見型・受動型」のものだったとすれば、
これからの私たちが目指すのは、自分で種をまいた花が咲くのを楽しみに待つような、
「創造・育成型・能動型」のわくわくです。
失ってしまったものを嘆く必要はありません。
これから、今のあなたにふさわしい、より深く、静かで、そして持続可能な新しいわくわくの「育て方」を、一緒に学んでいけばいいのですから。
【この章のポイント】
大人になって「わくわく」が減るのは、脳が賢く成長した証拠であり、自然な変化。
日々の「やるべきこと」に追われ、自分の「やりたい」という心の声が聞こえにくくなっている。
これからのわくわくは「見つける」ものではなく、自分自身で「育てていく」ものへと質が変わる。
【理論編】幸福の正体は「結果」ではなく「期待」。科学と哲学が示す真実

目標を達成した瞬間よりも、その直前がいちばん楽しかった。
旅行から帰ってきた時よりも、出発を待つ空港での高揚感が忘れられない。
あなたにも、そんな経験はありませんか?
私たちはつい、
「何かを手に入れた時」や「物事が完了した時」にこそ、幸福のピークがあると考えがちです。
でも、もし、幸福の本質が、その「結果」よりも、
そこへ至るまでの「期待」にこそ、より多く隠されているとしたら…?
この章では、最新の科学と古代の哲学という、一見すると全く違う分野の知見を借りながら、
この「期待こそが幸福の源泉である」という、少し意外な真実を解き明かしていきたいと思います。
スタンフォード大の神経科学が解明。「わくわく」を生むドーパミンの本当の役割
「ドーパミン」という言葉を、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。
近年の研究では、ドーパミンの面白い働きがわかってきました。
それは、ドーパミンが、
ご褒美を「もらった時」よりも、「もうすぐもらえそうだ!」と期待している時にこそ、最も多く放出される、
ということなんです。
(ゲームでレアアイテムがドロップするのを待っている時や、好きなアーティストのライブを心待ちにしている時などですね。)
スタンフォード大学の神経科学者アンドリュー・ヒューバーマン氏は、自身のポッドキャストで、
「ドーパミンは、報酬を得た後よりも、それを手に入れようと努力している時にこそ、モチベーションの源として最も強く働く」
と解説しています。
つまり、私たちの脳は、山頂にたどり着いたという「結果」そのものよりも、
山頂を目指して一歩一歩進んでいる「道のり」や、
もうすぐ頂上に着くぞという「期待感」にこそ、より大きな喜びを感じるように設計されている。
なんだか、とても希望が湧いてくる話だと思いませんか?
「積ん読の幸福論」なぜ私たちは“未来の楽しみ”に投資するのか?
この脳の仕組みを知ると、冒頭でお話しした「積ん読」の謎が、すっと解けてきます。
あの、まだ読んでいない本が机の上にあるだけで満たされる感覚。
あれはまさに、ドーパミンが「これからこの本を読めるぞ!」という期待に対して、たっぷりと放出されていた状態だったのですね。
私はこれを、敬意を込めて「積ん読の幸福論」と呼んでいます。
本を買うという行為は、単に「知識を得る」という未来の結果のためだけではない。
私たちは、ドーパミンがくれる心地よい「期待感」を味わうために、無意識のうちにお金と時間を投資しているのかもしれません。
これは、積ん読に限りません。
まだ封を切っていないゲームソフト。
行く計画を立てている旅行のパンフレット。
週末に見ようと決めている、ドラマの録画リスト。
私たちの日常には、実はこの「未来の楽しみへの投資」が溢れています。
だとしたら、私たちはこれまで、楽しみをすぐに消費してしまうことで、最も美味しくて、最も幸福感の詰まった「期待」という果実を、少しだけ食べ逃していたのかもしれませんね。
哲学は知っていた。アリストテレスが説く幸福「エウダイモニア」とは
そして、驚くべきことに、この「プロセスこそが重要だ」という考え方は、今から二千年以上も前の古代ギリシャで、すでに偉大な哲学者によって語られていました。
哲学者のアリストテレスは、幸福には2種類あると考えました。
一つは、美味しいものを食べたり、欲しいものを手に入れたりする一時的な快楽。
そしてもう一つが、彼が「エウダイモニア(Eudaimonia)」と呼んだ、より本質的な幸福です。
このエウダイモニアとは、
「自分自身の持つ可能性を最大限に発揮し、あるべき善い姿に向かって進んでいる、その状態そのもの」(『ニコマコス倫理学』より)
を指します。
少し難しい言葉ですが、私なりに解釈すると、
アリストテレスは、幸福とは山頂にたどり着いたという「結果」ではなく、
一歩一歩、自分なりの足取りで山を登っている、その「過程(道のり)」にこそ宿る、
と考えていたのではないでしょうか。
だとしたら、「わくわく」という感情は、
「今、自分は善い道のりを歩んでいるよ」
「その先に、きっと素晴らしい景色が待っているよ」
と、未来の自分から送られてくる、温かいサインなのかもしれませんね。
【この章のポイント】
幸福感をもたらすドーパミンは、目標を「達成した時」より「期待している時」に多く放出される。
「積ん読」のように楽しみをすぐに消費せず「期待感」を味わうこと自体が、幸福な時間である。
哲学的に見ても、幸福とは結果ではなく、自分の可能性に向かって進む「プロセス」そのものにある。
【実践編】心が動く感覚を取り戻す。今日から始める「わくわく」を育てる3つの方法

さて、ここまでの話で、「わくわく」の正体が未来への「期待」にあり、それは私たちの脳や心の仕組みに深く関わっていることが、なんとなく見えてきたのではないでしょうか。
理論がわかると、次はいよいよ実践です。
この章では、理論編で学んだことを、私たちの普段の生活の中に、無理なく、そして楽しみながら取り入れるための具体的な「技術」を、3つのアプローチからご紹介します。
難しく考える必要はありません。
「これ、ちょっといいかも」
そう思えるものが一つでも見つかったら、そこから気軽に試してみてくださいね。
方法1 未来の解像度を上げる【哲学的アプローチ】
最初にご紹介するのは、ぼんやりとして不安に見えがちな未来に、あなた自身の手で、温かい光の目印を立ててあげるアプローチです。
1. 「1年後の理想の感情」から逆算してみる
多くの人は目標を立てる時、「何を手に入れたいか」を考えがちです。
でも一度だけ、それを「どんな気持ちで日々を過ごしていたいか」という問いに変えてみませんか。
例えば、
「穏やかな気持ち」
「自信に満ちている」
「毎日、何かを面白がれている」
など、あなただけの理想の「感情」をゴールに設定してみるのです。
もし、「自信に満ちている」だとしたら、その自信は何から生まれるでしょう?
きっと、小さな成功体験の積み重ねかもしれませんね。
では、今週、あなたが確実に達成できる「小さな成功」とは何でしょう。
「毎朝5分早く起きて白湯を飲む」を1週間続ける。
それくらい、ごくごく簡単なことでいいんです。
2. 日々のタスクを「未来への種まき」と意味づける
理想の感情に繋がる小さな行動が見つかったら、次はその行動への「意味づけ」を少しだけ変えてみます。
例えば、毎日の退屈なデータ入力も、
「これを丁寧に続けることが、1年後の『自信に満ちた自分』に繋がる、大切な一歩なんだ」
と捉え直してみる。
この、ほんの少しの意識の転換が、灰色の日常を、未来への期待に満ちたカラフルな道のりへと変えてくれることがあります。
このアプローチは、未来への漠然とした不安を、自分でコントロール可能な「楽しみな道のり」に変えるための、古くて新しい哲学的な知恵なのです。
方法2 日常に「没頭」する時間を創る【心理学的アプローチ】
次は、少し未来から視点をずらして、目の前の「今」に深く集中することで、内側からエネルギーを生み出す方法です。
心理学者ミハイ・チクセントミハイは、時間を忘れるほど何かに夢中になる、あの最高の集中状態を「フロー体験」と名付けました。
この「フロー」の状態こそが、私たちに深い満足感と成長実感を与えてくれるのです。
【コツ① 「挑戦と能力の絶妙なバランス」を見つける】
フロー状態に入るには、課題が簡単すぎても、難しすぎてもいけません。
「今の自分にとって、頑張ればなんとかできそう」
という、ほんの少しだけ背伸びするくらいの挑戦が、いちばん心を燃えさせてくれます。
「挑戦的集中状態」ですね。
| 【簡単にできること】 | いつもと同じ料理を作る | 映画をただ観る |
|
【少し背伸びした挑戦(フローに入りやすい)】 |
少し手の込んだレシピに挑戦する |
映画の感想を3行だけノートに書く |
|
|
プロ級の料理に挑戦する | 専門的な映画レビューを書く |
【コツ② 結果ではなく「プロセス」に集中する】
挑戦する時は、「うまくやろう」と気負う必要はありません。
むしろ、
行為そのものを味わうことに意識を向けます。
スマートフォンを少し遠くに置いて、野菜を切る音、ペンが紙を走る感触、コーヒーの香り…。
そんな、目の前の世界の解像度をぐっと上げてみる。
この「没頭する時間」が、心を整え、次への挑戦意欲、つまり未来への自然な「わくわく」を生み出すエンジンになってくれます。
方法3 マンネリ脳をリセットする【脳科学的アプローチ】
最後は、私たちの脳の性質をうまく利用して、日常に新鮮な刺激を与え、わくわくしやすい「脳の状態」を意図的に作るアプローチです。
【習慣① 週に一度の「小さな初体験」をしてみる】
私たちの脳は、「予測できない新しい刺激」がなによりも大好きです。
マンネリ化した日常に、脳が喜ぶスパイスを少しだけ加えてあげましょう。
大それたことでなくて構いません。
-
いつもと違う道で帰ってみる
-
入ったことのないコンビニやスーパーに寄ってみる
-
普段は聞かないジャンルの音楽をかけてみる
この、ほんの少しの「いつもと違う!」が、脳にとっては最高のご馳走となり、日常を新鮮なものとして捉え直すきっかけになります。
【習慣②「できたこと」を可視化して自信を育てる】
どんなに小さなことでも、「できた!」という感覚は、脳にとって最高の報酬です。
そして、その報酬は「目に見える」とさらに効果が高まります。
例えば、「1日1ページだけ本を読む」という目標を立て、達成できたらカレンダーに好きな色のシールを貼っていく。
週末、シールで彩られたカレンダーを眺めた時、きっとあなたは「今週の自分、なかなかやるじゃないか」と、温かい気持ちになるはずです。
この「自分はちゃんと前に進んでいる」という感覚こそが、未来への揺ぎない自信と、わくわくの土台を育ててくれるのです。
これら3つのアプローチ、いかがでしたでしょうか。
どれか一つでも構いません。
あなたの心が「これなら、ちょっとだけ」と動いたものから、ぜひ気軽に試してみてくださいね。
【この章のポイント】
未来の「理想の感情」から逆算し、日々の行動に「未来への種まき」という意味を与える。
日常の中に「没頭」できる少し背伸びした挑戦を見つけ、プロセスそのものを楽しむ。
「小さな初体験」で脳に刺激を与え、「できたことの可視化」で自信を育てる。
【応用編】わくわくを一過性で終わらせない。「楽しみ」を持続させる仕組みづくり

実践編でご紹介した方法を試してみると、きっとあなたの日常に、ぽつり、ぽつりと小さな灯りのような「わくわく」が灯り始めるはずです。
ただ、ここで一つ、大切なことがあります。
それは、その灯りを一過性の線香花火で終わらせないための、「仕組み」を持っておくこと。
個人のやる気や努力だけに頼っていると、疲れた時にはどうしても気持ちが途切れてしまいますからね。
この章では、あなたの「わくわく」が自然と生まれ続けるサイクルを、生活の中に無理なく組み込むための、少し進んだ応用的なアイデアを3つご紹介します。
楽しみが途切れない。「わくわくのポートフォリオ」を持つという考え方
年に一度の海外旅行のような、大きな楽しみだけを目標にしていると、それが終わってしまった後の、あの心にぽっかり穴が開いたような感覚…つらいですよね。
まるで、花火大会後の、急な静けさのよう…
そこで私が提案したいのが、金融の世界で使われる「ポートフォリオ」という考え方を、私たちの「楽しみ」に応用してみることです。
なんだか難しく聞こえるかもしれませんが、やることはとてもシンプルですよ。
「わくわくのポートフォリオ」の作り方
期間の異なる楽しみを、バランス良く手帳やカレンダーに書き出してみるのです。
| 期間 | 楽しみの種類 | 具体例 |
| 短期 | すぐに実現できるご褒美 |
「週末に気になっていたパン屋さんに行く」 「金曜の夜に好きな映画を観ながら、少し良いアイスを食べる」 |
| 中期 | 少し計画が必要なイベント |
「来月、日帰り温泉に行く計画を立てる」 「読みたかった小説を3ヶ月かけて全巻読破する」 |
| 長期 | じっくり育てる自己投資 |
「半年後の資格取得を目指して、今日から1日15分勉強する」 「来年の春に向けて、ベランダでハーブを育て始める」 |
このように、期間の異なる楽しみをいくつか同時に持っておくことで、常に心の中に何かしらの「楽しみな予定(=期待)」が灯っている状態を、意図的に作ることができます。
一つの楽しみが終わっても、すぐに次の楽しみに意識を切り替えられる。
これは、あなたの心のエネルギーが枯渇しないようにするための、とても賢いセーフティネットになってくれるはずです。
わくわくは「伝染」する。あなたの“好き”を誰かに話してみよう
これまでは、自分一人で完結する方法を中心にお話ししてきました。
でも、時には「他者の力」を借りることで、私たちのわくわくは何倍にも増幅することがあります。
不思議なもので、自分が興味を持っていること、例えば最近ハマっているドラマや、
学び始めたことについて誰かに話そうとすると、頭の中が整理されて、改めて
「ああ、自分はこれが好きなんだな」
と、その気持ちを再確認できるんです。
言葉にすることで、わくわくはより輪郭を帯びて、くっきりとしてくるのですね。
そして、逆もまた然りです。
誰かが本当に楽しそうに、目を輝かせながら自分の好きなことを語っているのを聞くと、その熱量がこちらにも伝わってきて、
「なんだか面白そうだな」
と、自分の中の新しい興味の扉が、ふっと開かれることがあります。
大げさなプレゼンをする必要はありません。
今日のランチの時に、同僚に「週末、こんな面白いことがあって」と、少しだけ話してみる。
あるいは、聞き上手な友人に、「最近こんなことに興味があるんだ」と打ち明けてみる。
誰かに話さなくてもあなたがただ、幸せそうにしていれば、それでいい。
それだけで、あなたのわくわくは、あなただけのものから、誰かと分かち合える、より温かいものへと変わっていくはずです。
記録で「育てる」。好奇心ジャーナルで自分の“好き”の傾向を知る
実践編で、「心が動いた瞬間のメモ(好奇心ジャーナル)」という方法をご紹介しました。
この応用編では、それをもう一歩だけ進めてみましょう。
メモは、ただ書きっぱなしにするだけでは、少しもったいないかもしれません。
月に一度、5分だけでいいので、そのメモをぱらぱらと見返す時間を作ってみるのです。
そして、まるで探偵にでもなった気分で、そこに書かれた言葉を分析してみます。
「自分は、どんな言葉に心を動かされているんだろう?」
「無意識に、同じジャンルのことばかり気にしているな」
「意外と、自然に関する言葉が多いかもしれない」
そうやって、自分自身の「“好き”の傾向」を客観的に知ることで、次に何をすれば自分がわくわくするのかが、より明確に見えてきます。
「来月は、植物園に行ってみようかな」
「この分野について、もう少しだけ詳しく調べてみよう」
「記録 → 分析 → 次のワクワクする行動」
この能動的なサイクルを回していくことこそが、わくわくを、その場限りの感情ではなく、あなた自身の手で「育て続ける」ための、最も確かな仕組みなのです。
【この章のポイント】
楽しみを「短期・中期・長期」で組み合わせる「ポートフォリオ」で、心の期待感を途切れさせない。
自分の「好き」を誰かに話すことで、わくわくは増幅し、他者のわくわくも自分の刺激になる。
記録を見返して自分の「好きの傾向」を分析し、次の行動に繋げるサイクルを作る。
【心の守り方】わくわくできない日々の、優しく正しい過ごし方

ここまで読み進めてくださったあなたは、もしかしたら
「よし、明日から試してみよう!」
と、前向きな気持ちになってくれているかもしれません。
でも、その一方で、心のどこかでこんな声も聞こえてきませんか?
「…とは言っても、正直、そんな気力すらない日もあるんだよな」と。
その感覚は、全くもって正しいものです。
この章では、そんな風に心が疲れてしまった時のために、あなた自身を優しく守るための、とても大切な考え方をお伝えしますね。
大前提 わくわくしない日があって当たり前。自分を責めないで
まず、何よりも先にお伝えさせてください。
わくわくしない日があって、当たり前です。
心がまったく動かない日があって、当然なんです。
私たちの心は、常に一定の状態を保てる機械ではありません。
空に晴れの日もあれば、雨の日や曇りの日があるように、私たちの心にも、穏やかな日もあれば、どうしようもなく塞ぎ込んでしまう日もあります。
雨の日に、「なんで晴れないんだ!」と空を責めたりはしませんよね。
それと同じように、気分が落ち込んでいる時に、
「どうして自分は前向きになれないんだ」
と、あなた自身を責める必要は全くないのです。
この章で私が一番伝えたいのは、「何もしないこと」「わくわくしないこと」を、
あなた自身が、あなたに許可してあげる勇気のことです。
「不安」と「わくわく」は同じコインの裏表。不安は成長のサイン
わくわくできない原因の一つに、「未来への不安」があるかもしれません。
でも、その「不安」の正体を、少しだけ違う角度から眺めてみませんか?
もし、あなたの未来が、映画の結末のように、100%、寸分の狂いもなく予測できてしまったとしたら…。
それは、本当に「楽しい」と言えるでしょうか。
おそらく、安心はできるかもしれませんが、そこには「わくわく」が入り込む隙間のない、少し退屈な世界が広がっているだけかもしれません。
そう考えると、「不安」とは、「未来がまだ決まっていない」ということの裏返しです。
そして、
未来が不確定だからこそ、そこには、思いもよらない良い方向に変わっていく可能性(=わくわく)も、同じだけ秘められているのです。
心理学の世界に「コンフォートゾーン(快適な領域)」という言葉があります。
私たちが「不安」を感じるのは、この慣れ親しんだ快適な領域から、ほんの少しだけ外の、新しい世界(ラーニングゾーン)に足を踏み出そうとしている時だと言われています。
つまり、あなたが今感じている不安は、あなたがダメな証拠なのではなくて、
現状に留まらず、次のステージへ進もうとしている、とても勇敢な「成長のサイン」なのかもしれませんよ。
心が疲れた時のために。「心の避難場所リスト」を作っておこう
気分が落ち込んでいる時に、「さあ、何か楽しいことをしよう!」と考えるのは、かえって心のエネルギーを消耗してしまいます。
風邪を引いている時に、無理にジョギングをしようとしないのと同じです。
だからこそ、心が元気なうちに、
「いざという時のためのリスト」
を、あらかじめ作っておくことを、私は強くおすすめします。
「心の避難場所リスト」の作り方
-
テーマ 「頭を空っぽにして、ただ“心地いい”と感じられること」
-
3つの条件
-
ほとんどエネルギーを使わない
-
お金があまりかからない
-
すぐにできる
-
【リストの具体例】
-
お気に入りのふわふわの毛布に、ただくるまる
-
好きな香りのハンドクリームを、ゆっくり丁寧に塗る
-
温かいミルクティーを淹れて、窓の外を5分だけ眺める
-
昔、何度も観た好きなアニメの主題歌を、1曲だけ聴く
-
ベランダに出て、静かに深呼吸を3回する
このリストは、あなたのための「心の応急手当セット」です。
心が疲れてしまった日は、無理に何かをしようとせず、このリストの中から一つだけ選んで実行する。
そう決めておくだけで、「どうしよう…」と迷うエネルギーを節約でき、心が回復するための大きな助けになってくれます。
頑張るための方法を知っておくことと同じくらい、
上手に「頑張らない」ための方法を知っておくことは、この長い人生を、しなやかに歩んでいく上で、きっとあなたの心強いお守りになってくれるはずです。
【この章のポイント】
わくわくできない日があって当たり前。そんな日に自分を責めず、「何もしない」ことを許可する。
「不安」は未来が不確定である証拠であり、わくわくと表裏一体。それは「成長のサイン」でもある。
元気なうちに、エネルギーを使わずにできる「心の避難場所リスト」を作っておき、疲れた時に頼る。
【結論】あなたの物語は、いつでも始められる

この記事で伝えてきたのは、未来への「わくわく」は、
どこか遠くにある特別なイベントの中に見つけ出すものではなく、これから読む一冊の本への「期待」のように、あなた自身の手で育むことができる、静かで温かい感情である、
ということ。
そしてそれは、一部の人だけが持つ才能などではなく、誰にでも身につけることができる、ささやかで、だけれどもとても力強い「技術」である、ということでした。
私たちはつい、幸福とは、悩みも不安も何もない、完璧な状態という「ゴール」だと考えてしまいがちです。
でも、もしかしたら、そうではないのかもしれません。
未来にわくわくしながら、
たとえ不安や退屈を感じる日があったとしても、その道のりを自分なりの歩幅で、一歩、また一歩と歩んでいる。
その「プロセスそのもの」こそが、私たちがずっと探し求めていた「幸福」の、本当の姿なのではないでしょうか。
あなたの人生は、一冊の、まだ結末の書かれていない本のようなものです。
その面白さは、いつだって「これから」どうなるか、誰にも分からない、という点にあります。
過去のページがどんな内容であれ、今のあなたがどんな気持ちで立ち止まっていたとしても、次のページをめくるのは、他の誰でもない、あなた自身です。
さて、最後にお願いがあります。
この記事を閉じたら、紙とペン、もしくは
そして、ほんの少しだけ思い出して、
「ちょっと気になっていたこと」を一つだけ、書き出してみませんか?
道端に咲いていた花の名前。
テレビの旅番組で見た、知らない街の地名。
友人が話していた、面白そうな映画のタイトル。
なんでも構いません。
その、たった一行の言葉が、あなたの世界にほんの少しだけ「未知」を取り戻し、未来を少しだけ明るく照らす、最初の小さな灯火になるはずです。
あなたの新しい日々は、その一行から、静かに始まっていきます。
【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、このように日々の生活が少しでも豊かになるような、様々な「考え方」について研究し、発信しています。
もし、ご自身の「幸せ」や「豊かさ」とは何かを、もう少し探求してみたいと感じたら、ぜひ他の記事も覗いてみてくださいね。
あなたの気持ちが少しでも楽になるヒントが、他にも見つかるかもしれません。
引用
ドーパミンの働きに関する知見
引用元: スタンフォード大学の神経科学者 アンドリュー・ヒューバーマン氏
出典: 個人のポッドキャスト 『Huberman Lab Podcast』 の内容
幸福の概念「エウダイモニア(Eudaimonia)」に関する知見
引用元: 古代ギリシャの哲学者 アリストテレス
出典: 著作 『ニコマコス倫理学』
フロー体験に関する知見
引用元: 心理学者 ミハイ・チクセントミハイ
出典: 著書 『フロー体験 喜びの現象学』 (原題: Flow: The Psychology of Optimal Experience) をはじめとする一連の研究
これらの引用元は、記事の主張に科学的・哲学的な根拠を与えるために使用されています。