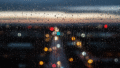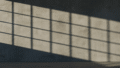自分の人生なのに、なぜか人生に対する主導権を握れていないような、そんな虚しさを感じる…
この記事を読めば、日々の選択に、ざらりとした確かな“手触り”を取り戻せると思うよ。
ここでは難解な哲学を応用し、「みんな」の声からそっと離れ、退屈な日常に自分だけの意味を見出すための、7つの具体的な「思考の型」を解説するね。
それは、哲学者が「世間」に流されず、自分を生きるための本質を、静かに見抜いていたからだよ。
さあ、その心の指針を、一緒に見つけにいきましょう。
ハイデガーの存在論は「日常の違和感」から始まる

朝、鳴り響くアラームを止めたはずのスマートフォンを、あなたは無意識に眺めているのかもしれないね。
他人のきらびやかな日常と、顔の見えない誰かの意見のシャワー。それをただ浴びて、気づけば30分が経っている。本当は、ゆっくりコーヒーでも淹れようと思っていたのに、ということもあるだろう。
あるいは、会社の会議。
場の空気を読んで、一番波風の立たない意見に静かに頷いてみる。
自分の本心とは、ほんの少しだけ違う。
けれど、「みんな」がそちらを向いているから、それでいいことにしてしまうんだ。
そんな風に、まるで自分の人生の運転席に、自分が座っていないような、ふとした違和感。大事な何かが、指の間からサラサラと、静かにこぼれ落ちていくような虚しさ。
そういった感覚、どこかで覚えたことはあるかな?
もしあるのなら、それはあなたの意志が弱いからでも、怠けているからでもないんだよ。
その違和感の正体とは、とてもシンプル。
“世間”や“みんな”という、顔の見えない誰かの声に、いつの間にか自分の時間や選択を明け渡してしまっている。
ただ、それだけのことだね。
これは、現代を生きる私たちが、あまりにも自然に、そして簡単にはまってしまう「見えない罠」のようなもの、と私は考えているよ。
…そして、実は今から100年近くも前に、この「見えない罠」の構造を完全に見抜き、そこから抜け出すための“地図”を描いた哲学者がいたんだ。
それが、マルティン・ハイデガーだね。
うん、「難解」「退屈そう」。
そう思うのも、無理はないよ。
しかし、彼の哲学の核心は、驚くほど私たちの日常に、ぐさりと突き刺さるような、切実な問いかけで満ちているんだ。
この記事では、その難解に見える哲学用語を一つずつ、あなたの日常で使える「思考の道具」へと、丁寧に翻訳していくね。
読み終える頃には、ハイデガーの存在論が、単なる知識ではなく、日々の選択の手触りを取り戻し、当たり前の風景をもう一度、自分自身のものとして味わうための、具体的な「心の指針」に変わっているはずだよ。
さあ、一緒にその道具箱を、そっと開けてみましょうか。
【この章のポイント】
日常で感じる漠然とした違和感や虚しさ。その正体は、「世間」に自分の選択を明け渡してしまっている状態にあること。
ハイデガーの存在論は、その状態から抜け出すための「地図」であり、実践的な「思考の道具」であること。
この記事は、その哲学を、あなたの日常で使える「心の指針」へと翻訳するものであること。
第1部【要点解説】ハイデガーの存在論 -「当たり前」を剥がす思考の地図
ハイデガーの存在論とは?私たちが「ただ、そこにいる」ことの謎
さて、ここからはいよいよハイデガーの思考の中へと、少しだけ入っていこうか。
ハイデガーの「存在論」。
なんだか、とても硬い言葉だね。でも、その問いかけは、驚くほどシンプルなんだよ。
「私たちは、なぜ“いない”のではなく“いる”のか。そして、その“いる”とは、一体どういうことなのか?」
…あまりにも当たり前すぎて、普段は誰も問わないような、そんな根本の謎。それを、じっと見つめること。それが彼の哲学の核心だね。
これは、人生の意味や成功法則をいきなり語る前に、まず「私たちというプレイヤーが立っている、この“いる”という地面そのもの」の性質を、徹底的に調べようとする試み、と言えるかもしれない。
実は、昔の賢い人たち…プラトンなんて呼ばれていたね…彼らはずっと、「存在する“モノ”」(神様とか、善とか、人間とは何か、とか)については熱心に語ってきたんだ。
でも、それら全ての土台にあるはずの「存在そのもの」の謎については、いつの間にかすっかり忘れてしまっていた。ハイデガーは、この状態を「存在忘却」と呼んで、強い危機感を抱いたんだ。
彼の哲学は、この壮大な“忘れ物”を、静かに思い出すことから始まるんだよ。
なぜ、そんなことが私たちにとって重要なのか。
それは、私たちが日常で感じるあの虚しさや違和感の多くが、この「地面」の性質を知らないまま、つまり、自分自身が「どういう風に“いる”のか」を理解しないまま、他人や社会が作った地図だけを頼りに歩いていることから生じているから、と私は考えているよ。
だからハイデガーは、その不確かな地図を一度脇に置き、まず自分自身の「出発点」を、この足元から確認しようとしたんだ。
その出発点となる揺るぎない事実が、次の2つだね。
出発点① 気づけばここにいた。私たちは皆「投げ込まれた」存在(被投性)
少し、あなたのことを考えてみてくれるかな。
あなたが、この時代に、この国で、その家族のもとに生まれたこと。
それらを、あなたは自分の意志で選んだのかな?
おそらく、答えは「NO」だろうね。
この、どうしようもない「選べなさ」。気づいたら人生という舞台に、ある配役としてポンと「投げ込まれていた」という、この感覚。
これこそが、ハイデガーが「被投性(ひとうせい)」と呼んだ、私たちの存在の、第一の動かせない事実なんだ。
この感覚は、まるで「途中から始まる映画」に例えられるかもしれないね。私たちは皆、物語の冒頭を見逃し、気づいたらスクリーンの中に登場人物として放り込まれている。
配役も、時代背景も、すでに決められている。私たちは、その状況から人生を始めるしかないんだ。
「自分探し」という言葉があるけど、それはこの「投げ込まれた」という変えられない事実から目を背けることではないんだよ。
むしろ、この「選べなさ」を、「これもまた、自分なのだ」と静かに認め、引き受けること。
それこそが、自分自身の人生を始めるための、本当のスタートラインになるんだね。
出発点② なぜか不安、なぜか退屈。世界と繋がる「気分」というセンサー
では、投げ込まれたこの世界で、私たちは物事をどうやって認識しているんだろう。ハイデガーの答えは、論理や理屈が先ではない、というものだったね。
その前に、私たちは世界を「気分」として、いわば肌感覚で感じ取っている、と考えたんだ。
- 理由はないけど、なんとなく不安。(これは、特定の対象を持つ日常の「恐れ」とは区別される、根源的な感覚だよ。)
- 今日は、なぜか世界がキラキラして見える。
- 全てがどうでもよくなるような、深い退屈。
これらこそが、私たちが世界と繋がる、最も根源的なチャンネルなのだと彼は言うね。この「気分」は、単にあなたの心の内側だけを映しているのではありません。
むしろ、それは「天気予報」のようなものだと考えてみて。
- 「気分」は、あなたを包む“世界の天気”を知らせてくれる、とても高感度なセンサーなんだ。
- 「不安」という天気は、「あなたの存在が、今、何かに脅かされているかもしれない」という世界のあり方を知らせている。
- 「退屈」という天気は、「目の前のモノや人が、あなたにとっての意味を失っている」という世界のあり方を知らせているね。
多くの人は、特に「不安」や「退屈」といった不快な“天気”を感じると、そこから逃れるために思考を止め、周りの喧騒に紛れてしまおうとする。うん、その気持ちも分かるよ。
そして、この無意識の行動こそが、次の章で解説する、私たちの日常を支配する「ある生き方」へと、私たちを静かに導いてしまうんだ。
【この章のポイント】
ハイデガーの存在論は、「私たちは、どういう風に“いる”のか?」という根本の謎を探求すること。
私たちの出発点は、自分の意志で選んだわけではなく、気づいたら状況の中に「投げ込まれていた」という事実(被投性)にある。
私たちは世界を、論理より先に「不安」や「退屈」といった「気分」を通して感じ取っており、それが次の行動への分岐点となる。
ハイデガーが解き明かす「私」の正体。存在論を構成する3つの本質
「投げ込まれ」、そして「気分」を通して世界を感じている私たち。では、そんな「私」とは、一体どういう特徴を持った存在なのかな。
一般的に、私たちは「私」というものを、世界から切り離されて、部屋の中で腕組みをしながら物事を考える「孤立した魂」のようにイメージしがちだね。しかし、ハイデガーの答えは、全く逆だった。
彼によれば、「私」とは、最初から世界という状況の中にどっぷりと浸かり、モノや他者との具体的な「関わり」の網の目の中にしか、そもそも存在しない、と考えるんだ。
これから解説する3つの本質は、この「関わりの中にいる“私”」の、いわば「取扱説明書」のようなものだと思って、少しだけお付き合いください。
本質①:モノとの「関わり」が「私」を作る。世界内存在という考え方
私たちは、世界を窓の外から客観的に眺めている傍観者ではないね。生まれた瞬間から、空気、重力、言語、文化といった「世界」の中にいて、それらと無関係ではいられない存在だ。
これが、ハイデガーの言う「世界内存在(せかいないそんざい)」の基本的な意味だよ。
少し難しく聞こえるかもしれないけど、これは私たちの日常に、それこそ空気のように満ち溢れている。ハイデガー自身が用いた有名な「ハンマー」の例を、現代的に翻訳してみましょうか。
あなたがハンマーで釘を打つとき、「ハンマーの重さは何グラムで…」などと、いちいち考えないだろう。ハンマーは、まるであなたの“腕の延長”のように、すっと意識から消えている。
ハンマーは、釘を打つという「関わり」の中に、完全に溶け込んでいるんだね。
これは、あなたが今この記事を読んでいる時も、全く同じだよ。スマートフォンは、あなたの“知覚の延長”となり、その存在を意識することなく、あなたは「情報」という世界と関わっている。
この、道具が身体の一部のように、ふっと透明になる状態こそ、「世界内存在」の最も分かりやすい姿なんだよ。
ここから分かる、とても重要なことがあるね。
それは、「私とは何か?」という問いの答えは、自分の頭の中に閉じこもって、うんうんと考えても見つからない、ということだ。
「私」とは、モノや人と関わる、その具体的な「やっていること」の総体。つまり、もし自分を変えたいと願うなら、その「関わり」の方を変えていくしかない。
なんだか、少しだけ希望が湧いてこないかい?
本質②:自らの存在を問う唯一の存在。ダーザイン(現存在)の本当の意味
私たちの周りには、石や机、動物など、たくさんのものが存在しているね。しかし、人間だけが持つ、決定的に特別なあり方がある。
石や机は、ただ「そこにある」だけだ。
それらが自らについて「自分は石でいいのだろうか?」と悩むことは、決してない。
しかし、人間だけは違うね。「このままでいいのか?」「どう生きるべきか?」と、常に自分自身の「あり方」が、自分にとっての「問い」になってしまう。
この、「そこに(Da)」「いる(sein)」こと自体が問いになっている特別な存在を、ハイデガーは「ダーザイン(現存在)」と名付けたんだ。ドイツ語で、Daseinと書くよ。
実は、この記事を読んでいる、まさにその瞬間のあなたも、ダーザインだね。
なぜなら、あなたは単に情報を受け取っているだけでなく、
「この解説は分かりやすいか?」
「これは自分の人生に役立つか?」
と、この記事との“関わり方”を、無意識のうちに常に問い直しているから。
うん、そういうものなんだよ。
つまりダーザインは、完成された「何か」として存在するのではなく、常に「まだ、こうなれるかもしれない」という「可能性」として存在しているんだ。
だからこそ私たちは悩み、迷う。
そしてこの「可能性」というテーマは、次に解説する「時間」と「死」という、私たちの存在の根本的な問題へと、深く、深く繋がっていくんだね。
本質③:「終わり」が「今」を照らし出す。時間性と向き合う死への存在
前の項目で述べた「可能性」とは、未来に向かって開かれている、ということだね。そして私たちは、常に過去(投げ込まれたという事実)を背負っている。
このように、私たちは過去・現在・未来という「時間性」の中に生きている、というより、私たち自身が「時間」そのものなのだ、とハイデガーは考えたんだ。
ここで、一つ思考実験をしてみようか。
もし、人生が無限に続くとしたら、どうだろう?
おそらく、今日の選択は、明日やり直せばいい。どんな決断も「仮のもの」でしかなく、そこに究極の真剣さは、きっと生まれないだろうね。
しかし、現実の私たちには「死」という、誰にも代わってもらえない、絶対に訪れる「終わり」がある。
ハイデガーは、この終わりへと常に向かっている私たちのあり方を「死への存在」と呼んだんだ。これは、決して暗い話ではないんだよ。
むしろ、この「終わり」があるからこそ、私たちの「今」は、かけがえのないものとして輝くのだと考えてみて。
「死」とは、いわば「物語の最終ページ」のようなものだね。最終ページがあるからこそ、そこに至るまでの一文一文が、取り返しのつかない意味を持つ。
死とは、私たちの人生という一度きりの経験に、意味と構造を与えてくれる、ただ一つの“締め切り”なんだよ。
この「締め切り」を意識して初めて、
「残された時間で、自分はどう生きるのか?」
という問いが、本当の切実さを持って、ずしりと、私たちの前に立ち上がってくるんだ。
そして不思議なことに、私たちの心は、この最も重要な問いから、つい目を背けようとしてしまう。その心の動きこそが、次のテーマである、私たちの日常を支配する巨大な力に繋がっていくんだね。
【この章のポイント】
「私」は孤立した存在ではなく、常にモノや他者との具体的な「関わり」の中にいる(世界内存在)。
人間は、ただ存在するだけでなく、自らのあり方を常に問うてしまう特別な存在である(ダーザイン)。
私たちの本質は「時間」そのものであり、「死」という終わりがあるからこそ、「今」という瞬間が意味を持つ(死への存在)。
日常を支配する2つの生き方。あなたは「みんな」か、「私」か
これまでの話を、少しだけ整理させてほしい。
私たちは、選べない過去を背負い(被投性)、いずれ訪れる死へと向かう(死への存在)、時間的な存在(ダーザイン)だね。
そして、そのどうしようもない事実の前に、漠然とした「不安」という気分を抱えている。この状況を踏まえると、私たちの日常は、実は常に2つの道が交わる“分岐点”の連続なのだ、とハイデガーは言うんだ。
その道とは、
匿名の「みんな」の声に判断を預け、責任から逃れる、楽な道。
自分だけの“どうにもならなさ”を引き受け、自ら決断する、困難な道。
私たちは、根源的な不安や、いつか死ぬという重い事実から、一瞬でも目を背けたい、という自然な弱さを持っている。だからこそ、無意識のうちに①の楽な道を選んでしまいがちになるんだね。うん、それは仕方のないことでもあるよ。
ここからは、この2つの道を、ハイデガーの言葉を借りて、もう少しだけ詳しく見ていこう。
道①:不安から逃れるための安易な道。ダス・マン(世人)という見えない支配者
「ダス・マン」とは、ドイツ語でDas Manと書き、日本語では「世人(せじん)」と訳されるね。
この「ダス・マン」という概念は、ハイデガーの主著である『存在と時間』の中で、私たちの日常的なあり方を分析するために導入された、中心的な考え方の一つだ。
これは、特定の誰かや組織のことではないんだよ。それは、「世間ではこう思われている」「普通はこうするべきだ」といった、正体不明の「空気」や「常識」そのものだね。
ダス・マンの本質は、私たち個人から「自分で決断する」という、少し重たい責任を奪い、その代わりに「みんなと同じ」という、心地よい安心感を与えてくれる、実に巧みな交換取引にあるんだ。
このダス・マンは、私たちの日常の、本当にあらゆる場所に潜んでいる。
会議のダス・マン:「誰も反対意見を言わないから、自分も黙でおこう」という、沈黙の同調。
SNSのダス・マン:「“いいね”がたくさん付いているから、きっとこれが正しいのだろう」という、数の論理への、思考の停止。
消費のダス・マン:「レビューサイトで星の数が多いから」という理由だけで、自分のザラザラとした感覚を信じずに商品を選ぶ行動。
ダス・マンは、いわば「平均化するミキサー」のようなもの、と私は考えているよ。
どんなに個性的で新鮮な果物(個人の意見や感覚)も、このミキサーにかかれば、あっという間に角が取れて、誰もが飲みやすいけれど特徴のない“ミックスジュース(世論)”になってしまうんだ。
ダス・マンに身を委ねることは、確かに楽で、一時的な安心をもたらしてくれる。その点は、否定できないね。
しかし、その代償として失うものは、あまりにも大きい。それは、「自分自身の人生を、自分の感覚で生きている」という、かけがえのない“手触り”そのものだからだよ。
道②:「死」を引き受け覚悟を決める道 – 本来性を取り戻すということ
では、ダス・マンから抜け出す、もう一つの道とは何だろう。
それが「本来性」を取り戻す、という生き方だね。
この言葉もまた、『存在と時間』で「ダス・マン」と対比される形で繰り返し論じられているよ。
ここで、一つだけ、とても重要な注意点がある。
「本来性」とは、社会的な役割を脱ぎ捨てた先にいる、どこか遠くにいるキラキラした“本当の自分”を見つけること…ではないんだ。
ハイデガーが言う「本来性」とは、むしろもっと静かで、地味なものだね。
それは、特別な状態になることではなく、ある「態度」や「覚悟」のことを指しているんだよ。
では、何の覚悟か。
それは、これまでに解説した、2つのどうにもならない事実から目を背けない、という覚悟だね。
誰にも代わってもらえない、自分だけの「死」。
自分の意志では選べなかった、自分だけの過去(被投性)。
この2つを、「それら全てを、他の誰でもない“私”のものとして引き受ける」と決める。
その覚悟のあり方そのものが、「本来性」なんだ。
これは、日々の小さな選択の中に、静かに現れる。特別な行動は、必要ないよ。
- 「みんなが勧めるから」ではなく、「私は、これが好きだから」という理由で昼食を選ぶこと。
- 失敗した過去を恥じるのではなく、「あの経験があったから、今の自分がいる」と、自分の物語の一部として認めること。
これらは全て、日々の選択の主語を「みんな」から「私」へと切り替える、静かですが決定的な「本来的な」態度だね。
「本来性」とは、どこかにあるゴールではないんだ。この「引き受ける」という覚悟を持って、一つ一つの選択を自分事として行っていく、その生き方そのものなんだよ。
そして、このダス・マンの強力な引力に抗い、本来的な生き方へと舵を切るための具体的な技術こそが、第2部でご紹介する「思考の型」なんだ。
【この章のポイント】
私たちの日常は、匿名の「みんな」に判断を委ねる道(ダス・マン)と、自分を引き受ける道(本来性)との、絶え間ない分岐点である。
「ダス・マン」とは、「世間の常識」や「空気」のことであり、私たちから決断の責任を奪う代わりに、安心感を与える。
「本来性」とは、特別な自分になることではなく、避けられない「死」や選べなかった「過去」を、全て自分のものとして引き受けるという「覚悟」のことである。
第2部「思考の道具箱」を開ける。哲学を日常という現場で使う
【実践編】ハイデガーの存在論を日常で使える7つの思考の型
さて、第1部では、ハイデガーというガイドと共に、私たちが立っている世界の「地図」を、一緒に手に入れたね。
日常のあの違和感の正体は、顔のない「みんな(ダス・マン)」に人生のハンドルを委ねてしまう、私たちの心の弱さにあること。
そして、そこから抜け出す道は、特別な自分になることではなく、どうにもならない事実(死や過去)を引き受けるという「覚悟(本来性)」にあること。
ここからは、その地図を片手に、あなたの日常という具体的な現場で、自分自身のための一歩を踏み出すための「道具」の話をするね。
なぜなら、地図(理論)をただ頭で理解するだけでは、長年私たちの心と身体に染み付いた「ダス・マンに流される」という、あの強力な引力には、なかなか抗えないからだ。本当に、なかなかね。
この引力に抗い、自分の足でちゃんと立つためには、やはり意識的な「練習」が必要なんだ。
つまり、これからご紹介する「思考の型」という道具を、実際に使ってみることが、どうしても不可欠になるんだね。
これからご紹介する7つの「思考の型」は、大きく3つのステップに分かれているよ。
ステップ1:まず、自分を縛るものの正体に「気づく」ための道具。
ステップ2:次に、小さな行動で「私が決める」感覚を「取り戻す」ための道具。
ステップ3:最後に、人生の有限性と向き合い、「今」を「深く味わう」ための道具。
一つずつ、ゆっくりと、あなたのペースで見ていこう。
注意:これは不安を消す魔法ではなく、「心の体幹」を鍛えるということ
本題に入る前に、一つだけ。とても大切な心構えを、お伝えさせてください。
これからご紹介する思考の型は、あなたの不安や退屈を、都合よく消し去るための「魔法の呪文」ではありません。
では、これは一体何なのか。
私は、これは「心の体幹トレーニング」のようなものだと考えているよ。
体幹トレーニングと同じように、これらは時々面倒に感じられたり、すぐに劇的な変化は感じられなかったりするかもしれないね。うん、正直に言って、そういうものだ。
しかし、もしあなたがこれを少しずつ続けていくなら、外部の圧力(ダス・マンの空気や他人の評価)に簡単にはぐらつかない、しなやかで強い「心の軸」が、あなたの内側に、確かに育っていくはずだね。
第1部で解説したように、私たちが「ダス・マン」に安易に寄りかかってしまうのは、根源的な不安の中で、自分の足だけで立つのが、やはり少ししんどいからだ。
このトレーニングは、その「しんどさ」を引き受けた上で、それでもなお自分の足で立つための、根本的な力を養うためのものなんだ。
ですから、ここでのゴールは、「不安を感じなくなること」ではないよ。
本当のゴールは、「不安や退屈を感じながらも、それに飲み込まれず、自分の意思で次の一歩を選択できるようになること」。
この、より現実的で、より力強い目標を、どうか心の隅に留めておいてください。この心構えを持ってもらった上で、最初のステップに進んでいこうか。
【この章のポイント】
第2部では、第1部で得た哲学の「地図」を元に、日常で使える具体的な「思考の型」という「道具」を解説する。
これらの思考の型は、不安を消すためのものではなく、不安の中でも自分の足で立つための「心の体幹トレーニング」である。
目指すゴールは、ネガティブな感情をなくすことではなく、それに飲み込まれずに、自分の意思で選択できるようになること。
ステップ1:『世間の声』と『自分の声』を区別する。ダス・マンからの分離
最初のステップは、最も地味だけど、最も重要な段階だね。
それは、私たちの思考や選択に、いかに頻繁に「世間の声(ダス・マン)」が、すっと忍び込んでいるか、その瞬間に「あ、今のがそうだ」と気づけるようになること。
ただ、それだけだよ。
これは、無意識の自動操縦状態で動いている心に、「おっと」と静かに声をかけ、意識的な手動操縦へと切り替えるための、最初の認識訓練だと思ってください。
そのための具体的な道具を、2つご紹介するね。
ステップ2:『頭の中』から『現実世界』へ踏み出す。本来性の実践
ステップ1で、自分を縛る「世間の声」の存在に気づけるようになったなら、次はいよいよ、自分自身の「声」を、小さな行動に移してみる段階だね。
といっても、何か大きな決断をする必要は、ここでも全くないよ。
ここでの目的は、長らく自動操縦モードだった心と身体に、「ああ、自分でハンドルを握るって、こういう感覚だったな」という、ささやかながらも確かな「実感」を取り戻させてあげること。
いわば、自分自身の人生の、ちょっとした「リハビリテーション」のようなものだと思って、気楽に取り組んでみてくれるかな。
ステップ3:『目を背けていたこと』と静かに向き合う。有限性の受容
ステップ1で「気づき」、ステップ2で「実感」を手に入れたあなたが、最後に取り組むのは「引き受ける」という、最も静かで、最も力強いステップだね。
私たちが本当に自由になるためには、
コントロールできること(今の選択)に集中するだけでなく、コントロールできないこと(過去や死)を、どうしようもない事実として、静かに受け入れる必要があるんだ。
これは、決してネガティブな諦めではないよ。むしろ、無駄な抵抗から解放され、今この瞬間に自分のエネルギーを注ぐための、積極的な「受容」の技術だと考えてみて。
実践する上での大切な心構え。「うまくできない」と感じるあなたへ
さて、7つの道具をご紹介しましたが、いざ使ってみようとすると、おそらくあなたの心は、巧みに抵抗を始めるだろうね。
- 「主語を『私』に切り替えようとしたけど、結局みんなの意見に流されてしまった…」
- 「『私が決めたこと』を書き出そうとしたけど、今日は一つも見つからなかった…」
そして、こう思うかもしれない。
「結局、私は何も変われないんじゃないか…」と。
もし、あなたがそう感じてしまった時にこそ、思い出してほしい、たった一つの大切な心構えがある。
これらの思考の型において、「失敗」というものはないんだ。
どういうことか?
「ああ、またダス・マンに流されてしまったな」と、その事実に“気づけた”瞬間、あなたはすでに、この思考の型の目的を100%達成しているんだよ。
この思考の型は、「常に本来的にある」ための完璧な人間を目指すトレーニングではないんだよ。
むしろ、私たちは常にダス・マンに流される弱い存在である、という事実を受け入れた上で、その無意識の自動操縦状態から、ふと我に返って「おっと、いけない」と気づく、その“我に返る”回数を少しずつ増やしていくための練習なんだ。
だから、うまくできなかった自分を、決して責めないでください。
「流されてしまった自分」に気づけたなら、「よく気づけたね」と、心の中で自分自身の肩をそっと叩いてあげるような、そんな優しい眼差しを向けてあげてほしいんだ。
その「気づき」そのものが、あなたを無意識の支配から解放する、最も価値のある光だね。
その光を見つけることさえできれば、あなたはもう、以前のあなたではないから。
【この章のポイント】
思考の型を実践する上で「失敗」という概念はなく、「流された自分に気づくこと」そのものが成功である。
目的は完璧になることではなく、「我に返る」回数を少しずつ増やしていくこと。
うまくできない自分を責めず、「よく気づけた」と優しく認めてあげることが、最も大切な心構えである。
まとめ ハイデガーの存在論は、当たり前の日常を「宝物」に変える心の指針

この記事の出発点となった、あの問いに立ち返ってみようか。
「自分の人生の運転席に、自分が座っていないような、ふとした違和感」。
その正体はもう、あなたにはお分かりのはずだね。あの運転席に座っていた見えない誰かの正体こそ、匿名の「世間(ダス・マン)」だった。
そして私たちは、根源的な不安から逃れるために、知らず知らずのうちに、その誰かにハンドルを明け渡してしまっていたんだ。
ハイデガーの存在論は、この「見えない運転手」の存在を私たちに教えてくれる『地図』であり、同時に、自分の手にそっとハンドルを取り戻すための、7つの具体的な『思考の道具』を与えてくれたね。
しかし、誤解しないでください。この道具を手に入れたからといって、明日からあなたの人生が、急にバラ色に変わるわけではないよ。
では、何が変わるのか。
それは、「世界の見え方の“解像度”」だと、私は考えているんだ。
ハイデガーの哲学は、ぼやけていた日常という風景のピントを、ぐっと合わせてくれる、新しいコンタクトレンズのようなもの、と言えるかもしれないね。
- これまでただ通り過ぎてきた、当たり前の風景。
- いつもの通勤路に立つ木々の葉脈の、っとするほどの精緻さ。
- 毎朝飲むコーヒーの湯気が描く、二度とない、ゆらりとした模様。
- 家族が発する何気ない一言の奥にある、言葉にならない、ふわりとした感情。
それらが、かけがえのない、一度きりの「宝物」として、その豊かな質感とともに、あなたの前にふと立ち現れてくる。ハイデガーの哲学がもたらすのは、そんな世界の感じ方の、静かで、しかし決定的な変化だね。
まずは、7つの道具のうち、どれか一つで構わないよ。あなたが一番ピンときたものを、明日、あなたの日常の中で、そっと試してみてほしい。
あなたの人生の主人公は、他の誰でもなく、あなた自身だ。その当たり前で、しかし、かけがえのない事実を、どうか忘れないでくださいね。
さらに探求したいあなたへ。ハイデガー存在論の理解を深めるおすすめ書籍2選
もし、この記事をきっかけに、ハイデガーという、さらに広くて深い森を、ご自身の足で散策してみたくなったなら。
ここでは、最も信頼できる2人の「案内人(書籍)」をご紹介しましょう。
どちらの案内人と歩むかは、今のあなたの心の声に耳を傾けて、決めてみてください。
【この章のポイント】
日常の違和感の正体は、「世間(ダス・マン)」に人生の主導権を渡してしまっていることだった。
ハイデガーの哲学は、その構造を暴く「地図」であり、主導権を取り戻すための「思考の道具」である。
その本質的な価値は、日常の見え方の「解像度」を上げ、当たり前の風景を「宝物」として再発見させてくれる点にある。
このサイトでは、哲学や心理学の知見や思想を応用して、あなたがより幸せや豊かさを感じられるようになるための様々な考え方を研究し、発信しているよ。
もしよろしければ、他の記事も覗いてみてね。
【こちらの記事も読まれています】