「正しいか、間違いか」って、そんな白黒ハッキリした思考に、心の方が少し疲れてきてないかな。
この記事では、あなたの頭を縛る、その見えない鎖をそっと解くための、具体的な四つの「思考の道具」を、お渡しするよ。
それはね、1800年も前から、人の心を静かに支え続けてきた、古くて、でも触れると不思議と新しい知恵なんだ。
よかったら、あなたの日常に、持ち帰ってみてね。
龍樹(ナーガールジュナ)の思想が、「思考の袋路」を抜け出すヒントになる
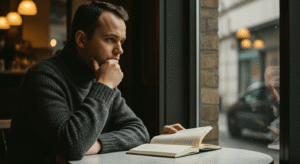
「正しいか、間違っているか」その二択で、迷ってしまうあなたへ
大事な判断を迫られた時。
あるいは、誰かと意見がぶつかって、心がざわついた時。
あなたの頭の中で、「Aか、Bか」「正しいのは、どっちだ」っていう二つの選択肢が、ぐるぐる回り出すことはないかな?
どちらを選んでも、何かを失っちゃうような気がして。
どちらが正解なのか、確信が持てなくて。
まるで出口のない、しんとした部屋を、一人でさまよっているような、あの感覚。
その思考のループにはまっちゃうと、本当に苦しいものだよね。息をするのも忘れちゃうくらいに。
でもね、それはあなたが弱いとか、決断力がないからってわけじゃないんだよ。
むしろ、物事に真剣に、まっすぐ向き合っているからこそ、陥ってしまう。人間が古くから持っている、ごく自然な「思考のクセ」みたいなものなんだ。
この記事で手に入る、あなたの「思考の土台」を更新する知恵
この記事では、そのどうしようもない「思考のクセ」そのものに、そっと光を当てて、あなたの思考の土台を新しくしていくための、具体的で、地に足のついた知恵をお渡しするよ。
具体的には、読み終える頃には、あなたは、こんなもの手にしているはずだよ。
1800年前の龍樹の思想が、なぜ現代の私たちの心に響くのか、その理由がわかる。
心を縛る固定観念や白黒思考から自由になるための、4つの具体的な「思考の道具」が手に入る。
日々の悩みやストレスに対する「見え方」そのものが変わり、気持ちが楽になる感覚を掴める。
この記事は、まず前半で龍樹の思想の全体像を、そして後半で、それを日常でどう使うかっていう実践的な道具について、順を追って解説していくね。
難しい哲学用語を、覚える必要はないよ。
あなたの日常の感覚に引きつけながら、ゆっくりと話を進めていくから、どうか安心してね。
【この章のポイント】
多くの人が、無意識に「白黒思考」のクセに陥り、知らず知らずのうちに心をすり減らしている。
その苦しみは、性格や能力の問題ではなく、誰にでもある「思考のクセ」が原因であることが多い。
この記事では、その「思考の土台」そのものを新しくしていくための、龍樹の思想に基づいた具体的な知恵を解説していく。
龍樹(ナーガールジュナ)の思想。その核心「空・縁起・中道」をわかりやすく解説
さて。
ここからは、いよいよ龍樹の思想の核心に、そっと触れていこう。
彼の考え方は、一見すると、少し掴みどころがないように感じるかもしれない。
でも、その一つひとつの言葉の奥には、私たちが日常で感じる、あの言いようのない生きづらさを、根元から解きほぐすための、ものすごく深い知恵が隠されているんだ。
まず龍樹とは誰か? 1800年前に「思考のクセ」を見抜いた天才
龍樹とは、一言で言えば「思考の革命家」。
そんな人だよ。
彼が生きたのは、今からおよそ1800年〜1900年ほど前の南インド。
当時の仏教界は、お釈迦様の教えが細かく、学問的に分析されすぎて、なんだか本来のいきいきとした力が失われかけている。そんな空気が漂っていた時代だった。
龍樹は、その澱んだ空気に、鮮やかな一石を投じるんだ。
難解になっちゃった教えを、見事な論理で磨き上げ、大乗仏教の重要な基礎を確立したことから、「第二の釈迦」とまで呼ばれるほどの、大きな新しい流れを作った。日本の多くの仏教宗派が、その源流をたどると、彼の思想に行き着くことから、「八宗の祖」っていう尊称で呼ばれているね。
…と、ここまで聞くと、なんだか完璧な聖人のように聞こえるかもしれない。
でも、彼にはとても人間味あふれる、少しやんちゃな伝説も残っているんだよ。
若い頃、仲間と共にお城の女性たちの部屋に忍び込んだことが見つかり、友人たちが斬り殺されるのを目の当たりにしてしまった、とかね。その経験から、欲望の恐ろしさを骨身にしみて感じ、仏教の道に入った、と伝えられている。
それが本当かどうかは、今となっては誰にもわからない。
でも、そんな彼も、私たちと同じように迷い、過ち、傷ついた経験を持つ一人の人間だったのかもしれない。
そして、そんな彼が生涯をかけて探求したのが、私たち人間をときに苦しめる、あのどうしようもない「思考のクセ」の正体だったんだ。
「空」とは何か? 「何もない」という大きな誤解を解く
龍樹の思想と聞いて、多くの人が「空(くう)」という言葉を思い浮かべるかもしれない。
そして同時に、「何もない、虚しいこと」といった、どこか冷たくて、寂しいイメージを持っているんじゃないかな。
もしそうだとしたら、それは本当にもったいない誤解だよ。
龍樹が伝えたかった「空」は、私たちの熱や可能性を奪うような、冷たい考え方じゃない。
むしろ、私たちをがんじがらめに縛りつけるあらゆる固定観念から解き放ってくれるための、希望に満ちた、とってもダイナミックな視点なんだ。
縁起で理解する「空」の本質。すべての物事は「関係性」の網の目である
では、「空」の本当の意味とは何か。
その鍵を握っているのが、「縁起(えんぎ)」という言葉だね。
これは、「すべての物事は、それ単独で孤立して存在しない。無数の原因や条件が相互に依存しあって成り立っている」っていう、この世界の法則を指す言葉。
…少し、難しく聞こえたかな?
じゃあ、あなたの目の前にある一杯のコーヒーを、思い浮かべてみて。
そのコーヒーは、ただ「そこ」にぽつんとあるわけじゃ、ないよね。
一粒のコーヒー豆があり、きれいな水があり、豆を育てた農家の人の汗があり、それを遠くまで運んだ人がいて、香ばしく焙煎した人がいる。あなたがそれを淹れるための静かな時間と知識があって、その温かさを受け止めるカップがあって…。
数えきれないほどの条件、つまり「縁」が、奇跡のように集まって、初めてその一杯は、あなたの目の前に存在している。どれか一つでも欠けていたら、それはもう、そのコーヒーでは、なくなってしまう。
この視点を、今度はそっと、あなた自身に向けてみよう。
「私」という存在も、全く同じなんだよ。
両親がいて、これまで口にしてきたたくさんの食事があって、受けた教育や、心を交わした友人、ふと開いた本、今いるこの社会…。そのすべてが複雑に絡み合って、今の「私」を形作っている。
つまり、カチッとした「コーヒー」っていう実体があるわけではないように、カチッとした「私」っていう不変の実体があるわけでもない。
どんなものにも「コレ」っていう不変な本体はない。すべては、巨大な関係性の網の目の中で、絶えずゆらぎ、変化し続けている。
これこそが、龍樹が伝えたかった「空」の、本当の温度感なんだ。
白黒思考を超える「中道」という、しなやかな思考法
この「空」という、すべてが関係性であるっていう視点に立つと、もう一つの大事な考え方、「中道(ちゅうどう)」が見えてくるよ。
「中道」と聞くと、「真ん中」とか「どっちつかずの曖昧な態度」をイメージするかもしれないけど、龍樹の言うそれは、単なる妥協や曖昧さとは全く違う。
彼の言う「中道」とは、「両極端な見解に、カチコチに固執しない、しなやかな立場」のことなんだ。
私たちはつい、物事を「有るか/無いか」「善か/悪か」「成功か/失敗か」といった、二つの箱にきっちり分けて考えたくなるよね。その方が、なんだかスッキリする気がして。
龍樹は、そのどちらの立場にも偏らないことの重要性を説いた。
「絶対に存在する」っていう見方も、「どうせ何もない」っていう見方も、どちらも物事の一つの側面に過ぎない、とね。
これはまさに、私たちが日常で陥りがちな、あの息苦しい「白黒思考」から自由になるための考え方だよ。
どちらか一方の正しさにしがみつくのではなく、その間にある、もっと豊かで、広くて、曖昧な現実を、そのまま見つめてみる。
それが「中道」っていう思考法なんだ。
【考察】現代科学は、1800年かけて龍樹の慧眼に追いついた
ここまでの解説で、龍樹の思想の奥深さを、少し感じてもらえたかもしれないね。
でも、彼のすごさは、それだけにとどまらないんだ。
驚くべきことに、彼が1800年も前にたった一人で見抜いていたことは、現代の科学が、ようやく解き明かし始めた人間の思考の本質と、面白いほどに、ぴたりと一致する。
なお、この記事での解説は、龍樹の広大で深遠な思想を、あくまで「現代の私たちが日常で実践的に活用する」という視点から光を当てた、一つの解釈だよ。
認知心理学とのつながり
龍樹は、私たちが言葉によって世界を分断し、「これはこうだ」と決めつけること(戯論)が苦しみを生む、と指摘した。
これ、現代の認知心理学でいう「ラベリング」や「認知バイアス」の問題と、本質的な洞察が驚くほどに通底しているんだよ。
私たちの脳は、複雑な世界をなんとか理解するために、無意識に単純なレッテルをペタペタと貼っていく。でも、その便利なはずのレッテルが、かえって私たち自身の視野を狭めて、不自由にさせてしまう。
龍樹は、そのことに、ずっと昔から気づいていたんだね。
システム思考とのつながり
「すべては関係性(縁起)の網の目である」という考え方は、現代の経営学などで重視される「システム思考」っていう考え方に、本当にそっくりだ。
問題が起きた時、その原因を誰か一人のせいにしたり、一つの出来事のせいにしたりしない。「そもそも、この問題を生み出している全体の構造や関係性は、どうなっているんだろう?」と考える。
この視点は、複雑な現代社会を生き抜く上で、ものすごく重要な考え方とされているんだ。
龍樹は、特別な観測装置も何もない時代に、ただ深い思索だけで、人間の思考の構造や世界のあり方を、驚くほど正確に見抜いていた。
そう考えると、彼の思想が、古いどころか、むしろ現代がようやく追いついてきた、普遍的な知恵だっていうことが、お分かりいただけるんじゃないかな。
【この章のポイント】
龍樹は、1800年前に人間の「思考のクセ」の本質を見抜いた「思考の革命家」である。
「空」とは虚無ではなく、「すべての物事は、関係性(縁起)のなかで成り立っている」という世界の真実を示す言葉。
「中道」とは、私たちが陥りがちな「白黒思考」から自由になるための、両極端に偏らないしなやかな思考法のこと。
これらの思想は、現代の認知心理学やシステム思考とも一致する、非常に普遍的でパワフルな知恵である。
龍樹(ナーガールジュナ)の思想から生まれた、心が軽くなる4つの思考技術
さて、ここからが本題。
前半で学んだ龍樹の深遠な知恵を、あなたの日常で今すぐ使える、具体的な「思考の道具」へと、一つひとつ翻訳していこう。
思想を、ただの知識で終わらせない。
明日からのあなたの日々の物事の見方・捉え方を少しだけ、変えてみる。
そんな実践的なステップに、一緒に進んでいこう。
自分自身の心の働きに、優しく気づくための「作法」や、続けていくことで自然と心が整っていく「習慣」のようなものだと、捉えてみてね。
STEP1:思考の渦から抜け出す「思考のライブ実況」の技術
これは、頭の中の、あの止まらないおしゃべりを、まるで他人事のように、ただ眺めるための技術だよ。
一つの失敗をきっかけに、「どうしてあんなことを…」「もうダメだ…」なんて、同じ思考がぐるぐると頭の中を駆け巡って、ずーっと悩んで不安になる。
そんな時は、心の中で、スポーツ実況を始めてみるんだ。
「おっと、ここで『自分はなんて無能なんだ』という思考が、力強く湧き上がってきました!これは強烈な自己批判ですねー!」
「ああ、それに伴って、胸のあたりが、なんかこう、きゅーっと締め付けられるような感覚も出てきた!不安という感情の波が、静かに押し寄せています!」
ポイントは、良い悪いの判断を、一切しないこと。
「なんてダメな思考なんだ」とジャッジするのではなく、「“ダメだ”という思考が、今ここに現れたな」と、ただ、客観的に観察する。本当に、ただそれだけだよ。
なぜ、こんなシンプルなことで効果があるのか。
それは、龍樹の「空」の思想に基づいているんだ。思考や感情もまた、様々な条件によって生まれては消えていく、実体のない、ゆらゆらとした現象にすぎない。
実況することで、暴れる思考と、本来の穏やかなあなた自身との間に、一枚、薄いガラスの壁が生まれるんだ。その距離が、あなたを感情の渦から、そっと救い出してくれる。
ちなみに、これは現代の心理療法(ACT)で「脱フュージョン」と呼ばれる技法と、本質的には全く同じことなんだよ。古代の知恵が、今もこうして、人の心を支えているんだね。
STEP2:自分を縛る決めつけを無力化する「ラベル剥がし思考」
これは、自分や他人に、無意識のうちにペタペタと貼っている「レッテル」を、一枚ずつ、意識的に剥がしていく作業だね。
「私は、どうせプレゼンが下手だから」
「あの人は、何を言っても話が通じないタイプだから」
私たちは日常的に、こんな風にレッテルを貼って、複雑な物事を単純化してしまいがち。だって、その方が楽だから。
でも、その一言が、気づかないうちに、あなた自身の可能性を、ぎゅっと縛りつけているかもしれない。
この思考法は、とてもシンプルだよ。
まず、自分が貼っているラベルに気づく。 例:「私は、人前で話すのが苦手だ」
次に、そのラベルに当てはまらない「例外の事実」を思い出してみる。 例:「でも、そういえば先月のチームミーティングでは、自分の意見をしっかり言えたな…」「親しい友人との会話は、むしろ好きな方だ」
最後に、ラベルをより現実に即した「事実」に、そっと書き換えてあげる。 例:「私は、“準備が不十分で、よく知らない人が大勢いる場では”、人前で話すのが苦手だと感じることがある」
どうかな。
「私は人前で話すのが苦手だ」っていう、まるで変えようのない「性質」が、「準備」や「環境」といった、対処可能な「状況」の問題に、すっと変わったのがわかるかな。
これもまた、「どんなものにも固定的な本質はない(無自性)」という龍樹の思想に基づいているんだ。
あなたが貼ってしまったラベルは「嘘」じゃない。でも、「全体の一部分」に過ぎないんだよ。
木を見て森を見ず。だね。
そのことに気づくだけで、世界はもっと、ずっと柔軟に見えてくるはずだよ。
STEP3:完璧主義を手放す「グラデーション思考法」
これは、物事を「点」ではなく、なめらかな「線」で捉えるための視点だね。
私たちはつい、「成功か、失敗か」「100点か、0点か」っていう、デジタルな思考に陥りがちだ。99点の素晴らしい出来でも、たった一つのミスで「ああ、もう全部ダメだ」と、あっけなく0点にしてしまう。
完璧主義な人ほど、この、息が詰まるような苦しさを、よく知っているかもしれない。
そんな時は、二つの点の間に、美しい色のグラデーションをイメージしてみて。
例えば、あなたが提案した企画が、会議で通らなかったとする。
白黒思考だと、これはもう、くっきりとした「失敗=0点」だ。
でも、グラデーション思考法では、こう考えるんだ。
「完全に通った状態が100点だとして、今の状況は、このグラデーションのどの辺りだろう? 部長は熱心に聞いてくれたし、Aさんからは良い質問ももらえた。じゃあ、今は30点くらいの地点かな。次は、指摘されたコスト面を補強して、もう少し明るい色の方へ、40点を目指してみよう」
このように考えることで、「失敗」という終着点が、「次につながる、ただの現在地」に変わるんだ。
これは、両極端な見方を離れる龍樹の「中道」の考え方を、日常で使いこなすための、ものすごく実践的な方法だよ。完璧な計画を一度で作ろうとするのではなく、小さな改善を、ただ繰り返していく。
これは、現代のビジネスで重視される柔軟な働き方にも、どこか通じるものがあるね。
STEP4:人間関係の悩みの根源に気づく「“私”抜きでの状況描写」
これは、問題の視点を「個人」から「関係性」へと、がらりとシフトさせる、少し面白い技術だね。
人間関係の悩みのほとんどは、「私」っていう主人公の視点から、世界を見ていることで生まれる。「なぜ“私”をわかってくれないんだ」「“あの人”のせいで、うまくいかない」…と。物語の主人公は、いつも自分。
そんな時は、一度、その物語から登場人物を、そっと消してみよう。
例えば、「上司が私の意見をいつも否定する」っていう、苦しい悩みがあったとする。
ここから「私」と「上司」を抜いて、ただそこで起きている「現象」として、カメラで撮るように描写してみるんだ。
「会議の場で、Aという意見が提示された。それに対して、Bという反対意見が出された。その結果、議論の流れはBの方向に進んだ」
どうだろうか。
個人の感情や意図を一度脇に置くと、
「なぜ、この場ではBの意見が通りやすいんだろう?」
「会社の評価基準が何か影響しているのかな?」
「そもそも、Aの意見の伝え方に、もう少し工夫の余地はなかったか?」
と、その現象を生み出している背景、つまり「関係性」や「システム」に、自然と目が向くようになる。
これこそ、すべては相互依存の関係性で成り立っている、という龍樹の「縁起」の視点そのものなんだ。
誰か一人を責めるっていう、不毛で、苦しいループから抜け出し、問題の構造そのものに働きかける。
これは、現代の組織論でいう「システム思考」とも、全く同じアプローチなんだよ。
【この章のポイント】
龍樹の思想は、現代の私たちが日常で使える、4つの具体的な「思考の道具」に応用できる。
STEP1:思考のライブ実況 → 思考の渦から客観的に距離をとるための作法。
STEP2:ラベル剥がし思考 → 自分や他人を縛る固定観念を無力化する作法。
STEP3:グラデーション思考法 → 白黒思考や完璧主義から自由になるための作法。
STEP4:“私”抜きでの状況描写 → 問題の視点を「個人」から「関係性」へと転換する作法。
【重要】龍樹(ナーガールジュナ)の思想を実践する上での「壁」の乗り越え方
ここまでの思考技術を読んで、「なるほど」と思う一方で、「でも、それができれば苦労はしない」って思うよね。
その感覚は、とっても大切なものだよ。
どんなに素晴らしい道具も、初めて手にした日から、すぐに使いこなせるわけではないんだ。この章では、その実践の過程で、誰もがきっとぶつかるであろう「壁」を乗り越えるための、現実的で、地に足のついたヒントを、いくつかお伝えするね。
わかっていても実践できない時の考え方
結論から言えば、わかっていても、すぐに実践できないのは、当然のことだよ。
だから、どうか、そんな自分を「意志が弱い」なんて責めないであげてほしい。
私たちの長年の思考のクセは、まるで、毎日たくさんの車が走り続けて、深く、固く舗装されてしまった高速道路のようなもの。あまりに慣れているから、何も考えなくても、自動運転のように、気づけばその道を走ってしまっているんだ。
一方で、新しい思考法を試すのは、まだ誰も通ったことのない草むらに、そっと一歩を踏み出すようなものなんだよ。
足元はふかふかで歩きにくいし、すぐに見失ってしまう。だから、ふと我に返ると、いつもの見慣れた高速道路に戻ってしまっている。
これはもう、本当に仕方のないことなんだ。
これらの技術は、「一度聞けばマスターできるテクニック」じゃない。
むしろ、スポーツや楽器の練習、あるいは、ゆっくりとした筋トレに似ている。
続けることで、少しずつ、少しずつ、脳に新しい神経の道が、か細くできていく。そんなイメージだよ。
だから、完璧を目指さなくて大丈夫。
「ああ、また、いつもの考え方をしてしまったな」と、そのことに後から気づけただけで、それはもう、大きな、大きな一歩なんだから。
「できない自分」を責めそうになった時の、唯一の対処法
実践がうまくいかない時、私たちを最も苦しめるのは、失敗という事実そのものでは、ないんだよね。
その後に、頭の中に、冷たく、大きく響いてくる「やっぱり自分はダメだ」っていう、あの自己批判の声だよ。
そんな時こそ、どうか思い出してほしい。
あなたがこの文章で、最初に学んだ、あの技術を。
「あ、今、『できない自分はダメだ』という思考が、湧いてきたな」
「自己批判の声が、ものすごく大きく響いている。そっか、そう感じているんだな、私は」
…そうだよ。
その自分を責める、鋭い声すらも、ただ、静かに「ライブ実況」してしまえばいいんだ。
これは、失敗のループから抜け出すための、最も効果的で、いつでも使える、あなただけのセーフティネットになる。
自己批判という思考の渦に、無防備に飲み込まれるのではなく、それを観察の対象にしてしまう。
うまくいかなくて落ち込みそうな時こそ、この技術は、あなたの心守ってくれるはずだよ。
よくある誤解①「努力しても無意味」というニヒリズムの罠
龍樹の思想を学んでいくと、ごく一部の人が、「どうせ全ては“空”なのだから、何をしても結局は無意味だ」っていう、深い虚無感に陥ってしまうことがある。
だけど、それは「空」の思想を、本来の意図とは全く逆の方向に解釈してしまった時に起こる誤解だよ。
龍樹の教えは、「結果はどうでもいい」ということではないんだ。
「結果を、あなたがコントロールしようと必死に執着する、その、握りしめた拳の苦しみから、自由になりなさい」ということなんだよ。
例えば、大事なプレゼンを控えているとする。
「絶対に成功させなければ」と結果に執着すると、プレッシャーで体が石のように硬くなり、かえって本来の力が、出せなくなってしまう。
一方で、「結果は、相手やその場の空気など、自分ではコントロールできない要素も大きい。自分にできるのは、ただ、目の前の準備に、心を込めて全力を尽くすことだけだ」と考える。
すると、不思議と肩の力が抜けて、目の前の作業に、深く、静かに集中できる。結果として、良いパフォーマンスに繋がりやすくなるんだね。
これは、優れたスポーツ選手が「ゾーンに入る」感覚にも、どこか似ている。
結果への執着を手放すことは、決して諦めではないよ。
むしろ、今この瞬間の行動の質を、最大限に高めるための、最高の集中法なんだ。
よくある誤解②「現実から目を背けるための言い訳」という勘違い
もう一つの危険な誤解は、「どうせ縁起(関係性)なのだから、自分一人が頑張っても、どうせ何も変わらない」と、この思想を「責任逃れの言い訳」に使ってしまうことだね。
これも、本来の意図とは全く逆の捉え方だよ。
縁起という美しい言葉を、「自分の無力さの証明」にしてはいけない。
龍樹の思想が教えてくれるのは、「責任の放棄」ではなく、「責任の、より賢明な再定義」なんだ。
どういうことか。
私たちはつい、問題が起きると「誰かのせいだ」と、特定の個人を責めることで、責任を取ったような気になる。でも、それは多くの場合、根本的な解決にはならず、ただ新しい憎しみを生むだけだったりする。
そうではなく、「この問題を生み出している、全体の構造(関係性)のどこに、そっと働きかければ、最も効果的に、全体の流れを良い方向に変えられるだろうか?」と考える。
これこそが、縁起の視点に立った責任の取り方だよ。
優れたリーダーが、部下のミスをただ感情的に叱責するのではなく、同じミスが二度と起こらないための「仕組み」や「環境」を整えるのに似ているね。
この思想は、あなたを無力感に導くものではない。
むしろ、複雑に絡み合った状況を本質的に打開するための、「最も賢明で、優しい介入点」を見つけ出すための、極めて戦略的な視点を、あなたのその手に与えてくれるものなんだ。
【この章のポイント】
「できない自分」を責める声すらも、「思考のライブ実況」の対象にしてしまうことで、心の平穏を保つことができる。
龍樹の思想は、「諦め」や「責任逃れ」の哲学ではない。むしろ、より質の高い行動と、より本質的な問題解決へと私たちを導く、非常に前向きな知恵である。
まとめ。龍樹(ナーガールジュナ)の思想を、あなたの「心の指針」にするために
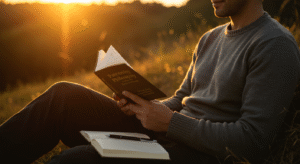
ここまで、1800年前に生きた天才、龍樹の思想の本質と、それを現代で使いこなすための四つの思考の道具、そして実践の壁を乗り越えるための考え方について、一緒に見てきたね。
最後に、この記事でお伝えしたかった、特に大事なことを、もう一度だけ、振り返ってみようか。
【この記事のポイント】
全ての物事は、それ単独でポツンと存在するのではなく、無数の関係性(縁起)のなかで、ゆらぎながら成り立っている(=空)。
だからこそ、「こうあるべきだ」という固定観念や、「白か黒か」という二元論の苦しさから、私たちはいつでも自由になれる。
そのための具体的な道具が、4つの思考の作法(観察する・ラベルを剥がす・視点を変える・“私”を手放す)である。
この知恵は、一度きりの知識ではないよ。
これからあなたが人生を歩む上で、迷ったり、心が苦しくなったりした時に、いつでも立ち返ることができる、静かな「心の指針」のようなものになるはずだ。
最後に、この記事を閉じる前に、あなたに一つだけ、試してみてほしいことがある。
四つの道具を、全て完璧に実践する必要は、まったくないよ。
ただ、今日この後、何か一つでも、あなたの心にチクッとするようなネガティブな思考が浮かんだら、
「あ、今、思考が、湧いてきたな」
と、心の中で一度だけ、そっと実況してみる。
本当に、それだけでいいんだ。
そのたった一度の、小さな「気づき」が、あなたの思考の土台を、これから少しずつ、でも確実に新しくしていく、はじめの、そして、ものすごく大きな一歩になる。
完璧にできなくても、全く構わない。そのことに、ただ気づけただけで、もう、100点満点だ。
龍樹の思想は、あなたを縛るための、新しいルールじゃない。
むしろ、あなたをあらゆる苦しみから解き放つための、頼れる道具なんだよ。
どうか、あなた自身を自由にするために、彼の知恵を、あなたのペースで、あなたのやり方で、自由に使ってみてね。
さらに探求したいあなたへ もし、この記事をきっかけに、龍樹や仏教の思想をもっと深く知りたいと感じたなら、いくつかの本が、あなたの好奇心を満たす、良い入り口になるかもしれないね。
【参考文献】
『般若心経・金剛般若経』中村元・紀野一義(岩波文庫) 龍樹の思想の根幹にある「空」の考え方を、多くの人に親しまれているお経と共に、深く味わうことができる。仏教学の大家による解説は、非常にわかりやすいよ。
『龍樹』中村元(講談社学術文庫) 龍樹という人物の生涯と思想の全体像を、本格的に、かつコンパクトに知ることができる一冊。
このサイトでは、こうした古今東西の知恵を手がかりに、私たちが日々をより幸せに、そして豊かに生きていくための「考え方」や「物事の捉え方」を探求しているよ。
もし、興味があれば、他の記事も覗いてみてくれると嬉しいな。
きっと、新しい発見があるはずだよ。
【こちらの記事も読まれています】



