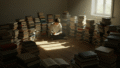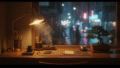「全然満足できない!」
そんな風に感じることはありませんか?
この記事では、
あなたの内なる「欲求」を、人生を最高に味わうエネルギーに変える、とてもシンプルな考え方のヒントを、
一緒に探していきます。
読み終える頃には、他人と比べるしんどさから解放され、何気ない日常が、少しだけよく見てくるはず。
さあ、あなただけの「人生の味わい方」を見つけにいきましょう。
なぜ、頑張っているのに心が「乾く」のか?
「足るを知る」=「諦め」? 7割が抱える、向上心の罪悪感
「足るを知る」。
昔から伝わる、とても賢明な言葉ですよね。
でも、この言葉に、どこか「もうこれ以上、望んではいけないよ」と、自分の可能性に蓋をされてしまうような、そんな窮屈さを感じたことはないでしょうか。
『足るを知る』という言葉から
- 成長の諦め
- 現状維持
といったネガティブなイメージを受けると思うんです。
これって、本当に根深い問題だと思うんです。
私たちは、常に自分をアップデートし、昨日より今日、今日より明日と、より良い自分であろうと努力している。
それなのに、「もっと良くなりたい」と願う自分に対して、「今の自分に満足できないなんて、私はなんて欲深いんだろう…」と、罪悪感を抱いてしまう。
私は、この状態を「向上心のジレンマ」と呼んでいます。
前に進みたいアクセルと、現状に留まろうとするブレーキを同時に踏み込んでいるような、本当にしんどい状態ですよね。
このジレンマこそが、私たちの心が、知らず知らずのうちに乾いていく、最初の、そして最も大きな原因の一つなのです。
あなたの”味わう力”を奪う、現代社会に潜む「2つの怪物」
では、なぜ私たちはこれほどまでに「向上心のジレンマ」に苦しめられてしまうのでしょうか。
その犯人は、あなたの心の中にいるのではありません。
私たちの生きるこの現代社会に静かに潜み、あなたの“味わう力”を、音もなく喰い尽くしていく
…私には、その正体がまるで「2匹の怪物」のように見えるのです。
一匹目の怪物の名前は、「SNS」です。
朝の通勤電車で、ランチの片手間に、そして眠る前のひとときに。
私たちは、もはや息をするように、SNSを眺めています。
そこには、同僚の華々しい昇進報告、友人のきらびやかな海外での写真、完璧に整えられた誰かの暮らしが、次から次へと流れてきますよね。
SNSは、他人の人生の「最高の瞬間だけを巧みに編集した、きらびやかな予告編」を、24時間365日、強制的に見せ続けられているようなもの。
それに対して、自分の人生は、うまくいかない舞台裏も、退屈な準備期間も全部含んだ、一本の長編ドキュメンタリーです。
自分の人生が、色褪せて見えてしまうのも、ある意味、当然のことなのかもしれません。
この怪物がもたらす最も恐ろしい害悪は、私たちが、自分の価値を「他人との比較」でしか測れなくなること。
自分の中にある絶対的な価値を見失い、「人生の相対評価」という、終わりのない地獄に迷い込んでしまうことなのです。
そして、もう一匹の怪物は、一見すると私たちの味方のような顔をしています。
その忌まわしき奴の名は、「タイパ(タイムパフォーマンス)至上主義」。
もちろん、時間を効率的に使うことは、忙しい毎日を乗り切る上でとても大切なスキルです。
私自身、その恩恵にあずかっていることは否定しません。
しかし、少しだけ立ち止まって、考えてみてほしいのです。
私たちはいつの間にか、食事を「作業」としてこなし、映画を「情報」として倍速で摂取するように、
かけがえのない「人生」そのものを、ただ消化すべきタスクのように「消費」してはいないでしょうか?
脳科学の世界では、効率や目標達成を求める「ドーパミン的幸福」と、今この瞬間の充足感を味わう「セロトニン的幸福」があると言われます。
タイパの過度な追求は、前者を過剰に刺激し、後者を感じるための、いわば「心の筋肉」を衰えさせてしまう危険性があるのです。
人生の“旨味”とは、タイパとは真逆の、
手間や余白、待つ時間の中にこそ、その本質は宿っているのかもしれません。
この2匹の怪物によって、私たちの内なる「味わうセンサー」は、知らず知らずのうちに麻痺させられてしまっている。
頑張っているのに心が乾いていく、その根本的な構造は、ここにあります。
でも、どうか諦めないでください。
この怪物たちの正体を知った今、あなたはすでに対策の第一歩を踏み出せています。
次の章からは、彼らからあなたの心を守り、人生の主導権を取り戻すための、古代から受け継がれる「哲学」という名の強力な武器を、一つひとつ、あなたに授けていきます。
第1章【哲学の光】「質の高い欲求」だけが、あなたの魂を救う
序章でお話しした、私たちの心を蝕む「2匹の怪物」。
では、私たちは彼らと、一体どう戦えばいいのでしょうか。
そのヒントは、驚くことに、今から2000年以上も昔、古代ギリシャの青空の下で、一人の賢人がすでに示してくれていました。
彼の名は、アリストテレス。
現代にまでその名が轟く大哲学者が遺してくれた「幸福」についての深い洞察は、情報に溺れ、時間に追われる現代の私たちにこそ、一筋の光を投げかけてくれます。
古代哲学の答え アリストテレスが喝破した「偽物の幸福」と「本物の幸福」
アリストテレスは、私たちが追い求める「幸福」には、実は2種類があることを見抜いていました。
一つは、すぐに消えてしまう、脆い幸福。
そしてもう一つは、魂の奥底からじんわりと湧き上がってくる、揺るぎない幸福です。
① 偽物の幸福(ヘドニア)
これは、感覚的で、すぐに手に入る「快楽」のこと。
「ミクロ快楽」みたいに私は思っています。
美味しいケーキを食べる、SNSでたくさんの「いいね」をもらう、欲しかった洋服を手に入れる…。
心が浮き立つような、嬉しい瞬間ですよね。
でも、その高揚感は、残念ながらあまり長続きはしません。
ケーキは食べればなくなりますし、新しい「いいね」はすぐに過去のものになる。
これは、いわば「消費する幸福」です。
次から次へと新しい刺激を求めないと、すぐに心が渇いてしまいます。
② 本物の幸福(エウダイモニア)
一方、こちらは少し趣が異なります。
例えば、ずっと苦手だったスキルを練習の末に習得する、自分の知識や経験で誰かの悩みを解決してあげる、試行錯誤の末に、納得のいく何かを創り上げる…。
これらは、自分の持てる力を最大限に発揮し、
「より善い自分であろうとするプロセス」そのものから得られる、静かで、持続的な喜びです。
アリストテレスは、これを「エウダイモニア」と呼びました。
これは、消費されることのない、「育てる幸福」と言えるかもしれません。
こちらは「マクロ快楽」とでも呼びましょう。
少し、胸に手を当てて考えてみてください。
最近、あなたが「幸せだな」と感じた出来事は、「消費する幸福」でしたか?
それとも、「育てる幸福」でしたか?
どちらが良い悪いという話ではありません。
ただ、もしあなたの心が乾いていると感じるなら、それはきっと、「消費する幸福」ばかりに目を向け、「育てる幸福」という、魂にとっての栄養が、少し不足しているというサインなのかもしれませんね。
【本記事の核心】「良い欲求」と「悪い欲求」を分ける、たった一つの絶対的な基準
では、私たちの心に次々と湧き上がる欲求が、「偽物の幸福」につながるのか、それとも「本物の幸福」につながるのか。
それを見分ける、シンプルで、でもとても強力な方法はあるのでしょうか?
答えは、驚くほど簡単です。
その欲求が「どこからやって来たか」という源泉を、じっと見つめるだけです。
悪い欲求(他人軸の欲求)
その源泉は、常に「あなたの外側」にあります。
「あの人よりも稼ぎたい」
「同期にだけは、負けたくない」
「みんなから、すごい人だと思われたい」
これらはすべて、「他人との比較」から生まれる欲求です。
他人が持っているモノサシに、自分の価値を委ねてしまう、とても不安定で、危険な道と言えるでしょう。
この道を進んでも、心はなかなか満たされません。
良い欲求(自分軸の欲求)
一方、こちらの源泉は、常に「あなたの内側」にあります。
「この仕組みの、もっと深い部分が知りたい」
「昨日よりも、ほんの少しだけ上手にできるようになりたい」
「自分が心から正しいと思える、生き方をしたい」
これらは、あなた自身の「好奇心」や「価値観」から生まれる、とても純粋な欲求です。
誰かと比べる必要はなく、追求すればするほど、あなたという存在そのものが豊かになっていく。
揺るぎない、安心できる道です。
つまり、本当に重要なのは、何を欲するか(What)という表面的なことではなく、なぜそれを欲するのか(Why)という、心の奥深くにある動機なのです。
自分の内側にある気持ちを大切にしてください。
あなたの欲求はどっち?心を潤す「泉」か、心を枯らす「沼」か
最後に、少しだけ想像してみてください。
あなたの心の、一番深いところには、一つの水源があると。
「他人との比較」から生まれる欲求は、濁った「沼」のようなものです。
他人の評価という雨が降れば、一時的に水かさは増すかもしれません。
でも、その水は生温かく、飲んでも渇きは癒えない。
そこからは、嫉妬や焦りといった、よどんだ匂いが、いつも微かに立ち上っています。
一方、「自分の内側」から生まれる欲求は、こんこんと湧き続ける、澄み切った「泉」です。
その水は、ひんやりと冷たく、飲めば飲むほどあなたの心と体を潤し、生命力を与えてくれます。
この泉は、誰かに奪われることもなければ、あなたがあなたである限り、決して枯れることはありません。
私たちの人生を本当に豊かに味わうというのは、もしかしたら、この「自分だけの泉」を見つけ出し、その周りに美しい草花を植え、大切に、丁寧に育てていく、そのプロセスそのものなのかもしれません。
……でも、頭では「泉」が大切だと分かっていても、気づけば「沼」のほとりで立ちすくんでしまうのが、私たち人間ですよね。
次の章では、もしあなたが「沼」にはまってしまった時、そこから抜け出し、再び自分の足で歩き出すための、さらに強力な哲学の知恵を、一緒に見ていきたいと思います。
第2章【絶望と希望】うまくいかない日々の「意味」を見つける哲学
「自分軸の欲求が大切なのは、よくわかった」
「でも、現実はそんなに甘くない…」
そうですよね。
頑張ってもなかなか結果が出なかったり、そもそも頑張る気力すら湧いてこなかったり。
私たちの日常は、そんな風に、うまくいかないことの連続です。
そんなあなたにこそ、ぜひ知ってほしい哲学があります。
それは、ときにあまりにも過激で、しかし、最高に力強いエールを私たちに送ってくれる、一人の哲学者の思想です。
ニーチェに学ぶ「運命愛」。失敗や挫折すらも、人生の“深み”として味わう思考術
彼の名は、フリードリヒ・ニーチェ。
「神は死んだ」という、有名な言葉で知られる、ドイツの哲学者です。
彼が提唱した「運命愛(アモール・ファティ)」という思想は、「ポジティブシンキング」といった生易しいものではありません。
それは、人生の光も影も、成功も失敗も、そのすべてを「これこそが、私の望んだ人生だったのだ」と、丸ごと引き受ける、力強い覚悟のことです。
ニーチェは、こんな思考実験を提案しました。
もし、今あなたが送っているこの人生を、一分の違いもなく、全く同じように、これから永遠に、無限に繰り返さなければならないとしたら?
あなたは、それに絶望するだろうか?
それとも、「もう一度!」と叫ぶだろうか?
正直、ゾッとするような問いですよね。
でも、この問いが教えてくれるのは、「失敗は成功のもと」といった、ありきたりな慰めの言葉ではない、もっと本質的なことなのです。
それは、
「この失敗も、この挫折も、この退屈な一日でさえも、すべてが私の人生を構成する、取り除くことのできない重要なピースなのだ」
と受け入れること。
ここで、あなたの人生を、一枚の美しい「織物」に例えさせてください。
輝くような金色の糸(成功や喜び)はもちろん素晴らしい。
でも、それだけでは、きっと単調で、奥行きのない布になってしまうでしょう。
深く、静かに沈んだ藍色の糸(悲しみや苦悩)。
ごわごわとした、無彩色の灰色の糸(退屈や停滞)。
そういった、一見ネガティブに見える色の糸が織り込まれるからこそ、あなたの織物は、誰にも真似できない、複雑で、深みのある、世界でたった一つの美しい模様になるのではないでしょうか。
失敗や挫折は、あなたの人生というタペストリーに、かけがえのない「深み」を与えるための、必要不可欠な、大切な「色」なのです。
ここで注意したいのは、運命愛とは、決して「何もしないことの言い訳」ではない、ということです。
むしろ、変えられることには全力を尽くす。
その上で、変えられない結果をも含めて「これが我が人生だ」と引き受ける、極めて能動的で力強い態度なのです。
ストア派の知恵に学ぶ。人生の“コントロールできないこと”を手放す勇気
とはいえ、日々の生活の中では、上司の機嫌や、同僚の心ない一言、予測不能なトラブルに、どうしても心をかき乱されてしまいますよね。
本当に、しんどいことです。
この悩みに対し、約2000年前、古代ローマの皇帝でありながら哲学者でもあった、マルクス・アウレリウスも実践した「ストア派」の哲学が、驚くほど有効な処方箋をくれます。
彼の個人的な思索ノートである『自省録』にも、
そのエッセンスは色濃く反映されています。
それは、自分の心を悩ませる物事を、
「コントロールできること」と「コントロールできないこと」に、はっきりと切り分ける。
というシンプルな知恵です。
あなたの心を、一つの「コントロール盤」だと考えてみてください。
【内側の円(自分で変えられること)】
-
自分の思考
-
今日の行動
-
物事への解釈
-
学ぶ姿勢
【外側の円(自分では変えられないこと)】
-
他人の評価
-
過去と未来
-
景気や天候
-
他人の感情
悩みが出たらまず一度、深呼吸してみてください。
そして、その悩みが
「内側の円」(自分が変えることのできるもの)
にあるのか、
それとも
「外側の円」(自分には変えることのできないもの)
にあるのかを、自分に問いかけてみるのです。
もし、その悩みが「外側の円」にあるのだとしたら…。
それは、あなたがどれだけ心を痛めても、決して変えることのできないものです。
であるならば、それはもう、あなたが悩むべき問題ではありません。
その重荷は、そっと手放していいのです。
有限な心のエネルギーを、変えられないことで浪費するのではなく、変えられることに集中させる。
たったそれだけで、人生の風通しは、驚くほど良くなっていきます。
承認欲求の沼に溺れた私が、人生を味わうきっかけをくれた一冊の本
ここまで偉そうに哲学を語っている私ですが、ほんの数年前まで、序章でお話しした「承認欲求の沼」で、文字通り、息もできずにもがいていました。
同期のSNSでの活躍を見ては、胸がざわつき、眠れない夜を過ごす。
会議では、上司の顔色ばかりを窺って、本当に言うべきことを言えない。
週末は、何かをしなくてはと焦る気持ちばかりが空回りして、結局、一日中天井を見つめて終わる。
深夜のオフィスで、誰に見せるわけでもない資料のフォントを、延々と修正していた時の、あの言いようのない虚しさを、今でもはっきりと覚えています。
そんなある日、私は、まるで何かに吸い寄せられるように、一冊の本を手に取りました。
精神科医ヴィクトール・フランクルが、ナチスの強制収容所での体験を綴った、『夜と霧』です。
極限状態の中、人間としての尊厳がすべて奪われていく。
そのあまりにも壮絶な内容に、言葉を失いました。
しかし、その地獄のような世界の中で、フランクルは一つの真実を発見します。
それは、
「どんな絶望的な状況に置かれても、その出来事をどう解釈し、どう振る舞うかという『心の自由』だけは、誰にも奪うことはできない」
という、人間の最後の砦とも言える真理でした。
この一節を読んだとき、私は、まるで頭を強く殴られたような衝撃を受けました。
他人の評価や、コントロールできない状況に、自分の心の主導権を、いとも簡単に明け渡していたのは、他の誰でもない、私自身だったのだと。
その日から私は、どんなに疲れていても、寝る前に3分だけ、その日あった「コントロールできたこと」と「できなかったこと」を書き出す、小さな習慣を始めました。
偉そうなことを言える立場ではありませんが、その小さな積み重ねが、溺れかけていた私にとって、最初の、そして最も確かな「浮き輪」になってくれたのです。
もちろん、これはあくまで私の物語です。
あなたには、あなたの物語があります。
一本の映画かもしれないし、誰かとの何気ない会話かもしれない。
あるいは、道端に咲く一輪の花かもしれません。
大切なのは、心のアンテナを立て続けること。
そして、自分を救ってくれるかもしれない「何か」と出会った時に、
それを見過ごさないことです。
哲学とは、決して高尚な議論のことではありません。
それは、私たちが人生の暗い夜道を歩むときに、そっと足元を照らしてくれる、ポケットの中の、小さな「懐中電灯」のようなものなのです。
さあ、心の守り方を手に入れた今、いよいよ次章では、あなたの日常そのものを、輝きに満ちた「探求のフィールド」へと変えるための、具体的な技術を、一緒に手にしていきましょう。
第3章【実践の羅針盤】あなただけの「人生の哲学」を育てる技術
さあ、ここからは座学ではなく、実践の時間です。
あなたの心という、この世で最も面白く、そして尊い場所を探るための、ささやかな探検に出かけましょう。
一枚の紙とペンを用意してみてください。
もちろん、いつも使っているスマートフォンのメモ帳でも大丈夫ですよ。
これから行うのは、難しい分析ではありません。
自分自身との、静かで、穏やかな対話の時間です。
【ワークシート付】あなたの心を占める「欲求の正体」を暴き出す魔法の質問
まずは、あなたの心の中に今、どんな「欲求」があるのかを、そっと取り出してみましょう。
Step 1 心の棚卸し
-
難しく考えずに、今あなたが「欲しい」「なりたい」「してみたい」と感じることを、思いつくままに5つ、書き出してみてください。
Step 2 欲求の品質チェック
-
書き出した欲求を一つひとつ眺めながら、自分に優しく問いかけてみましょう。これが、あなたの「欲求の正体」を暴き出す、魔法の質問です。
Q1. もし、世界中の誰もこのことを知らなくても、あなたはまだそれを欲しがりますか?
(例:「すごい!」と誰も言ってくれなくても、本当にその昇進は欲しい?)Q2. その気持ちは「誰かとの比較」から? それとも「過去の自分との比較」から?
(例:あの人が持っているから欲しい? それとも、昔から憧れていたから?)Q3. それを手に入れた瞬間を想像してください。感じるのは「やった!」という興奮? それとも「ああ、満たされる…」という静かな満足感?
(例:一瞬で消える花火? それとも、じんわり温かい焚き火?)Q4. なぜ、あなたはそれを欲するのですか? その理由を、最低5回「なぜ?」と繰り返してみてください。
(例:「お金が欲しい」→なぜ?「安心したいから」→なぜ?「将来の不安をなくしたいから」→なぜ?…)
どうでしたか?
もしかしたら、思った以上に多くの欲求が、「他人からの評価」や「一瞬の快楽」に繋がっていたかもしれませんね。
でも、どうか落ち込まないでください。
それに気づけたことこそが、何より素晴らしい、大きな一歩なのですから。
大切なのは、良い・悪いとジャッジすることではありません。
「ああ、私の心は今、こう感じているんだな」
と、ただ、知ってあげることです。
今日から、ほんの少しだけ、あなたの心の奥底から湧き出る「泉」のような欲求に、耳を澄ませてみませんか。
私が発見した「人生を味わう達人」3つの共通ルール
「自分軸で生きる、泉のような欲求…」
そう言われても、なかなか具体的なイメージが湧きにくいかもしれませんね。
しかし、その生き方には、驚くほどはっきりとした「3つの共通ルール」があることに気づきました。
ルール①:評価の基準が、常に「自分の内側」にある。
ルール②:結果よりも、「プロセスそのもの」に喜びを見出している。
ルール③:自分の探求が、結果的に「誰かへの小さな貢献」に繋がっている。
彼らは、特別な人間ではありません。
ただ、自分の心の「泉」のありかを知り、それを大切に育てる術を知っているだけなのです。
日常を「探求」に変える2つの技術
では、私たちも「達人」に近づくために、日常で使える具体的な「技術」を、2つだけ、ご紹介しますね。
日々のルーティンワークや、目的のわからない会議。
正直、「味わう」どころではない、と感じてしまいますよね。
でも、たった一つの「問い」を自分に投げかけるだけで、どんな退屈な作業も、ワクワクする知的な探検の始まりに変わることがあります。
その問いとは、「これは一体、なぜこうなっているんだろう?」です。
Before
「ああ、またこの報告書を作らなきゃ。面倒だな…」
After
「なぜ、部長はこのデータを、いつもこの形式で欲しがるんだろう?」
「この数字の裏には、どんなお客様の気持ちが隠れているんだろう?」
「もっと、相手が本当に知りたいことの本質を突く報告はできないだろうか?」
この「なぜ?」という、たった一つの問い。
それが、あなたを「受け身の作業者」から、主体的に世界に関わる「能動的な探求者」へと変身させてくれるのです。
私たちはつい、目標を達成した「瞬間」だけが、価値のあるゴールだと思い込んでしまいがちです。
でも、それでは、人生のほとんどの時間が「ゴールまでの、我慢の時間」になってしまいます。
プロセスそのものを味わうための、ちょっとしたコツがあります。
それは、自分自身を、「一人の主人公」として、少し離れた場所から客観的に観察してみることです。
まるで、あなたという主人公のドキュメンタリーを撮っている、優しい監督のような視点を持つ、と言ってもいいかもしれません。
Before
「また失敗してしまった…。なんて自分はダメなんだろう」
After
「おっと、主人公(私)はここで大きな壁にぶつかったか。なるほど、この試練が、後の成功の場面を、よりドラマチックにするための、いいスパイスになるわけだな。さて、監督として、この主人公にどんなアドバイスを送ろうか?」
この視点を持つだけで、成功も失敗も、喜びも苦しみも、すべてがあなたの人生という、かけがえのない作品を豊かにするための「味わい深い名シーン」に変わっていくのです。
さあ、これであなたの道具箱には、人生を味わうための素晴らしいツールが、いくつか揃いました。
でも、もしかしたらあなたは、心のどこかでこう思っているかもしれませんね。
「自分のこんな小さな探求が、一体、何の意味があるというのだろう?」と。
最終章では、その小さな泉が、やがて大きな流れとなり、大海へと注いでいく。
そんな、壮大で、希望に満ちた景色を、最後にお見せしたいと思います。
終章【自己実現の、その先へ】人生を味わう究極の境地とは

私たちは、心の渇きの正体を知り、哲学という光でそれを照らし、そして、日常を探求に変えるための、具体的な道具を手にしてきました。
あなたが大切に育て始めた「自分だけの泉」。
その、ささやかで、しかし確かな潤いは、あなたの心を少しずつ満たしてくれていることと思います。
しかし、もしあなたが、「自分の小さな探求なんて、結局は自己満足に過ぎないのではないか?」と、心のどこかで感じているとしたら。
最後に、その泉がやがてどこへ向かっていくのか、その壮大な旅路の、最終目的地をお見せしたいと思います。
マズローが晩年にたどり着いた「自己実現」という幸福の頂
第1章で、私たちは心理学者マズローの欲求5段階説に触れ、その一番上。「自己実現」という山の頂を目指すことの大切さを学びました。
覚えていますか?
実は、マズロー自身も晩年には、この『自己実現』を達成した人々のさらに先の境地として、『自己超越(Self-Transcendence)』の概念を提唱していました。
これは、自己実現のピラミッドの頂点というよりも、自己実現を超えた、より高次の幸福の形として捉えられています。
その段階こそが、「自己超越(Self-Transcendence)」の欲求です。
これは、一体どういうことなのでしょうか。
-
「自己実現」が、自分の能力を最大限に発揮し、「自分という存在を完成させる」ための欲求だったのに対し、
-
「自己超越」は、その完成した「自分」という小さな枠組みすらも超えて、他者への貢献、より大きなコミュニティや未来、あるいは自然や宇宙といった、自分を超えた何かと繋がり、そのために生きることで得られる、至高の幸福のことなのです。
難しく聞こえるかもしれませんね。
でも、これは、あなたが育てている「泉」の物語そのものです。
あなたが、自分の内なる「知りたい」「できるようになりたい」という泉を、ただ夢中で掘り下げていく。
すると、その泉の水は、やがて満ち溢れ、あなたの外側へと流れ出していきます。
その澄んだ水は、あなたの隣で渇きに苦しんでいる誰かを潤すかもしれない。
あなたの何気ない探求の記録が、未来の誰かの道標になるかもしれない。
そう。
あなたがあなたらしくあろうとすることが、意図せずして、誰かのための、世界のための、小さな光になっていく。
「自分」という枠を超え、より大きな何かと溶け合っていくような、静かで、しかし圧倒的な喜び。
それこそが、マズローが最後にたどり着いた、人生を味わうことの、究極の境地なのです。
欲求は敵じゃない。あなたを想像もできない場所へ連れて行く、最高の相棒だ
思い出してみてください。
私たちは、「欲求」というものを、自分を苦しめる厄介な、できれば消してしまいたい存在だと感じていましたよね。
しかし、ここまで一緒に歩んできた今なら、もうお分かりのはずです。
欲求とは、決してあなたの敵ではありません。
それは、あなたがどちらへ向かうべきかを、いつも静かに教えてくれる
「人生のコンパス」であり、前に進むための尽きないエネルギーをくれる「最高の相棒(パートナー)」
だったのです。
他人軸の欲求(沼)の存在に気づき、
自分軸の欲求(泉)のありかを見つけ、
その泉を大切に育てる(探求)ことで、
やがてその水が溢れ出し、他者を、世界を潤していく(自己超越)…。
このプロセス全体こそが、「人生を深く味わう」ということの、本当の意味なのでしょう。
あなたの、ささやかで純粋な探求心は、きっと、あなたが今想像もできないほど、豊かで、素晴らしい場所へと、あなたを連れて行ってくれるはずです。
さあ、明日、世界にどんな「問い」を立ててみますか?
最後に、私からあなたへ、一つだけ、宿題を出させてください。
この記事を読み終えた後、あなたがすべきことは、たった一つです。
それは、
明日、あなたがこの世界に対して立ててみたい、たった一つの「問い」を決めること。
どうか、難しく考えないでくださいね。
「人類の未来のために…」なんて、壮大な問いである必要は全くありません。
例えば、こんな、本当にささやかな問いでいいのです。
-
「なぜ、いつも利用する駅のあのポスターは、この色を使っているんだろう?」
-
「なぜ、うちの猫は、いつもあの窓辺で日向ぼっこをするんだろう?」
-
「なぜ、あの上司は、会議でいつも、あの言葉を口にするんだろう?」
-
「なぜ、私は、熱いコーヒーを飲むと、こんなにもホッとするんだろう?」
どんなに小さな「なぜ?」でも構いません。
その問いこそが、あなたの色褪せた日常を、輝きに満ちた「探求のフィールド」へと変える、魔法の鍵なのですから。
そして、その鍵は、もう、あなたの手のひらの中にあります。
あなたの日々が、これからさらに味わい深く、豊かなものになることを、心の底から願っています。
さあ、顔を上げて。
あなたの、本当の探求は、今、この瞬間から、始まったばかりです。
【こちらの記事も読まれています】