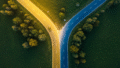SNSでぶつかる正義と正義に、心が少し疲れていませんか。
この記事を読めば、なぜ価値観がすれ違うのか、その仕組みが分かって人間関係のモヤモヤからすっと解放されると思うよ。
ここでは、哲学の知恵「道徳的相対主義」を、あなたの心を楽にする「思考の道具」として具体的に解説してみたんだ。
古くて新しいこの考え方が、きっとあなたの「心の指針」になるはずだよ。さあ一緒に、その地図を広げてみようか。
道徳的相対主義とは?私たちが無意識に持つ「絶対主義」との違い【要点解説】
あなたの「正しさ」がふと揺らぐとき。
それは、私たちの心の中に、初めから異なる2枚の「地図」が知らぬ間に存在しているからかもしれないね。
一枚は、多くの人が子供の頃からごく自然に手にしている、とても馴染み深い地図。
そしてもう一枚は、様々な経験を経て「おや?」と、その存在に少しずつ気づいていく、もう一つの地図だよ。
その地図の名前が、それぞれ「道徳的絶対主義」と「道徳的相対主義」と言うんだ。
この章ではまず、私たちの“初期設定”ともいえる絶対主義がどういうものかを理解して、その上で、もう一枚の地図である相対主義とは一体何なのかを、一緒にじっくりと見ていこうかな。
私たちの初期設定。「唯一の正解がある」と考える道徳的絶対主義
まずはこちらから。
道徳的絶対主義とは、「時代や文化、個人の立場に関係なく、誰にとっても普遍的で唯一絶対の正しい答え(道徳的真実)が存在する」という考え方だね。
少し硬い言葉だよ。
これは、多くの伝統的な宗教における神の教えや、一部の哲学における「人間なら誰でもそう考えるはずだ」といった考え方を土台にしている。
だからこそ、私たちの思考の“初期設定”として、心の奥深くに結構しっかりと根付いていることが多いんだよ。
具体的には、こんな風に考える傾向がそれにあたるね。
- 「嘘をつくことは、いかなる状況でも、絶対に悪いことだ」
- 「人を助けるのは、誰にとっても、いつでも善い行いに決まっている」
どちらも、一見すると、まあ、当たり前のことに聞こえるかもしれない。
この考え方を何かに例えるなら、そうだね…「硬くて決して変わることのない一本の物差し」のようなものでしょうか。
誰がいつどこで何を測ったとしても、その目盛りは絶対に変わらない。
そんな、頼もしい物差しだよ。
この「一本の物差し」は、社会の秩序を保ち、私たちに「何を信じればいいのか」という、一種の安心感を与えてくれる、とても大切な役割を果たしてきたんだ。
まずは、私たちの多くが、この揺ぎない物差しを、心のどこかで今もぎゅっと握りしめているんだな、という事実を知ることがここでの出発点になるよ。
もう一つの考え方。「正解は一つではない」とする道徳的相対主義
さて、これに対して、道徳的相対主義は、その「唯一絶対の正しい答え」の存在そのものを、「本当にそうなのかな?」と一度立ち止まって静かに疑ってみる考え方だね。
そして、「何が善で何が悪かという基準は、時代や文化、社会あるいは個人の立場によって移り変わっていくものだ」と考えるんだ。
先ほどの絶対主義が「硬い一本の物差し」だったとしたら、こちらは、「測る場所や相手によって目盛りがしなやかに変化する巻尺(メジャー)」のようなもの。そんな風にイメージすると、少し分かりやすいかもしれない。
絶対的な数値よりも、その場の状況や文脈・背景をとても大切にする考え方、とも言えるね。
例えば、私たちの身の回りを見渡すだけでも、この「基準の変化」は、本当に簡単に見つけることができるよ。
ほら、こんな風に。
立場や文化、時代が違えば、善悪の判断は、時に正反対にさえなってしまうんだ。
道徳的相対主義は、この少し落ち着かない現実を、ただありのままに静かに見つめることから始まる。
ここで肝心なのは、どちらの地図が優れているなんていう優劣を決めることでは、全くないんだよ。
最も重要な、そしてすべてはここから始まるという第一歩は、「私たちは、そもそも違う地図を見ているのかもしれない」と、その可能性にふと気づくことだね。
このささやかで、けれどとても大切な気づきこそが、無用な対立や心の消耗を減らし、他者とそして自分自身と、より深く向き合っていくための、本当の出発点になるんだ。
【この章のポイント】
道徳的絶対主義とは、「唯一絶対の正しい答えがある」と考える“一本の物差し”のような考え方。私たちの思考の初期設定に近い。
道徳的相対主義とは、「正しい答えは立場や文化によって変わる」と考える“しなやかな巻尺”のような考え方。
大切なのは優劣ではなく、「そもそも見ている地図が違うのかもしれない」と、その可能性に気づくこと。
道徳的相対主義を深掘り。わかりやすく理解する3つの視点
前の章で、私たちは心の中に2枚の異なる地図が存在する可能性に、なんとなく気づくことができたね。
では、その「道徳的相対主義」という、少しばかり複雑な、もう一枚の地図。
これを私たちはどうすれば正しく読み解いて、日々の暮らしの中で上手に使いこなしていけるのだろうか。
この思想は、とても強力な視点を与えてくれる一方で、そうだね…少し誤解されやすい、危うさのようなものも持っているんだ。
この章では、その地図を正しく読み解き、あなたの「思考の道具」にするために、特に重要だと私が思う「3つの視点」を、一緒にゆっくりと見ていこう。
視点①事実の観察と倫理的な判断。混同されがちな相対主義の“2つの顔”
道徳的相対主義を使いこなす上で、まず最初にこれだけは知っておいてほしい、という大切なことがあるよ。
それは、この思想には、よく似ているけれど実は全く異なる“2つの顔”があるということだね。
- ① 事実認識としての側面(記述的相対主義) これは、ただ「世界には実際にいろんな価値観が存在しているなあ」と、ありのままの現実を観察する、いわば科学者のような、冷静な目線のこと。
- ② 倫理的主張としての側面(規範的相対主義) そしてこちらは、「だから、自分と違う価値観だからといって頭ごなしに否定するべきではないだろう」という、一歩踏み込んだ姿勢や態度のことを指すんだ。
この2つ、似ているようで全然違うだろう?
これをうっかり混同してしまうと、「違いがあるのだから(事実)何をしても許されるべきだ(主張)」という、なんとも短絡的で少し危険な考えに陥りやすくなってしまう。
後の章で詳しくお話しする「ニヒリズム」や「思考停止」といった落とし穴は、大抵この混同から始まってしまうんだね。
例えば、また食文化の例で考えてみようか。
- Step1:観察(事実認識) 「A国では犬を食べ、B国では食べない。ふむ、これは文化の違いという『事実』だな」 …ここでは、良いも悪いもなくただ客観的に事実を観察しているだけだね。
- Step2:判断(倫理的主張) 「その事実を知った上で、では、その食文化に対して自分は一体どのような態度を取るべきだろうか?」 …ここからが、あなた自身の倫理観に基づいた判断になってくるわけだ。
このように、冷静に「事実を観察すること」と、その上で「どう振る舞うかを判断すること」は、全く別のステップだよ。
この区別を、頭の片隅にそっと置いておくだけでも、感情的な反応を抑えて物事をぐっと冷静に見つめることができるようになるはずだよ。
視点② なぜ現代は対立が絶えない?SNSの「フィルターバブル」という背景
それにしても、2500年も前に生まれたこの思想が、どうして「今」これほどまでに重要なのでしょうか。
少し皮肉なことだけど、その答えは、私たちの世界をかつてなく繋げたインターネット、とりわけSNSの仕組みの中に隠されているんだ。
あなたも、こんな言葉をどこかで耳にしたことがあるかもしれないね。
フィルターバブル アルゴリズムという、まあ、コンピューターの賢い仕組みがですね、ユーザーの好みをどんどん学習して、その人が「見たいだろうな」と思う情報ばかりを、まるで“泡”のように、その人の周りに集めてしまう状態のことだね。
エコーチェンバー 自分と似た意見を持つ人々が集まる、閉じた空間(コミュニティ)の中で、同じような意見ばかりがやまびこのように何度も何度も反響し合う。
そうしているうちに、それがまるで世の中全体の総意であるかのように錯覚してしまう状態のことだ。
これらの仕組みによって、私たちは、本当に自分でも気づかないうちに、「自分と同じ価値観」や「自分にとって心地よい情報」ばかりにふわりと囲まれて暮らしているんだ。
気づけば、タイムラインには自分と似たような政治的意見を持つ人ばかりが並んでいたり。好きな趣味の話をしていると、それが世界の常識であるかのように感じてしまったり。
…どうだろう、少し心当たりはないかな。
この「心地よい泡」の中に長くいると、私たちの価値観は、少しずつ少しずつ純化され、そして強化されていくんだ。
だからこそ、いざ、その泡の外にある、全く異なる価値観にばったりと出くわした時。
その衝撃や反発は、必要以上にとても大きなものになってしまうんだよ。
道徳的相対主義は、この無意識のうちに作られた、あなただけの泡の存在に「おや?」と気づかせて、そこから一歩引いて世界を客観的に見るための「針」のような役割を果たしてくれる。
「ああ、そうか。自分は今、泡の中にいたのかもしれないな」と。
そう気づくだけでも、見える景色というのは案外大きく変わってくるものだよ。
視点③ 精神的な成熟のしるし。「ルールだから」から「なぜ?」への成長
相対主義的な視点を持つ、と聞くと、なんだか優柔不断になったり、自分の軸を失ったりするような、少しネガティブな印象を持つ方も、いるかもしれないね。
しかし、心理学の世界では、このような視点の獲得は、むしろ人間が精神的に「成熟」していくごく自然なプロセスなのだ、と考えられているんだ。
心理学者ローレンス・コールバーグが提唱した「道徳性発達理論」というものを、本当にごくごく簡単に、少しだけ覗いてみようか。
彼は、人の道徳的な判断力は、いくつかの段階を経てゆっくりと成長していく、と考えたんだ。
子供の段階:「親や先生に怒られるから、これはやめておこう」といった、罰を避けるための道徳。
社会適応の段階:「ルールだから守る」「みんながそうしているから、これが正しい」といった、社会の規範を絶対のものと考える道徳。
成熟した段階:「待てよ、そのルールは、本当にすべての人にとって公平なのだろうか?」と、規範そのものを一度立ち止まって吟味し、人権や尊厳といったより普遍的な原理から判断しようとする道徳。
例えば、そうだね…「校則だから」と何の疑問も持たずに髪を黒く染めていた学生が、大人になって、「なぜ、当時はあんなにも髪の色を規制する必要があったのだろう?」と、その背景や意味をふと問い直すようになる。
これは、まさに第二段階から第三段階への移行。思考が、確かに深まっている証拠と言えるね。
「ルールだから」と絶対視する段階から、「なぜ?」と物事の背景や文脈を考える、相対的な視点へ。
あなたが今、感じているかもしれない、あの「価値観の揺らぎ」というものは、混乱などではなく、まさにこの「成熟」の過程で生じる、健全でそしてとても大切な痛みなのかもしれないよ。
【この章のポイント】
相対主義には「事実の観察」と「倫理的な判断」という2つの顔がある。
この区別を意識することが、とても大切。
SNSの「フィルターバブル」は、無意識に私たちの視野を狭める。相対主義は、その泡の存在に気づかせてくれる針のようなもの。
相対的な視点を持つことは、優柔不断さではなく、精神的な「成熟」の証。
思考が深まっている、良いサインだよ。
【落とし穴】道徳的相対主義が抱える問題点と2つの危険性
さて、道徳的相対主義という地図の読み解き方を、少しずつ少しずつ深めてきたね。
うん、良い感じだよ。
でも、この強力な考え方は、一歩その使い方を間違えてしまうと、私たちを思わぬ「落とし穴」にストンと導いてしまう危険性もちゃんと持っているんだ。
どんなに優れた道具にも、光の側面と、そして影の側面があるものだね。
この章では、この思考の道具をあなたが安全に使いこなすために、絶対にこれだけは知っておいてほしい「2つの大きな誤解」と、それがもたらす「危険性」についてお話ししようと思う。
光と影の両方を知ることで、初めて私たちは、その道具の本質を本当の意味で理解できるからね。
誤解①「なんでもあり」の無法地帯ではない。社会ルールとの明確な境界線
読者の方が、最も抱きやすい誤解の一つが、おそらくこれだろう。
「結局のところ、正しい答えは一つではない、ということは、『何をしても許される』ということになってしまわないか?」
結論から、はっきりとお伝えするね。
道徳的相対主義は、「何をしても許される」という、無法地帯を肯定する思想では、決して断じてないよ。
その最大の理由は、「個人の内面的な道徳観」と、「社会を平穏に維持するための法規範(ルール)」は、全く別の次元(レイヤー)にあるからだ。
道徳的相対主義が、主に「どうだろうか?」と問いかけるのは、あくまで前者。つまり、個人の心の中にある、善悪の基準についてだよ。「だから、社会のルールを無視していいですよ」なんてことは、一言も言っていないんだね。
少し極端だけど、分かりやすい例を挙げてみようか。
ある人が、心の中で「私は、人を傷つけることにどうしようもなく喜びを感じてしまう」と思っていたとする。
その“個人の道徳観”を、ただ心の中で思うこと自体は、内心の自由の範囲かもしれない。
しかし。その考えに基づいて、実際に誰かを傷つけてしまえば、それは、この日本という国の「法律」という、社会全体の共通ルールによって、明確に「悪」としてきちんと裁かれるんだ。
この関係性は、そうだね…「個人の心という『プライベートな庭』と、誰もが使う『公共の道路』の違い」と考えるとすっと腑に落ちるかもしれない。
自分の庭で、どんな不思議な花を育てようと、基本的にはその人の自由だね。だけど、一歩、公共の道路に出たならば、誰もが交通ルールを守らなければ安全は保てないだろう。
「他者の多様な価値観を尊重すること」と、「社会のルールを破る行為を容認すること」は、全く別の話だよ。
この、当たり前のようで、でもとても大切な境界線を、まずはっきりと理解しておくこと。それが、この思想を社会生活の中で健全に使うための、絶対的な前提条件になるよ。
誤解②思考停止に陥る「どうせ人それぞれ病」とニヒリズムの危険性
もう一つ。
こちらの方がより深刻で、多くの人が知らず知らずのうちに陥りがちな内面的な落とし穴だね。
それが、「思考停止」と、その先に待っている「ニヒリズム(虚無主義)」の危険性だ。
この思想を、浅くそして少しだけ雑に理解してしまうと、私たちは、あるとても便利な言葉に頼りたくなってしまう。
「どうせ、何が正しいかなんて、人それぞれでしょ?」
この一言で、あらゆる物事をふわりと片付けてしまうんだ。
私はこれを、冗談半分本気半分で、一種の「どうせ人それぞれ病」と呼んでいるよ。
本来、「人それぞれ」という言葉は、他者への寛容さを示す、とても優しく温かい言葉のはずだね。
しかし、それが時として、「自分と違う意見について、これ以上深く考えることを放棄する」ための、都合のいい言い訳として使われてしまうことが、残念ながらあるんだ。
社会問題のニュースを見て、「うーん、いろんな意見があるみたいだし、何が正しいかなんてもう分からないや」と、すぐに思考を打ち切ってしまう。
友人との真面目な議論の最中に、「まあ、価値観は人それぞれだからね」と、少しだけ格好をつけて対話を早々に切り上げてしまう。
…これもまた、どこか心当たりのある風景かもしれない。
そして、この思考停止がさらに、じわじわと心の奥深くまで蝕んでいくと、やがて、すべての価値が等しく無意味に感じられる「ニヒリズム(虚無主義)」へとゆっくりと至る危険性があるんだ。
「どんな価値観も、結局は同じようなものなら、何を信じても何をしても、意味なんてないじゃないか」と。
19世紀の哲学者ニーチェが「神は死んだ」と、あの有名な言葉を述べた際に、本当に警鐘を鳴らしたかったのは、まさにこの、社会全体が拠り所とする価値を完全に、見失ってしまう、そんな状態のことだったんだ。
この「どうせ人それぞれ病」は、道徳的相対主義という、強力な薬が持つ、一種の“副作用”のようなもの。
では、この副作用を上手に抑え、この思想の良い面だけを私たちの力にしていくには、一体どうすればいいのだろうか。
その鍵は、実は、「自分の軸」と「他者との対話」という、とてもシンプルなものの中にあるんだ。
この点については、また後の章で、詳しくゆっくりと見ていくことにしようね。
【この章のポイント】
相対主義は、決して「なんでもあり」ではない。
「個人の道徳観」と「社会のルール」は、全く別の次元の話。
「どうせ人それぞれ」という言葉で思考を停止させてしまうと、ニヒリズム(虚無主義)という、心の虚無感に陥る危険性がある。
これらの落とし穴を避ける鍵は、意外にも、「自分の軸を持つこと」と「他者と対話すること」にある。
道徳的相対主義から学ぶ、心を楽にする思考の型の「土台」
さて、私たちは、道徳的相対主義という一枚の地図の読み解き方を学び、同時に、そこに潜んでいるいくつかの落とし穴の存在も確認することができたね。
うん、一歩一歩着実に進んでいるよ。
ここから先は、いよいよ実践編だ。
この、少しばかり複雑な思想を、どうすれば私たちの日常の中で、心をすっと楽にするための具体的な「思考の型」として活かしていくことができるのだろうか。
そのために、まずたった一つだけ。
とてもとても重要なステップを、ここに挟む必要があるよ。
それは、抽象的な思想と具体的な実践を結びつけるための、頑丈な“土台”を、あなたの心の中にゆっくりと丁寧に築いていくことだね。
なぜこの思想が実践で役立つのか?「自分の相対化」がもたらす心の余裕
結論から、お話ししてしまおう。
道徳的相対主義が、私たちの心をふわりと楽にする思考法の“土台”となる。その最大の理由は、この考え方が、「自分の相対化」という特別な視点を、私たちに与えてくれるからだ。
「自分の相対化」。
うん、また少し硬い言葉が出てきたね。これは一体どういうことだろうか。
「この世に、絶対的な正しさはない」ということを、あなたが心の底からすとんと理解できたとするよ。
そうすると、私たちは必然的に、ある一つの、少しだけ勇気のいる事実に静かに向き合うことになる。
それは、「今、この瞬間に、自分が、正しいと信じているこの『正しさ』もまた、絶対ではないのだ」という、ごく当たり前の事実だね。
つまり、これまで疑うことすらしてこなかった、あなた自身の価値観を、「唯一絶対の正解」という、きらびやかな“玉座”から一度そっと降ろしてみる。
そして、「たくさんある、様々な価値観のうちの一つ」として、少し離れた場所から客観的に静かに眺めてみること。
これが「自分の相対化」だよ。
この感覚は、そうね…まるで、「自分が主人公の物語から、一度だけ降りてみて、客席から舞台全体をぼんやりと眺めてみる感覚」みたいな感じ。
主人公として夢中で舞台の上に立っている時には、決して気づけなかった、舞台装置の巧みな仕組みや、他の登場人物たちの細やかな表情の動き、そして物語全体の、大きな構造のようなものがふと見えてくる。
そんな感覚に、少しだけ似ているかもしれないね。
この「自分の相対化」が、少しずつ少しずつできるようになってくると、私たちの心には、あるとても大きな変化が生まれてくるんだ。
これまでのあなた 他人から意見を少しでも否定されると、まるで「自分自身の人格が丸ごと攻撃された!」かのように感じてしまって、カッとなったりずんと深く落ち込んだりする。
これからのあなた 意見を否定されても、「なるほど、その視点からはそう見えるのか。私の意見とは少し違うけれど」と、
“あなたという存在” と “あなたの、その時の意見”を上手に切り離して、冷静に受け止められるようになる。
この「自分と意見の切り離し」こそが、心理学の世界で「メタ認知(自分を、一つ上の視点から客観的に認識する能力)」と呼ばれる、健やかな心を保つための、とても重要なスキルのまさに、その入り口なんだ。
この「自分の相対化」という、柔らかくも頑丈な土台。
これが、あなたの心の中にしっかりと築かれて初めて、私たちは、感情の波にむやみに振り回されることなく、冷静に物事を判断し、他者と本当に建設的な関係を築いていくための、具体的な「思考の型」を本当の意味で使いこなせるようになるんだね。
さあ、土台はできたよ。
それでは、この土台の上に、私たちは一体どのような「道具」を置いていけば、あなたの日常はより穏やかなものになっていくのだろうか。
次の章から、明日あなたの日常で実際に使える、6つの具体的な思考の型を、一つひとつゆっくりと見ていくことにしよう。
【この章のポイント】
道徳的相対主義が、なぜ実践で役立つのか。その理由は、それが「自分の相対化」という特別な視点を、私たちに与えてくれるから。
「自分の相対化」とは、自分の価値観を絶対視せず、「数あるうちの一つ」として、客観的に眺めてみること。 これができるようになると、“自分”と“自分の意見”を、上手に切り離せるようになる。
これが、心を楽にするための、何より大切な「土台」となる。
【実践編】道徳的相対主義を応用した6つの思考の型
「自分の相対化」という、柔らかくて頑丈な土台が、あなたの心の中に、なんとなくできたね。
さあ、いよいよその上に、私たちの心を、日々のストレスからそっと守り、人間関係をより豊かで穏やかなものにするための、具体的な「道具」を、一つひとつ置いていこうか。
大丈夫。ここで紹介するのは、何か難しい特別な訓練が必要なものでは全くない。
日常の、ほんの些細な瞬間に、少しだけ意識の向け方を変えるだけで、誰にでも実践できる、ささやかな6つの「思考の型」だ。
全部を一度にやろうとしなくても、全く構わないからね。
まずは「これなら、今の自分にも試せそうだな」と、あなたが感じるもの、一つからで十分だ。どうぞ、気軽な気持ちで始めてみて。
思考の型①【自分の相対化】心のザワつきを客観視する実況中継
【どんな時に使う?】
SNSの投稿や、他人の何気ない一言にカッとなったり、心がザワザワしたり…あなたの感情がふと波立った、まさにその瞬間に使うんだ。
具体的な方法 心の中で、そうだね…スポーツ実況のアナウンサーにでもなったつもりで、自分自身の、今の心と体の状態を、ただただ客観的に描写してみてほしい。
「おっと、今、眉間にぐっと力が入りましたねえ。どうやらこの意見には、かなり強く反論したい気持ちが湧き上がっている模様です」
「ああ、心臓が、少しだけトクトクと速く打っています。これは、想定外の出来事に少し動揺しているという証拠でしょうか」
ここでの一番大切なポイントは、そこに「良い・悪い」の判断を一切加えないこと。
ただ事実としてありのままを観察することに徹するんだ。
【なぜ、これが効くのか?】
これは、感情の渦に“飲み込まれている自分”から、“その感情を少し離れて観察している自分”へと、視点を強制的にすっと引き離すための方法だよ。
心理学の世界では「メタ認知」と呼ばれ、感情的な反応を抑制し、問題解決能力を高める効果が実証されているんだ。冷静さを取り戻すための、ほんの数秒の、貴重な「間」を作り出すことができるんだね。
【注意点(落とし穴)】
これは、決して自分を責めるためのものではないからね。
「なぜ、私はこんな些細なことでイライラしてしまうんだ!」なんていう余計な自己分析を始めてしまうと、かえって苦しくなってしまう。
目的はあくまで、感情との間に、ふわりと一枚の薄紙を挟むように距離を置くこと。
ただそれだけだと、覚えておいてほしい。
思考の型②【時間の相対化】感情的な反応を避ける情報の一晩寝かせ
【どんな時に使う?】
怒りや不安を強く強く煽ってくるようなニュースや投稿に触れて、「今すぐ、何か言わなければ気が済まない!」という強い衝動に駆られた時。そんな時に特に有効だね。
具体的な方法 その、燃え上がるような衝動のままに、すぐに返信したり投稿したりするのをぐっとこらえてみる。
そして、その情報を一度、あなたの心の中で「保留」にしてみよう。
物理的にスマートフォンをそっと置いたり、パソコンのタブを静かに閉じたりするのがとても効果的だよ。
最低でも6秒(怒りの感情のピークが過ぎると言われる時間)、できれば1時間、そしてもしできるのなら一晩。その情報から意識的に物理的に距離を置いてみるんだ。
時間を置いた後、もう一度、冷静になった頭でそれを見て、「本当に、これは今この瞬間に、私が反応する必要のあることだろうか?」と優しく自分に問い直してみてください。
【なぜ、これが効くのか?】
私たちの「正しさ」の感覚というものは、その時の、燃え盛るような感情によって、実は大きく大きく左右されてしまう、とても移ろいやすいものなんだ。
つまり、時間によっても、その正しさは相対的に変化するんだね。
感情の渦中にある「今この瞬間」の正しさと、冷静さを取り戻した「明日」の正しさは、必ずしも同じではない。
時間を置くという、そのほんの少しの手間が、感情というけたたましいノイズを取り除き、より本質的な静かな判断へとあなたを導いてくれるんだ。
【注意点(落とし穴)】
もちろん、緊急性の高いお仕事の連絡など、すぐに対応すべきことまで、のんびりと寝かせてしまうのは問題だね。
ただ、私たちの日常で遭遇する、あの心をかき乱すような感情的な問題の9割以上は、実を言うと、一晩じっくり待っても何も困ったことにはならないものだったりするよ。
思考の型③【自分の軸の確認】流されないための「譲れないことリスト」
【どんな時に使う?】
周囲のたくさんの意見の波にざぶざぶと流されてしまいそうになったり、他人のもっともらしい価値観を受け入れるべきか迷いに迷って、自分の立ち位置がすっかり分からなくなってしまった時。そんな時に使うんだ。
【具体的な方法】
できれば静かな一人の時間に、紙とペンを用意してみてほしい。
そして、
- 「私が、一人の人間として、これだけはどうしても許せないことは、何だろうか?」
- 「どんな状況にあっても、これだけは守り続けたいと心から思っていることは、何だろうか?」
と、自分自身に深く問いかけてみる。そして、その答えをたった3つだけでいいので書き出してみよう。
例えば、
- 「人を、不当に傷つけない」
- 「嘘をつかない。正直である」
- 「誰かへの感謝を、忘れない」
など。あなたにとっての心の核心となる言葉で、大丈夫だよ。
【なぜ、これが効くのか?】
健全な相対主義というのは、確固たる「自分の軸」があって、初めてその真価を発揮するんだ。
このリストは、多様な価値観がまるで荒波のように渦巻く海の中で、あなた自身が自分という船の場所を見失わないための、重たい「碇(いかり)」の役割を果たす。
何を受け入れ、何を受け入れないべきか。そのあなただけの判断基準がぐっと明確になるんだね。
【注意点(落とし穴)】
繰り返しになるけど、これは他人を裁くための冷たいリストではないよ。
あくまで、あなた自身の心の平穏を保ち、「私はこう考える。あなたは違うかもしれないね」という、健全でそして温かい境界線を引くためのものであることを、どうか忘れないでね。
思考の型④【問題の相対化】無駄な対立を避けるための問題の仕分け術
【どんな時に使う?】
誰かとの議論がどうにもこうにも噛み合わない。なんだか不毛な言い争いになりそうだな、とあなたが感じた時。その瞬間に、頭の中でさっと使ってみてほしい。
具体的な方法 目の前にある、そのごちゃごちゃとした問題を、あなたの頭の中で3種類の小さな箱に、ぽんぽんぽんと「仕分け」していくんだ。
- 「好みの箱」(議論不要): 食べ物やファッションの好みなど、そもそもどちらが正しいという正解のない、個人の趣味の問題。
- 「ルールの箱」(確認・議論要): 法律や会社の規則など、その共同体の中での一時的な合意事項に関する問題。
- 「尊厳の箱」(対話・対決要): 差別やいじめ、暴力など、人としてそして社会として、決して譲ってはならない、最後の一線に関わる問題。
【なぜ、これが効くのか?】
私たちは、本当に無意識のうちに、「好みの問題」を、まるで「尊厳の問題」であるかのように、眉間にしわを寄せて熱く熱く語ってしまいがちなんだ。
問題の“種類”を、こうして相対的に見ることで、「どこまでが、『まあ人それぞれだよね』で済み、どこからが真剣に言葉を尽くして話し合うべき領域なのか」を、驚くほど冷静に判断できるようになるよ。
これだけで、無駄なエネルギーの消費をぐっと減らすことができる。
【注意点(落とし穴)】
この「仕分け」そのものが、実は人によって少しずつ異なる場合がある、ということも心の片隅にそっと置いておくと、さらに良いだろう。
相手にこの分類をむりやり押し付けるのではなく、あくまであなた自身の絡まった頭の中をすっきりと整理するための、便利な道具として上手に使ってみてね。
思考の型⑤【相手の視点の尊重】背景を想像し、理解の糸口を探す
【どんな時に使う?】
相手の言っていることが、あなたの価値観からすると、もう到底理解できない。信じられない、と感じた時。そんな時にこそ、試してみてほしいんだ。
【具体的な方法】
その、トゲトゲした意見そのものを、真正面からぐっと受け止めるのを一度やめてみる。
そして、少し視点を変えて、「なぜ、その人はそう考えるに至ったのだろう?」という、その人の背景にある“その人だけの、小さな物語”をそっと想像してみるんだ。
心の中で、こんな風に自問してみてほしい。
- 「一体、どんな経験をしたら、この考え方になるのだろう?」
- 「この、一見すると乱暴な意見を声高に叫ぶことで、この人は本当は、何を守ろうとしているのだろう?」
と。
【なぜ、これが効くのか?】
相手の立場や経験(文脈)によって、その人なりの切実な「正しさ」が形作られる。
これは、道徳的相対主義のまさに基本となる考え方だね。この思考法は、それを応用したものだよ。
「同意」はできなくても、全く構わない。
ただ「理解」の、ほんの小さな糸口が少しでも見つかるだけで、相手は、あなたにとっての“理解不能な、攻撃してくる敵”ではなく、“ただ、自分とは違う物語を持つ、一人の人間”にすっと変わるんだ。
この不思議な視点の転換が、あなたの心の重たい負担を驚くほどふわりと軽くしてくれることがあるんだよ。
【注意点(落とし穴)】
これは、もちろん、相手の非倫理的な言動までをも、「まあ、仕方ないよね」と、全て正当化するためのものでは決してないよ。
あくまで、あなた自身の心の平穏をまず第一に保つための、思考の実験だ。
あなたが、あなた自身で定めた「譲れないことリスト(思考の型③)」の、その大切な一線は、何があってもしっかりと守ることが大前提となるよ。
思考の型⑥【対話の出発点】「私はこう思う」から始める誠実な伝え方
【どんな時に使う? 】
あなたの、その大切な意見を、相手にできるだけ穏やかに、そして誠実に伝えたい、と思った全ての場面で使えるよ。
具体的な方法 とてもとてもシンプルだね。話す時の主語を、「あなた(You)」ではなく、「私(I)」にすることをただ意識するだけ。
(△)「あなたの考えは、少し、間違っていますよ」
(〇)「なるほど…。私は、少しだけ違う視点を持っていて…」(△)「普通は、こうするべきです」
(〇)「そうですか。私は、こうするのが良いのではないか、と考えています」
【なぜ、これが効くのか?】
「あなたは~だ」という言葉は、どうしても相手への“断定”や“評価”のように聞こえてしまい、無意識の小さな反発を生んでしまうんだ。「YOU(ユー)メッセージ」主語が【「あなた」】
「私は~思う」という伝え方は、相手に判断を委ねる形になるため、相手も心を開きやすく、本当に建設的な意味のある対話の扉を開くことができるんだね。
コミュニケーション心理学で「I(アイ)メッセージ」【主語が「私」】と呼ばれ、相手を非難せず、自分の感情や考えを誠実に伝えるための、最も基本的な手法として知られている。
【注意点(落とし穴)】
もちろん、これを言えば必ず相手が「なるほど!」と納得してくれるわけでは、ないよ。そんなに世の中は簡単ではないからね。
しかし、少なくとも、あなたが一方的な対立ではなく、お互いを理解するための対話を望んでいるという、その誠実な姿勢はきっと相手に伝わる。
私たちが本当にコントロールできるのは、相手の反応ではなく、自分の、その発する言葉だけ。それで、もう十分すぎるほど十分なのだと、私は思うよ。
【この章のポイント】
- ① 実況中継:自分の感情を、心理学の「メタ認知」を応用して客観視し、冷静になる「間」を作る。
- ② 一晩寝かせ:時間を味方につける。感情的な衝動的な判断を上手に避ける。
- ③ 譲れないことリスト:あなただけの「軸」を言葉にして明確にすることで、流されないための心の碇(いかり)とする。
- ④ 問題の仕分け:目の前の問題の種類を冷静に見極め、無駄な消耗するだけの対立を避ける。
- ⑤ 背景の想像:相手の見えない物語を想像することで、「同意」はできなくとも、「理解」の糸口を探す。
- ⑥ Iメッセージ:コミュニケーション心理学の基本「Iメッセージ」を使い、誠実な対話のその第一歩を踏み出す。
【深掘り分析】道徳的相対主義の限界と、その先にあるもの
ここまで見てきた6つの思考の型。
これらはきっと、日常の本当に多くの場面で、あなたの心を楽にしてくれるはずだよ。
しかし、ですね。
ここで、もう一度だけ静かに立ち止まって、考えてみようか。
この道徳的相対主義という、ある意味でとても万能に見える地図が、
全く役に立たなくなる場所。
あるいは、使うべきではない、特別な領域も本当にないのだろうか。
この最後の章では、この思想の“限界”というものを正直にまっすぐに見つめて、その上で、私たちが本当に目指すべき、真に成熟した心の在り方とは一体何なのかを、一緒にゆっくりと考えていきたいと思う。
「絶対悪」は存在するのか?この思想が唯一、沈黙する場所とは
ここで、あなたに、一つだけ。
とてもとても大切な問いを、投げかけさせてほしい。
「では、ホロコーストのような、組織的な大量虐殺や、いわれのない苛烈な差別、あるいは、人の尊厳を根こそぎ奪う奴隷制度といった、誰がどう見ても非人道的で残虐な行為も、『立場や文化が違えば、それもまた一つの正しさとして認められてしまう』とでも言うのでしょうか?」
この、重い問いに対する、私の答えは。
明確に、そして一切の迷いなく、「ノー」だよ。
そして、その根拠として、こうお伝えすることができる。
ほとんどの現代の倫理学者や思想家たちは、たとえ相対主義的な視点をどれだけ深く、その思考に取り入れたとしても、『人間の尊厳を、その根本から踏みにじるような行為』や、『他者に、一方的で全く不必要な苦痛を与え続けること』については、決して相対化が許されない、人間として超えてはならない、最後の一線だと考えているんだ。
思い出してみてほしいね。
前の章で一緒にお話しした「思考の型④:問題の仕分け術」を。
ホロコーストや奴隷制度といった、歴史上の、そして現代にも残る、深くて深い悲しみは、「好みの箱」や「ルールの箱」に収まるような問題では断じてないよ。
それらは議論の余地なく、私たちの「尊厳の箱」に入る問題だね。
そして、道徳的相対主義という、あのしなやかな考え方でさえも、この「尊厳の箱」の前では、その有効性をすっかりと失い、ただ沈黙せざるを得ないんだ。
なぜなら、それは「まあ人それぞれだからね」などという生半可な言葉で片付けては絶対にならない、私たち人類が共有すべき、最低限の心の基盤に関わる問題だからだ。
どんなに優れた道具にも、必ず「適用範囲」というものがある。
道徳的相対主義という、強力で時に鋭利な思考の道具にも、限界がある。その限界が一体どこにあるのかを、正確にはっきりと知っておくこと。
それこそが、この強力な道具を、決して危険な方向に誤用しないための、最高のそして唯一の知恵となるんだよ。
私たちが目指すべき「しなやかな相対主義」という在り方
この思想の、光とそしてその限界を理解した上で。
では、私たちは、これからどのような心の在り方を、目指していけばいいのだろうか。
私は、その私たちが目指すべき、一つの理想の姿を、「しなやかな相対主義」という言葉で、表現してみたい、とそう考えているんだ。
落とし穴として、少しだけお話しした「不健全な相対主義」と、私たちがこれから目指すべき、この「しなやかな相対主義」には、見た目は似ていても、その中身には決定的な違いがあるよ。
| 不健全な相対主義(思考停止に陥った、脆い状態) | しなやかな相対主義(成熟した、強い心の状態) | |
| 自分の軸 | ない(ただ風に流されるだけ) | ある(譲れない一線を持つ) |
| 他者への態度 | 無関心(「どうせ人それぞれ」と突き放す) | 寛容と敬意(「違い」から学ぼうとする) |
| 対話 | 避ける(面倒、無意味だと諦めている) | 求める(より良い答えを共に探そうとする) |
ここで、大切なことを付け加えさせてほしい。
「絶対的な正解はない」からといって、全ての価値観が、全く同じように等しい価値しか持たない、ということでは決してないんだ。
むしろ、道徳的相対主義は、私たちに、こう問いかけてくる。
「絶対的な神や王が、もう答えをくれないのだとしたら。私たちは、私たち自身の力で、その時代、その文化、その共同体の中で、最も合理性があり、より多くの人の幸福に繋がる『より良い価値観』を、絶えず粘り強く探求していく責任があるのではないか?」
と。
この、「より良い答えを探し続ける」という、誠実な姿勢。
それが、「しなやかな相対主義」の、まさに心臓部にあたる部分なんだ。
そして「対話」だけが、分断された私たちを繋ぎとめる
絶対的な、たった一つの答えがなく、誰もが少しずつ違う地図を手にしている。
そんな、少しだけ頼りなく、そしてだからこそ、豊かなこの世界で。
それでも、私たちが、ほんの少しでもより良い方向へと一緒に進んでいくためにできることは、たった一つしかないよ。
それが、「誠実な対話」だね。
ここで言う「自分の軸」とは、他人を論破するための硬い棍棒のようなものではない。
それは、あくまで「対話に参加するための、あなただけの出発点」だ。
そして、その軸自体が、他者との真剣で温かい対話を通じて、いつでも修正され、改善される可能性がある。
そんな「開かれた軸」でなくてはならない。
そうでなければ、それはただの独りよがりな考え、「独善」になってしまうからね。
哲学者のハーバーマスといった思想家たちは、こう考えたんだ。
「正解は、どこか天上にあらかじめきらきらと“在る”ものではない。それは、異なる意見を持つ私たち人間が、お互いを一人の人間として深く尊重しながら、真剣に言葉を尽くして話し合う。その、骨の折れるプロセスの中で、その都度その都度、必死に“創り出していく”ものなのだ」
と。
道徳的相対主義は、この本当の意味での対話を始めるための、いわば心と体の「準備運動」のような、大切な役割を果たしてくれるんだ。
つまり、「自分の信じる正しさが、唯一絶対のものではないのだ」と、心の底から知るからこそ、私たちは、初めて本物の謙虚さを、その身にまとい、他者の、か細い声に真剣に耳を傾けることができるようになるんだよ。
道徳的相対主義の、本当の本当の目的は、人々を「どうせ、人それぞれだから」と、バラバラに冷たく孤立・分断させることでは、決してない。
むしろ、全くその逆だね。
「私たちは、違う。だからこそ、話さなければならない」
この、真の意味での対話への、重くしかし希望に満ちた扉を開くこと。
それこそが、この少しだけ複雑な思想が、今の私たちに与えてくれる、最も大きくてそして最も温かい、贈り物なのだと、私はそう信じているよ。
【この章のポイント】
相対主義には、明確な限界がある。
「人間の尊厳」に関わる「絶対悪」の前では、私たちは、決して、沈黙してはならない。
私たちが目指すべきは、確固たる「開かれた軸」を持ち、「より良い価値観」を探求し続ける「しなやかな相対主義」という在り方。
絶対的な正解がない世界で、私たちがより良い答えを見つけ出す唯一の方法は、誠実で、そして、根気強い「対話」を、続けること。
まとめ

お疲れさまでした。
最後に、この記事を通じて、私があなたに一番伝えたかったことについて、本当にほんの少しだけ、お話しさせてほしい。
道徳的相対主義は、あなたを、ああでもないこうでもないと迷わせるための小難しい哲学ではないよ。
この、どこまでも複雑でままならない世界を、あなたの心が少しでも楽に、そしてしなやかに生きていくための、ささやかな「思考の道具」だ。
それは、絶対的な正解をずばりと言い当ててくれる、便利な「答えの書」ではないよ。
そうではなくて、あなた自身が、あなただけの納得できる答えを、手探りで見つけていく、その長い道のりで、きっと役に立つ「地図」や、進むべき方向をそっと照らしてくれる「心の指針」のようなもの。
そんな風に、思ってみてほしい。
この記事の、たくさんの言葉たちを、明日からのあなたがふとした瞬間に思い出せるように。
3つのとてもシンプルな指針として、ここにそっと残しておくね。
まず、あなたの「開かれた軸」を持つこと。
流されないために、「これだけは譲れない」と、あなたが心の底から思えることは、一体何だろうか。それを、対話の出発点として自分自身に優しく問いかけてみて。
次に、あなたの「正しさ」を、ほんの少しだけ疑ってみること。
「自分の見え方が、世界の全てでは、ないのかもしれないな」という、そのささやかで愛おしい謙虚さが、あなたの心に驚くほど大きな、ふかふかの余裕を生んでくれるんだ。
そして、違いを恐れず、「対話」を始めること。
私たちは、違う。だからこそ、話さなければならないんだ。その、少しだけ勇気のいる、しかしとても尊い出発点として、「私は、こう思うんだ」と、あなたのありのままの言葉で誠実に伝えてみてほしい。
このたった3つのステップこそが、私たちが目指すべき、あの「しなやかな相対主義」への、確かでそしてとても具体的な道筋だよ。
世界に絶対的な正しさが、もしないのだとしたら。
それは、一見すると少しだけ足元がぐらつくような、不安なことのように思えるかもしれないね。
しかし、見方を変えれば、それは、私たち一人ひとりが、自分自身の「正しさ」を、他者との温かい対話を通じて、自分たちの手でゆっくりと丁寧に創り上げていく。そんな壮大な自由と、そしてさわやかな責任を与えられている、ということでもあるんだ。
完璧な答えなど、おそらくこの世界のどこにもないのだろう。
だからこそ、私たちは、迷い、学び、時に傷つき、そして人と関わり合いながら、その時々で自分だけの小さな小さな納得解を探し続けることができる。
その、不器用でままならない、プロセスそのものが、人間としてこの時代を生きるということの本当の豊かさなのかもしれないね。
最後まで読んでくださった、あなたのその素晴らしい知的な探求心と、現状をほんの少しでもより良くしようと願う、その真摯な気持ちに、心からの敬意とそして感謝を。
この記事が、あなたの明日からの人間関係や、情報との少し厄介な向き合い方にとって、ささやかながらも確かな心の指針となれば、私にとって、それ以上に嬉しいことはないよ。
…このブログでは、他にも様々な角度から、あなたの人生がより良いものになるための考え方や視点について、日々研究し、言葉を紡いでいるよ。
もしよろしければ、他の記事も覗いてみてほしいな。
【こちらの記事も読まれています】