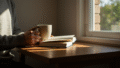なぜか消えない漠然とした不安に、心が疲れていませんか?
考えすぎてしまう夜、本当にしんどいですよね。
この記事を読み終える頃、あなたは「まあいっか」と物事を軽やかに受け流せるようになり、穏やかな気持ちで一日を終えられる、そんな自分に出会えるはずです。
そのために、この記事ではあなたの不安の正体を優しく解き明かし、明日からすぐに使える、驚くほどシンプルな3つの「思考の道具」をお渡しします。
これは単なる精神論ではなく、2000年以上もの間、偉人たちの悩みに寄り添い続けた「哲学」という、人類の確かな知恵に基づいています。
「考えすぎてしんどい…」哲学は、そんなあなたのための思考法
仕事のプレッシャー、将来のこと、ちょっとした人間関係のすれ違い…。
ベッドに入ると、様々な考えが頭の中を駆け巡って、気づけばもう深夜。
その気持ち、本当によくわかります。
何を隠そう、かつての私もそうでした。
いつも頭の片隅にモヤモヤとした霧がかかっているような感覚で、心から休まる日がなかったように思います。
実は、心理学の研究などでも、私たちの悩みの多くは
「自分ではコントロールできない過去や未来、他人のこと」
に関するもので、それが大部分を占めると言われています。
だからこそ、この記事のタイトルは「9割の不安は解消できる」なんです。
その大部分を占める悩みに対する“考え方”さえ変えることができれば、驚くほど心は楽になる。
そのための知恵が、哲学には詰まっています。
この記事では、そのための具体的な方法を、一つひとつ丁寧に解説していきますね。
「哲学」と聞くと、なんだか小難しくて、自分にはあまり関係のない学問のように感じてしまうかもしれませんね。
ですが、不安解消に哲学がこれほどまでに有効なのは、それが単なる学問ではないからです。
哲学とは、悩みを解決するために、人類の知恵が詰まった「思考の道具箱」であり、私たちの「心のOS」をアップデートするための、実践的なプログラムのようなものなのです。
古代ローマの皇帝やギリシャの偉大な賢者たちも、私たちと全く同じように、仕事や人間関係に深く悩んでいました。
哲学とは、そんな彼らが2000年以上もかけて検証し続けてきた、いわば「人類の悩みのビッグデータ」。
この記事では、その知恵を解説するだけでなく、『仕事のミス』や『SNSでの落ち込み』といった日常の具体的な悩みへの応用例(ケーススタディ)も交えながら、あなたが明日からすぐに使える形でお届けします。
さあ、準備はよろしいでしょうか。
あなたの心を縛る重荷を、一緒に解き明かしていきましょう。
【この章のポイント】
あなたの悩みの9割は「コントロールできないこと」。だからこそ哲学の思考法が有効です。
この記事では、悩みを解消するための具体的な「思考の道具」とその使い方を、応用例も交えて解説します。
哲学とは、2000年以上続く、悩みを解決するための実践的な「心の技術」です。
【不安の正体】まず知ることから。あなたの「なぜか不安」を哲学で解き明かす
「こんなことで不安になるなんて、自分の心が弱いからだ…」
もし、あなたが心のどこかで、ご自身をそんな風に責めてしまっているとしたら。
まず最初に、これだけははっきりとお伝えさせてください。
その不安は、あなたの意志の弱さとは、全く関係ありません。
実は、私たちの脳には「扁桃体(へんとうたい)」という部分があります。
これは、別名「情動の司令塔」とも呼ばれ、好き・嫌いや快・不快といった、感情の基本的な色付けを行っている場所です。
危険や脅威を瞬時に察知し、情動反応を引き起こす脳の部位の一つですね。
そして、この偏桃体は、危険を察知するための、非常に優秀な「火災報知器」のような役割も担っています。
本来、この報知器は、命の危険があるような本物の“火事”が起きた時に、私たちに警告してくれる大切な生存システムです。
でも、ストレスの多い現代社会では、この優秀な報知器が、少し敏感になりすぎてしまっているようなのです。
例えば、上司からの厳しいメールや、SNSでの誰かの何気ない一言といった、いわば“湯気”のようなものにまで、全力で反応して「火事だ、火事だ!」とサイレンを鳴らしてしまう。
これが、私たちの感じる「不安」の、脳科学的な正体の一つです。
この過剰な反応は、人間がまだ自然の中で暮らしていた頃、常に危険と隣り合わせの環境で生き延びるために備わった、大切な名残でもあります。
つまり、あなたが不安を感じやすいのだとしたら、それは、あなたを守るための防衛システムが、人一倍まじめに、忠実に働いてくれている証拠なんです。
まずは、「いつも守ってくれてありがとうね」と、ご自身の脳を、そっと労ってあげてみてください。
脳の報知器が鳴りやすい、ということは、なんとなくご理解いただけたかと思います。
では、一体「何が」その報知器のボタンを、何度も押してしまっているのでしょうか。
その引き金を引いているのが、実は私たち自身の、無意識の「心の癖」なのです。
ストア哲学などの賢者の教えを紐解いていくと、その「心の癖」は、驚くほどシンプルで、大きく分けて3つのパターンに集約されていきます。
【不安を生み出す3つの「心の癖」】
-
コントロールできないことへの執着
-
「あの人は私のことをどう思っているんだろう」「将来、会社は大丈夫だろうか」といった、自分ではどうにもならないこと、変えられないことを、どうにかしようともがいてしまう癖です。
他人の評価や未来の出来事は、まさにこの代表例ですね。
-
-
「今、ここ」にいない心
-
意識が、すでに終わってしまった過去への後悔(ああすればよかった…)か、まだ来ていない未来への心配(もし失敗したらどうしよう…)のどちらかに飛んでしまっている状態です。
心が常に未来や過去に飛んで“留守”になっていて、目の前のことに集中できていない感覚、といえば分かりやすいでしょうか。
-
-
「完璧でなければならない」という思い込み
-
完璧主義からくる不安は、非常に根深いものです。
「仕事は完璧にこなすべきだ」「人から嫌われるべきではない」といった、「~べき」という思考に、知らず知らずのうちに心を縛られてしまう癖です。
-
いかがでしょうか。
あなたのモヤモヤとした不安も、このどれかに当てはまるような気がしませんか。
でも、安心してください。
これらは、あくまで長年かけて身についた「癖」です。
そして、癖である以上、正しい「思考の道具」の使い方を学べば、少しずつ、でも確実に、手放していくことができます。
次の章では、そのための具体的な方法を見ていきましょう。
【この章のポイント】
不安を感じるのは、あなたの意志が弱いからではなく、脳の防衛システムが正常に働いている証拠です。
その不安の引き金を引いているのは、「コントロールできないことへの執着」「今にいない心」「完璧主義」という3つの「心の癖」です。
これらは「癖」なので、正しい方法を学べば、必ず手放していくことができます。
【実践編】不安を手放す哲学の思考法3選|心のOSをアップデートしよう
さて、ここからはいよいよ実践編です。
あなたの不安を生み出している「心の癖」を、少しずつ手放していくための、具体的で強力な「思考の道具」を3つご紹介します。
これらの思考法は、あなたの不安を解消し、「まあいっか」と軽やかに思えるようになるための、いわば心のトレーニングです。
難しく考える必要はありません。
まずは「へえ、そんな考え方があるんだ」と、気楽な気持ちで読んでみてくださいね。
「上司の機嫌が悪いのは、もしかして自分のせいだろうか…」
「あの人は、私のことを本当はどう思っているんだろう…」
ストア派哲学が教える不安との向き合い方は、非常にシンプルです。
私たちの悩みの多くは、このように、他人の感情や評価といった“自分以外の何か”が中心になっていることが、本当に多いものです。
そんな時に絶大な効果を発揮するのが、「課題の分離」という思考法です。
これは、あなたの頭の中にある悩みを、
-
自分にコントロールできること
-
自分にはコントロールできないこと
この2つに、くっきりと分ける思考の技術です。
ストア派の哲学者エピクテトスは、その主著『エンキリディオン(Enchiridion)』(通称『ハンドブック』)の中で、こう語っています。
「我々を悩ますのは物事そのものではなく、物事に対する我々の意見である」
現代風に分かりやすく言うと、こんな感じでしょうか。
「“雨が降っている”という事実は、あなたを濡らすだけだ。しかし、“せっかくの休みなのに最悪だ”というあなたの解釈が、あなたの心を不幸にするんだよ」
つまり、私たちが本当に向き合うべきは、「コントロールできない事実」ではなく、「コントロールできる自分の解釈」だけだ、ということです。
▼ やってみよう 悩みを2つの箱に仕分ける
さあ、あなたの番です。
今、心の中にあるモヤモヤとした悩みを、スマホのメモ帳か、手近な紙でいいので、この2つの箱に仕分けてみてください。
| 自分にコントロールできること | 自分にコントロールできないこと |
| ・今日の自分の行動 | ・他人の評価、機嫌 |
| ・仕事の提出物の質 | ・過去の失敗 |
| ・人への丁寧な言葉遣い | ・未来の景気 |
| ・物事の受け止め方 | ・電車の遅延 |
どうでしょうか。
驚くほど多くの悩みが、右側の「コントロールできないこと」の箱に入りませんでしたか?
ストア哲学によれば、その箱に入ったものは、今日からあなたの“課題”ではありません。
そこにエネルギーを注ぐのをやめるだけで、心の大部分は晴れていきます。
そして、
あなたの貴重なエネルギーのすべてを、左側の「コントロールできること」だけに集中させる。
これができれば、あとは「人事を尽くして天命を待つ」という心境、つまり「まあいっか」と思えるようになるのです。
パソコンで仕事をしているはずなのに、頭の中は週末のプレゼンのことでいっぱい…。
友人と食事をしているのに、ふと過去の失敗を思い出して、心から楽しめない…。
私たちの心は、本当によく“旅”に出ます。
「今、この瞬間」を留守にして、まだ起きていない未来か、もう変えられない過去のどちらかへ、さまよい出てしまうのです。
この思考法は、そんな風にさまよってしまったあなたの意識を、「今、この瞬間」に、力強く引き戻す技術です。
哲学者のセネカは、『道徳書簡集』の中でこう言っています。
「我々は現実においてよりも、想像においてより多く苦しむ」
彼は、未来を憂うあまり「今」という唯一の確かな時間を失ってしまうことの愚かさを、誰よりも深く理解していたのでしょう。
この古代の知恵は、現代のマインドフルネスの考え方と、驚くほどよく似ています。
▼ やってみよう 五感を味わう練習
難しいことは、何もありません。
不安が襲ってきたら、意識を「思考」から「五感」へと、そっと切り替えてあげてください。
例えば、温かいお茶を飲むとき。
ただ何となく飲むのではなく、
-
(視覚)湯気や、お茶の美しい色を、じっと眺めてみる。
-
(嗅覚)立ち上る香りを、ゆっくりと楽しんでみる。
-
(触覚)カップを持つ手のひらの、温かさを感じてみる。
-
(味覚)口に含んだお茶が、舌の上で広がる感覚を、ただ味わう。
未来や過去という“物語”の世界から抜け出し、「今、ここ」に心をつなぎとめる。
そうすれば、「先のことはわからないけど、まあいっか」と、目の前のことに集中できるようになります。
「もっと頑張るべきだ」
「人から嫌われるべきではない」
「失敗は、決してすべきではない」
完璧主義からくる不安は、真面目で、誠実な人ほど、心を縛りつけます。
そんなあなたに、そっとお渡ししたいのが、哲学の祖・ソクラテスが遺した、「無知の知」という、心の“お守り”です。
「自分は何も知らない、ということを知っている」
これは単に開き直ることではありません。
「人間とは、そもそも不完全で、間違う存在なのだ。だから、全てを知っているなんてことはありえない」
という、ある種の“健全な諦め”を持つための考え方。
古代ギリシャで最高の賢者と讃えられたソクラテスでさえ、自らを「無知」だと言ったのです。
だとしたら、私たちが完璧でなくても、知らないことがあっても、それは当たり前のこと。
『無知の知』は、何もかも完璧に知っているという傲慢さを捨て、自分にはまだ知らないことがあるという謙虚さを自覚することで、真の知恵を求める姿勢へとつながるものです。
大切なのは、「不安ゼロ」を目指すことではありません。
アリストテレスが説いた「中庸(ちゅうよう)」のように、ちょうどいい“真ん中”の付き合い方を見つけることです。
▼ やってみよう 言葉の言い換えトレーニング
もし、あなたの頭の中に「~べき」という言葉が浮かんできたら。
今日から、それを「~できたらいいな」と、心の中で、そっと言い換えてみてください。
「完璧にこなすべき」→「完璧にできたらいいな」
たったこれだけで、あなたの心を縛っていた固いロープが緩み、その隙間に、「まあ、いっか」という、人にも、自分の心にも優しい気持ちがきっと生まれてくるでしょう。
【この章のポイント】
課題の分離 悩みを「コントロールできること」と「できないこと」に分け、後者は手放しましょう。
今への集中 五感を使って意識を現在に戻すことで、「まあいっか」と目の前のことに集中できます。
無知の知 人間は不完全で当たり前。「~べき」という完璧主義を手放し、自分を許してあげましょう。
【ケーススタディ】日常の“あるあるな悩み”を哲学で乗り越える方法
さて、3つの思考法をご紹介しましたが、「じゃあ、実際の生活でどう使えばいいの?」と思われるかもしれませんね。
この章では、私たちが日常でつい陥りがちな、具体的な悩みの場面を取り上げて、哲学の「思考の道具」をどう使えば、気持ちが楽になるのかを一緒にシミュレーションしてみましょう。
誰にでも経験がある、本当に辛い状況。
頭の中が「どうしよう」「なんて思われただろう」でいっぱいになってしまいます。
こんな時こそ、3つの道具を順番に使ってみましょう。
-
まず「課題の分離」で、状況を整理する。
-
コントロールできないこと
-
起きてしまったミス(過去)
-
上司や同僚の評価、感情
-
-
コントロールできること
-
誠実に謝罪し、報告すること
-
同じミスを繰り返さないための対策を考えること
-
今できる、目の前の仕事に集中すること
-
-
-
次に「無知の知」で、自分を許す。
-
「人間だから、ミスをするのは当たり前。完璧じゃなくていいんだ」と心の中で呟いてみてください。自分を責めすぎることが、一番のエネルギーの無駄遣いです。まずは、「まあ、いっか。次頑張ろう」と自分に声をかけてあげましょう。
-
-
最後に「今、ここ」に集中する。
-
ぐるぐると考えが止まらなくなったら、一度席を立って、温かいコーヒーでも淹れてみませんか。そして、その香りや温かさだけに、1分間だけ集中してみる。暴走する思考をリセットし、「今できること」に意識を戻すための、大切な時間です。
-
このように、道具を組み合わせることで、ただ落ち込むだけではなく、次への具体的な一歩を踏み出せるようになります。
SNSを開けば、輝いて見える他人の人生が目に飛び込んでくる…。
自分の人生が、なんだか色褪せて見えてしまう時、ありますよね。
この悩みには、「課題の分離」が特に有効です。
-
他人の人生は、その人の「課題」であり、あなたの「課題」ではない。
-
友人がどこで何をして、どんな評価を得ているか。それは、完全に「コントロールできないこと」であり、あなたが悩むべき問題ではありません。
-
-
見えているのは、編集された“ハイライト”に過ぎない。
-
SNSは、その人の人生の“良い部分”だけを切り取ったダイジェスト版です。その裏にある悩みや苦労は、決して見えません。私たちは、他人のハイライトと、自分の日常(舞台裏も含む)を比べて、勝手に落ち込んでいるだけなのです。
-
「これは私の問題じゃないな。まあ、いっか」
そう思えたら、そっとスマホを閉じて、あなたが今、本当に大切にしたいこと(例えば、目の前の本を読む、家族と話すなど)に、時間を使ってあげてください。
キャリア、お金、人間関係…。
考えれば考えるほど、未来は不確かで、不安になりますよね。
この「漠然とした未来への不安」は、まさに「今、ここ」にいない心の状態です。
-
コントロールできない未来を、今悩んでも仕方がない。
-
未来のことが不安なのは、それが「コントロールできないこと」だからです。考えても答えの出ない問題に、大切な睡眠時間を捧げるのは、本当にもったいないことです。
-
-
今できることは、ただ一つ。「今日、しっかり休む」こと。
-
未来のために「今」できる最善のことは、明日の自分を万全の状態にしてあげることです。つまり、ぐっすり眠ること。それが、一番合理的で、未来の自分への最高のプレゼントになります。
-
ベッドに入って不安が襲ってきたら、
「未来のことは、未来の私に任せよう。今日の私の仕事は、休むこと。まあ、いっか」
と心の中で宣言してみてください。
そして、意識を「思考」から「身体の感覚」へと移してみましょう。
布団の温かさや、枕の柔らかさに意識を向ける。
それだけで、心は少しずつ、静けさを取り戻していきます。
【この章のポイント】
仕事のミスには、3つの思考法を組み合わせて対処しましょう。
SNSでの焦りは、「課題の分離」で、自分と他人を切り離すことで楽になります。
未来への不安は、「今、ここ」で休むことに集中することで、手放すことができます。
【Q&A】「頭では分かるけど…」あなたの“できない”に寄り添う哲学のヒント
ここまで、具体的な思考法や使い方を見てきました。
もしかしたら、
「なるほど、理屈はわかった。でも、いざやろうとすると、感情がついていかないんだよな…」
と感じている方も、いらっしゃるかもしれません。
大丈夫です。
その感覚は、全くおかしなことではありません。
この章では、そんなあなたの「わかっているけど、できない…」という正直な気持ちに、とことん寄り添ってみたいと思います。
Q. 頭では「コントロールできないことだ」と分かっていても、どうしても考えてしまう時は、どうすればいいですか?
A:自然なことなので、無理に止めようとしないで大丈夫。
まず、考えてしまうご自身を、決して責ないでください。
私たちの思考には、長年の癖のようなもの、いわば「慣性の法則」が働いています。
ずっと考え続けてきたことを、今日からピタッと止めるのは、猛スピードで走る車が急に止まれないのと同じで、とても難しいことなのです。
大切なのは、「考えないようにすること」ではありません。
「あ、また考えてしまっているな」と、それに“気づく”ことです。
そして、気づいたら、心の中でこんな風に実況中継してみてください。
「お、今私は『コントロールできない他人の評価』について、考えているな」と。
感情の渦に飲み込まれるのではなく、それを客観的に観察する。
心理学では「ラベリング」と呼ばれる、とても効果的な方法です。
もう一つ、試してみてほしいのが「5分ルール」です。
無理に考えるのをやめようと抵抗するのではなく、逆に「よし、今から5分だけ、このことについて本気で悩もう!」と、時間を区切ってしまうのです。
タイマーをセットしてもいいでしょう。
そして、5分経ったら、「はい、おしまい!」と、意識的に別の作業(例えば、コーヒーを淹れるとか、好きな音楽を聴くとか)に移る。
考えてしまう自分を否定せず、むしろ悩む時間に“許可”を与えることで、不思議と心は落ち着いていくものです。
「まあいっか、5分だけなら」と、気軽に試してみてください。
Q. SNSでキラキラしている友人や同僚を見ると、つい自分と比べてしまい、焦りや不安な気持ちになります。どうしたらいいですか?
A:「課題の分離」の応用と、物理的な距離を置くことが有効です。
友人の結婚報告、同僚の昇進、キラキラした海外旅行の写真…。
SNSを開けば、編集された他人の“ハイライト”が、次々と目に飛び込んできます。
それを見て、自分の人生がなんだか色褪せて見えてしまう…。
本当に、しんどい気持ちになりますよね。
実は、人間の脳は、もともと他者と比較することで、自分の立ち位置を確認するようにできています。
そしてSNSは、その脳の性質を、最大限に増幅させてしまう仕組みになっているのです。
つまり、あなたが焦りを感じてしまうのは、ある意味で、当然のこと。
あなたは、人類の歴史上、最も他人と比較しやすい、過酷な環境にいるのですから。
そんな時にこそ、思い出してほしいのが「課題の分離」です。
SNSで見える他人の人生は、あくまで「その人の課題」です。
それは、決してあなたの課題ではありません。
そして、それはその人の人生の、ほんの一部を切り取って、綺麗に編集したものに過ぎない、という事実も忘れないでください。
その上で、もし気持ちが楽にならないのなら、物理的に距離を置くというのも、非常に賢明で、有効な解決策です。
-
寝る前の1時間は、スマホに触らない
-
週末だけ、SNSのアプリをホーム画面から隠してみる
-
特に気持ちが落ち込んでいる時だけは、見ないようにする
思考法だけで何とかしようとせず、自分を守るための「環境」を整えてあげる。
これもまた、自分を大切にするための、立派な知恵だと思います。
【この章のポイント】
考えてしまう自分を責めず、「考えているな」と気づくことが大切です。
SNSでの比較は、「課題の分離」と物理的な距離を置くことで対処しましょう。
まとめ 哲学は一生使える「お守り」。あなたの心が楽になる確かな一歩

あなたの心を縛り付けていた、漠然とした不安の正体。
それは、
①コントロールできないことへの執着
②「今、ここ」にいない心
③完璧主義
という、3つの「心の癖」でした。
そして、それらの癖から心を自由にするための道具が、
「課題の分離」「今への集中」「無知の知」
という、古代から受け継がれてきた哲学の知恵です。
これらの思考法は、一度きりのテクニックではありません。
これからあなたが人生で何度も出会うであろう、様々な悩みや困難の場面で、あなた自身を守り、進むべき道をそっと照らしてくれる、一生使える「お守り」のようなものです。
哲学を学ぶということは、誰かの価値観や、目まぐるしく変わる外部の状況に振り回されることなく、あなたの中に、静かで、しかし揺るぎない「心の指針」を、ゆっくりと育てていくことでもあります。
さあ、そのための、本当に小さな、
しかし、最も確かな第一歩を、今ここから踏み出してみませんか。
最後に、一つだけ。
このリストを「全部やらなきゃ」と、どうか気負わないでくださいね。
一つでも「やってみようかな」と思えたら、それだけで100点満点です。
「まあいっか、これくらいなら」そんな優しい気持ちで、眺めてみてください。
【最初のアクションリスト】
□ 窓を開けて、いつもより3秒だけ長く、ゆっくりと息を吐いてみる。
□ スマホのメモ帳に、一番心に残った哲学者の言葉を、一つだけ書き出してみる。
□ 今夜寝る前に、今日一日であった「まあ、いっか」と思えたことを、一つだけ思い出してみる。
□ ノートの最初のページに、「これは、私の課題か?」とだけ、お守りのように書いてみる。
もし、この中のどれか一つでも試してみようと思えたなら、それは、昨日までのあなたより、遥かに大きな、素晴らしい一歩。
あなたの心が、少しでも穏やかな静けさを取り戻し、あなたらしい日々を送れるようになることを、心の底から願っています。
大丈夫。
哲学という古くからの知恵が、これからは、いつもあなたのそばにいます。
【こちらの記事も読まれています】

今回の「不安」というテーマだけでなく、このブログでは、あなたが自分にとっての「豊かさ」や「幸せ」とは何かを探求していくための、様々な考え方のツールを発信しています。
もし、ご自身の「幸せ」について、もう少しだけ深く考えてみたくなったなら、こちらの記事も、きっとあなたの「心の指針」を見つける手助けになるはずです。
【読んでくださった方へ】
この記事は、哲学の知恵を日常生活に活かす考え方を発信することで、気持ちを楽にすることを目的としています。
医学的・心理学的な診断や治療に代わるものではありません。
もし、日常生活に支障をきたすほどの深刻な不安や心の辛さを感じている場合は、決して一人で抱え込まず、専門の医療機関やカウンセラーにご相談ください。