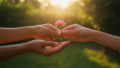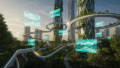「考えがまとまらない」
「いつも同じことで悩んでしまう…」
そんな風に、頭の中がごちゃごちゃになっていませんか?
この記事を読めば、情報に振り回されずに物事の本質が見え、あなた自身の判断に、すっと自信が持てるようになりますよ。
この記事では、あなたの頭を柔らかくし、深く考える力を養う、具体的な『50の思考トレーニング』を厳選してご用意しました。
それは、難解な学問ではなく、古くから伝わる哲学の知恵を、今のあなたの日常で、すぐに使えるようにしたものです。
さあ、一緒に「考える力」を、少しずつ鍛えていきましょう。
その悩み、「思考停止」が原因かも?哲学で「考える力」を鍛えるための第一歩

会議で、なんだかうまく意見がまとまらない。
たくさんの情報を見聞きして、何が本当に正しいのか分からなくなって、頭の中がごちゃごちゃになってしまう。
ぐるぐると、いつも同じ場所を回っているような感覚がして、抜け出せないのがしんどいですよね。
それは、あなたの「考える力」が少しだけ、お休みしているサインなのかもしれませんね。
少しだけ、ドキッとする言葉だったでしょうか。
でもね、私たちは日々、
知らず知らずのうちに「思考停止」に陥りやすい環境で生きていますから。
次から次へと、スマホから流れてくる情報。常に求められる素早い判断。
じっくりと一つの物事に向き合う時間が、社会全体からふわりと消えつつある。
だから、考える力が鈍ってしまうのは、ある意味で仕方のないことなのですよ。
決して、あなたの能力や才能の問題ではありません。
ただ、考えるための「習慣」や、ちょっとした「型」を知らなかった。
本当に、ただそれだけのことなんです。
この記事は、小難しい哲学の理論を解説するものではありません。
いわば、あなたの頭脳のための「思考のジム」。
ごちゃごちゃした頭の中をスッキリさせ、物事の本質を見抜くための、具体的な「思考のトレーニングメニュー(=50の問い)」を厳選してご用意しました。
このトレーニングを続けることで、あなたは、
-
物事の本質を、落ち着いて見抜けるようになる
-
情報に振り回されず、自分なりの判断に自信が持てるようになる
-
日々の悩みや人間関係が、少しずつ気持ちの楽なものに変わっていく
そんな変化を、きっと実感できるはずです。
理論は、後からついてくれば大丈夫。
何より大切なのは、まずあなたの頭を、実際に動かしてみることですから。
さあ、準備運動はここまで。
あなたの眠っている思考力を呼び覚ます、最初の一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。
【この章のポイント】
多くの悩みは、能力ではなく「思考停止」という習慣が原因かもしれない、ということですね。
この記事は、具体的な「問い」を通じて「考える力」を鍛える、実践的なトレーニング集です。
誰でも、正しいトレーニングを積めば、後から「考える力」を伸ばすことができるのですよ。
【哲学で思考を鍛える】実践トレーニング問題50選
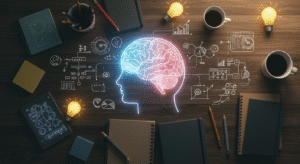
さあ、ここからが、あなたの思考を実際に動かしていく時間です。
50の問いを、思考の範囲を少しずつ広げていく4つのステップに分けてご用意しました。
①日常 → ②自分 → ③仕事・他者 → ④世界
こんな風に、ごく身近なところから少しずつ視野を広げていく構成になっています。
もちろん、すべてを順番通りにやる必要なんてありませんよ。
今のあなたが最も心惹かれるステップから、ピンときた問いを一つだけ選んで、少しだけ考えてみてください。
大切なのは、立派な答えを出すことよりも、「問いと向き合う」その時間そのものですからね。
STEP1「前提を疑う」練習問題 日常の思い込みを外す思考トレーニング
【こんな方に】
-
周りの意見に、つい流されてしまうことが多い
-
たくさんの情報に振り回されて、なんだか疲れてしまう
-
クリティカルシンキングの基礎を身につけたい
まずは、凝り固まった頭をほぐす、準備運動からです。
私たちが普段、無意識に「当たり前」だと思っていること。
その見えない思考の枠に気づいて、優しく揺さぶりをかけるためのトレーニングですよ。
それではどうぞ。
-
あなたが毎日「なんとなく」続けている習慣は、本当に今日のあなたにとって必要ですか?
-
いつも使う通勤・通学路。今日は「初めてこの道を歩く探検家」だとしたら、何に気づき、何を感じますか?
-
「常識的に考えて…」という言葉を聞いた時、その「常識」とは、一体誰にとっての常識でしょうか?
-
「時間がない」と口にしてしまう時、それって「事実」ですか?それとも、あなたの「解釈」ですかね?
-
あなたが「普通」だと思っていることは、地球の裏側に住む人にとっても「普通」だと思いますか?
-
ニュースの見出しを見て感じたその「第一印象」。それ、誰かにそう思わせるように作られたものではないでしょうか?
-
なぜ多くの人は、文句も言わずに列に並んで順番を待つのでしょう?
-
あなたが「正しい」と信じていること。その考えを持つことで、あなたが得をしていることは何ですか?
-
もし、今日一日スマホを使わずに過ごすとしたら、どんな良いことがあり、どんな不都合がありそうですか?
-
「大人になる」って、具体的にどういう状態になることだと思いますか?
-
いつも行くコンビニやスーパー。もしあなたが商品の配置を決める担当者なら、今と何を変えますか? なぜでしょう?
-
今あなたが信じている健康法や食事法は、50年後も「正しい」とされているでしょうかね。
-
つい「すみません」と謝ってしまう場面。本当に謝るべきは誰で、何に対してでしょうか?
-
なぜ学校の授業は、きれいに科目ごとに時間が区切られているのでしょうか?
-
あなたが「これはこういうものだ」と諦めていること。もし、その前提が、根っこから間違っていたとしたら?
さて、このSTEP15個の問いの中で、あなたが最も『ドキッ』としたのは何番でしたか?
まずはその問いの番号だけでも、手帳に書き留めてみましょう。
STEP2「自己分析」を深める問題|メタ認知で自分の本音を知るトレーニング
【こんな方に】
-
自分が本当に何をしたいのか、時々わからなくなる
-
自分の感情の起伏に、自分で振り回されてしまうのがしんどい
-
自分なりの「心の指針」を見つけたい
次は、あなた自身の内側へと、少し深く潜ってみましょうか。
自分でも気づいていない、自分の心の中にある本当の願いや価値観を探る。
自分という、最も身近で最も謎多き存在と、じっくり向き合う時間です。
-
最近、あなたが「怒り」や「嫉妬」で心がザワザワしたのはどんな時ですか?その感情の奥には、どんな「願い」が隠されていますか?
-
もし、お金や時間の制約が、本当に、一切なかったとしたら、明日の午前中、何をしますか?
-
あなたが「絶対に許せない」と感じること。それを許せないのは、あなたが何を、心の底から大切にしているからでしょうか?
-
10年前の自分に、今のあなたがアドバイスをするとしたら、たった一つだけ、何を伝えますか?
-
どんな言葉をかけられると、あなたは「ああ、この人は分かってくれているな」と、じんわり感じますか?
-
あなたの「弱み」だと思っている部分。見方を変えれば、それはどんな「強み」や「魅力」になりますか?
-
最後に「時間を忘れるほど夢中になった」のはいつですか? 何をしている時でしたか?
-
「本当の自分」という言葉がありますが、あなたにとって「嘘の自分」を演じているのは、どんな瞬間ですかね。
-
あなたが今、一番「怖い」と感じていることは何ですか?その怖さの正体って、一体何だと思いますか?
-
他人の評価を一切気にしなくてよいなら、あなたはどんな服を着て、どんな髪型をしますか?
-
あなたが「ああ、豊かだなあ」と、しみじみ感じるのは、どんな瞬間ですか?
-
今のあなたが、人生で最も「感謝している」人や物事は何ですか?
-
あなたが「学ぶ」のは、一体何のためですか?
-
人生で一番「お金をかけてよかった」と思うものは何ですか?それはなぜですか?
-
あなたの人生という物語の「主人公」は、今、何をしようとしているのでしょうか?
このSTEPで、一番あなたの心に引っかかった問いは何でしたか?
その問いを、しばらく考えてみるのもいいかもしれませんね。
STEP3「本質を見抜く」応用問題|仕事と人間関係の課題解決力を鍛える
【こんな方に】
-
会議や商談で、もっと的確な意見が言えるようになりたい
-
対人関係の悩みが尽きず、気持ちが楽にならない
-
目の前の問題に対して、もっと根本的な解決策を見つけたい
ここからは応用編です。
STEP1と2で手に入れた視点を、日常の具体的な課題解決に活かしてみましょう。
物事の表面ではなく、その裏側にある「構造」や「本当の目的」を見抜く力を養います。
これができると、ぐっと楽になりますよ。
-
今あなたが取り組んでいるその仕事は、最終的に「誰の」「どんな感情」を動かすためのものですか?
-
なぜか意見が合わないあの人。その人は、その主張をすることで、一体何を「守ろう」としているのでしょうか?
-
もし、あなたが今の上司(あるいは部下)の立場だったら、今のあなた自身をどう評価し、どう動かしますか?
-
この会議の「本当の目的」って何でしょう?もし3分で終わらせるとしたら、何を決めますか?
-
その「問題」が解決したら、次にどんな問題が起こると思いますか?
-
失敗の原因は「誰か」のせいですか?それとも、同じ失敗を繰り返させる「仕組み」のせいですか?
-
なぜ、そのルールは存在するのでしょうか?そのルールがなかったら、誰が一番困りますかね?
-
あなたが「すごいな」と尊敬する人は、あなたと何が決定的に違いますか?
-
相手に何かを頼む時、「期待していること」を具体的な言葉で伝えられていますか?
-
目の前の仕事は、「緊急ではないが重要なこと」ですか?それとも「緊急だが重要ではないこと」ですか?
-
あなたが今、提供している価値(仕事)は、お金に換算すると、なぜその金額になるのでしょうか?
-
5年後、あなたの業界で最も価値のあるスキルは何だと思いますか?そのために、今から何を始めますか?
-
「頑張ります」という言葉の代わりに、具体的な「最初の行動」を一つだけ言うとしたら、それは何ですか?
-
なぜ、あの人はあなたを信頼してくれる(あるいは、してくれない)のだと思いますか?
-
このトラブルや困難な状況から、たった一つだけ学べるとしたら、それは何ですか?
仕事や人間関係の悩みは尽きないもの。
この中で、今のあなたの状況に一番近い問いを、お守りのように持っておくのもいいでしょう。
STEP4「視野を広げる」思考実験|行き詰まりを打破するラテラルシンキング問題
【こんな方に】
-
最近、考え方が凝り固まっている気がして、行き詰まりを感じている
-
誰も思いつかないような、まったく新しいアイデアが欲しい
-
目の前の悩みから、少し距離を置いてみたい
最後のステップは、思考の枠組みそのものを、意識的に、えいっと壊してみる「思考実験」です。
時間や空間のスケールを極端に変えることで、凝り固まった視点をリセットし、新しい発想の入り口を見つけます。
-
100年前の人々が、現代の私たちの生活を見て、最も「幸せそうだ」と感じることと、最も「不幸そうだ」と感じることは何だと思いますか?
-
もし、あなたが人間以外のもの、例えば道端の「石」や空に浮かぶ「雲」だったとしたら、あなたの今の悩みは、どのように見えますか?
-
あなたの今の悩みを、宇宙の歴史(138億年)という時間軸の上で捉え直した時、それはどれくらいの大きさに見えますかね。
-
10年後の未来のあなたが、今のあなたへ手紙を書くとしたら、どんな悩みを聞き、どんな励ましの言葉をかけますか?
-
あなたがこの世を去る時、たった一つだけ、後世の人々に残せる「問い」があるとしたら、それはどんな問いですか?
どうでしょう、少しだけ、頭がクラクラしましたか?それでいいんです。行き詰まった時、またこの場所に戻ってきてくださいね。
【この章のポイント】
思考トレーニングは「日常の当たり前」を疑うことから始まります。うん、まずはそこから。
自分自身の感情や価値観を深く知ることが、ブレない思考の土台になります。
仕事や人間関係の問題は、視点を変え「本質」を問うことで解決の糸口が見えてきます。
行き詰まった時は、時間や空間のスケールを極端に変える「思考実験」が有効ですよ。
【思考を鍛える実演】哲学の問題はこう使う!思考が深まるプロセスを全公開

50もの問いを前にして、「うん、問いは分かったけど、これをどう考えればいいの?」と、少し戸惑ってしまったかもしれませんね。
大丈夫、大丈夫。
ここからは、思考のパーソナルトレーナーによる実演みたいなものだと思ってください。
たった一つの問いを例にとって、浅い考えが、どのように深い洞察へとじんわり変わっていくのか。
そのプロセスを、あなたの隣で一緒に体験してみたいと思います。
今回取り上げるのは、STEP3にあったこの問いです。
STEP3:2 なぜか意見が合わないあの人。その人は、その主張をすることで、一体何を「守ろう」としているのでしょうか?
では、始めましょうか。
【モデルケース】資料作成での、同僚Aさんとの対立
あなたは今、会議で使う資料の作り方について、同僚のAさんと意見がぶつかっている、と想像してみてください。
-
あなたの主張 「要点を絞って、誰にでも分かりやすいシンプルな資料にすべきだ」
-
Aさんの主張 「後で質問された時のために、関連データはすべて詳細に盛り込むべきだ」
いつものあなたなら、どう考えますか?
心の中で、こんなつぶやきが漏れてしまうかもしれません。
Level 1 反射的な思考(多くの人が陥る罠)
まず、多くの人が無意識にやってしまうのが、このレベルの思考です。
ぱっと、瞬間的に頭に浮かぶやつですね。
「またAさんは細かいことを言っている…。資料は分かりやすさが一番なのに、頭が固いなあ。自分のやり方に固執しているだけで、説得するのが本当に面倒だ…」
これは、相手を「問題」や「障害物」として捉える、ごく自然な反応です。
でも、この考え方からは、ため息やストレスしか生まれない。
なんだか、虚しいですよね。
Level 2 問いの適用(哲学のスイッチを入れる)
ここで、意識的に思考のスイッチを、カチッと切り替えます。
先ほどの問いを、自分自身にそっと投げかけてみるのです。
「待てよ。Aさんは、一体何を『守ろう』としているんだろう?」
Aさんの主張そのものではなく、その裏側にある動機に、目を向けてみます。
相手の靴を履いて、少しだけ想像力を働かせてみる。
「もしかしたらAさんは、以前、上司から資料の細かい点について厳しく追及され、答えられずに恥ずかしい思いをした経験があるのかもしれないな。
だから、『どんな質問が来ても自分自身が困らないように』という『安心』や、『準備不足だと思われたくない』という『プライド』を守ろうとしているのではないか?」
どうでしょう。
先ほどまで「面倒な人」だったAさんが、少しだけ人間味のある、不安や過去を持つ一人の人物として、見えてこないでしょうか。
Level 3 視点の転換と行動の変化(本質的な解決策へ)
Level 2の洞察を得た瞬間、問題の見え方が、面白いほどガラリと変わります。
問題の本質は、「資料のスタイルの対立」ではありませんでした。
本当の課題は、「Aさんの『失敗したくない』という不安を、どうすれば解消できるか」だったのですね。
これが分かれば、あなたの取るべき行動も、おのずと変わってきます。
相手を論破する必要なんて、どこにもなかった。
「Aさんの懸念ももっともです。ですので、発表で使う本編の資料はシンプルにして、想定される質問への詳細データは、参考資料として別紙で準備しておくのはどうでしょう?そうすれば、分かりやすさと網羅性の両方を満たせますよね」
このように、対立から協調へと、視点をすっと変えることができる。
そして何より、相手を打ち負かそうとするギスギスしたストレスから解放され、あなた自身の気持ちが、ふわっと楽になるのです。
ね、哲学の問いは、単なる気休めではないでしょう?
あなたの日常をより良くするための、このように極めて実践的な「思考の道具」なのです。
【この章のポイント】
哲学の問いは、反射的な思考を止め、視点を切り替える「スイッチ」になります。
相手の主張の裏にある「守ろうとしているもの(感情や価値観)」を想像することで、問題の本質が見えてきます。
本質が見えれば、行動は「対立」から「協調」へと自然に変化し、自分の気持ちも楽になるのですよ。
なぜ哲学の問題が効くの?あなたの思考力を根本から鍛える3つの仕組み

ここまで実践的な問いに取り組んできて、
「うんうん、でも一体どうしてこんなシンプルな問いが、本当に思考力を鍛える効果があるの?」
と、その裏側にある仕組みが気になったかもしれませんね。
素晴らしい疑問です。
その効果の秘密を、ここですこしだけ種明かししましょうか。
思考を鍛える上で欠かせない、いわば「3つのエンジン」の役割を果たす、古今東西の知恵をご紹介しますね。
仕組み①「無知の知」で思考停止を脱出。ソクラテスに学ぶクリティカルシンキングの原点
私たちの思考が、ぱったりと止まってしまう最大の原因。
それは、「自分はもう十分に知っている、分かっている」という、無意識の思い込みにあります。
自分でも気づかないうちに、そうなってしまっていることが多いんですね。
この根深い思い込みを、コロンと打ち破る、強力な言葉があります。
古代ギリシャの哲学者ソクラテスが遺した、「無知の知」という考え方です。
これは、難しいことではありません。
「賢い人とは、多くの知識を持つ人ではなく、『自分がいかに多くのことを知らないかを知っている人』のことだ」
という、至ってシンプルな真実です。
すべての知的探求は、この「自分はまだ知らないことがあるなあ」という、謙虚な自覚から始まります。
例えば、あなたが後輩に仕事を教えていて、「なんでこんなことも分からないんだ」と、ついイラッとしてしまったとしましょう。
その瞬間こそ、思考の分かれ道。
そこで一歩立ち止まり、「待てよ。自分は本当に、『後輩がどのポイントで、なぜつまずいているのか』を100%理解しているだろうか?」と自問してみる。
この一瞬の問いこそが、「無知の知」を実践し、思考停止から脱出するためのスイッチなのです。
STEP1でご紹介した「前提を疑う」問題は、まさにこの「無知の知」を日常的にトレーニングするために作られているんですよ。
仕組み②「メタ認知」で感情と思考を分離。客観視で判断ミスを防ぐ方法
私たちは、とても感情的な生き物です。
本当に。
怒りや不安といった強い感情に思考を乗っ取られ、後になって
「なんであんなことを言ってしまったんだろう…」
と、布団の中で頭を抱えてしまう。
誰にでもある経験ですよね。
そんな時に役立つのが、「メタ認知」という力です。
これもまた、少し難しく聞こえるかもしれませんが、要は「もう一人の冷静な自分が、まるで空の上から自分自身を、ふわりと観察しているような感覚」のこと。
例えば、上司からの厳しいメールにカッとなり、感情的な反論を書きそうになった時。
もう一人の自分が、あなたの肩をポンと叩いて、こう囁いてくれるイメージです。
「おっと、今、怒りの感情に思考がハイジャックされているな。本当に伝えたいことは、このトゲのある言葉で伝わるんだっけ?」
この一瞬の客観視。
このワンクッションが、致命的な判断ミスや人間関係のこじれを、驚くほど防いでくれます。
STEP2の「自己分析を深める問題」は、この「もう一人の自分」を育て、自分の感情や思考のクセを客観的に把握するための、極めて効果的なトレーニングなのです。
仕組み③「ストア派哲学」で悩みを仕分け。ストレスを減らし、本質的な意思決定を行う
私たちの悩みのほとんどは、実はたった一つの勘違いから生まれている、と言われています。
それは、「自分ではコントロール不可能なこと」を、どうにかしようともがくことから、です。
この問題に対する、とても強力な解決策を、古代ローマの賢人たちはすでに見つけていました。
皇帝マルクス・アウレリウスも実践したと言われる「ストア派哲学」の知恵です。
その核心は、とてもシンプル。
目の前の問題を、「コントロールできること」と「コントロールできないこと」に、ただ仕分けるだけです。
| 【コントロール できない こと】 | 【コントロール できる こと】 |
| 他人の評価・感情 | 自分の今日の行動 |
| 過去の出来事 | 物事の受け止め方 |
| 未来の不確実性 | 何を学ぶかという選択 |
例えば、仕事での失敗をいつまでも引きずってしまう時。
「なぜあんなミスを…」と過去(コントロールできないこと)を責め続けるのではなく、
「この失敗から何を学び、次の行動(コントロールできること)にどう活かすか?」
と、自分のエネルギーを注ぐべき方向を意識的に切り替える。
これが、心をすり減らさず、思考を常に未来へと向けるための技術です。
答えの出ない問いと向き合う時も、このストア派の考え方は、焦りや不安からあなたを守る、心のOSとなってくれるでしょう。
【この章のポイント】
無知の知 「自分はまだ知らない」と認めることが、思考停止から抜け出す第一歩です。
メタ認知 もう一人の自分が自分を客観視することで、感情に流されない判断が可能になります。
ストア派哲学 「コントロールできること」に集中することで、無駄な悩みから解放され、思考がクリアになりますよ。
三日坊主で終わらせない。「思考トレーニング」を日常の習慣にする3つのコツ
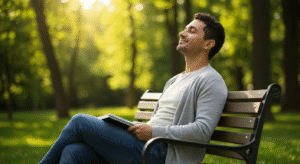
「トレーニングがいいのは分かったけれど、これを毎日続けるのは正直、自信がないな…」
ここまで真剣に読み進めてくださったあなただからこそ、そんな風に感じているかもしれませんね。
うんうん、その気持ちはよく分かりますよ。
ご安心ください。
大切なのは、毎日頑張ることではありません。
50問すべてを制覇することが目的ではなく、
日常のほんの少しの隙間に、「問いを持つ」というささやかで豊かな習慣を、そっと溶込ませることなのです。
そのための、具体的なヒントを3つご紹介します。
コツ① 計画的に仕組み化する「週に一度の問い」
もしあなたが、計画を立てるのが好きなタイプだったり、つい物事を忘れがちだったりするなら、この方法が向いているかもしれません。
やり方は簡単です。
毎週月曜の朝、今週じっくり向き合ってみたい問いを50のリストから一つだけ選び、いつも目にする場所に書き写しておくのです。
-
手帳のウィークリーページ
-
スマホのロック画面のメモ
-
PCのデスクトップの付箋
これはいわば、自分自身との小さなアポイントメント。
強制的に「考えよう!」と意気込むのではなく、ふとした時に目に入ることで、「ああ、そういえば今週はこの問いだったな」と思い出す。
そのくらいの、ゆるやかな関わり方が、習慣化の秘訣です。
コツ② 五感と思考を結びつける「思考の散歩」
机に向かって、うんうん唸るのがどうも苦手だ、という方もいますよね。
そんな方には、この「思考の散歩」がぴったりです。
これもやり方はシンプル。
答えを出すことは一旦忘れて、ただ一つの問いを頭の片隅に入れたまま、イヤホンを外して15分だけ、近所を歩いてみるのです。
風の匂いや、木々のざわめきを感じながら。
実はこれ、科学的にも理にかなっているんですよ。
歩行のようなリズミカルな運動は、私たちの脳の、特に創造性に関わる部分を活性化させることが知られています。
不思議なもので、煮詰まった頭で机に向かうよりも、リラックスして歩いている時の方が、ずっと良いアイデアがふっと降りてきたりするものです。
コツ③ 挫折を防ぐ心の解決策「それは思考の筋肉痛です」
すぐに効果が感じられないと、どうしても続けるのが嫌になってしまいますよね。
問いについて考えても、頭が真っ白になったり、何も思い浮かばなかったりする時。
そんな時は、それを「失敗」だなんて思わないでください。
それは、いわば「思考の筋肉痛」だと考えてみるのはどうでしょう。
普段使っていなかった筋肉を動かすと、翌日、心地よい筋肉痛がやってきますよね。
それは、筋肉が成長している証拠です。
同じように、「思考がうまく進まない感覚」も、あなたの脳の中で新しい神経のつながりが生まれようとしている、成長のサインなのです。
そう捉え直すだけで、停滞期も少しだけ、前向きな気持ちで乗り越えられるようになりますよ。
まずは、この3つの中から「これならできそう」と感じたものを、遊び感覚で一つだけ試してみてください。
大切なのは、昨日よりほんの少しだけ、世界を面白がれるようになること。
その小さな変化こそが、思考を鍛えることの、最大の報酬なのですから。
【この章のポイント】
完璧を目指さず、「週に一度の問い」など仕組みでゆるやかに続けることが大切です。
机に向かうのが苦手なら、脳を活性化させる「思考の散歩」がおすすめです。
うまく考えられない時は「思考の筋肉痛」と捉え、成長のサインだと考えてみましょう。
哲学で思考を鍛える際の「よくある疑問」
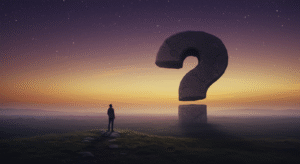
ここまで読み進めてくださったあなたの中に、まだいくつか残っているかもしれない、ささやかな疑問や不安。
この最後のセクションで、それらを一つひとつ、丁寧に解消していきましょうか。
Q. この思考トレーニングは、どのくらいの頻度でやればいいですか?
A. まずは、週に1問からで十分ですよ。
このトレーニングの目的は、問題の数をこなすことではありませんからね。
日常の中に「ふと立ち止まって、問うてみる」という、新しい習慣のリズムを作ることです。
量よりも、一つの問いとじっくり向き合う「質」の方が、ずっと大切になります。
毎日ジムに通うのではなく、まずは週に一度のストレッチから始めるような感覚で、気軽に取り組んでみてください。
Q. 問いについて考えても、頭が真っ白になってしまいます。どうすればいいですか?
A. それは失敗ではありません。むしろ、素晴らしい第一歩です。
なぜならそれは、「自分はこの問いの答えを知らないのだ」ということを、はっきりと自覚できた瞬間だから。
まさに、この記事の中でも触れた「無知の知」の状態です。
答えは、すぐに出なくていいんです。
ええ、本当に出なくていい。
むしろ、簡単には答えの出ない問いこそが、あなたの思考を水面下で、深く豊かに育ててくれます。
その問いを、急かさずに、しばらく心の中で温めるように持ち続けてみてください。
Q. このトレーニングで、論理的思考(ロジカルシンキング)も鍛えられますか?
A. はい、鍛えられます。特に、その「土台」となる部分が強化されますね。
少し、料理に例えてみましょうか。
-
論理的思考(ロジカルシンキング)
物事を筋道立てて整理する「技術」です。料理で言えば、材料を正しく切り、手順通りに調理する「レシピ」のようなものです。
-
哲学的な思考
「そもそも、なぜこの料理を作るのか?」「本当にこの食材でいいのか?」と、レシピの前提そのものを問う「姿勢」です。料理で言えば、「全体のコンセプト」を考える力に近いかもしれません。「イタリアン」とか「和食」とか。
レシピ通りに作る技術ももちろん大切ですが、その前に「何を作るべきか」という本質を見抜く力がなければ、素晴らしい料理は生まれませんよね。
特に、この記事のSTEP3「本質を見抜く」の問題は、物事の因果関係や構造を捉える訓練になるため、論理的思考に直結します。
哲学的な思考は、論理的思考をより深く、本質的に使うための、いわばOS(オペレーティングシステム)のようなものだと考えてみてください。
【この章のポイント】
トレーニングの頻度は、まず「週に1問」からで十分です。
頭が真っ白になるのは「知らないことを知れた」という成長の証ですよ。
哲学的な思考は、論理的思考(ロジカルシンキング)をより深く使うための「土台」を鍛えます。
おわりに 思考力を鍛える最高の道具は、あなたの中にすでにある

50もの問いと向き合い、頭を悩ませ、時には新しい視点に驚かれたかもしれません。
その知的で、誠実な探求の時間そのものが、すでにあなたの「考える力」を鍛える、素晴らしい一歩となっています。
うん、間違いなく。
この記事を通して、私が一番伝えたかったこと。
それは、哲学的な思考とは、一部の専門家だけが持つ特別な知識や才能ではない、ということです。
それは、
自分自身に良質な「問い」を投げかける、一つの「技術」であり「習慣」なのです。
そして、その思考力を鍛えるための最高の「道具」は、高価な本や難しいセミナーの中にあるのではありません。
あなたの頭の中に、もうすでに、すべて備わっています。
この記事ができたのは、その素晴らしい道具の「使い方を思い出すための、ささやかなきっかけ」に過ぎません。
さあ、最後にもう一つだけ。
今日ここで出会った50の問いのうち、たった一つで構いません。
あなたの心に最も響いたその問いを、明日からの日常の、小さなお守りにしてみてください。
その小さな問いが、あなたの見る世界を少しずつ、しかし確実に豊かなものに変えていくことを、心から願っています。
あなたの思考の時間は、今、始まったばかりです。
【この章のポイント】
哲学的な思考とは、特別な才能ではなく、誰でも身につけられる「問いかける技術」。
思考力を鍛える最高の道具は、すでにあなたの中に備わっています。
【こちらの記事も読まれています】



このブログでは、このように「考える力」を育むことを通じて、あなた自身の「豊かさ」や「幸せ」とは何かを探求していくための、様々なヒントを発信しています。
もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。