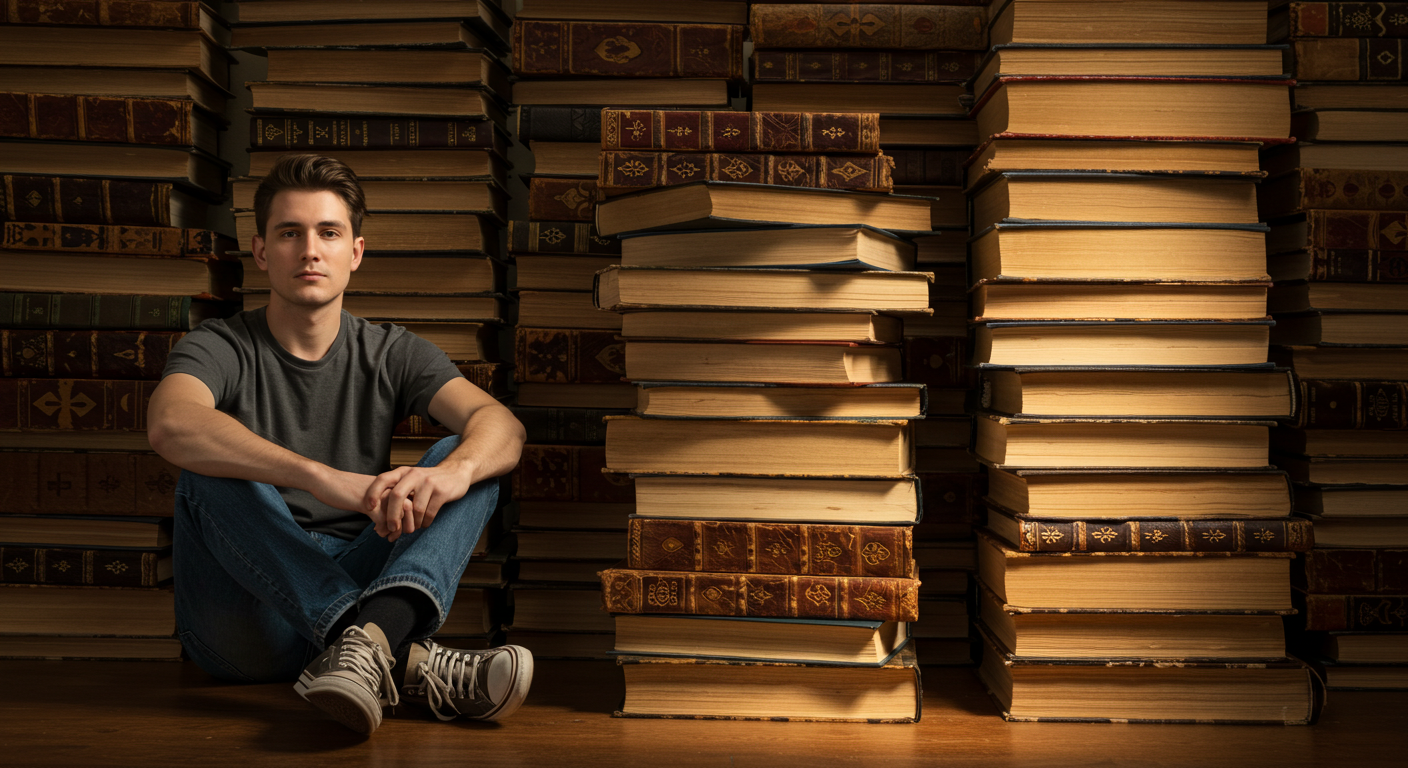人の顔色をうかがっては、どっと疲れてしまう…。
そんな風に感じていませんか?
この記事を読めば、もう他人に振り回されず、もっと「あなたらしく」気持ちが楽に生きられるようになります。
ここでは、あなたの心を守り、明日から楽になるための具体的な「思考リセット術」だけを、厳選してお伝えしますね。
難しい理論ではなく、何千年もの時を超えてきた、先人たちの確かな知恵に基づいているものです。
さあ、あなただけの心地よい人間関係を、ここから一緒に見つけていきましょう。
もう、誰かの顔色をうかがって心をすり減らすのは、終わりにしませんか?

職場の同僚が交わした、ほんの些細な一言。
なぜかその言葉が、帰り道の電車の中でもずっと頭から離れない…。
LINEの返信が少し途絶えただけで、
「何か悪いことしちゃったかな…」
と、何度もスマホを確認してしまう…。
本当はもうクタクタなのに、誰かに頼み事をされると、つい「大丈夫ですよ」と笑顔で引き受けてしまう…。
あなたは、これまで本当に、よく頑張ってこられましたね。
その疲れた心、少し休ませてあげませんか。
その気疲れ、あなたの「優しさ」が原因かも。まずは自分を責めないことから
そんなふうに感じてしまうのは、あなたが弱いからでは、決してないんです。
むしろ、それだけ相手の気持ちを繊細に感じ取れる「優しさ」や、物事を深く考えられる「思慮深さ」を、あなたが豊かに持っている証拠なんですよ。
ただ、その素晴らしい才能が、時としてあなた自身を少しだけ疲れさせてしまうのかもしれません。
だから、どうか、もう「こんなことで疲れる自分はダメだ」なんて、ご自身を責めるのはやめにしませんか。
まずは、これまでずっと頑張ってきた、その優しいご自身の心を、そっと認めてあげるところから、すべては始まります。
この記事で得られること 哲学で「しなやかな心」を手に入れる具体的な方法
「優しさを、弱さではなく、強さに変えられたら…」
きっと、そう思いますよね。
その答えは、小手先のコミュニケーション術ではなく、何千年もの間、人類が悩み抜いた末に見つけ出した「哲学」という知恵の中にあります。
といっても、難しい学問の話をするつもりは全くありませんので、安心してくださいね。
ここで言う哲学とは、私たちと同じように人間関係で悩んできた遠い昔の先人たちが遺してくれた、
「心を楽にするための、実践的な道具箱」
のようなものです。
この記事を最後まで読んでいただければ、
-
なぜ疲れるのか? あなたの疲れの「正体」がスッキリわかります。
-
どう心を守るか? 他人の言動に振り回されない「心の盾」が手に入ります。
-
どう心地よく生きるか? 自分軸で、楽な人間関係を築くための「心の指針」が見つかります。
さあ、一緒に、他人に振り回されない「しなやかな心」を手に入れるための、具体的なレッスンを始めましょう。
【この章のポイント】
人間関係の疲れは、あなたの「優しさ」の証拠。自分を責める必要は全くありません。
この記事では、哲学を「心を楽にするための実践的な道具」として活用します。
読み終える頃には、人間関係に振り回されない「しなやかな心」を手に入れる方法がわかります。
なぜ?を知れば楽になる。あなたの「人間関係の疲れ」の正体を突き止める

原因がわからない体の不調が一番不安なように、心の疲れも、その正体がわかれば、ぐっと対処しやすくなるものです。
焦る必要はありません。
まずは、
「どうして、私ばっかりこんなに疲れてしまうんだろう?」
という長年の疑問に、一緒にじっくりと向き合ってみましょう。
原因①「こうあるべき」に縛られてない?他人軸で生きる思考の癖
「社会人なら、これくらいできて当たり前」
「母親なんだから、子どものために我慢するべき」
「いい人だと思われたいから、断るべきじゃない」
…あなたの頭の中で、こんな「~べき」という声が、自動的に再生されてしまうことはありませんか。
その声の正体は、多くの場合、世間や親、あるいは過去の経験から、いつの間にか自分の中に住み着いてしまった価値観。
いわゆる「他人軸」で物事を考えているサインかもしれません。
それは、まるでサイズの合わない窮屈な服を、
「これが自分に与えられた服だから」
と思い込んで、ずっと着続けているような状態なんです。
窮屈で、動きにくくて、ただただ疲れてしまうのは、当然ですよね。
少しだけ、ご自身の心に問いかけてみてください。
【「他人軸」思考のセルフチェック】
□ 何かを選ぶとき、自分がどうしたいかより「普通はどうか」を無意識に優先してしまう。
□ 自分の意見を言う前に、相手の顔色をうかがい、頭の中で何度もシミュレーションしてしまう。
□ 「NO」と言うことに、強い罪悪感や、関係が壊れることへの恐怖を感じる。
□ 人から褒められるとホッとするが、少しでも否定的な態度をとられると、一日中引きずってしまう。
もし一つでも当てはまるなら、あなたはこれまで、自分の気持ちに蓋をしてでも、周りの期待に応えようと、本当に一生懸命に頑張ってこられたのだと思います。
大切なのは、まず「あ、私、他人軸で考えていたかもしれないな」と、その“癖”の存在に、ただ気づいてあげることです。
それが、あなたにピッタリ合う、心地よい服に着替えるための、本当に大きな第一歩になりますから。
原因② 他人の感情に振り回されるのは「心の境界線」が曖昧なサイン
上司が不機嫌だと、オフィス全体の空気が重く感じて、自分の仕事が全く手につかない…。
友人の悩み相談に乗っていたら、いつの間にか自分まで同じくらい、どんよりと落ち込んでしまった…。
そんな経験、ありませんか?
これは、「自分と他人の心の境界線」が、少し曖昧になっている状態なのかもしれません。
実は、心理学には「感情的伝染」という言葉があります。
これは、
相手の感情が、まるで風邪のウイルスのように、自分に伝染してしまう現象のこと。
特に、あなたのように共感性の高い方は、無意識のうちに相手の感情を受け取ってしまう脳の働きが、もともと強いと言われているんです。
これは、素晴らしい才能である一方、境界線が曖昧だと、他人の感情という雨が、傘もささずに自分の心に直接降り注いでくるようなもの。
相手がイライラしていれば、その雨で自分の心も濡れて冷たくなってしまう。
これでは疲れてしまうのも無理はありません。
本来、相手がどんな感情でいるか(機嫌)は、「相手の課題」なんです。
あなたが、その責任まで感じる必要はないんですよ。
この「心の境界線」は、相手を冷たく突き放すための「壁」ではありません。
むしろ、お互いを尊重しあうための、心地よい「垣根」のようなもの。
この垣根の上手な引き方は、次の章で詳しくお話ししますね。
【深掘りコラム】なぜ私たちは、特に人間関係に疲れやすいのか?
「海外の人と比べて、日本人は特に気を遣いすぎて疲れる」。
そんな話を、一度は聞いたことがあるかもしれません。
実はこれ、単なるイメージだけではなく、私たちが生きる、この社会の文化的な背景も少し関係しているんです。
-
「和を以て貴しとなす」という文化
私たちは昔から、個人の意見を主張することよりも、集団全体の調和を大切にする文化の中で生きてきました。それはとても美しい精神ですが、一方で、
「波風を立てないように」
「周りに合わせなくちゃ」という、見えないプレッシャーを生みやすい側面もあります。
-
言葉にしなくても察しあう「空気を読む」文化
「言わなくてもわかってくれるだろう」という、いわゆるハイコンテクストなコミュニケーションも、私たちの特徴です。これは、相手の気持ちを深く思いやれる素晴らしい能力ですが、常に「相手はどう思っているんだろう?」とアンテナを張り巡らせる必要があり、知らず知らずのうちに心を消耗させてしまう原因にもなるんですね。
つまり、あなたが人間関係に疲れやすいのは、あなたの性格だけのせいではなく、この社会でうまくやっていこうと、真面目に、誠実に努力してきた結果とも言えるのです。
だからこそ、今の時代を生きる私たちは、意識的に、自分の心を守るための
「思考の道具」を持つことが、これまで以上に大切になっていると私は考えています。
次の章では、そのための具体的で、とても強力な道具をご紹介しますね。
【この章のポイント】
疲れの原因は、無意識の「~べき」という他人軸の思考にあるかもしれません。
他人の感情に振り回されるのは、「感情的伝染」という自然な心の働きも一因。あなたのせいだけではありません。
疲れやすいのは個人の性格だけでなく、文化的な背景も関係しています。自分を責める必要はありません。
人間関係の疲れから「心を守る」哲学。もう傷つかない思考リセット術

誰かに心ない言葉を言われたり、理不尽な態度をとられたりした時に、心のダメージを最小限に食い止める。
そんな、自分を守るための実践的な技術を、一緒に学んでいきましょう。
これは、心を閉ざすためのものではなく、あなたの優しさを、これからも守り抜くためのものです。
【守りの技術①】悩みの9割を手放す。ストア派哲学「コントロール二分法」
頭の中が、過去への後悔や、未来への不安、他人の些細な言動でごちゃごちゃになって、本当に考えるべきことに集中できない…。
そんな時、ありませんか?
古代ローマの賢帝マルクス・アウレリウスも実践したと言われるストア派の哲学に、この問題を解決する、驚くほどシンプルな知恵があります。
やることは、たった一つ。
あなたの悩みを、「自分でコントロールできること」と「できないこと」の2つに、心の中で仕分けるだけです。
| コントロールできないこと(=考えても仕方ない、手放す領域) | コントロールできること(=自分の力で変えられる、集中する領域) |
| 他人があなたのことをどう思うか | 今日の自分の行動や選択 |
| 上司や同僚の機嫌 | 人に対して使う言葉遣い |
| 過去にしてしまった失敗 | 物事の受け止め方、解釈 |
| 友人のSNSの投稿 | 仕事や勉強への取り組み方 |
| 天候や電車の遅延 | 自分の機嫌 |
この考え方は、いわば「心の断捨離」です。
コントロールできないことについて考えるのを意識的にやめるだけで、心の中に驚くほどのスペースと静けさが生まれます。
そして、本当に大切な「コントロールできること」に、自分のエネルギーを集中させることができるようになるんです。
└「わかっているけどできない…」感情が追いつかない時の対処法
「他人の評価はコントロールできない。…うん、頭ではわかってる。でも、やっぱり気になって心がザワザワしちゃう…」
その気持ち、痛いほど、よくわかります。
それは、あなたの意志が弱いからでは決してありません。
長年の思考の「癖」ですから、できなくて当たり前なんです。
自転車だって、最初は誰でもぐらつきますよね。
それと全く同じです。
もし、感情が追いつかないと感じたら、完璧を目指さずに、こんな「心の応急手当」を試してみてください。
【感情が追いつかない時の、3つの応急手当】
心の中で実況中継する
「あ、今わたし、コントロールできないあの人の言葉で、心がザワザワしているな」と、自分の状態を客観的に言葉にしてみる。悩む時間を制限する
「よし、この件で悩むのは、お風呂に入るまでのあと15分だけ!」と、意識的に時間を区切ってみる。ハードルを極限まで下げる
「今日は1分でも気にしない時間があったら、それで自分に100点満点をあげよう」と考えてみる。
これは、いわば「心の筋トレ」のようなもの。
焦らず続けていくうちに、少しずつ、でも確実に「気にしない筋力」がついてきますから、どうかご自身のペースを大切にしてくださいね。
【守りの技術②】他人の評価が気にならなくなる。アドラー心理学「課題の分離」
「これを言ったら、相手はどう思うだろう…」
「この誘いを断ったら、嫌われてしまうかもしれない…」
こうした、相手の評価を気にするあまりの恐怖が、私たちの行動をどれほど縛っていることでしょう。
ベストセラーになった『嫌われる勇気』でも有名なアドラー心理学に、この鎖を断ち切るための、非常に強力な考え方があります。
それが「課題の分離」です。
これは、人間関係のトラブルに直面した時、
「その選択によってもたらされる結末を、最終的に引き受けるのは誰か?」
と問いかけることで、自分と相手の問題を、はっきりと切り分ける考え方です。
例えば、「友人からお金を貸してほしいと頼まれた」場面で考えてみましょう。
-
あなたの課題
貸すか、貸さないかを決めること。友人を信頼できるか、貸すことで自分の生活は大丈夫か、などを考えるのは「あなたの課題」です。 -
友人の課題
あなたが「貸せない」と決めた場合、それを受け入れること。お金がなくて困っている状況を、別の方法でどう乗り切るかを考えるのは「友人の課題」です。
あなたが介入していいのは、自分の課題まで。
これまでずっと他人の期待に応えてきたあなたが、急にこれを実践しようとすると、最初は強い罪悪感や、見捨てられることへの恐怖を感じるかもしれません。
それは、今まで使っていなかった心の筋肉を、急に動かそうとしているようなもの。
痛みを感じて、当たり前なんですよ。
└「課題の分離」は冷たい?その誤解と、本当の意味
「『相手がどう思うかは相手の課題』だなんて、なんだか冷たくて、自己中心的な人だと思われそうで怖い…」
そう感じますよね。
その優しさ、本当に素敵だと思います。
でも、安心してください。
「課題の分離」は、決して人を突き放すための冷たい理論ではないんです。
課題の分離は、相手を見捨てる「放任」とは全く違います。
むしろ、
「あなたには、あなた自身の力で、あなたの課題を乗り越える能力があると信じています」という、相手への深い「信頼」のメッセージが込められているのです。
相手の課題にまで踏み込むことは、相手から「自分で考えて成長する機会」を奪ってしまうことにもなりかねません。
もし、冷たいと思われないか不安なら、こうしてみてください。
自分の課題として「断る」という決断をした上で、
「もし、私に他に手伝えることがあったら、いつでも声をかけてね」
と、一言添えるのです。
この一言があるだけで、「課題の分離」は、あなたの優しさと両立できる、最強のツールになりますよ。
課題の分離は、相手を信じて見守ることであると同時に、あなた自身が他人の評価という鎖から自由になるための、力強い手段でもあるのです。
【この章のポイント】
悩みを「コントロールできること」と「できないこと」に分けるだけで、心の負担は激減します。
頭でわかっていても感情が追いつかない時は、できなくて当たり前。「心の筋トレ」だと思って少しずつ試しましょう。
「これは誰の課題か?」と問いかけることで、他人の評価から自由になれます。
課題の分離は「冷たさ」ではなく、相手への深い「信頼」の証です。
自分軸で楽になる。心地よい人間関係を「育てる」哲学思考

心をストレスから「守る」ための盾を手に入れましたね。
でも、
ゴールは、心を閉ざして一人でいることではありません。
ここからは、その盾でしっかりと心を守りながら、自分らしさを大切にし、本当に大切な人と心地よい関係を「育てていく」ための、より積極的なステップに進んでいきましょう。
これは、あなたの人生を、もっと豊かにするためのレッスンです。
【育てる技術①】世間の”普通”から自由になる。ニーチェに学ぶ「自分軸」の作り方
「みんなが持っているから、私も欲しい」
「この年齢なら、結婚するのが”普通”だから」
「常識的に考えて、こうするのが正しい」
私たちは、そんな世間の「普通」や「常識」という物差しで、無意識に自分の選択を決めてしまっていることがあります。
哲学者ニーチェは、そんな私たちに「自分自身の主人であれ」という、非常に力強い言葉を投げかけました。
これは、誰かが決めた価値観やルールにただ従うのではなく、あなた自身の心の声に従い、あなただけの価値観を創造していくことの重要性を説いたものです。(参考:『超訳 ニーチェの言葉』など)
ニーチェは、これまでの社会が作り上げてきた「~べき」という常識や道徳を疑い、自分だけの価値観を創造する「超人」になることを説きました。
これは、他人の期待に応えるだけの人生から、あなた自身の人生を取り戻すための、いわば「独立宣言」のようなものなのです。
壮大な話に聞こえるかもしれませんが、「自分軸」を育てるために、今日からできることは、とてもシンプルですよ。
【「自分軸」を育てるための3つのステップ】
Step1 小さな「好き/嫌い」に気づく練習
まずは、今日のランチ選びから。「みんなと同じものでいいや」ではなく、「私は、本当は何が食べたいんだろう?」と、自分の心の微細な声に、丁寧に耳を澄ませてあげてください。
その小さな「好き」を大切にすることが、自分を大切にする第一歩です。
Step2 小さな「自己決定」を積み重ねる
気が乗らない飲み会を、勇気を出して断ってみる。周りに合わせず、今日は一人で静かに過ごす時間を選んでみる。
そんな、自分の「心地よさ」を優先する小さな行動を、意識的に選んでみましょう。
その一つひとつが、「自分で決めていいんだ」という自信を育てます。
Step3 自分への「問いの質」を変える
何か大きな決断に迷った時、「人にどう思われるか?」と問うのをやめて、こう自問してみてください。「5年後の自分が、今の自分に『よくやった』と感謝するのは、どっちの選択だろう?」と。
未来のあなたが、きっと最高の答えを教えてくれます。
誤解しないでほしいのですが、自分軸で生きることは、ワガママになることとは全く違います。
それは、自分の人生のハンドルを、自分でしっかりと握るという、とても誠実で、潔い生き方です。
人生の主導権を握る感じです。
その先には、他人の評価にいちいち心が揺れない、穏やかで自由な毎日が、きっと待っていますよ。
【育てる技術②】無理に好かれなくていい。ソクラテスに学ぶ「本物の信頼関係」の築き方
「自分軸を大切にすると、周りから浮いてしまって、ひとりぼっちになるんじゃないか…」
そんな不安が、次に顔を出すかもしれませんね。
最後に、そんな不安を希望に変えるためのヒントを、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの知恵からご紹介します。
彼の有名な言葉に「無知の知」というものがあります。
これは、「私は、自分が何も知らないということを、知っている」という意味。
この一見、謙虚な姿勢こそが、実は、上辺だけではない本物の信頼関係を築くための、最高の鍵となるのです。
ソクラテスは、相手に答えを与えるのではなく、対話を通して相手の中から答えが生まれるのを手助けする「問答法(産婆術)」を実践しました。
これこそ、相手を尊重し、本物の信頼を築くコミュニケーションの原型だと私は思います。
これを、私たちの日常に置き換えると、こういうことです。
-
アドバイスではなく、純粋な「関心」を向ける
「どうして、あなたはそう感じたの?」「もう少し、その話を聞かせてくれないかな?」と、相手をジャッジせず、ただその人の世界を深く知ろうとすること。人は、自分の話を評価されずに、ただ深く聞いてもらえた時に、心を開くものです。
-
「正しさ」の争いから、そっと降りる
会話が「どっちが正しいか」の議論になりそうになった時、ソクラテスならこう考えるでしょう。「私には私の正しさがあり、あなたにはあなたの正しさがある。どちらが優れているかを決めるのではなく、なぜそう思うのか、その背景にある物語を、まずはお互いに理解しあうことから始めよう」と。
無理に共感したり、話を合わせたりして「好かれよう」とする必要はないんです。
ただ、誠実に、相手を「理解しよう」と努めること。
その静かで温かい姿勢が、あなたにとって本当に大切な人との、何にも代えがたい揺るぎない信頼関係を、ゆっくりと、でも着実に育てていくのです。
【この章のポイント】
世間の「普通」ではなく、自分の「心地よさ」を基準にする「自分軸」を、小さなことから育てていきましょう。
自分軸で生きることはワガママではなく、自分の人生のハンドルを自分で握るという誠実な生き方です。
無理に好かれようとせず、相手を「理解しよう」と努める姿勢が、本物の信頼関係を築きます。
明日から使える!あなたの「心の境界線」見える化シート

これまでの章で、心を楽にするための様々な「考え方」を学んできました。
でも、いざ自分の悩みとなると、頭の中がごちゃごちゃしてしまって、
「一体どこから手をつけていいの…?」
と、途方に暮れてしまう時もありますよね。
そこで、そんなあなたのために、頭の中をスッキリと整理し、客観的に自分を見つめるための特別なツール、「思考の断捨離シート」をご用意しました。
手を動かして紙に書き出すことは、「書く瞑想」と言われるほど、心を落ち着かせる不思議な効果があるんですよ。
ぜひ、試してみてください。
書き出すだけで気持ちが楽になる「思考の断捨離」シート
このシートは、第2章でご紹介したストア派哲学の「コントロール二分法」と、アドラー心理学の「課題の分離」を、たった一枚で実践できるように設計した、この記事だけのオリジナルツールです。
完璧に埋めようとしなくて、全く大丈夫。
むしろ、うまく書けない自分に気づくだけでも、本当に大きな一歩です。
まずは一つ、今あなたの心に浮かんでいるモヤモヤを、試しに書き出してみませんか?
【思考の断捨離シート】
① いま、心にあるモヤモヤは?
(例:職場の先輩から、少しキツい言い方をされて一日中落ち込んでいる…)
② これは、主に「誰の課題」?
□ 自分 ☑ 相手 □ 共同
先輩がどんな言い方をするかは「相手の課題」。それに対して私が落ち込んでいるのは「自分の課題」。③ これは、自分で「コントロールできる」こと?
☑ できる ☑ できない
先輩の言い方は「できない」。私の受け止め方や気分の切り替えは「できる」。④【手放す練習】(②が相手/③ができない場合)
これを、どう考え、どう手放しますか?
(例:「先輩は今日、何か虫の居所が悪かっただけかもしれない。私の人格が否定されたわけじゃない」と心の中で唱えてみる)⑤【最初の一歩】(②が自分/③ができる場合)
心を楽にするために、今すぐできる小さな行動は?
(例:今日はもう仕事のことは考えないと決める。お気に入りの入浴剤を入れて、ゆっくりお風呂に入る)
【使い方】3ステップで実践。人間関係の悩みを仕分ける方法
「シートはわかったけど、どう使えばいいの?」という方のために、具体的な使い方を3つのステップでご説明しますね。
-
Step1 心のモヤモヤを、ありのまま「吐き出す」
まずは一番上の①の欄に、頭の中に浮かんでいる悩みや不安を、評価や判断を一切せず、ただありのまま書き出してみてください。「こんなこと、書いてもいいのかな…」なんて思う必要は全くありません。ここは、あなただけの安全な場所ですから。 -
Step2 客観的な目で、冷静に「仕分ける」
次に、②と③のチェックボックスを使って、書き出した悩みを冷静に仕分けていきます。一歩引いて、「これは本当に、私の問題だろうか?」「私自身の力で、変えられることだろうか?」と、自分に問いかけてみてください。
この作業だけで、感情的になっていた心が、少し落ち着いてくるのを感じられるはずです。
-
Step3 具体的な「行動」に変換する
分析だけで終わらせないのが、このシートの最も大切なポイントです。
仕分けた結果に応じて、④か⑤の欄を埋めてみましょう。
「気にしないようにする」といった曖昧な目標ではなく、「深呼吸をする」「好きな音楽を聴く」といった、今すぐできる、ごくごく小さな行動に落とし込むのがコツです。小さな行動こそが、心を楽にする一番の近道だったりしますからね。
このシートを、週に一度、日曜の夜に心を整理する時間に使ってみたり、スマホに保存しておいて、通勤電車の中でモヤモヤした時にサッと見返してみたり。
ぜひ、あなたのペースで、ご自身の心を整えるための、お守りのような存在にしてあげてください。
【この章のポイント】
悩みを書き出すことは、心を落ち着かせる「書く瞑想」の効果があります。
「思考の断捨離シート」を使えば、学んだ哲学を誰でも簡単に実践できます。
悩みを分析するだけでなく、「今すぐできる小さな行動」に変換することが、気持ちを楽にする鍵です。
まとめ 本当の人間関係は、あなたが自分を大切にすることから始まる

この記事では、あなたの心を疲れさせていたものの正体を探り、心を守るための盾を手にし、そして自分らしい関係を育てるための指針を見つけてきました。
哲学は難しい学問じゃない。あなたの人生を支える「考える道具」です
哲学とは、決して、本棚に飾っておくための難しい学問などではありません。
悩んだり、迷ったりした時に、いつでも取り出して使える、あなたの人生を力強く支えてくれる
「サバイバルツール」であり、心を健やかに保つための「メンテナンスキット」なのです。
この記事でご紹介した、先人たちの知恵を、お守りとして、最後にもう一度だけ。
-
ストア派の教え
あなたは「変えられないこと」で、もう悩む必要はない。 -
アドラーの教え
あなたは「他人の期待」に、もう応える必要はない。 -
ニーチェの教え
あなたは、これからは「あなた自身の主人」になっていい。
この3つの道具が、これからのあなたの毎日を、きっと、少しだけ風通しの良いものにしてくれるはずです。
完璧じゃなくていい。今日からできる「自分を大切にする」小さな一歩
この記事を読んで、「明日から、全部やらなきゃ!」なんて、どうか意気込まないでくださいね。
むしろ、そうやっていつも一生懸命に頑張りすぎてしまうことが、あなたを疲れさせてきたのかもしれないのですから。
もし、あなたが今日から何か一つだけ、新しいことを始めるとしたら。
それは、「寝る前にたった5分だけ、自分のために時間を使う」こと。
これだけで、十分すぎるくらいです。
その5分で、今日あった楽しかったことを思い出してもいいし、付録のシートにモヤモヤした気持ちを書き出してみてもいい。
ただ、温かいお茶を飲んで、ボーっとするだけでも、もちろんいいんです。
大切なのは、「誰かのため」ではなく、「100%、自分のためだけに」、意識的に時間を使ってあげること。
その小さな、ささやかな積み重ねが、少しずつ、あなたの中に「自分を大切にしていいんだ」という温かい感覚を育てていきます。
そして、不思議なことに、あなたがあなた自身を本当に大切にできるようになればなるほど、あなたの周りの人間関係も、あなたを大切にしてくれる、心地よいものに、きっと変わっていくはずです。
例えば、気の乗らない誘いに「ごめんなさい、その日は先約があって」と、穏やかな気持ちで断れるようになる。
一人の時間を心から楽しみ、誰かと過ごす時間はもっと楽しめるようになる。
会った後にドッと疲れるのではなく、むしろ温かいエネルギーをもらえるような、そんな人間関係が、あなたのスタンダードになっていくのです。
忘れないでくださいね。
あなたの人生の主役は、他の誰でもなく、あなた自身です。
この記事が、あなたがあなた自身の人生を、心から楽しむための、ほんの小さなきっかけになれたなら、これほど嬉しいことはありません。
【この章のポイント】
哲学は、あなたの人生を支える実践的な「道具」です。いつでも取り出して使ってください。
明日から完璧にやろうとせず、まずは「自分を大切にする小さな習慣」を一つだけ始めてみましょう。
あなたが自分自身を大切にすることが、心地よい人間関係を築くための、最も確かな第一歩です。
【こちらの記事も読まれています】


このブログでは、他にもあなたがより豊かに、幸せになるための様々な「考え方」をご紹介しています。
もしよろしければ、自分にとっての「幸せ」や「豊かさ」とは何かを探求するヒントとして、他の記事も覗いてみてくださいね。