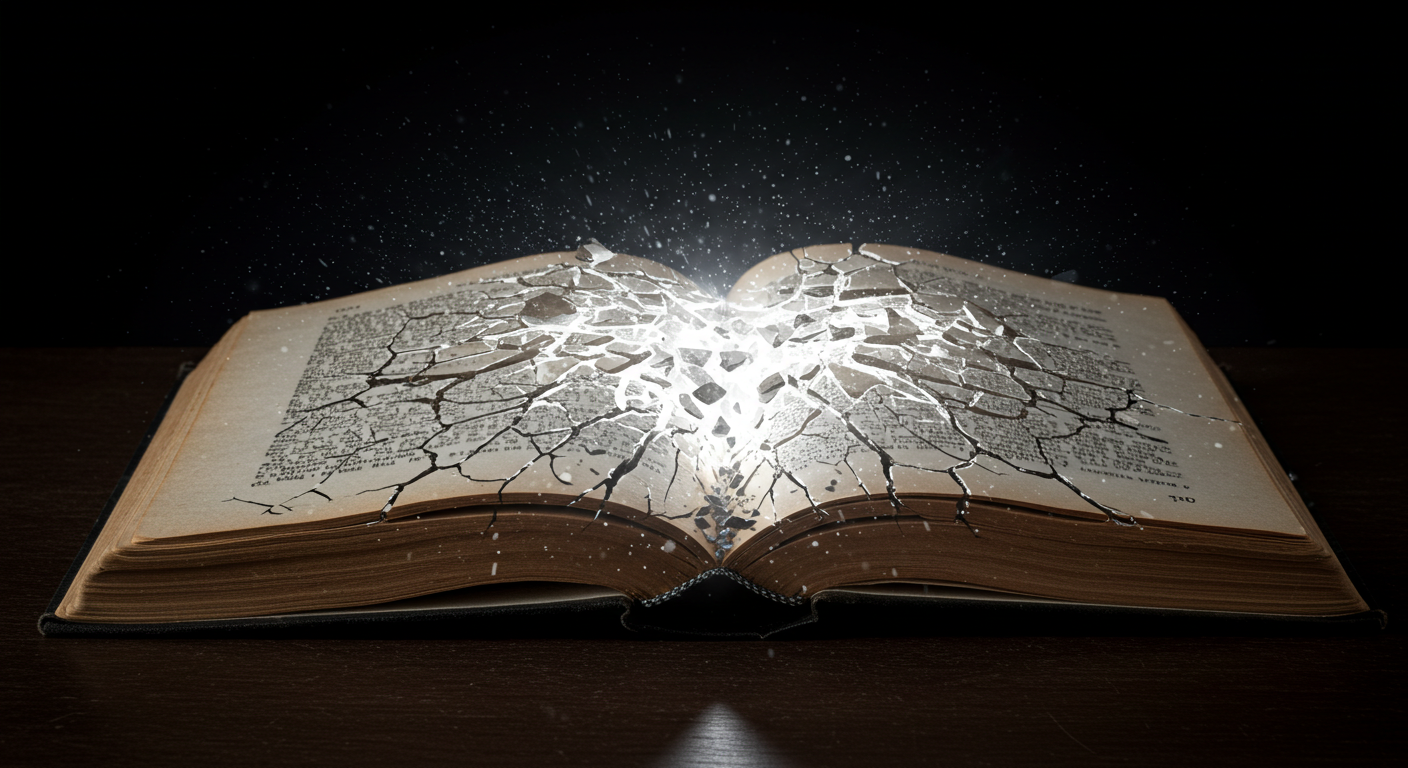目の前のことに追われて、物事の根本を考える余裕がない。そんな風に感じることはあるかな。
この記事はね、そんなあなたの思考を少しだけ整理して、物事の見え方を変えるヒントになるかもしれないよ。
ここでは、古代ギリシアの哲学者の考え方を、明日からあなたが使える、とてもシンプルな6つの「思考の型」として具体的に解説する。
それは、情報が圧倒的に少なかった時代に、本質だけを抜き出すために極限まで磨かれた、普遍的な知恵だからね。
もしよかったら、少しだけ、昔の話にお付き合いください。
タレスの思想【全体像】なぜ「哲学の祖」と呼ばれるのか?
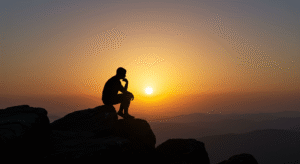
「情報が多すぎて、何が本質かよくわからない」
「物事の表面をなぞっているだけで、どうも手応えがない」
もしあなたがそんな風に感じているなら、少しだけ、昔の話にお付き合いください。
面白いことに、タレスが生きた時代は、世界に関する情報が圧倒的に「不足」していたんだ。だからこそ彼は、数少ない観察から本質をぐっと抜き出す思考を、極限まで磨き上げた。
その思考法が、逆に情報が「過剰」になった現代で、無数のノイズを見抜き、大切なことだけを掴むための、なんだか不思議なほど強力な武器になるんだよ。
まずは、タレスの思想がなぜ「哲学の始まり」と言われるほど重要なのか、その全体像から、ゆっくりと掴んでいこうか。
彼が行ったのは、単なる一つの発見、というよりは、
世界の「見方」そのものを、がらりと変えてしまうような、静かな革命だったんだ。
タレス以前の世界観。全てを説明した「神話」の時代
今の私たちにとって、自然の裏側には何かしらの「法則」がある、と考えるのは、もう呼吸をするくらい当たり前のことかもしれない。だけど、かつては全く違ったんだ。
タレスが生まれる前の世界では、人々はあらゆる出来事を「神話」で説明していたよ。
なぜ、空から雷が落ちるのか。
それは、大神ゼウスが怒っているから。
なぜ、日食が起きて太陽が隠れるのか。
それは、神々が何か不吉なことを知らせる前兆。
こんな風に、世界の全ては、人格を持った神々の、その日の気分によって動いている。そう考えられていたんだ。そこにあるのは、予測のつかない、気まぐれな展開ばかり。
人間は、その展開をただ受け入れ、畏れ、祈ることしかできない。
世界を「理解」しようとするのではなく、世界の「機嫌」をうかがう。それが、当時の人々の、ごく普通の感覚だったわけだね。
タレスの功績。神話を疑い「なぜ?」で世界の法則を探した
そんな時代に、すっと一人の人物が登場する。
タレスは、それまでの常識だった神話の世界観に、はっきりと「待った」をかけたんだ。
「本当に、雷は神の怒りなのだろうか」
「この世界には、神々の気分とは関係のない、もっと普遍的なルールがあるんじゃないか」
彼の功績の本質は、世界の出来事を、神々の気まぐれな物語(ミュートス)で説明するのをやめて、人間の理性(ロゴス)で説明しようと試みた、その“態度の転換”にあった。
哲学の歴史では「ミュートスからロゴスへ」なんて呼ばれたりもする、とても大きな出来事だよ。
自分の頭で「なぜ?」と問い、世界の法則を探求する。
この姿勢こそが、哲学の、そしてあらゆる知的探求の、輝かしい第一歩となったんだ。
何かを新しく「発見した」こと以上に、この「問いの立て方」そのものを発明したこと。
そこに、彼の本当のすごみがあると、私は思うよ。
タレス思想の要点。「問い・探求・仮説」という思考の構造
タレスのこの革新的な態度は、単なる思いつきではないんだ。誰でも真似できるような、再現性のある思考の構造を持っている。
それは、大きく3つのステップに分けることができるよ。
- ステップ1:問いの立て方を変える(常識を疑う)
「神話が世界の常識」という前提を疑い、自分の目で見たこと、感じたことを起点に「なぜ?」という問いを立てる。- ステップ2:本質を探求する(根源を探す)
目の前の多様な現象の奥にある、たった一つの根本的な原因・原理(アルケー)は何か、と物事の中心を探求する。- ステップ3:仮説を立てる(観察から結論へ)
神々のような超自然的な力には頼らず、あくまで自分の観察だけを根拠として、論理的な答え(仮説)を導き出す。
この「問い・探求・仮説」というシンプルな構造こそが、タレスの思想の要点だね。
そして、この後の章で詳しく見ていく、私たちが日常で使える思考の型の、もとになったものでもあるんだよ。
【この章のポイント】
タレス以前の世界は、神々の気まぐれな「神話」が全てを説明していた。
タレスの功績は、神話を疑い、自分の頭で「なぜ?」と世界の法則を探求する「態度」そのものにあった。
彼の思考は「問い・探求・仮説」という、現代にも通じる普遍的な構造を持っている。
タレスの思想の核心。「万物の根源は水」の本当の意味

タレスの思考の構造、なんとなく掴めてきたかな。
ではいよいよ、彼の最も有名な思想「万物の根源は水である」という言葉の、その奥を覗いてみることにしよう。
なぜ彼は世界の「根源」を探し、そして、なぜよりにもよって「水」という、たった一つのものにたどり着いたんだろうね。
「アルケー(根源)」とは何か?本質を探求する思考の重要性
まず少しだけ立ち止まって、タレスが探した「アルケー(根源)」という言葉について。
彼は、ただ世界の「材料」を探していた、というわけでもないんだ。
彼が追い求めた「アルケー」は、単なる材料ではなく、後の時代の哲学者たちが「根源」という言葉で捉えることになる、こんな二重の問いを含んでいた、と考えると、しっくりくるかもしれない。
全てを形作る「根源的な素材」は何か。
全ての物事がそこから生まれ、またそこへと還っていく、世界の最も原始的な土台。(錬金術とかに出てくるプリママテリアみたいなものだね。)
変化の背後にある「変わらない法則」は何か。
目まぐるしく変化し、多様に見える世界の、背後にある一つの普遍的な原理。
あえて言うなら、「複雑な現象をぐっと貫いている、一本のシンプルな背骨」のようなもの。それを探していたと考えると、少しイメージがしやすいかな。
じゃあ、なぜそこまでして「根源」を探すことが重要だったのか。
それはきっと、複雑で混沌として見える世界を「シンプルな法則で理解したい」という、人間の、どうしようもなく根源的な知的欲求の現れだったんだろうね。
世界を、理解可能な「秩序(コスモス)」として捉え直すための、とても大切な一歩だったわけだ。
なぜ「水」だったのか?観察から生まれた最も合理的な仮説
現代の私たちが聞くと、「万物の根源が水」というのは、なんだか素朴な考えに感じるかもしれない。うん、その感覚はわかるよ。
でも、タレスが挙げた根拠を見ていくと、そのじっとりとした観察眼の鋭さに、ちょっと驚かされるんだ。
彼が「水」を根源だと考えた理由は、主に以下の3つの観察に基づいている。
根拠1:生命との関連。全ての生物の栄養は湿っており、あらゆる種子も湿気を含んでいる。生命があるところには、必ず水がある。
根拠2:形態の変化。水は、固体(氷)、液体(水)、気体(水蒸気)と、その姿を自在に変える。一つのものが、多様な姿になれることを示している。
根拠3:世界構造との関連。タレス自身が、広大な海の上に大地が浮いている、と考えていた。(この説は、地震を水が揺れるためと説明することにも繋がった。)
ここで一番、ぐっとくるところ。
それは、彼が「神々のような超自然的な力を一切持ち出さず、誰もが自分の目で確かめられる『観察可能な事実』だけを積み上げて、結論を導き出した」という点だね。
この思考のプロセスこそが、神話的思考との決定的な違いであり、現代にまで続く「科学的な思考」の、静かで、しかし確かな第一歩だったと言えるだろう。
それはもう、頑張ったことだろう。(本当に偉い!)
【本質】結論より価値があるタレスの「思考のOS」
「とはいえ、結局『万物の根源は水』という答えは、現代の科学から見れば間違いですよね」
うん、その通りだね。きっと多くの人が、心のどこかでそう思っていたでしょう。
しかし、タレスの思想の本当の価値は、そこにはないんだ。
ここで、少しパソコンやスマートフォンのことを思い浮かべてみて。あれらには、「OS(オペレーティングシステム)」と、その上で動くたくさんの「アプリ」があるよね。
アプリ(個別の知識や答え)は、時代と共に情報が古くなったり、もっと優れたものが出たりして、いつかは役立たなくなるものだ。
一方で、OS(物事を考えるための根本的な姿勢や構造)は、普遍的で、新しいアプリを動かすための、ずっと変わらない土台であり続ける。
タレスが私たちに遺してくれたのは、古びてしまった「水という答え=アプリ」ではない。新しい知識や問いを生み出し続けるための、頑丈で優れた「思考のOS」そのもの。
私は、そう考えているよ。
そして、この普遍的な「OS」を、私たちの日常という現場で実際に動かすための具体的な方法。それが、次の章で紹介する「6つの思考の型」というわけだね。
【この章のポイント】
タレスが探した「アルケー(根源)」とは、世界の背後にある「変わらない本質」のこと。
「万物の根源は水」という結論は、当時の知識において、観察に基づいた極めて合理的な「仮説」だった。
タレスの思想の本当の価値は、古びる「答え(アプリ)」ではなく、普遍的に使える「思考のOS」そのものにある。
【実践編】タレスの思想から学ぶ、日常で使える6つの思考の型

さて。ここからは、これまで見てきたタレスの「思考のOS」を、あなたの仕事や日常で実際に動かすための、6つの具体的なアプリケーション、「思考の型」をご紹介するね。
といっても、いきなり全てを完璧にこなす必要は全くない。
肩の力を抜いて、「これなら自分にもできそうかな」と感じるもの一つから、気軽に試してみて。
① 常識を疑う思考の型。「思考の”神話”剥がし」
私たちの頭の中は、自分でも気づかないうちに「どうせうちの会社では無理だ」とか、「このやり方が昔からの決まりだから」といった、見えない前提、いわば現代の「神話」で、結構いっぱいになっているものだ。
タレスが当時の常識だった「神話」を疑ったように、まずは自分の中にある思い込みを、客観的な事実から、そっと引き剥がしてみようか。
Step1:まず「思い込み」を書き出す。
課題に対して感じている自分の考えを、正直に書き出す。
(例:「私の企画は、どうせ部長に反対されるに決まっている」)
Step2:次に「客観的な事実」だけを並べる。
その思い込みとは一旦切り離して、誰が見ても「そうだね」とわかる「事実」だけをリストアップする。
(例:「先月、若手Aさんの企画が採用された」「部長はいつもデータに基づいた根拠を求めている」「過去3回、私の企画は準備不足を指摘された」)
Step3:最後に、事実だけをじっと眺めてみる。
どうだろう。事実だけを静かに眺めてみると、感情的な思い込みとは、少し違う景色が見えてこないかな。
次の一手は、そこから考え始めるのが、きっと有効だよ。
もし、この作業中にあなたの頭の中で「でも…」「だって…」という言葉がふわっと浮かんだら、それこそがあなたが剥がすべき“神話”のサインかもしれないね。
② 本質を掘る思考の型。「一点突破の問い」
「なぜかいつも、同じような問題が再発する…」そんな風に感じるとき、私たちは表面的な原因だけに対処する、いわゆる「モグラ叩き」に陥っているのかもしれない。
タレスが「万物の根源は何か?」と、世界のたった一つの本質を問うたように、私たちも目の前の問題の「本質」は何か?を、一度立ち止まって問うてみよう。
そのための方法は、二つの問いをセットで使うことだ。
「なぜ、こうなっているのか?」(原因を探る問い)
「そもそも、何のためにやっているのか?」(目的を探る問い)
例えば、「資料の修正にいつも時間がかかってしまう」という問題があったとする。
「なぜ?」→「毎回ゼロから体裁を整えているから」。
「そもそも、何のため?」→「関係者で迅速に情報を共有するため」。
ここまで掘り下げると、
「迅速な共有が目的なら、体裁に時間をかけるより、テンプレート化してすぐに共有できる仕組みを作るべきだ」
という、より本質的な解決策が、すっと顔を出してくる。
ちなみに、「なぜ?」だけを繰り返すと、相手を問い詰めるような、ちょっと冷たい雰囲気になりがちだね。
未来に目を向けた「何のため?」と組み合わせることで、対話がずっと建設的になるから、これは覚えておくといいかもしれない。
③ 中心を見抜く思考の型。「”アルケー”発見術」
やるべきことが多すぎて、何から手をつければいいか分からず、結局全てが中途半端に…。多忙な現代では、これはもう、誰しもが経験することだと思うよ。
タレスが世界の根源(アルケー)を探したように、私たちも溢れるタスクや情報の中から、最も重要で、影響力の大きい一点を見つけ出すことが必要だ。
そのために、自分にこんな質問をしてみてほしい。
「もし、今日たった一つしか仕事ができないとしたら、どれをやるか」
「このプロジェクトで、これを失ったら全てが台無しになる『魂』みたいなものは、なんだろう」
例えば、新商品の企画会議。デザイン、機能、価格、宣伝方法など、色々な意見が飛び交うとする。
そんな時、
「この商品の“アルケー”は、『忙しい親が、罪悪感なく子供に与えられる安心感』という、この一点だ」
と中心を定める。そうすることで、全ての議論がその一点に自然と収束し、ブレがなくなっていくんだ。
常に「成果の8割を生み出す、最も重要な2割の活動は何か?」と考える癖をつけること。
それが、この思考法の本質、というわけだね。
④ 枠を外す思考の型。「ゼロベース質問法」
私たちは、知らず知らずのうちに「この仕事は、このやり方でやるものだ」という、見えない枠の中で物事を考えてしまいがちだ。
改善を重ねてはいるけれど、どうも成果が頭打ちになっている…。
そんな停滞感は、案外この「枠」が原因かもしれないね。
タレスが「世界は神々が作った」という当時の絶対的な前提(枠)を疑ったように、
私たちも目の前の当たり前を、一度ぜんぶゼロにして考えてみようか。
そのための、ちょっと面白い問いがあるよ。
「もし、〇〇がなかったら」
この〇〇に、当たり前になっている業務やルールを、ぽんと入れてみて。
「もし、この毎週の定例会議が、そもそも存在しなかったら」
「もし、競合のA社という存在を、完全に無視していいとしたら」
例えば、「毎月の報告書作成」という業務。
これに「もし、この報告書がなかったら、どんな問題が起きるだろう」と問いかけてみる。
「上司が進捗を把握できなくなるな」という答えが出たとしよう。
では、「報告書という形よりも効率的に、かつ正確に進捗を把握できる方法はないだろうか」と、思考が次の新しいステージに進むことができるだろう。
この質問は、時に非現実的なアイデアを生むこともある。でも、それでいいんだ。
一度思考の枠を、えいっと壊してみることで初めて、今まで見えなかった新しい選択肢が、ふっと姿を現したりするから。
⑤ 小さく試す思考の型。「仮説構築サイクル」
「新しい施策を導入したいけれど、失敗するリスクを考えると、なかなか一歩を踏み出せない…」
これは、多くの人が抱える悩みだと思う。
慎重になるのは、自然なことだからね。
タレスが「自然をじっと観察し、そこから仮説を立てた」ように、私たちも頭の中だけで考え込まず、現実の世界で小さな実験を繰り返すことで、より確かな答えを見つけ出すことができる。
そのための、シンプルな4ステップのサイクルだ。
Step1:観察 まずは先入観なく、「なぜかうまくいかないな」「ここがいつも滞るな」と感じることを、静かに観察する。
Step2:仮説 その原因について、「もしかしたら、〇〇が原因ではないか」と、自分なりの仮説を立ててみる。
Step3:小さな実験 その仮説を検証できる、誰にも迷惑をかけないレベルの、ごく簡単な実験を試す。
Step4:振り返り 実験の結果、何がわかったかを振り返り、次の行動を考える。
例えば、「チームのチャットが、業務連絡ばかりでどうも活性化しないな」と観察したとする。
そこで、「スタンプを一つ押すだけでもOK、というルールにすれば、心理的なハードルが下がるのではないか」と仮説を立て、
「まず自分のチームだけで1週間試してみよう」と小さな実験をする。
この繰り返しだね。
完璧な仮説や壮大な実験は、全く必要ない。
60点の仮説でいいから、まずやってみること。
この思考法が重視するのは、壮大な計画よりも、素早い学習なんだ。
⑥ 全体を掴む思考の型。「統合的思考」
個別の問題への対処に追われていると、いつも後手に回っているような、そんな感覚に陥ることがあるよね。「森を見ずに、木ばかり見ている状態」とでも言おうか。
私はいつも「マクロ視点」・「ミクロ視点」と呼んで活用しているよ。
マクロが森で、ミクロが木とか葉っぱだ。
タレスが「雨、川、氷、生命」といった多様な現象を、「水」という一つの概念で束ねて統合したように、私たちも一見バラバラに見える情報の中から、本質的な繋がりを見つけ出すことが大切だ。
そのための、具体的な3ステップだよ。
Step1:並べる。
関連する情報や出来事を、付箋やメモに一つずつ書き出して、机の上や壁に、物理的に並べてみる。Step2:繋げる。
それらを眺めながら、グループに分けたり、関係性のありそうなものを線で結んだりして、情報の関係性を可視化する。Step3:束ねる。
そして、「これら全てを貫く、一つのキーワードや概念は何か」と自分に問いかける。「これらは全て、結局のところ〇〇の問題だ」と言えるような、束ねる言葉を探すんだ。
例えば、
- 「A顧客からは価格への不満」
- 「B顧客からは機能不足の指摘」
- 「C部署からは営業プロセスの非効率さ」
というバラバラな情報があったとする。
これらを並べて眺めていると、
「これらは全て、結局のところ『顧客の本当の課題を、我々が正しく理解できていない』という一点に集約されるのではないか?」
という、より本質的な課題が、もやの中から浮かび上がってくるかもしれない。
すぐに答えが見つからなくても、情報を並べてぼんやり眺めているだけでも、結構効果はあるよ。
脳は、私たちが意識していなくても、情報同士の繋がりを、ちゃんと探そうと働き始めてくれるものだからね。
【この章のポイント】
日常で使える思考の型として、
常識を疑う「神話剥がし」、
本質を掘る「一点突破の問い」、
中心を見抜く「アルケー発見術」などがある。これらの思考法は、タレスの哲学の本質である「常識を疑い、本質を探求する」という態度を、現代の課題に合わせて応用したものだ。
大切なのは、完璧にこなすことではなく、まずは一つでも意識して使ってみるという、小さな実践。
日常で使える思考の型には、
枠を外す「ゼロベース質問法」、
小さく試す「仮説構築サイクル」、
全体を掴む「統合的思考」などがある。これらの思考法は、タレスの哲学の本質である「前提を疑い、観察から仮説を立て、本質で統合する」という態度を応用したもの。
大切なのは、壮大な計画よりも、日常の中での小さな問いかけや、ごく簡単な実験を繰り返すこと。
まとめ タレスの思想の要点を、明日からの「知恵」に変える
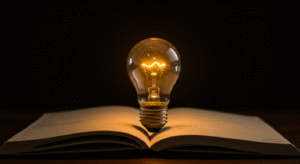
さて。ここまで、古代ギリシアの哲学者タレスの思想を、単なる歴史の知識としてではなく、現代を生きる私たちが使える「思考の道具」として、色々と話してきたよ。
タレスが私たちに遺してくれた一番の贈り物は、「万物の根源は水である」という、古くなった答え(アプリ)ではない。
その本質は、「自分の頭で、世界の”なぜ”を問い続ける姿勢」そのものなんだ。
そして、この姿勢こそが、物事を考えるための土台となる、普遍的な「思考のOS」なのだと、私は考えている。
情報という激流の中で、やみくもに泳ぎ続ければ誰しも疲れてしまうものだね。タレスの思想は、その流れの底にある、決して動かない「岩(本質)」を見つけるための方法、と言えるかもしれない。
ただ、この思考のOSは、どんな問題も解決してくれる万能薬、というわけでもない。
OSだけでは何も生み出せないからね。
その上で、あなたがこれから得る知識や経験、そして今回紹介したような「思考の型(アプリ)」を動かして初めて、その真価が発揮されるんだ。
だから、どうか完璧にやろうとしないでください。
紹介した6つの思考の型の中から、たった一つで構わないよ。
あなたが最も「面白そうだ」あるいは「これなら試せそうだ」と感じたものを、明日の仕事で、あるいは日常のちょっとした疑問に対して、こっそりと使ってみて。
その、たった一つの小さな問いかけが、今まで見過ごしていた何かを、ふと気づかせてくれるかもしれない。
タレスが始めた「知を愛し求める」という営みは、もしかしたら、そんな日常の小さな一歩から始まるのかもしれないね。
【この記事のポイント】
タレスの功績は、「神話」で説明されていた世界を、自分の頭で「なぜ?」と問い、法則を探求する対象へと変えたことにある。
彼の思想の本当の価値は、古びる「答え」ではなく、時代を超えて使える「思考のOS(物事を考えるための根本的な姿勢)」を私たちに示してくれた点にある。
日常で使える「6つの思考の型」を、まずは一つでも試してみることが、その知恵を自分のものにするための確かな一歩となる。
このブログでは、こんな風に、少しだけ物事の捉え方を変えることで、日々の気持ちが楽になるような「考え方」や「心の指針」を探求しているよ。
もし、あなたが自分なりの「豊かさ」や「幸せ」を見つけるヒントを探しているなら、他の記事も覗いてみてほしいな。
きっと、何か新しい発見があると思うよ。
【こちらの記事も読まれています】