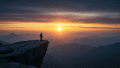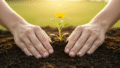頭の中が考え事でいっぱいで、心が晴れない…。
その状態から抜け出し、驚くほどシンプルに頭と心を整える方法を紹介します。
この記事では、あなたの悩みに合わせた3つの「歩く哲学」実践法から、ひらめきを確かな力に変える独自メソッドまで、具体的に解説しますね。
それは、偉大な哲学者の知恵と脳科学に裏付けられた、とても合理的な方法なんです。
さあ、あなたの日常を少しだけ豊かにする、最初の一歩をここから始めましょう。
「歩く哲学」こそ最強の思考法。なぜ、ただ歩くだけで答えが見つかるのか?

「本当にただ歩くだけで、そんなに効果があるの?」
きっと、そう思いますよね。
その答えは、なんというか…、昔の偉い人たちが残した足跡と、最近の脳科学が解き明かした事実の、両方の中にあるんですよ。
少しだけ、その理由を覗いてみましょうか。
ニーチェは山で、ルソーは森で。天才たちが「歩きながら」考えた本当の理由
「偉大な思想はすべて歩くことから生まれる」。
これは、ドイツの哲学者ニーチェの思想を象徴する言葉として、広く知られています。
ニーチェは生涯、病弱な身体と心の苦悩を抱えていましたが、スイスのシルス・マリア湖畔を歩きながら思索にふけり、あの有名な『ツァラトゥストラはかく語りき』の着想を得たと言われています。
彼にとって歩くことは、ただ考える時間というだけでなく、自分自身との、ある種の闘いだったのかもしれませんね。
そして、フランスの哲学者ルソーも、こんなことを書き残しています。
「私は歩きながらでなければ、ほとんど考えることができない。立ち止まると私の頭は働かなくなる」
彼にとって、社会の喧騒から離れて森の中を一人で歩く時間は、自分自身の内なる声にじっと耳を澄ますための、何にも代えがたいひとときだったようです。
他にも、古代ギリシャのアリストテレスは、弟子たちと学園の庭をぶらぶらと歩きながら(これを逍遙(しょうよう)と言います)講義をした、なんて話も残っています。
彼らにとって歩くことは、単なる健康法や気分転換じゃなかった。
そう。
思考をじっくり深め、新しいアイデアを生み出し、そして自分自身と向き合うための、なくてはならない「思考の道具」だったのです。
脳科学が解明した事実。歩くあなたの脳内で起きている「3つのすごい変化」
そして、面白いことに、こうした哲学者が経験的に「なんか、いいぞ」と感じていたことを、現代の科学が少しずつ証明してくれているんですよ。
私たちが歩いている時、脳の中では主に3つの、なかなかすごい変化が起きているんです。
-
変化① 脳の”おしゃべり”が、すーっと止まる
頭の中で同じ悩みがぐるぐる、ぐるぐる回ってしまう、あの現象。
あれは、「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」という脳の回路が過剰に働きすぎている状態なんです。いわば「思考のアイドリング状態」ですね。
歩行のような単調なリズム運動は、このDMNの活動を穏やかに鎮め、思考のアイドリング状態をオフにしてくれる効果があります。これでようやく、脳が本当に休息できるわけです。
-
変化② アイデアの”源泉”が、ぽこっと湧き出す
スタンフォード大学が2014年に行った研究では、座っている時と比べて、歩いている時は創造性が平均で60%も向上した、という、ちょっと驚くような結果が出ています。
これは、歩くことで脳が適度にリラックスして、普段は結びつかないような記憶や情報が、ふわふわと自由に結びつきやすくなるから。行き詰まった時にひらめきが舞い降りてくるのは、「偶然」なんかじゃなく、ちゃんと理由があったのですね。
-
変化③ 心の”幸福スイッチ”が、そっとONになる
歩いた後、なんだか理由もなく気持ちが楽になるのにも、化学的な根拠があります。
リズミカルな運動は、「幸福ホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌を促してくれるんです。このセロトニンには、精神を安定させ、漠然とした不安を和らげてくれる働きがあります。
歩くことは、いわば自分自身で心のバランスを整えるスイッチを、そっと入れてあげるような行為なのですね。
つまり、「歩く哲学」は根性論や精神論なんかじゃなくて、歴史と科学にちゃんと裏付けられた、とても合理的な思考の技術と言えるんですよ。
【この章のポイント】
ニーチェやルソーといった偉大な哲学者は、歩くことを「思考の道具」として活用していた。
脳科学的に、歩くことには「脳の雑念を鎮め」「創造性を高め」「心を安定させる」という明確な効果が証明されている。
「歩く哲学」は、歴史と科学の両方に裏付けられた、信頼できる思考法である。
【悩み別】あなたのための「歩く哲学」実践法。今日からできる3つのアプローチ

さて、ここからは実践編です。
「歩く哲学」と一言で言っても、
そのやり方は一つじゃありません。
今のあなたの心の状態に合わせて、「あ、これならできそうかな」としっくりくるものを選んでみてください。
一番大切なのは、自分を追い込まず、心地よく感じられるものから試してみることですよ。
「考えすぎて疲れた…」なら。頭を空っぽにする【思考デトックス・ウォーク】
もう、情報を取り込みすぎて頭がパンクしそう…。
同じ悩みが、ぐるぐると回り続けて、本当に疲れた…。
そんな時は、まず頭の中をからっぽにして、脳をしっかり休ませてあげましょう。
このウォークの目的は、何かを生み出すことではありません。
ひたすら「手放すこと」。
そう、いわば思考の断捨離ですね。
-
① 歩行瞑想
これは、禅の修行で行われる「経行(きんひん)」という方法を、とても簡単にしたものです。-
まずは、ゆっくりとしたペースで歩き始めてみてください。
-
歩きながら、頭の中に浮かんでは消えていく思考や感情を、無理に追い払おうとせず、ただ「ああ、今、仕事のことを考えているな」「少し、焦っているな」と、ぼんやりと眺めます。まるで、空に流れる雲を眺めるような感覚ですね。
-
一番大切なのは、その思考を良い・悪いと判断(ジャッジ)しないこと。ただ、気づいて、手放す。本当に、それだけでいいんです。
-
-
② マインドフルネスウォーク
こちらは、ぐるぐる回る思考から意識をそっと逸らし、「今、ここ」の身体の感覚に集中する方法です。-
「右足の裏が、じわりと地面に触れる感覚」
-
「風が、頬をふわっと撫でていく感覚」
-
「遠くから聞こえてくる、サイレンの音」
-
「雨上がりの、土の匂い」
こんなふうに、五感で感じられることに、そっと意識を向けてみてください。
-
もし途中で考え事をしてしまっても、「あ、逸れたな」と気づいて、また優しく感覚に戻ってくれば大丈夫。
完璧じゃなくて、いいんですよ、全然。
「もう何も浮かばない…」なら。行き詰まりを打破する【アイデア孵化器ウォーク】
仕事の企画や、プライベートの問題解決で、どうにもこうにも行き詰まってしまった時。
あぁ、もう何も浮かばない…って、なりますよね。
そんな時は、脳を適度にリラックスさせ、偶然のひらめきが生まれやすい状態を作ってあげましょう。
思考を無理やり絞り出すんじゃなくて、「脳をかき混ぜて、アイデアが生まれるのを、まあ待ってみるか」くらいの、そんなイメージです。
-
① 「問い」を一つだけ持って歩く
-
歩き出す前に、「〇〇の企画を面白くするには、どうすればいいかな?」というように、考えたいテーマをシンプルな「問い」の形にして、一つだけ心に決めます。
-
そしてここからが面白いのですが、歩いている間は、その問いを一旦、忘れてください。
ええ、忘れるんです(笑)。
無理に答えを出そうとせず、ただ景色を眺めたり、リズムよく歩くことに集中します。
-
すると、脳がバックグラウンドで勝手に情報を整理してくれて、ふとした瞬間に「あ!」というアイデアが、向こうからひょっこりやってくることがあります。
-
-
② フラヌール的散歩
これは、目的地もルートも決めず、自分の好奇心の赴くままに街をさまよい歩く方法です。「フラヌール」というのは、フランス語で「遊歩者」という意味なんですよ。
普段は絶対に通らない、細い路地裏。
偶然見つけた、名前も知らない公園。
なんだか妙に気になる、古いお店の看板…。
そんな「意図的な道草」が、あなたの凝り固まった思考に、新鮮な風を吹き込んでくれます。
「自分が分からない…」なら。不安の正体を見つける【自己との対話ウォーク】
これといった大きな問題はないはずなのに、なぜか心が晴れない。
自分が本当に何をしたいのか、どう感じているのか、分からなくなってしまった…。
そんな時は、誰かに相談する前に、まず自分自身と静かに向き合う時間を作ってみましょう。
これは、最も手軽で、とても効果的な「セルフカウンセリング」。
そうですね、心の“棚卸し”をする作業、とでも言いましょうか。
-
① ソクラテス式・問答ウォーク
古代ギリシャの哲学者ソクラテスが使った「問答法」を、自分一人でやってみる方法です。-
まずは「なぜ今、私は不安なんだろう?」と自分に問いかけます。
-
心に浮かんだ答え(例えば「仕事で失敗するのが怖いから」)に対して、さらに「そっか。じゃあ、なぜ、失敗するのが怖いのかな?」と問いを重ねます。
-
これを3〜5回ほど繰り返していくと、表面的な感情の奥に隠れていた、自分でも「あ、そうか…」と驚くような本音や価値観にたどり着くことがあります。
-
-
② 感情の身体マッピング
感情は「心」だけで感じるものではなくて、必ず「身体」にも、何かしらの反応として現れています。
歩きながら、自分の身体をスキャンするように、そっと観察してみてください。-
「不安を感じると、みぞおちのあたりが、きゅーっと重たくなるな…」
-
「焦りを感じると、無意識に肩にぐっと力が入っているな…」
-
「嬉しいことがあると、胸のあたりが、ぽかぽかと温かくなるな…」
このように感情を「身体の感覚」として客観的に捉えることで、感情の渦に飲み込まれにくくなり、少し冷静に向き合うことができるようになります。
-
【この章のポイント】
考えすぎて疲れたら【思考デトックス・ウォーク】 思考を手放し、頭を空っぽにすることに集中する。
行き詰まったら【アイデア孵化器ウォーク】 問いを立てて一旦忘れ、偶然のひらめきを待つ。
自分が分からなくなったら【自己との対話ウォーク】 自問自答を繰り返し、自分の心の声に耳を澄ます。
【独自】「歩く哲学」の効果を10倍に。歩いて見つけた“答え”を逃さない思考定着術

歩いていると、ふっと良いアイデアが浮かんだり、悩みの糸口が見えたりすること、ありますよね。
でも、家に帰って一息ついた頃には、
「あれ、さっき何を思いついたんだっけ…?」
と、大切なひらめきがシャボン玉みたいに、ぷつんと消えてしまった経験、ありませんか?
あれって、本当に悔しいし、がっかりしますよね。
せっかく見つけた「答え」のタネを、決して逃さないために。
ここでは、
「歩く」の効果を一過性のもので終わらせず、あなたの確かな力に変えるための、独自の技術をお伝えします。
歩きながら「ひらめき」を捕獲する、最強のボイスメモ活用術
歩いている最中に浮かぶひらめきは、とても繊細で、びっくりするくらい忘れやすいものです。
だからこそ、浮かんだその瞬間に「捕獲」してあげる必要があります。
そのための最強の道具が、お手持ちのスマートフォンに入っている「ボイスメモ」の機能。
なぜ、手書きのメモじゃないのかって?
それは、歩きながらメモ帳を取り出して、文字を書くという行為が、せっかくの良い思考のリズムを、ぷつりと断ち切ってしまうから。
(でも手書きがダメってわけではありませんよ。私も手書きにするときも多いですし。)
その点、ボイスメモなら、歩みを止めることなく、浮かんだ思考をそのまま、そっくり記録できます。
-
【準備】歩き出す前に
iPhoneの「ボイスメモ」など、標準で入っている録音アプリを、すぐに起動できるようにスマホのホーム画面に出しておきましょう。もしマイク付きのイヤホンをお持ちなら、スマホをポケットに入れたままリモコン操作で録音を開始できるので、さらに便利ですよ。
-
【録音】ひらめいた瞬間に
完璧な文章で、格好良く話そうなんて、まったく思う必要はありません。
「あ、そうか」「なるほどな…」といった感情のつぶやきや、「企画書、もっとシンプルに」「あの人に、連絡」といった単語の断片で十分。
一番大切なのは、思考の“つぶやき”を、その熱量が冷めないうちに、そのまま録音しておくこと。後で聞き返した時に、その時の感覚まで、ありありと思い出せるはずです。
なんだか「思考の虫取り網」みたいで、少し楽しくなってきませんか?
帰宅後10分がカギ。「書く瞑想」で思考を自分のものにする技術
さて、ボイスメモでひらめきを捕まえたら、次はその思考を、ちゃんと「自分のもの」にする工程です。
声の記録は、あくまで一時的な「仮置き場」。
それを文字にすることで初めて、思考は客観的に眺められ、整理され、本当の意味での「力」に変わります。
おすすめは、歩き終えて、まだ少し身体がぽかぽかしている帰宅後10分以内。
このゴールデンタイムに、「書く瞑想」とも言えるジャーナリングの時間を、ほんの少しだけ設けてみましょう。
-
まず、先ほど録音したボイスメモを聞き返します。
-
ノートやPCのまっさらなページに、日付と簡単なタイトル(例:「10/26の散歩」)を書きます。
-
あとは、形式など一切気にせず、ボイスメモの内容や、歩きながら感じたこと、考えたことを、ただ自由に書き出していくだけ。
箇条書きでも、文章でも、図やイラストでも、何でも構いません。
「思考のゴミ出し」のように、綺麗にまとめようとせず、頭の中にあるものをいったん全部そこに出してしまう、という感覚が大切です。
そして、最後に一つだけ。
書き出したものの中から、「具体的にできる“小さな一歩”」を見つけ出し、ページの最後に書き加えてみてください。
-
「〇〇さんに、このアイデアを雑談がてら話してみようかな」
-
「気になったあの本のことを、寝る前にネットで調べてみよう」
この「魔法の1行」が、あなたの思考を現実の世界で動かすための、力強いエンジンになってくれます。
この「歩く(発散)→ 録る(捕獲)→ 書く(定着)」という一連の流れ。
これを「思考の収穫サイクル」と呼んでいます。
ぜひ、試してみてくださいね。
【思考の収穫サイクル】
① 歩く(発散と思考整理)
↓
② 録る(ひらめきの捕獲)
↓
③ 書く(思考の定着と行動計画)
↓
(①へ戻る)
【この章のポイント】
歩いて得たひらめきは、ボイスメモで思考のリズムを止めずに「捕獲」する。
帰宅後10分以内に、捕獲した思考をノートに書き出すことで、客観視し、定着させる。
最後に「明日できる小さな一歩」を書き出すことで、思考を行動へと繋げる。
もっと知りたい!「歩く哲学」Q&Aと、やってはいけない3つの落とし穴

さて、ここまで読んで「よし、ちょっとやってみようかな」と思ってくださった方もいるかもしれませんね。
でも、いざ始めるとなると、「これで合っているのかな?」と、細かいことがふと気になったりするものです。
ここでは、そんなあなたの素朴な疑問や不安を、一つ一つ解消していきす。
音楽は聴く?速さは?時間は?「歩く哲学」の素朴な疑問にすべて答えます
-
Q1. 音楽やポッドキャストは聴いてもいいですか?
-
A. 目的によりますが、最初は「聴かない」のがおすすめです。
特に、頭の中を空っぽにしたい「思考デトックス」や、自分の心と向き合いたい「自己との対話」が目的の場合は、外部からの情報をシャットアウトした方が、より深く集中できます。周りの風の音や、自分の足音に耳を澄ますのも、なかなか良いものですよ。
もしどうしても何か聴きたい場合は、歌詞のない穏やかなBGMや、川のせせらぎのような自然音などに留めておくのが良いかもしれませんね。
-
-
Q2. 歩くペース(速さ)は、どれくらいがいいですか?
-
A. 「あなたが心地よいと感じる速さ」が、もうそれだけで正解です。
これは健康のためのウォーキングではないので、息を切らして「はぁ、はぁ」と頑張る必要はまったくありません。むしろ、少しゆっくりすぎるかな、と感じるくらいでちょうど良いかもしれません。
「周りの景色がちゃんと目に入ってくる速さ」を目安にしてみてください。
-
-
Q3. 時間はどれくらい歩けばいいですか?また、いつ歩くのが効果的ですか?
-
A. まずは「5分だけ」からで十分。時間帯によって、少し効果が変わります。
30分や1時間と気負う必要はありませんよ。大切なのは長さよりも、生活の中に無理なく組み込むことです。
-
朝の散歩は、日光を浴びることで体内時計がリセットされ、頭がしゃっきりと目覚めます。ポジティブな気持ちで1日を始めたい時にぴったりです。
-
夜の散歩は、1日分の情報を頭の中で整理して、心身をリラックスモードに切り替えるのに役立ちます。穏やかな気持ちで眠りにつきたい時におすすめですよ。
-
-
何よりも大切なのは、ルールに縛られすぎず、あなた自身が「ああ、なんか気持ちいいな」と感じられるスタイルを見つけることです。
【要注意】これをやると逆効果。「歩く哲学」ありがちな3つの失敗パターン
せっかくの「歩く哲学」も、ほんの少しのことで効果が半減してしまうことがあります。
そうならないために、ついやってしまいがちな「落とし穴」を、先にお伝えしておきますね。
-
落とし穴① スマホを操作しながら歩いてしまう
これは最もありがちで、最も効果を下げてしまう行為です。
メッセージを返したり、ニュースを眺めたりしながら歩いていては、脳はずっと情報処理モードのまま。いつまで経っても脳は休まりません。
歩き出す前に、スマホは機内モードにするか、いっそポケットやカバンにしまってしまうことを、強く、強くおすすめします。
-
落とし穴② 「歩かなきゃ」が義務になってしまう
「毎日30分歩くぞ!」と意気込むのは素晴らしいことですが、「~ねばならない」という義務感は、知らず知らずのうちにストレスになります。これでは、リラックスするどころか、逆効果ですよね。
「今日は疲れているからやめておこうかな」と自分を許すことも、長く続けるためには、とても大切なことなんですよ。
-
落とし穴③ 無理に「答え」を出そうと焦ってしまう
特に「アイデア孵化器ウォーク」の時にやりがちですが、「何か良いアイデアを出さないと!」と焦れば焦るほど、脳はきゅーっと緊張して、自由な発想を妨げてしまいます。ひらめきって、力を抜いた瞬間に、ふっとやってくるものですから。
「答えが出なくても、気持ちが楽になればそれで十分」くらいの、大らかな気持ちで歩いてみてください。
雨の日でも、忙しい日でも大丈夫。継続を支えるささやかな工夫
習慣化のいちばんの敵は、「できない日」が続いて、そのまま心がぽきんと折れてしまうこと。
でも、大丈夫。
外を歩けなくたって、できることはたくさんあります。
大切なのは、完璧を目指さないこと。
そして、途切れても気にせず、またいつでも、ひょいと再開できることです。
-
ベランダや窓辺で5分、外の空気を吸う
これだけでも、部屋にこもっているのとは気分がまったく違います。遠くの空をぼーっと眺めるだけでも、脳はリフレッシュできますよ。
-
部屋の中を、ゆっくりと歩いてみる
ただ部屋の中をぐるぐると歩くだけでも、足の裏が床に触れる、その感覚に集中すれば、立派な「歩行瞑想」になります。 -
Googleストリートビューで「デジタル散歩」
少しユニークな方法ですが、行ってみたい海外の街並みや、懐かしい故郷の道を画面で眺めてみるのも、脳に良い刺激を与えてくれます。 -
日常の動作を、少しだけ意識してみる
エスカレーターを階段に変えてみる。一駅手前で降りてみる。そんなささやかな工夫の積み重ねが、あなたの思考を少しずつ、でも確実に変えていくはずです。
【この章のポイント】
音楽や時間は気にしすぎず、自分が「心地よい」と感じるスタイルを見つけるのが一番。
「スマホを見ながら」「義務感で」「焦って答えを出す」のは逆効果なので避ける。
歩けない日があっても大丈夫。完璧を目指さず、できる範囲で続けることが何より大切。
【究極の歩く哲学へ】それは、新しい自分に出会うための思考の道

さて、ここまで「歩く哲学」の具体的な方法やコツについてお話ししてきました。
日々の悩みを解決するための、とても実用的な知恵。
でも、もしよろしければ、最後にもう一歩だけ、深い世界へ足を踏み入れてみませんか。
「歩くこと」が持つ、あなたの人生そのものを、より豊かにしてくれるかもしれない、本質的な意味について。
誰かの「正解」はいらない。自分の「納得解」を見つけるということ
私たちは、情報が溢れる社会の中で、知らず知らずのうちに、
誰かが提示する「正解」や「効率的な方法」を探すことに、すっかり慣れてしまっているのかもしれません。
ですが、あなたの仕事のこと、人間関係のこと、そしてこれからの人生のこと…。
そういった悩みに、万人共通の「たった一つの正解」なんて、本当に、あるのでしょうかね。
「歩く哲学」を通じて見つかるのは、おそらく、論理的に100点満点の「正解」ではないでしょう。
そうではなく、あなたの頭と、心と、そして身体が、すべて一緒になって
「これだ」
「なんだか、しっくりくるな…」
と感じられる、あなただけの「納得解」なのです。
なぜ、歩くとそんな「納得解」が見つかりやすいのか。
思うに、机の前でうんうん唸って考える思考は、どうしても論理や理性を司る「左脳」の働きに偏りがちです。
一方で、リズムよく歩きながら考える時、私たちは身体の感覚や、ふと目に入る景色の美しさといった、直感や感性を司る「右脳」も、ごく自然に使っています。
この「頭(左脳)」と「心・身体(右脳)」が、歩くことを通じて穏やかに対話を始め、両者が深く「うんうん」とうなずき合えた地点に、本物の「納得解」は生まれる。
なんかね、そんな気がするんですよ。
誰かが決めた「正しさ」ではなく、あなた自身が「よし、これでいこう」と心から思える答え。
それを見つけるための時間が、「歩く哲学」なのだと思います。
ニーチェに学ぶ「自己超越」の道。歩くことは自分を更新し続ける行為である
この記事の中で、何度かニーチェという、ちょっと風変わりな哲学者の名前に触れてきました。
彼にとって「歩くこと」は、単なる思考整理や健康法という次元を、遥かに超えていました。
彼の哲学の中心には、「自己超越」という考え方があります。
これは、簡単に言えば
「今までの自分の殻を一つ破って、より広い視点を持つ、新しい自分へと生まれ変わっていくこと」です。
歩くという行為は、とても当たり前ですが、物理的に「今いる場所」から「まだ見ぬ別の場所」へと、自分自身を移動させる行為ですよね。
ニーチェはきっと、この物理的な移動に、精神的な移動を、そっと重ね合わせていたのでしょう。
つまり、
一歩、また一歩と大地を踏みしめるごとに、古い悩みや凝り固まった価値観を足元にぽいっと脱ぎ捨てて、歩みを進めるごとに、新しい自分へと近づいていく。
彼にとって歩くことは、まさに「自己を更新し続けるための、ささやかな儀式」そのものだったのです。
あなたが「歩く哲学」を続けていくことで、得られるもの。
それは、日々の悩みの解決策だけではないかもしれません。
知らず知らずのうちに、昨日までの自分とは少し違う景色が見えるようになっている。
ほんの少しだけ、大きな視点から物事を捉えられるようになっている。
歩くという道は、誰のためでもない、あなた自身の人生を、あなた自身の手で豊かにしていくための道なのです。
【この章のポイント】
「歩く哲学」で見つかるのは、誰かの「正解」ではなく、**自分自身が心から「しっくりくる」と感じる「納得解」**である。
歩くことは、物理的な移動であると同時に、古い自分を脱ぎ捨て、新しい自分へと更新し続ける「自己超越」のプロセスでもある。
日々の実践の先には、悩みの解決だけでなく、より豊かな人生観を得られる可能性が広がっている。
【まとめ】思考の迷路の出口は、玄関のドアのすぐ外にある

特別な道具も、難しい理論も、優れた才能も、何もいりません。
この記事を通してお伝えしたかったのは、「歩く哲学」という、私たちが生まれながらに持っている、最もシンプルで、それでいて最も奥深い「思考の道具」。
あなたの脳をクールダウンさせ、新しいアイデアの源泉となり、そしてあなた自身の心と深く向き合うための最強のツールは、すでにあなたの中に、そしてあなたの足元に、ちゃんと備わっているのです。(そう、足元に。)
「でも、時間がなかなか取れないし…」
「なんだかんだ、面倒になってしまうかも…」
そうですよね。
頭の中だけで、また新しい「やらない理由」を探し始めてはいませんか?
もう、その思考の迷路の中だけで答えを探し、考えをこねくり回すのは、今日で終わりにしましょう。
大切なのは、完璧な計画を立てることでも、正しいやり方をマスターすることでもありません。
不完全なままでも、よく分からなくても、ただ、最初の一歩をえいっと踏み出してみること。
本当に、ただそれだけなんです。
ぜひ、靴を履いてみてください。
まずは5分、ただ家の周りをぐるっと歩いてみる。
あるいは、普段の生活のついでに、いつもと少しだけ違う道を意識して通ってみる。
その、ほんのささやかな一歩が、あなたの思考を、そして日常を、少しだけ豊かに変える、確かなきっかけになるはずです。
あなたがずっと探し続けていた「答え」との出会いは、案外、次の角を曲がったすぐそこにあるかもしれませんよ。
【こちらの記事も読まれています】

【参考文献】
-
Oppezzo, M., & Schwartz, D. L. (2014). Give your ideas some legs: The positive effect of walking on creative thinking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(4), 1142–1152.
-
フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはかく語りき』
-
ジャン=ジャック・ルソー『孤独な散歩者の夢想』
このブログでは、こんなふうに日々の生活の中で使える「考え方の道具」を、これからも色々とご紹介していきたいと思っています。
もし、あなたが「自分にとっての幸せって何だろう?」とか、「もっと豊かに生きていくにはどうすればいいんだろう?」といったことに少しでも興味があれば、他の記事も覗いてみてくださいね。
きっと、何か新しい発見があると思いますよ。