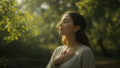他人の言動に心がザワついたり、考えても仕方ないことでいつも悩んでいませんか?
大丈夫、難しい話は一切ありませんよ。
この記事では、「悩みの正体」を解き明かし、日常で使える、心を軽くする具体的な「技術」だけを、優しくお伝えします。
読み終える頃には、振り回されていた心が穏やかになり、人生の主導権を自分の手に取り戻せるはず。
さあ、一緒にその第一歩を踏み出してみましょう。
もう、自分を責めなくていい。気持ちが楽になる「人生の主導権」を取り戻す方法

ふとした瞬間に、頭の中でグルグルと同じことが回り続けてしまう。
-
あの人の、何気ない一言がずっと胸に刺さっている…
-
考えても仕方ないのに、将来のことを思うと、急に心細くなる…
-
SNSを開けば、誰かの輝かしい姿と自分を比べて、なんだか落ち込んでしまう…
そんなふうに、自分の力では「どうにもならないこと」で心が疲れ果てて、動けなくなってしまうこと、ありませんか。
頭では「気にするだけ無駄だ」と分かっているのに、どうしてもやめられない。
そんな自分を
「なんて意志が弱いんだろう」
「考えすぎる性格が悪いんだ」
なんて、責めてしまったりもする。
その気持ち、本当にしんどいですよね。
でも、もし。
その悩み続ける癖が、あなたの“性格”や“弱さ”のせいではなかったとしたら、どうでしょう。
何を隠そう、私自身が前はひどい完璧主義で、他人の評価という“コントロールできないこと”に振り回され、眠れない夜を数えきれないほど過ごしてきました。
だからこそ、その苦しさが、私には痛いほどわかるんです。
この記事は、単なる気休めの言葉や、一時的なポジティブシンキングをお伝えするものではありません。
なぜ私たちは悩み、どうすればその連鎖から抜け出せるのか。
その根本的な仕組みを、心理学や脳科学の知見を交えながら、ゆっくり、丁寧に解きほぐしていきます。
そして、あなた自身の力で心の主導権を取り戻し、穏やかな毎日を送るための、具体的な「技術」をお渡しします。
これは、一度身につければ、あなたの人生をずっと支え続けてくれる「一生モノの技術」です。
読み終える頃にはきっと、気持ちが楽になり、穏やかな自信が内側から湧いてくるのを感じられるはずです。
それでは、一緒に始めていきましょう。
第1章【悩みの正体】なぜ私たちは「どうにもならないこと」で心を消耗するのか?

まず最初に、私たちの心を悩ませる「正体」について、少しだけ知っておきましょう。
敵の正体がわかれば、むやみに怖がる必要はなくなりますからね。
原因はあなたの“性格”ではない。脳と心が持つ「2つの癖」のせいだった
あなたが「どうにもならないこと」で悩んでしまうのは、人間が、はるか昔から生き延びるために進化の過程で身につけてきた、ごく自然で、大切な機能のせいなのです。
これには、人間が持つ「コントロール幻想(Illusion of Control)」という心の働きも関係しています。
これは、偶然の出来事に対して、自分にはコントロールする力があると思い込んでしまう、ごく自然な心理的な癖のことです。
この癖の背景には、私たちの脳と心が持つ、生まれつきの2つの性質があります。
-
① 脳が持つ「危険を察知する」癖
私たちの脳の奥深くには、危険を察知するための「警報装置」のような機能が備わっています。この装置は、コントロールできない「不確実なこと」を危険とみなし、「大丈夫か?」と常に警戒し続ける性質があるのですね。将来への不安が尽きないのは、この警報装置が優秀に働いてくれている、ある意味、健康な証拠とも言えるのです。 -
② 心が持つ「仲間と繋がりを求める」癖
人間は、一人では生きていけない社会的な生き物です。だからこそ私たちの心は、集団の中でうまくやっていくために「仲間からどう思われているか」を気にするようにできています。「嫌われたくないな」「認められたいな」と感じるのは、人との繋がりを大切にするための、とても人間らしい本能なんです。
どうでしょう。
「考えすぎてしまう」というあなたの性質は、決して弱さなどではなく、危険を回避し、人との繋がりを大切にするための、
一種の「生存戦略」だったのかもしれません。
まずはそのことを、どうか知っておいてくださいね。
その重荷、本当にあなたのもの?古代の賢人に学ぶ「悩みの仕分け方」
悩むのが自然なことだとわかっても、やっぱり、その苦しさからは解放されたいですよね。
そのヒントは、今から2000年も前の、ある賢人の言葉に隠されています。
皇帝にも教えを説いたほどの賢人、ストア派の哲学者エピクテトスは、こう言いました。
「われわれを悩ますのは、物事そのものではなく、物事に関するわれわれの意見である」
「上司が不機嫌だ」という出来事そのものではなく、「嫌われたらどうしよう」という、あなた自身の”意見(解釈)”が、あなたを苦しめている、という考え方です。
この普遍的な教えを、現代心理学の父の一人、アルフレッド・アドラーは、
「課題の分離」
という、さらに具体的な技術へと発展させました。
これは、あなたの目の前にある悩みが、
「自分の課題」なのか、
「他人の課題」なのかを、はっきりと分ける考え方です。
-
他人の課題(=あなたにはコントロールできないこと)
-
他人がどう思うか、どう感じるか
-
他人がどんな決断をし、どんな行動をとるか
-
-
自分の課題(=あなたにコントロールできること)
-
自分がどう考え、どう行動するか
-
自分が何を学び、どう成長するか
-
「課題の分離」とは、決して冷たい突き放しではありません。
それは、相手の領域を土足で踏み荒らさないという「成熟した優しさ」であり、相手を信頼して任せるという「健全な関係の第一歩」でもあるのですね。
まずは、背負う必要のない“他人の課題”という重荷を、そっと下ろすことから始めてみませんか。
あなたのエネルギーを注ぐべきはココ!「関心の輪」と「影響の輪」
課題の仕分け方がわかったら、次は、自分の貴重なエネルギーをどこに集中させるべきか、というお話です。
世界的な名著『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー博士)の中に、
「関心の輪」と「影響の輪」
という、とても分かりやすい考え方があります。
私たちの関心事すべてを、大きな円(関心の輪)だと想像してみてください。
この中には、景気や政治、他人の評価など、気になるけれど、あなたの力では変えられないことがたくさん含まれています。
そして、その大きな円の中心に、もう一つ小さな円(影響の輪)があります。
ここにあるのは、今日の自分の行動や、人に対する言葉遣い、新しい知識を学ぶことなど、あなたの力で直接変えられることです。
コヴィー博士は、私たちのエネルギーには不思議な法則があると言います。
もし、あなたが変えられない「関心の輪」のことばかりに気を取られていると、無力感が募り、「影響の輪」はどんどん縮んでいってしまうのです。
逆に、自分が変えられる「影響の輪」の中のことに集中していると、自信や達成感が生まれ、結果的に「影響の輪」そのものが、じわじわと大きく広がっていく。
私は、この「影響の輪」が、自分だけに与えられた「小さな庭」みたいに思っています。
その庭に生える雑草(=変えられないことへの不満)を抜くのに時間を使うか、美しい花(=できること)を愛情込めて育てるのに時間を使うか。
それを決められるのは、庭師である、あなただけなのです。
【この章のポイント】
悩みすぎるのは、あなたのせいではなく、脳と心の自然な働き。
他人の課題は相手に任せ、自分にコントロールできることだけに集中しよう。
あなたのエネルギーは、人生を変える力がある「影響の輪」にだけ注ごう。
第2章【最重要ワーク】人生が変わる「思考の羅針盤」を3ステップで手に入れる

さて、ここからはお待ちかねの実践パートです。
この章では、第1章の学びをあなたの人生に落とし込むための、具体的で、誰にでもできるワークをご紹介します。
それは、あなたのこれからの人生の道筋を照らし、もう迷わないための「思考の道しるべ」を手に入れるための、とても大切なステップです。
ステップ①:頭の中の“モヤモヤ”を全部書き出す「心の断捨離」
まず最初に、あなたの頭の中という、一番大切なお部屋をスッキリと片付けていきましょう。
用意するものは、入りのペンと、少し大きめの紙かノート。
それだけです。
「書き出す」という行為は、頭の中で無限にグルグルと回り続ける思考を、「文字」として外の世界に出してあげることで、初めて、それを客観的に眺めることができるようになります。
自分と問題との間に、安全な距離を作るための方法だと思ってください。
やり方は、とてもシンプルですよ。
-
タイマーを10分間にセットします。
-
時間が始まったら、頭に浮かんでくる悩み、イライラ、不安、気になることを、一切ジャッジせずに、すべて紙に書き出していきます。
-
「こんなこと書いても意味ないかも」なんて考えなくて大丈夫。途中で「書くことがないな」と感じたら、「書くことがない」とそのまま書いてみてください。
さあ、どうぞ。
…お疲れ様でした。
紙の上がどんなに散らかって見えても、まったく問題ありません。
それは、あなたの頭の中が、その分だけスッキリと片付いた、素晴らしい証拠なのですから。
ステップ②「変えられること/変えられないこと」に仕分ける【分類シート付】
心の断捨離、お疲れ様でした。
次は、出しっぱなしにした思考の荷物を、2つの箱に丁寧に仕分けていきましょう。
新しいページに、大きな枠(箱)を2つ描き、それぞれに名前をつけます。
【① 自分でコントロールできないこと】の箱
【② 自分でコントロールできること】の箱
準備ができたら、先ほど書き出した項目を、一つひとつ、どちらの箱に入るか振り分けていきます。
この作業は、あなたの貴重なエネルギーを、どこに投資すればリターンが最も大きいかを見極めるための、「戦略マップ作り」のようなものです。
【思考の分類シート(テンプレート)】
ご自身のノートに書き写して使ってみてください。
| ① 自分でコントロールできないこと | ② 自分でコントロールできること |
| 例:上司の評価 | 例:提出する資料の質を高める努力 |
| 例:過去の失敗 | 例:その失敗から教訓を学ぶこと |
| 例:他人の気分や発言 | 例:自分の受け止め方、反応の仕方 |
| … | … |
| … | … |
この仕分けこそが、第1章でお話しした理論を、あなたの人生で実践する、まさにその瞬間なのです。
【本記事の神髄】「変えられないこと」を「希望のタネ」に変える変換思考トレーニング
さて、ここからがこの記事の神髄です。
多くの自己啓発では「できないことは手放せ」と説きます。
しかし、ここではもう一歩踏み込みます。
手放して終わりではなく、
それを建設的な行動の“出発点”に変える。
これこそが、他とは違う、この技術の核心です。
「コントロールできないこと」の箱にある項目を一つひとつ眺めながら、自分にこう問いかけてみてください。
「では、この状況に対して、今の私にできることは、何だろう?」
これが、「変換思考」です。
コントロールできない現実を嘆くのではなく、それを“所与の条件”として受け入れた上で、「じゃあ、どうするか?」と、自分のコントロールできる行動へと、意識を転換させる技術です。
少し、一緒にトレーニングしてみましょうか。
-
テーマ「仕事」
-
(悩み) 上司が感情的で、正当に評価してくれない。
-
(変換思考) → では、私にできることは? → 次の面談で、感情論ではなく客観的な事実(成果や貢献)を伝えられるよう、今のうちから具体的なデータを資料にまとめておこう。
-
-
テーマ「将来」
-
(悩み) 将来のお金やキャリアのことを考えると、漠然と不安になる。
-
(変換思考) → では、私にできることは? → まずは情報収集から。今の自分の市場価値を調べてみよう。あるいは、今日から1日30分だけ、興味のある分野の勉強を始めてみようか。
-
-
テーマ「過去」
-
(悩み) あの時、あんな失言をしてしまった…。思い出すたびに辛い。
-
(変換思考) → では、私にできることは? → 過去の出来事は変えられない。でも、その経験から「相手に言葉を伝える時は、一度立ち止まって考える」という教訓を得ることはできる。この学びを、これからの人間関係に活かしていこう。
-
どうでしょう。
「コントロールできないこと」という、どうしようもないと思っていた悩みが、具体的な「今日からできる行動」に変わっていく感覚、つかめてきたでしょうか。
この「変換された行動」こそが、暗闇を照らす確かな光であり、あなたの人生の主導権を取り戻すための、何よりも力強い「希望のタネ」なのです。
【この章のポイント】
頭の中のモヤモヤは、一度すべて紙に書き出して「見える化」しよう。
書き出した悩みを「できること/できないこと」に仕分け、エネルギーの投資先を明確に。
「できないこと」を嘆くのではなく、「では、自分にできることは?」と問いかけ、行動に変換しよう。
第3章【人間関係編】もう、他人の言動に振り回されない「心のバリア」の作り方

さて、この章では、私たちが抱える悩みの、おそらく大部分を占めるであろう「人間関係」というテーマに、焦点を当てていきたいと思います。
どんなに自分の心を整えても、他人の予期せぬ言動ひとつで、心は簡単に波立ってしまう。
そんな経験、誰にだってありますよね。
ここでは、そんな人間関係の荒波から自分の心を守り、もっと穏やかで、自由な関係を築くための、具体的な技術を一緒に見ていきましょう。
「あの人のせいで…」は錯覚。アドラー心理学「課題の分離」を実践する技術
「あんなこと言わなくてもいいじゃん」
「そんな言い方しなくても…」
私たちの心は、つい、そうやって“誰かのせい”にしてしまいがちです。
ですが、実はこの「あの人のせいで…」という考え方こそが、私たちを人間関係の悩みから抜け出せなくしている、大きな“錯覚”なのです。
なぜなら、その考え方は、自分の感情のスイッチを、相手の手に渡してしまっているのと同じだからです。
ここで、もう一度思い出してほしいのが、第1章で登場したアドラー心理学の「課題の分離」です。
-
相手がどんな感情で、どんな言葉を選ぶかは、相手の課題。
-
その言葉をどう受け止め、どう反応するかは、自分の課題。
この境界線を、自分の心の中に、そっと引いてみる。それが、他人の言動に振り回されないための、最初のステップです。
具体的には、2つの言葉のスキルが、あなたを守る「心のバリア」になってくれます。
① 心で唱える、お守りの言葉
相手の理不尽な言動に心がザワッとしたら、すぐに反応するのではなく、心の中で一度だけ、こう唱えてみてください。
「それは相手の課題。そして、私がどうするかは、私の課題」と。
これだけで、相手の感情の嵐に巻き込まれるのを、不思議と防ぐことができるはずです。
② 相手に伝える、魔法の言葉(Iメッセージ)
もし、何かを伝える必要がある時は、相手を主語(YOU)にして責めるのではなく、私を主語(I)にして、自分の状況や気持ちを伝えてみましょう。
これは「アサーティブ・コミュニケーション」という、確立された手法です。
-
(YOUメッセージ) 「なんで、いつも手伝ってくれないの!」
-
(Iメッセージ) 「私は、今ちょっと手が一杯だから、少し手伝ってもらえると、すごく助かるな」
いかがでしょう。「課題の分離」とは、相手を見捨てる冷たい行為ではありません。
それは、相手の領域を尊重するという敬意の表れであり、自分も相手も大切にするための、とても成熟したコミュニケーション技術なのですね。
「わかってほしい」を手放す勇気。“期待しない”が最高の人間関係を築く
「言わなくても、これくらいわかってほしい」
近しい関係であればあるほど、私たちは、相手にそう“期待”してしまいます。
そして、その期待が裏切られた時、他の誰よりも深く傷つき、失望してしまう。
この「わかってほしい」という気持ちの正体は、
実は
「相手に“自分と同じであれ”と求める、無意識のコントロール欲求」
なのかもしれません。
ここで、少し視点を変えてみましょう。
「期待」と、よく似た言葉に「信頼」があります。
この二つは、まったくの別物です。
-
期待とは…
相手に「こうあってほしい」という条件をつけ、見返りを求めること。 -
信頼とは…
相手がどうであれ、その人の存在を無条件に信じること。見返りは求めません。
期待を手放すことは、諦めや無関心とは違います。
それは、
相手を自分とは違う、一人の独立した人間として100%尊重するという、最高の「信頼」の証。
少し勇気がいるかもしれませんが、その先にこそ、本当の意味で穏やかで、自由な関係が待っているのです。
SNSの“キラキラ”に疲れたあなたへ。他人と比べない心の守り方
さて、現代の私たちを悩ませる、もう一つの人間関係。
それが、SNSの世界です。
まず、大前提として知っておいてください。
あなたがSNSで見ているのは、他人の人生の「最高の瞬間だけを切り取った“予告編”」です。
私たちは、その華やかな予告編と、舞台裏の苦労や退屈な時間もすべて含んだ、自分の人生の“本編”とを、無意識に比べてしまっているのです。
これほど、不公平な比較はありませんよね。
この不毛な比較ゲームから抜け出し、自分の心を守るために、今日からできる3つの具体的な方法があります。
-
情報を「選んで」見る
SNSを、ただ目的もなく眺めるのはやめてみませんか。「今日は、〇〇さんの投稿だけを見よう」とか「10分だけ」と、意識的なフィルターをかける。そして、見た後に「今の自分の心は、どんな気持ち?」と確認する癖をつけるのです。 -
時間と距離を「物理的に」とる
「朝起きてすぐ」と「夜寝る前」は、心を穏やかに保ちたい大切な時間。この時間だけはSNSを見ないと決め、自分だけの「デジタル・サンクチュアリ(聖域)」を作ってみましょう。 -
「ミュート」や「フォロー解除」を恐れない
見ていて心がザワザワしたり、落ち込んだりするアカウントがあるなら、それはあなたの心が「この情報は、今の私には合わないよ」と教えてくれているサインです。ミュートやフォロー解除は、相手への攻撃ではありません。それは、自分の心の健康を守るための、立派な「セルフケア」なのです。
SNSは、他人と自分を比べて落ち込むためのツールではありません。
本来は、あなたの「影響の輪」(=興味や知識、素敵な人との繋がり)や自分の価値観を広げてくれる、とても便利な“道具”のはず。
どうか、振り回されるのではなく、あなたが主体的に、この道具を使いこなしてあげてくださいね。
【この章のポイント】
人間関係の悩みは「課題の分離」で、自分と他人との間に健全な境界線を引こう。
相手への「期待」を手放す勇気が、最高の「信頼」関係を築く第一歩。
SNSは「予告編」。自分の人生という「本編」と比べて、落ち込む必要はまったくない。
【実践テクニック】日常で使える!心を穏やかに保つ「3つの即効スキル」

この章では、日常のふとした瞬間に使える「即効性のあるスキル」を3つ、あなたにお渡ししたいと思います。
これは、コントロールできない思考や感情の渦に巻き込まれそうになった、まさにその瞬間に、あなたを救い出してくれる「心の応急処置セット」のようなものです。
スキル①【気づく力】思考の暴走を止める「メタ認知」という名のブレーキ
「また、あの時の失敗を思い出してグルグル考えてる…」
この暴走を止めるための、最も根本的で、最も強力なスキルが「メタ認知」です。
これは、脳の前頭前野という、人間を人間たらしめている高度な思考を司る部分の働きによるものです。
やることはとてもシンプル。
少し離れた場所から「もう一人の自分」が、今の自分の思考や感情を、冷静に観察してあげること、
ただそれだけです。
具体的には、思考の渦にハマっていることに気づいたら、心の中で、こんなふうに“実況中継”をしてみてください。
-
「おっと、今、自分は【昨日の会議での発言】について、繰り返し考えているな」
-
「なるほど、今、私の心は【将来への不安】を感じて、ザワザワしているんだな」
ポイントは、良い悪いのジャッジをせず、ただ淡々と、他人事のように実況すること。
この「気づく力」は、あらゆる感情の暴走に対する、最も信頼できる「心のブレーキ」だと、私は思っています。
スキル②【戻す力】不安が消える、身体を使った「五感スイッチ」5選
思考の暴走にブレーキをかけ、「気づく」ことができた。でも、時には、それでも心のザワザワが、なかなか消えてくれないこともありますよね。
そんな時は、無理に心で心をコントロールしようとするのではなく、「身体」の力を借りてみましょう。
「心が迷子になったら、身体に帰ってくればいい」
と、シンプルに覚えておくだけで十分ですよ。
-
【触覚スイッチ】 冷たい水でゆっくりと手を洗う。
-
【聴覚スイッチ】 イヤホンで大好きな曲を1曲だけ、音に集中して聴く。
-
【嗅覚スイッチ】 温かいコーヒーやお茶の香りを、ゆっくりと、深く吸い込む。
-
【視覚スイッチ】 今いる部屋の中で、「青色のもの」を5つ、意識して探してみる。
-
【味覚スイッチ】 一粒のチョコレートを、口の中でゆっくりと溶かしていく感覚を味わう。
スキル③【仕掛ける力】意志力に頼らない習慣術「if-thenプランニング」
最後にお伝えするのは、そもそも問題が起きにくいように、あらかじめ仕掛けておくという、とても賢い予防策です。
心理学者のピーター・ゴルヴィッツァー氏によって提唱された「if-thenプランニング」という技術で、その驚異的な効果から、教育やリハビリなど様々な分野で応用されています。
やり方は、驚くほど簡単。
「もし(if)、〇〇が起きたら、そのとき(then)、△△する」
というルールを、事前に自分の中で決めておくだけです。
-
もし(if)、 夜、ベッドの中で仕事の不安が頭をよぎり始めたら、
そのとき(then)、 ゆっくりと3回深呼吸をして、枕元に置いておいた好きな本を1ページだけ読む。 -
もし(if)、 SNSを見て、他人と自分を比べて落ち込みそうになったら、
そのとき(then)、 静かにスマホを閉じて、立ち上がってキッチンの窓から空を眺める。
このルールをいくつか作っておくことで、あなたの脳は、悩む前に、体が勝手に行動してくれる「自動操縦モード」に入ることができます。
【この章のポイント】
思考の暴走は「メタ認知」で気づき、ブレーキをかけよう。
心がザワザワしたら「五感スイッチ」で、意識を“今、ここ”の身体に戻そう。
「if-thenプランニング」で良い行動を仕組み化し、意志力に頼るのをやめよう。
第5章【挫折しそうなあなたへ】この技術が、うまくいかない時の“お守り”
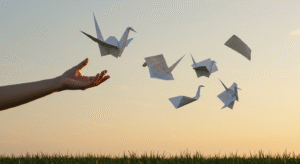
この章は、あなたがこの先で挫折しそうになったら、いつでも開いてほしい「転ばぬ先の杖」です。
「また考えちゃった…」そんな自分を責めないで。それが普通だから大丈夫
新しい技術を実践しようとした後で、元の思考パターンに戻ってしまった時、私たちは強烈な自己嫌悪に襲われがちです。
でも、それは「人間として、ごくごく自然な現象」なのです。
だから、ここで最も大切な視点をお伝えしますね。
「また、考えてしまった…」と落ち込む代わりに、
「あ、今、元の道に戻りかけてるな、と“気づけた”!」
と、考えてみてほしいのです。
この「気づけた」ということ自体が、この記事を読む前のあなたからの、とてつもなく大きな、素晴らしい進歩なのですから。
「よし、気づけた!私、えらい!」
と、心の中でガッツポーズをする。
その小さな自己承認こそが、あなたの心を育て、次の一歩を踏み出すための、温かいエネルギーになるのです。
三日坊主になったら読む“処方箋”。セルフ・コンパッションのすすめ
「ワークもスキルも、結局、三日坊主で終わってしまった…」
そんな時にこそ、あなたに知っておいてほしい、究極の心の処方箋があります。
それが、心理学者クリスティン・ネフ博士が提唱する「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」という考え方です。
もし、あなたが三日坊主になって落ち込んでしまったら、この3つのステップを、そっと試してみてください。
-
自分に、親友のように接してみる
もし、あなたの大切な親友が同じように落ち込んでいたら、どんな言葉をかけますか?その優しい言葉を、今、そのまま自分自身にかけてあげてください。 -
「みんな、そんなものだよ」と知る
完璧な人間なんて、この世のどこにもいません。「人間なんて、みんなそんなものだよな」と、自分の不完全さを、人類共通の愛すべき欠点として、受け入れてみる。 -
自分の感情を、ただ認めてあげる
落ち込んでいる自分、がっかりしている自分を、無理に励ましたり、否定したりしなくていいのです。ただ、「ああ、今、私は落ち込んでいるな」と、その感情の存在を、ただ静かに認めてあげてください。
失敗した時にこそ、「大丈夫だよ」と、あなたを内側から支えてくれる、揺るぎない心の土台。
それがセルフ・コンパッションです。
どうしても心が晴れない時に試してほしい、たった1つのこと
これまでの全てを試してみた。でも、どうしても心が重く、分厚い雲が晴れない…。
そんな、本当につらい時のために、最後のセーフティネットをお渡しします。
あなたに試してほしい「たった一つのこと」。
それは、
「何もしない」という選択を、あなた自身が、あなたに意識的に“許可”してあげることです。
これは、怠けや敗北ではありません。
前に進むために、あえて立ち止まる「意図的な休息」です。
-
一日中、パジャマのままで過ごすことを、自分に許可する。(許してあげる)
-
栄養のあるものを考える気力もなければ、出前を取ることを、自分に許可する。(許してあげる)
-
誰とも連絡を取らず、好きな映画だけを見て過ごすことを、自分に許可する。(許してあげる)
そうやって、自分を守り、回復させるための、神聖で、誰にも邪魔されない時間(サンクチュアリ)を、あなた自身にプレゼントしてあげてください。
もちろん、もし、このどうしようもなくつらい状態が長く続くようでしたら、専門家(カウンセラーや心療内科など)に相談することも、自分を大切にするための選択肢の一つだということも、どうか心の片隅に置いておいてくださいね。
【この章のポイント】
元の思考に戻っても「気づけた自分」を褒めてあげよう。それが大きな一歩。
三日坊主で落ち込んだら「セルフ・コンパッション」で、親友のように自分を思いやろう。
本当につらい時は「何もしない」を自分に許可する勇気を持とう。
【最後に】あなたの人生の主導権を取り戻すために

あなたはもう、ただどうしようもなく悩んでいた頃の自分ではありません。
自分の心を守り、人生の舵を取るための、たくさんの知恵と技術を、その両手にしっかりと持っているのです。
【振り返り】この記事で得た「一生モノの心のコンパス」
いつでも振り返れるように、紹介してきたものをここに記しておきますね。
-
【第1章】悩みの正体を知り、自分を責めるのをやめる
-
考えすぎてしまうのは、あなたのせいではなく、人間の脳と心が持つ自然な癖が原因でした。他人の課題はそっと手放し、自分の力で変えられる「影響の輪」にだけ、エネルギーを注ぐことの大切さを学びましたね。
-
-
【第2章】思考を整理し、「できること」を見つけ出す
-
頭の中のモヤモヤをすべて書き出し、「できること/できないこと」に分類しました。そして、「できないこと」の中から「では、自分にできることは?」と問いかけ、具体的な行動へと変換する、この記事の心臓部とも言える技術を習得しました。
-
-
【第3章】人間関係のストレスから、自分の心を守る
-
「課題の分離」で自分と他人との間に健全な境界線を引き、「期待」を手放す勇気が、より良い関係を築くことを知りました。SNSとの健全な付き合い方も学びましたね。
-
-
【第4章】日常で使える、即効性のある3つのスキル
-
思考の暴走に「気づき」、身体の五感を使って「今、ここ」に意識を「戻し」、良い行動を「仕掛けておく」。この3つのスキルが、あなたの日常を穏やかにしてくれます。
-
-
【第5章】挫折しても大丈夫、という最大のお守り
-
うまくいかなくても、決して自分を責めないこと。何度でも立ち上がれる「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」という、何よりも大切な心の土台を手に入れました。
-
今日からできる、あなたの世界を変える最も確実な「最初の一歩」
これらすべての根底には、たった一つの、とてもシンプルで、力強い真実が流れています。
それは、
「嵐(=コントロールできない出来事)を、この世界からなくすことはできない。しかし、その嵐の中で、自分の船の舵をどう切るかは、100%、あなたが決められる」
ということです。
あなたの人生という船の船長は、あなた以外に、誰もいません。
もちろん、お伝えしたこと全てを、明日から完璧に実践する必要は、まったくありませんよ。
さあ、最後に。
あなたの世界を変える、最も確実で、最も力強い「最初の一歩」を、お伝えしますね。
あなたの「コントロールできること」を、どんなに些細なことでもいいので、たった一つだけ、見つけてみてください。
それは、
「今夜飲むお茶を、いつもより少しだけ丁寧に淹れて、その香りと温かさをじっくりと味わう」
ことかもしれません。
または、
「一番近しい人に、照れくさいけれど『いつもありがとう』と、一言だけ伝えてみる」
ことかもしれません。
あるいは、
「今日は疲れたから、5分だけ早くベッドに入る」
ことかもしれません。
その、あなたが見つけた小さな、しかし、あなた自身が選んだ確かな「できること」こそが、あなたの人生の主導権を、その手に力強く取り戻すための、何よりも尊い一歩なのです。
あなたのこれからの航海が、穏やかで、あなたらしい喜びに満ちたものでありますよう、心から願っています。
【こちらの記事も読まれています】