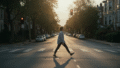「何が正しいのかわからない…」その迷いは、あなたが“本質”に近づいているサイン
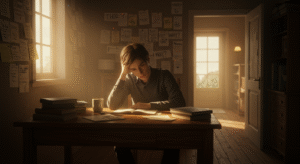
「何が正しいのか、もう分からない…」
「真理とは、いったい何なのだろう?」
そんな、答えのない問い。
この記事では、難しい哲学ではなく、歴史上の偉人たちの知恵を借りて
「自分だけの納得できる答え」
を見つける、具体的な方法だけをご紹介します。
もう、毎日のあふれる情報や他人の意見に振り回されることはありません。
読み終える頃には、自分を信じる穏やかな自信が、きっと心に生まれているはずです。
さあ、あなたの気持ちを楽にする、思考の整理を始めましょう。
知識を詰め込むのではなく、自分だけの「指針」を見つけるヒント
なんて言うと、少し難しい話に聞こえるでしょうか。
大丈夫です。
この記事は、哲学の小難しい言葉を並べたり、「これが絶対の真理です!」と一つの答えを押し付けたりするものではありませんので、どうか安心してください。
そうではなくて。
歴史上の賢い人たちが残してくれた“考え方のヒント”を少しだけお借りしながら、情報に振り回されることなく、あなた自身が
「うん、これなら納得できるな」
と思えるような、自分だけの“指針”を見つけるためのお手伝いをすること。
それが、この記事の目的です。
読み終える頃にはきっと、
「ああ、完璧な答えなんて、無理に探さなくても良かったんだ」
と、気持ちが少し楽になっているはず。
そして、明日から見える世界が、ほんの少しだけ、違って見えるようになるかもしれません。
※この記事では、主に西洋哲学の視点から「真理」について考えていきます。東洋思想や宗教など、世界には他にも多様で素晴らしい考え方があることも、心の片隅に留めておいていただけると嬉しいです。
【準備運動】なぜ私たちは「絶対の真理」という“たった一つの答え”を求めてしまうのか?
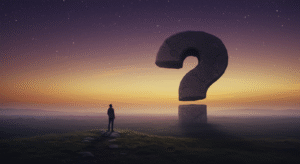
その前に、少しだけ準備運動をしましょうか。
そもそも、どうして私たちはこんなにも「たった一つの答え」が欲しくなってしまうのでしょう。
その心の仕組みを少しだけ知っておくと、この先の探求が、ぐっと楽になりますよ。
「早く楽になりたい」は人間の本能?“答え”に飛びつく脳の仕組み
白黒ハッキリさせたい。
ややこしいことは考えずに、スパッと答えが欲しい。
そんな風に感じてしまうこと、ありますよね。
実はそれ、あなたが特別せっかちなわけではなくて、私たちの脳が生まれつき持っている、ある賢い機能のせいなんです。
私たちの脳って、毎日ものすごい数のことを判断していて、実はとっても働き者なんです。
そのため、「ここは頑張りどころ!」という時以外は、できるだけエネルギーを使わないようにする「省エネ機能」のようなものが備わっています。
たとえば、こんな経験はありませんか?
-
ランチを選ぶ時、たくさんのメニューを読むより、本日のオススメの中から直感で選んでしまう。
-
専門家がテレビで「これが最新の健康法です!」と言うと、なんだか深く考えずに「そうなんだ」と納得してしまう。
これはまさに、脳が思考のエネルギーを節約するために、無意識に「こっちの方が早くて楽そうだ」という近道を選んでいる状態なんです。
だから、「絶対の真理」や「たった一つの答え」といった、分かりやすくて、それ以上考えなくてもよさそうなものに心が惹かれてしまうのは、ある意味、とても自然なこと。
まずは「そっか、自分の脳には、そういうクセがあるんだな」と。
そう知っておくだけで、気持ちが少し楽になりませんか?
【要注意】信じたいものだけ見てしまう「確証バイアス」という思考の罠
でも、この脳の便利な「省エネ機能」には、一つだけ、注意が必要な落とし穴があるんです。
それが、「確証バイアス」と呼ばれるクセです。
これは、自分が「こうだ」と信じていることや、「こうであって欲しい」と願うことを肯定してくれる情報ばかりを、無意識に探して集めてしまう働きのことを言います。
このような思考のクセは、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンの研究などでも知られており、誰にでも備わっている普遍的な心の働きです。
そして、その考えに反する都合の悪い情報は、なぜか目に入らなかったり、見ても「これは例外だ」と無視してしまったりする…。
誰の心にも潜んでいる、ちょっと厄介な思考の罠です。
思い当たることはないでしょうか。
-
一度「あの人は苦手だな」と感じてしまうと、その人の欠点ばかりが目について、良いところが見えなくなってしまう。
-
「このダイエット法は絶対に効く!」と信じると、その成功体験ばかりを読み漁り、「効果がない」という声には耳を塞いでしまう。
この状態が続いてしまうと、私たちはまるで「自分だけの正しさ」でできた、心地いいけど小さな部屋に閉じこもってしまうようなもの。
新しい視点や、物事のより深い本質に触れるチャンスを、自ら手放してしまうことになります。
それは、なんだかとても、もったいないですよね。
では、私たちはどうすれば、この厄介な心のクセと上手く付き合いながら、もっと広く、深く世界を見ることができるのでしょうか。
そのヒントを、次からの章で、歴史上の偉人たちの知恵に一緒に学んでいきましょう。
【この章のポイント】
「分かりやすい答え」を求めてしまうのは、脳の省エネ機能による自然な働き。自分を責める必要はない。
ただし、自分の信じたい情報ばかりを集めてしまう「確証バイagis」という罠には注意が必要。
あなたへの問いかけ あなたが最近、「これは絶対に正しい!」と信じて疑わなかったことは何ですか?
【実践哲学】日常の悩みが軽くなる。偉人たちの“思考ツール”5選
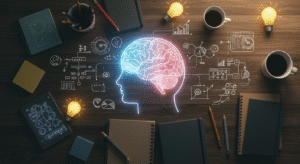
ここからは、いよいよ歴史上の偉人たちが残してくれた、とっておきの“思考ツール”を一緒に見ていきましょう。
今回ご紹介する5人は、古代ギリシャから近代に至る西洋哲学の歴史の中で、「真理」に対する考え方を大きく転換させた、いわばターニングポイントとなった人物たちです。
彼らの思想の変遷を辿ることで、私たちが今、どのような考え方の土台の上に立っているのかが見えてきます。
哲学、と聞くと少し身構えてしまうかもしれませんが、大丈夫です。
難しい学問としてではなく、あなたの日常の悩みを少しだけ軽くしてくれる、便利な「ポケットツール」のようなものだと思って、気軽に読み進めてみてくださいね。
①SNSの“正義”に疲れたら…【ソクラテス】の「無知の知」という最強の盾
SNSを開けば、誰かの“正義”と誰かの“正義”がぶつかり合っている。
それを見ているだけで、なんだか心がザワザワして疲れてしまうこと、ありますよね。
そんな時に私たちを守ってくれるのが、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの
「無知の知」という考え方です。
これは、「自分は何も知らない、ということを知っている」という彼の姿勢を表す言葉。
知らないことを認めるのは、恥ずかしいことではなく、むしろ物事の本質に近づくための、とても大切な第一歩だと彼は考えたのです。
この考え方は、情報が洪水のように押し寄せる現代で、私たちの心を守る「最強の盾」になってくれます。
ネットで何かを見かけて、反射的に
「許せない!」
「その通りだ!」
と感じる前に、心の中でそっと、こう呟いてみるんです。
「待てよ。私はこの件の背景を、本当にすべて知っているだろうか?」
たったこれだけ。
これだけで、感情の大きな波にすぐに飲み込まれてしまうのを、防ぐことができるのです。
知らないことを認め、分かった気にならない謙虚さ。
それが、不要な情報や他人の感情から、あなたの心を穏やかに守ってくれるはずですよ。
②理想と現実のギャップに苦しい…【プラトン】の「イデア」との上手な付き合い方
「もっとキラキラした自分になりたかったのに」
「理想のキャリアを歩むはずだったのに…」
思い描いていた理想と、目の前にある現実。
そのギャップに落ち込んでしまうのは、あなたが真面目で、向上心がある証拠です。
そんなあなたの気持ちを、そっと軽くしてくれるのが、プラトンの「イデア」という考え方です。
※イデア:プラトン哲学の中心概念。
私たちが目にする世界の背後にある「完璧な本物の形」です。
現実のものは、その完璧な形をまねた不完全なコピーだとプラトンは考えました。
この「イデア」を、私たちが絶対に到達できない完璧なゴールだと考えると、すごく苦しくなってしまいます。
そうではなくて、暗い夜道で、進むべき方角を教えてくれる「北極星」のようなものだと考えてみるのはどうでしょうか。
北極星にたどり着くことはできなくても、それがあるおかげで、私たちは道を見失わずに済みますよね。
それと同じで、
「理想の私(イデア)なら、こんな時どうするかな?」
と、行動のヒントをもらうための道しるべとして使うのです。
完璧じゃなくても大丈夫。
そちらの方角を向いて、昨日より半歩でも進めている自分を、認めてあげればいいんです。
③職場の意見対立で板挟みに…【アリストテレス】の「中庸」という着地点の見つけ方
「コストを最優先すべき!」という営業出身のA部長。
「品質こそが命だ!」という開発出身のB課長。
どちらの言い分も分かるからこそ、板挟みになってしまってつらい…。
そんな経験、身に覚えがありませんか。
こんな時、アリストテレスの「中庸(ちゅうよう)」という知恵が、きっとあなたの助けになります。
これは、単に両極端の意見の「真ん中を取る」という消極的な妥協案ではありません。
無謀すぎず、臆病すぎない「勇気」のように、両極端の欠点を避け、それぞれの良いところを活かした、
その状況における「最も優れた状態」
を、積極的に見つけ出す技術なんです。
つまり、「A案かB案か」で考えるのを、一度やめてみる。
そして、
「限られたコストの中で、お客様が最も喜んでくれる品質を実現する工夫は何か?」
と、問いそのものを変えてみるのです。
この視点を持つことで、あなたは単なる調整役ではなく、チームをより良い結論へと導く、価値ある存在になれるはずです。
④周りの意見に流され自分が無い…【デカルト】が教える「最強の自分軸」の作り方
親はこう言うし、友達のアドバイスも気になる。ネットで調べれば調べるほど、何が正解か分からなくなって動けない…。
そんな風に、自分軸がグラグラしてしまう感覚は、本当につらいものです。
そのグラグラした心を、どっしりと大地に根付かせてくれるのが、デカルトの有名な言葉、
「我思う、故に我あり」
に隠されたヒントです。
彼は、世の中のあらゆることを「本当にそれは正しいのか?」と徹底的に疑っていきました。そして最後に、どうしても疑いようのない一つの真実にたどり着きます。
それは、
「どんなに疑っても、今こうして疑っている“この自分の存在”だけは、確かに在る」
ということでした。
この考え方は、情報社会で迷子になりがちな私たちにとって、「最強の自分軸」になります。
周りの意見や常識、SNSの情報。
それらを一旦、心の中で( )に入れて、脇に置いてみる。
そして、最後に残る、たった一つの問いと向き合うのです。
「それでも“私”は、どうしたいんだろう?」
その静かな心の声こそが、誰にも奪われない、あなたの決断の出発点なのです。
⑤人生のレールが見えず不安…【ニーチェ】に学ぶ「自分だけの価値」の創造法
良い大学、良い会社、そして結婚…。
そんな、世間で言われる“当たり前”の幸せに、どうしてもしっくりこない。
かといって、自分に特別な何かがあるわけでもない。
まるで、自分だけ人生の用意されたレールから外れてしまったような、漠然とした不安。
本当に、苦しいですよね。
その深い不安に、力強い光を投げかけてくれるのが、ニーチェという哲学者の考え方です。
彼の有名な「神は死んだ」という言葉は、「絶対的な正しさ」や「万人が信じるべき価値」の力が失われた時代を表しています。
そして彼は、それを嘆くのではなく、むしろ「チャンスだ」と考えました。
絶対の正解がないからこそ、私たちは、自分自身で「何が価値あることか」を創り出すことができる、自由な存在になったのだ、と。
ニーチェは、この新しい時代を生きる、自ら価値を創造する強い意志を持った人を
『超人』
と呼びました。
誰かが決めた「正しさ」を追いかけるのではなく、
「私にとっての喜びは何か」
「私が美しいと感じる生き方は何か」
を問い、自分だけの人生を創造していく。
もし、「何が正しいんだろう?」という問いで行き詰まってしまったら、一度、問いかけを変えてみてください。
「どちらが、私の心が震えるだろうか?」
その小さな心の震えこそが、あなただけの価値を創造していくための、何よりの道しるべになるはずです。
| 哲学者 | キーワード | どんな悩みに効く? | 思考のポイント |
| ソクラテス | 無知の知 | SNSの「正義」疲れ | 「本当に知ってる?」と問い、心を守る |
| プラトン | イデア | 理想と現実のギャップ | 「理想」をゴールではなく「方角」として使う |
| アリストテレス | 中庸 | 意見の板挟み | 「AかBか」ではなく「両方を活かすC」を探す |
| デカルト | 我思う、故に我あり | 周囲の意見への迷い | 他の声を( )に入れ「私はどうしたい?」と問う |
| ニーチェ | 価値創造 | 人生のレールへの不安 | 「正しさ」より「心の震え」を信じる |
【この章のポイント】
哲学は難しい学問ではなく、日常の悩みを軽くする「思考ツール」である。
歴史上の偉人たちの多様な視点を借りることで、一つの考え方に縛られず、物事を多角的に見ることができるようになる。
あなたへの問いかけ 今日の5人のうち、あなたが一番「使ってみたい」と感じた思考ツールはどれですか?
【深掘り分析】“真理の探求”があなたを苦しめる、3つの落とし穴

さて、ここまで偉人たちの素晴らしい思考ツールを見てきましたが、ここで少しだけ、正直な話をさせてください。
実は、「真理の探求」には、注意しないとハマってしまう、いくつかの“落とし穴”があるんです。
これは、探求を始めた人だからこそ、かえって陥りやすい、ちょっと厄介な罠、と言えるかもしれません。
でも、大丈夫ですよ。
これからお話しする罠の存在をあらかじめ知っておくだけで、それに気づき、賢く避けることができますから。
あなたの探求が、より安全で豊かなものになるための「転ばぬ先の杖」だと思って、少しだけ耳を傾けてみてくださいね。
罠①知れば知るほど動けない…「分析麻痺」という底なし沼
いろんな考え方を知れば知るほど、
「これも正しい気がするし、あっちの意見も一理ある…」
と、選択肢が多すぎて、結局どれも選べずに一歩も踏み出せない。
そんな、まるで底なし沼に足を取られたような感覚に、陥ったことはありませんか?
その状態は、「分析麻痺(アナリシス・パラリシス)」と呼ばれる罠かもしれません。
情報を集めすぎ、考えすぎることで、かえって決断や行動ができなくなってしまう、心の状態です。
その背景には、
「もっと完璧な答えがあるはずだ」
「絶対に失敗したくない」
という、思いが隠れていることが多いように感じます。
でも、せっかくの知識が、あなたを自由にする翼ではなく、身動きを封じる重い鎧になってしまうのは、本当に、もったいないですよね。
罠②自分だけが正しい?「独善」に陥り、大切な人を遠ざける危険性
少し物事の本質が見えてくると、ふと、
「どうして周りの人は、こんなことも分からないのだろう?」
と、心の中で人を見下してしまう…。
そんな、自分の心に潜む小さなトゲに気づくことはありませんか。
これは、認めるのが少しつらい感覚かもしれません。
それは「独善」という、とても悲しい罠の入り口。
自分だけの正しさに固執してしまい、他人の意見に耳を貸せなくなる状態ですね。
せっかくの探求が、あなたを孤独にしてしまうとしたら、それほど寂しいことはありません。
「答えを知っている自分は、他人よりも優れている」。
そんな無意識の優越感が、あなたの視野を狭くしてしまうのです。
かつてソクラテスが戒めた「知っていると思い込むこと」に、探求者であるあなた自身が陥ってしまう…。
これは、なんとも皮肉な罠だと言えるでしょう。
罠③「答えが分からない自分はダメだ」と責めてしまう自己否定のループ
「こんなに本を読み、時間をかけて考えているのに、一向に『これだ!』という答えが見つからない…」
「やっぱり自分には、物事を深く考える才能なんてないんだ」
そうやって、自分自身にがっかりしていませんか?
これは、探求の道のりで最もつらく、そして多くの人が陥ってしまう罠、「自己否定のループ」です。
「答えが見つからないこと」と「自分に価値がないこと」を、知らず知らずのうちに、イコールで結んでしまうのです。
でも、少しだけ考えてみてください。
歴史に名を残すあの偉大な哲学者たちでさえ、生涯をかけてこの問いと格闘し続けました。
すぐに答えが見つからないのは、決してあなたが劣っているからではありません。
その問いが、それほどまでに奥深く、尊いものだからなのです。
本当の価値は、「最終的な答え」にあるのではありません。
悩み、迷い、考え続けるその道のりそのものが、あなたの心を耕し、人間としての深みを与えてくれる、かけがえのないものなのですから。
【この章のポイント】
探求には「分析麻痺」「独善」「自己否定」という3つの罠があることを知っておく。
これらの罠に気づき、客観視できること自体が、健全な探求の証である。
あなたへの問いかけ あなたは今、この3つの罠のどれかに、少しだけ足を踏み入れていると感じますか?
【育成プログラム】知識を“血肉”に変える。自分だけの「納得解」の見つけ方・育て方
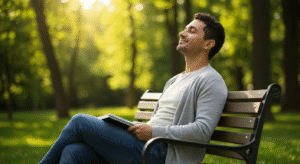
さて、偉人たちの知恵に触れ、時には探求の落とし穴も覗いてきました。
でも、どんなに素晴らしい知識も、あなたの毎日の中で使われなければ、ただの宝の持ち腐れになってしまいますよね。
「でも、何から始めたらいいの?」
「なんだか難しそう…」
そう感じるかもしれません。大丈夫ですよ。
ここからは、誰にでも、今日から、まるでゲームをクリアしていくような感覚で試せる、とても簡単な3つのステップをご紹介します。
大切なことなので先にお伝えしますが、完璧にやろうなんて、決して思わないでくださいね。
つまみ食いでも、三日坊主でも、まったく問題ありません。
あなた自身が「面白いな」「心地いいな」と感じるペースで、気軽に試してみてください。
STEP1 自分の価値観の“鉱脈”を掘り当てる「1日3行・感情ジャーナル」
自分なりの「解」を見つけるための、すべての土台となるのが「自分を知ること」です。
そのためにまず、あなた自身の「心の声」に、丁寧に耳を澄ませてみましょう。
名付けて、「1日3行・感情ジャーナル」。
やり方は、本当に簡単です。
夜寝る前に、スマホのメモ帳や手帳に、今日心が動いたことをたった3行、書き留めるだけ。
もしよければ、こんな「お題」で書いてみてください。
【感情ジャーナルのヒント】
心がポカポカしたこと(嬉しかった、感謝したことなど)
心がザワッとしたこと(腹が立った、悲しかった、違和感を覚えたことなど)
「へぇ!」と思ったこと(新しい発見、学びなど)
ポイントは、「なぜそう感じたのかな?」と、自分に軽く問いかけてみることです。
これを数日続けるだけで、あなたが何を喜び、何を嫌い、何に好奇心をそそられるのか。
つまり、あなただけの「価値観の鉱脈」のありかが、ぼんやりと見えてくるはずです。
STEP2 偉人の視点をレンタルする「1日1哲学者チャレンジ」
自分の心の動きが少し見えてきたら、次は、物事をいつもと違う角度から見る練習です。
偉人たちの「視点」「頭脳」を、少しだけレンタルしてみましょう。
これもゲーム感覚で。
「1日1哲学者チャレンジ」です。
「○○なら、どう考える?」を行います。
朝、コーヒーを飲みながら「よし、今日はデカルトの日!」と決めるだけ。
一日中意識する必要はありません。
たった一度でも、その哲学者の“メガネ”をかけて物事を見られたら、もう大成功です。
デカルトDAYなら SNSの情報を見て、反射的に信じる前に「本当に?」と心の中で呟いてみる。
アリストテレスDAYなら ランチで迷った時、AとBの『ちょうどいいとこ取り』のC定食を選んでみる。
ニーチェDAYなら 仕事帰りに、「やるべきこと」より「心がワクワクすること」を優先して、本屋に寄り道してみる。
この「なりきり」チャレンジは、あなたの凝り固まった思考パターンを優しくほぐしてくれる、最高の思考のストレッチ。
一つの問題に対して、たくさんの解決策の引き出しを持つことができるようになりますよ。
STEP3 「マイ格言(仮)」を作り、少しずつ更新していく楽しみ
最後のステップは、これまでの気づきを、あなただけの「納得解」のタネとして、大切に育てていく作業です。
ジャーナルやチャレンジを通して感じたことを元に、手帳の片隅に、こんな風に書き留めてみるのです。
「私にとって、今のところの幸せは、美味しいご飯を食べることだ!(仮)」
ここで何よりも大切なのは、格言の最後に必ず「(仮)」とつけること。
これは、
「この答えは、今日の私にとってのベスト。でも、経験を積んだ明日の私は、もっと素敵な答えを見つけるかもしれない」
という、未来の自分への信頼の証です。
答えに縛られるのではなく、答えを育てていく自由のサインなのです。
このノートは、誰に見せるでもない、あなただけの哲学の書。
数ヶ月後に見返して、赤線で消したり、「やっぱりこっちかも」と書き加えたり…。
そうやって、自分だけの言葉を紡ぎ、自分だけの地図を描いていく。
そのプロセスそのものが、答えが見つかること以上に、あなたの人生を、きっと豊かにしてくれるはずです。
【この章のポイント】
STEP1: 感情ジャーナルで「自分の心のクセ」を知る。
STEP2: 哲学者ごっこで「思考の柔軟性」を鍛える。
STEP3: 「マイ格言(仮)」で、自分だけの解を、焦らず育てていく。
あなたへの問いかけ この3つのステップのうち、あなたが「これならできそう」と一番感じたものはどれですか?
【まとめ】「真理」は見つけるものではなく、あなた自身が“なっていく”もの

探求の道のりこそが、誰にも描けないあなたの尊い答えになる
「真理とは、何か?」
そんな壮大な問い。
私たちは、歴史上の賢人たちが残してくれた、驚くほど多様な“答えの形”を知りました。
そして、一つの答えにすぐに飛びついてしまう脳のクセや、探求の道のりに潜む、意外な落とし穴があることにも気づきました。
さらには、自分だけの「納得解」をゆっくりと育てていくための、ささやかだけれど、とても大切な実践方法も手にしました。
ここまで、一つひとつ歩みを進めてきたあなたなら、もうお気づきかもしれません。
そうです。
「真理」とは、どこか遠くにある、完成された宝物を見つけることでは、なかったのです。
悩み、迷い、時に立ち止まりながらも、自分の心に問いかけ、より良く生きようと試行錯誤する。
その真摯な「プロセスそのもの」が、他の誰にも描くことのできない、あなただけの尊い“答え”となっていく。
あなたは真理を探しているようで、実は、あなた自身のその歩みこそが、「真理」を体現しているのです。
最後に。あなたの日常に、哲学の光を灯すための第一歩
もしよろしければ、この記事を閉じた後、今日ご紹介した5人の哲学者やアニメや漫画、小説のキャラクターのうち、ちょっとでも一番心に残った人の名前を、一つだけピックアップしてみてください。
そして、そのキャラクターの“思考ツール”を、ちょっとだけ模倣してみるのです。
悩んだ時、迷った時、そのお守りが、きっとあなたの思考を少しだけ自由にし、気持ちを少しだけ楽にしてくれるはずです。
それが、あなたの日常に哲学の光を灯す、ささやかでだけど、決定的な第一歩となります。
あなたのこれからの探求が、喜びと発見に満ちた、豊かで素晴らしいものでありますように。
心から、応援しています。
この記事では「真理」という大きなテーマから、自分なりの「指針」を見つけるヒントを探求してきました。
このブログでは、この他にも
「自分にとっての豊かさとは何か?」
「どうすれば、もっと幸せを感じられる日々を送れるのか?」
といった、あなたの人生がより味わい深くなるような様々な考え方をご紹介しています。
もしご興味があれば、他の記事も覗いてみてくださいね。
【こちらの記事も読まれています】

【参考文献】
この記事は、以下の信頼できる情報を基に、筆者の解釈を加えて分かりやすく解説したものです。より深く学びたい方は、ぜひ手に取ってみてください。
-
プラトン (著), 納富 信留 (翻訳) 『ソクラテスの弁明』 光文社古典新訳文庫, 2012年.
-
ルネ・デカルト (著), 谷川 多佳子 (翻訳) 『方法序説』 岩波文庫, 1997年.
-
フリードリヒ・ニーチェ (著), 中山 元 (翻訳) 『善悪の彼岸』 光文社古典新訳文庫, 2009年.
-
岡本 裕一朗 (著) 『哲学の基本がわかる事典』 PHP研究所, 2015年.
-
ダニエル・カーネマン (著), 村井 章子 (翻訳) 『ファスト&スロー(上・下)』 早川書房, 2012年.