【なぜ私は存在する?哲学の「存在論」7つの基本ポイント】
「なぜ?」を哲学の「知」へ。存在論の世界へようこそ

ふと、窓の外を眺めているとき。
温かいコーヒーを一口飲んだとき。
「なぜ私は、今ここにいるんだろう?」
そんな、答えのない問いが心をよぎったことはありませんか。
その問いは、決してあなた一人のものではありません。
それは、人類が何千年もの間、大切に受け継いできた、最も根源的で、最も人間らしい問いかけなのです。
この記事では、そんなあなたの心の奥にある「なぜ?」を手がかりに、哲学の世界で最も重要で、最も面白い分野の一つ、
「存在論(そんざいろん)」の世界を一緒に探検していきたいと思います。
存在論とは、一言でいえば「『存在する』って、一体どういうこと?」を考える学問です。
目の前にあるスマートフォン。
これは確かに「存在」していますよね。
では、SNSの中にいる、もう一人の自分はどうでしょう。
多くの人が信じている「正義」という考えは、スマートフォンと“同じように”存在していると言えるのでしょうか。
ほら、なんだか不思議な感じがしませんか。
この記事を読み進めるうちに、あなたが普段「当たり前」だと思っていた世界の輪郭が、少しずつ変わっていくはずです。
この記事のゴールは、単に知識をインプットすることではありません。
読み終える頃には、
あなたが哲学の最重要分野である「存在論」の歴史的な流れと、その核心的な問いを、ご自身の言葉で誰かに説明できるようになること。
それを目標にします。(難しかったらごめんなさい)
※この記事は、特定の学術論文を解説するのではなく、信頼できる複数の入門書や哲学史の概説書、そして主要な哲学者の主著(原典)に基づき、そのエッセンスを可能な限り平易な言葉で再構成したものです。
「哲学なんて初めて…」という方も、どうぞご安心ください。
専門用語は一つひとつ丁寧に解説し、難解な概念は、できるだけ身近な例に置き換えながら進めていきます。
さあ、準備はよろしいでしょうか。
一緒に、奥深く、刺激的な思索の世界を覗いてみましょう。
【第1部】これだけは押さえたい。「存在論」の基本地図

まず、言葉の基本から押さえましょう。
存在論は、古代ギリシア語の
「ontos(オントス)=存在する(もの)」と、
「logos(ロゴス)=理論・学問」を合わせた言葉です。
文字通り、「存在に関する理論」という意味なんですね。
その核心的な問いは、とてもシンプル。
「そもそも、『存在する』とはどういうことか?」
これに尽きます。
私はよく、存在論を「哲学のOS(オペレーティングシステム)」のようなもの、と説明することがあります。
パソコンやスマホにOSがなければ、他のどんな便利なアプリも動きませんよね。
それと同じで、哲学にも「存在論」というOSがなければ、他の様々な問い(アプリ)を考えることすら、おぼつかなくなってしまうのです。
「OS」と言われても、まだピンとこないかもしれませんね。
では、もし哲学に「存在論」がなかったら、他の分野がどう困ってしまうか、少し考えてみましょう。
-
認識論(知識について考える学問)の場合
「私たちはどうやって物事を知るのか?」と考える前に、もし「知られるべき対象」そのものが存在するのかどうか、はっきりしなかったらどうでしょう。議論の土台がグラグラで、何も考えられなくなってしまいますよね。 -
倫理学(善く生きることを考える学問)の場合
「『優しさ』は善いことだ」と考える時、もしその「優しさ」や「善」という価値が、客観的に存在するものではなく、ただの個人の思い込みだとしたら…。「善く生きる」ための指針そのものが、とても頼りないものになってしまいます。
このように、「何が存在し、どのように存在するのか?」という存在論の問いは、あらゆる哲学的な思索の「大前提」になる、避けては通れない重要な分野なのです。
ここで、哲学を学ぶ人が一度は混同してしまう言葉を整理しておきましょう。
それは「形而上学(けいじじょうがく)」です。
| 用語 | 説明 | 比喩 |
| 形而上学 |
感覚や経験を超えた、世界の根本原理を探る学問。 「神」「精神」「世界の根源」など、形のないものを扱う。 |
家全体 |
| 存在論 |
形而上学の一部であり、その中核。 「存在そのもの」に焦点を当てて探求する。 |
家の土台 |
形而下(けいじか)が「形あるもの」、つまり私たちが見たり触れたりできる物質的な世界を指すのに対し、形而上はその逆。
アリストテレスが『自然学(Physica)』の書物の「後(meta)」に置いたことから、メタピュシカ(Metaphysica)と呼ばれるようになった、世界の最も根源的な問いを扱う分野です。
とても大雑把に言うと、形而上学という大きな家があり、
その最も重要な土台部分が、存在論だと思ってください。
まずは、このイメージを持っておけば十分ですよ。
【この章のポイント】
存在論とは「『存在する』とはどういうことか?」を問う、哲学のOS(土台)である。
他の哲学分野(認識論、倫理学など)は、存在論を「前提」としなければ成り立たない。
形而上学という「家全体」の中核をなすのが、存在論という「土台」である。
【あなたへの問いかけ】
あなたの身の回りで、「存在しているかどうか、少し曖昧だな」と感じるものはありますか?
さて、そんな哲学の土台である存在論ですが、その問いかけは、大きく分けると2つの種類があります。
この2つを区別できると、この後の歴史の話がぐっと分かりやすくなります。
一つ目の問いは、とてもストレートです。
「この世界に、本当に『存在する』と言えるものは、一体何なのだろうか?」
という問いです。
まるで、“レゴブロック”で遊ぶ時に、「最も基本的なブロックは何だろう?」と探すような感覚に近いかもしれません。
-
目に見える原子や素粒子だけが、本当に存在するのか?
-
私たちの「心」や「意識」は、本当に存在するのか?
-
「数」や「正義」といった概念は?
-
「神」は存在するのか?
こうした問いに、古代から多くの哲学者が挑んできました。
世界の“究極の部品”を探す、壮大な探求ですね。
二つ目の問いは、少しだけ繊細です。
「同じ『存在する』と言っても、その“あり方”には違いがあるのではないか?」
という問いです。
私はこれを、存在の“スタイル”や“モード”の違い、と呼んでいます。
例えば、考えてみてください。
-
あなたの目の前にある「机」の存在の仕方と、
-
あなたが誰かに抱いている「愛」という感情の存在の仕方。
この二つは、同じ「存在する」という言葉で語られますが、そのスタイルは明らかに違いますよね。
他にも、
-
「1+1=2」という数式のように、必然的に存在する(そうとしか考えられない)もの。
-
目の前の机のように、偶然に存在する(ここになくてもよかったかもしれない)もの。
こうした存在の“あり方の違い”を分析し、整理していくのも、存在論の非常に重要な役割なのです。
この「存在のスタイル」という視点、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。
【この章のポイント】
存在論の問いは、大きく2種類に分けられる。
問い①(What) 世界に「何が」本当に存在するのかを探る。
問い②(How) 「存在のあり方(スタイル)」の違いを分析する。
【あなたへの問いかけ】
「机の存在」と「愛の存在」。あなたはこの二つの“存在のスタイル”の違いを、どんな言葉で説明しますか?
【第2部】歴史を旅する。「存在」を巡る2500年の思想史

私たちの周りの世界は、常に変化していますよね。
日は昇り、沈み、季節は移ろい、人も生まれては死んでいく。
多様で、絶えず動いている。
それが、私たちの実感です。
ところが、今から2500年以上も昔の古代ギリシアに、その「実感」こそが幻想だ、と喝破した哲学者がいました。
その人の名は、パルメニデス。
彼は、こう主張しました。
「あるものはあり、あらぬものはあらぬ(無いものは無い)」
一見すると、当たり前のことを言っているように聞こえます。
でも、この言葉が持つ意味は、とてつもなく根本的なものでした。
彼の論理はこうです。
「無い(無)」というものは、存在しないのだから、考えることも、語ることもできない。
そして、もし「変化」が起こるとすれば、それは「無かった」ものが「有る」ようになることだから、「無」が存在しない以上、変化なんて起こるはずがない。
…どうでしょう。
私たちの実感とは、まったく逆ですよね。
彼は、私たちの移ろいゆく感覚の世界を「思い込み(ドクサ)」と断じ、理性によってのみ捉えられる「ただ一つで、不動不変の“存在”」だけが真実なのだ、と主張したのです。
この思想は、哲学史に最初の、そして最大の「問い」を投げかけました。
「私たちは、自分の感覚と理性の、どちらを信じるべきなのか?」と。
この後、2500年以上続くことになる壮大な知的格闘の、まさに幕開けでした。
パルメニデスが投げかけた「変化するこの世界をどう説明するんだ?」という巨大な問い。
これに、二人の天才が、それぞれ全く違う形で壮大な「回答」を示しました。
哲学史上、最も有名で、最も重要な師弟。
プラトンと、その弟子アリストテレスです。
【プラトンの回答 真の存在は、理想の世界「イデア」にある】
プラトンは、師ソクラテスの教えとパルメニデスの思想を受け継ぎ、こう考えました。
「確かに、この目に見える世界は移ろいゆく不確かなものだ。だが、その“お手本”となる、永遠で完璧な世界が、どこか別の場所に存在するはずだ」
これが、かの有名な「イデア論」です。
例えば、私たちが「美しい」と感じる花や絵画は、時代や場所によって様々です。
でも、それらが美しいのは、この世ならざる場所に「美そのもの(美のイデア)」が存在し、個々の美しいものがそれを不完全に分け与えられているからだ、とプラトンは『国家』などの著作で考えたのです。
【アリストテレスの回答:真の存在は、目の前の「現実」にこそある】
一方、プラトンのアカデメイアで20年も学んだ秀才アリストテレスは、師とは全く逆の道を歩みます。
彼は、師プラトンが少し軽んじた、この目の前にある「現実」の世界こそを探求の対象としました。
アリストテレスは、イデアのような“彼方の世界”を持ち出すのではなく、目の前にある「この机」「この木」といった一つひとつの「個物(こぶつ)」に注目します。
そして、それらが
「何でできているか(質料)」
と
「何であるか(形相)」
という観点から、存在を体系的に分析していきました。
ルネサンス期の画家ラファエロが描いた『アテナイの学堂』という絵画があります。
その中央で、プラトンは天を指さし、アリストテレスは地を指さしている。
まさに、この二人の思想の違いを象徴する、見事な描写です。
彼らは単なるライバルというだけでなく、
その後の哲学の二大潮流(理想主義と現実主義)の、まさに源流となったのです。
【この章のポイント】
パルメニデスは「有るものは有り、無いものは無い」と主張し、「感覚」より「理性」を重んじる哲学の幕を開けた。
プラトンは、真の存在は永遠不変の「イデア」の世界にあると考えた(理想主義)。
アリストテレスは、真の存在は目の前の「個物」にこそあると考えた(現実主義)。
【あなたへの問いかけ】
あなたはプラトンとアリストテレス、どちらの考え方に、より共感しますか?それはなぜでしょう?
古代ギリシアの自由な思索の時代が終わり、ヨーロッパがキリスト教の教えのもとに一つになった中世。
この時代、哲学は、それ自体が目的ではなくなりました。
哲学の最も重要な役割は、信仰を理性的に説明すること、つまり
「神は、なぜ、どのように存在するのか」
を、論理的に明らかにすることになったのです。
これをスコラ哲学と呼びます。
このスコラ哲学を大成させたのが、トマス・アクィナスという、とてつもない知性の持ち主でした。
彼は、当時アラビア経由で再発見されたアリストテレスの哲学を、キリスト教の教えと見事に融合させるという大事業を成し遂げます。
その中で、彼は存在論に関して、非常に重要な区別を導入しました。
それは、「本質(ほんしつ)」と「実存(じつぞん)」の区別です。
| 用語 | 説明 | 具体例 |
| 本質 | 「それが何であるか」という定義や性質のこと。 | 「人間とは、理性的な動物である」ということ。 |
| 実存 | 「それが現実に存在している」という事実のこと。 | あなたや私が、今、ここに、現実にいること。 |
トマスによれば、神によって造られた私たち被造物においては、この本質と実存は一致していません。
「人間とは何か」という本質が分かっても、その人間が実際に存在するかは別の話ですよね。
しかし、神においてのみ、本質と実存は完全に一致している、と彼は考えました。
神とは「存在すること」そのものであり、自らの他に原因を持たない、究極の「存在そのもの」なのだ、と。
難しいですね。
アリストテレスの哲学を武器に、神の存在を壮大に論証してみせたのです。
(※スコラ哲学における「実存」は、後のサルトルが言う「実存」とは意味合いが異なる点に注意が必要です。ここでは「現実存在」くらいの意味で捉えておくと分かりやすいです。)
やがて、絶対的と信じられていた教会の権威は、ルネサンス期の人間中心主義の芽生えや、科学革命によって、少しずつ揺らぎ始めます。
「本当に確かなものは、一体どこにあるのだろう?」
そんな、時代の不安を一身に背負ったかのような哲学者が登場します。
ルネ・デカルトです。
彼は、たった一つでいいから「絶対に疑い得ない、確実な知識の礎」を見つけるために、孤独な思索の旅に出ました。
その方法が、有名な「方法的懐疑」。
少しでも疑えるものは、全て偽物として徹底的に疑い、捨て去っていく、というやり方です。
感覚も、身体も、世界の存在すら疑った末に、デカルトは気づきます。
たった一つ、どうしても疑えないものが残ることに。
それは、「すべてを疑っている、この“私”の“思考”は、確かに存在する」という事実でした。
この劇的な発見が、彼の主著『省察』の中で語られる、哲学史で最も有名な命題の一つ、
「我思う、ゆえに我あり(コギト・エルゴ・スム)」です。
この発見がなぜ革命的だったか、お分かりでしょうか。
それは、存在の確実性の根拠が、それまでのように
外部にある「神」から、自分自身の内なる「私(主観)」へと、180度ひっくり返った瞬間だったからです。
現代の私たちが、ごく当たり前に持っている「自分だけの内面世界」という感覚。
その感覚の、いわば“発明者”がデカルトだったと言えるかもしれません。
ここから、哲学は「近代」という新しいステージへと、大きく舵を切っていくことになります。
【この章のポイント】
中世哲学では、トマス・アクィナスが「本質」と「実存」を区別し、神を「存在そのもの」として論証した。
近世になると、デカルトが「我思う、ゆえに我あり」によって、存在の確かな根拠を「神」から「私」へと大転換させた。
この「主観性」の発見が、近代哲学の出発点となった。
【あなたへの問いかけ】
もしあなたがデカルトなら、「考える私」以外に、何か絶対に疑えないものを見つけられますか?
デカルトが「私」という確固たる出発点を見つけて以降、哲学はある大きな難問に突き当たっていました。
それは、
「私の主観(心)は、どうやって外の世界を正しく認識できるのだろう?」
という問題です。
この問いは、近世哲学をずっと悩ませ続けました。
この長年の論争に、一つの終止符を打ったのが、ドイツの哲学者イマヌエル・カントです。
彼は、まさに天動説が地動説に変わった時のような、発想の大転換を行いました。
後に「コペルニクス的転回」と呼ばれる、その考え方とは、こういうものです。
「世界がどうあるかを私たちが認識するのではない。私たちの“認識の形式”が、世界がどう現れるかを決定しているのだ」
カントは、人間の認識を「色メガネ」に喩えました。
もし私たちが、生まれつき「青い色メガネ」をかけているとしたら、世界は当然、すべて青みがかって見えるはずです。
でも、私たちはそのメガネを外すことができないので、世界が「本当は」何色なのか、確かめる術がありません。
カントは、これと同じことが人間の認識全般に言える、と考えたのです。
私たちは、時間や空間、あるいは因果律といった、人間が生まれつき持っている「認識の形式(主観の構造)」というフィルターを通してしか、世界に触れることができません。
その結果、カントが主著『純粋理性批判』で示した結論は、衝撃的なものでした。
私たちが認識できるのは、あくまでも私たちの主観のフィルターを通して現れた「現象」の世界だけ。
フィルターを通す前の、ありのままの「物自体(ものじたい)」がどうなっているのかは、私たちには永遠に知り得ないのだ、と。
このカントの思想は、存在論における「謙虚さの革命」と呼べるかもしれません。
「人間は世界の全てをありのままに知ることができる」という、それまでの哲学が漠然と抱いていた自信を打ち砕き、人間の理性が持つ「限界」を初めて明確に示したことの重要性は、計り知れません。
カントによって、世界の「物自体」を探求することに限界が見えた後、哲学の関心は、より「人間」そのものへと向かっていきます。
特に、二度の世界大戦という未曾有の危機を経験した20世紀には、
「この私がいま、ここに、こうして存在していることは、一体どういう意味を持つのか?」
という、極めて切実な問いが哲学の中心となりました。
ハイデッガーと「存在の意味」への問い
こうした時代の空気の中、カント以来、哲学の脇役に追いやられていた「存在論」を、再び哲学の中心に呼び戻したのが、マルティン・ハイデッガーです。
彼は、他のモノの存在と、私たち人間の存在は、根本的に違うと考えました。
机や石は、ただそこに「在る」だけです。
しかし、私たち人間は、自分が「存在している」ということを自覚し、「自分の存在の意味は何か?」と問うことができる。
そして何より、自分がいずれ「死ぬ」という事実を知っている。
ハイデッガーは、この人間特有の存在のあり方を「現存在(げんそんざい / ダーザイン)」と呼び、その分析から、
忘れられていた「存在そのものの意味」をもう一度問い直そうとしました。
サルトルと「自由」という名の刑
ハイデッガーの思想を、よりラディカルに、そして情熱的に展開したのが、フランスのジャン=ポール・サルトルです。
彼は、かつて中世のトマス・アクィナスが立てた「本質が実存に先立つ」という神学的な考えを、真っ向からひっくり返して、こう叫びました。
「実存は本質に先立つ」
これは、実存主義のスローガンとして、あまりにも有名ですね。
彼が言いたかったのは、こういうことです。
ペーパーナイフなら、まず「紙を切る」という目的(本質)があってから、作られます(実存)。
しかし、人間はそうではない。
人間には、予め定められた目的や意味(本質)など何もないまま、ただ理由もなくこの世に放り込まれる(実存)。
そして、
自らの行動や選択によって、自分自身で「自分とは何者か」を、後から作り上げていくのだ、と。
これは、人間に絶対的な「自由」を宣言する、力強いメッセージです。
しかし同時に、サルトルは言います。
人間は「自由の刑に処せられている」と。
生きる意味を、誰のせいにもできず、全て自分で背負わなければならない。
それは、時にめまいがするほど、重く、しんどいことでもあるのです。
これまでの存在論が、世界の客観的な構造を問うことが中心だったのに対し、彼ら実存主義者は、存在論の問いを、私たち一人ひとりの、切実で主観的な魂の問題へと引き寄せたのでした。
【この章のポイント】
カントは「コペルニクス的転回」により、私たちは世界の「現象」しか認識できず、「物自体」は知り得ないと論じ、人間の理性の限界を示した。
ハイデッガーは、人間特有の存在のあり方「現存在」の分析から、「存在の意味」を問い直した。
サルトルは「実存は本質に先立つ」と主張し、人間は自らの選択によって自分を創造していく、絶対的に自由な存在であると説いた。
【あなたへの問いかけ】
あなたは、サルトルの言う「自由の刑」を、重いと感じますか?それとも、希望だと感じますか?
【第3部】知的好奇心を刺激する、存在論の核心的テーマ

さて、ここからは少しギアを上げて、哲学の内部で古来から続く、最も根源的で重要な論争の一つを覗いてみましょう。
その名も「普遍論争(ふへんろんそう)」。
一見すると地味ですが、実は私たちの世界の見方を根底から揺さぶる、とてもエキサイティングなテーマなんです。
まず、想像してみてください。
あなたの目の前に、真っ赤なリンゴが3つあります。
この3つのリンゴは、それぞれ大きさも形も違う、別々のモノですよね。
でも、私たちはこれらを同じ「リンゴ」だと認識し、「赤色」という共通の性質を見出すことができます。
では、ここからが哲学の問いです。
この、個々のリンゴを超えた共通の性質である「リンゴ性」や「赤性」といったもの
(哲学の言葉で「普遍(ふへん)」と呼びます)
は、一体どこに、どのように存在するのでしょうか?
この問いに対する回答は、大きく分けて2つの立場に分かれます。
こちらは、プラトンを祖とする考え方です。
彼らは、「普遍は“本当に”存在する」と主張します。
つまり、「赤性」という普遍は、個々の赤いリンゴとは独立して、イデアの世界のような場所に客観的に実在している、と考えるのです。
この立場からすれば、「人間性」という普遍が、私たち一人ひとりとは別に、しっかりと実在するからこそ、私たちは皆「人間」として尊厳を持つ、ということになります。
共通の理想や性質を信じる、力強い考え方ですね。
一方、こちらは中世の哲学者オッカムなどが代表する考え方です。
彼らは、こう主張します。
「実際に存在するのは、目の前にある個々のモノだけだ。普遍(赤性やリンゴ性)とは、私たちが似たものを便宜上ひとまとめにして呼んでいる『名前』に過ぎない」
と。
この立場からすれば、「人間性」というものは、あくまで私たちが作り出した便利なラベル(名前)であって、現実に存在するのは、あなたや私といった、具体的な個人だけ、ということになります。
あくまで個々の事実だけを信じる、非常にクールで分析的な考え方です。
「どっちでもいいじゃないか」と思われるかもしれません。
でも、この対立は、私たちの価値観の根っこに深く関わっています。
例えば、「人間の尊厳」について考えてみましょう。
実在論のように「人間性」という普遍がカッチリと実在するなら、私たちの尊厳の根拠は揺るぎません。
しかし、唯名論のように、もしそれが「名前」に過ぎないとしたら…?
私たちの尊厳を支えているものは、一体何になるのでしょうか。
このように、普遍論争は、科学の基礎(「法則」は実在するか?)から、人権や倫理の問題まで、私たちの世界のあらゆる場面に潜んでいる、今なお終わらない大問題なのです。
【この章のポイント】
普遍論争とは、「リンゴ性」や「人間性」といった共通の性質(普遍)が実在するかをめぐる大論争である。
実在論は「普遍は(イデアのように)本当に存在する」と考える。
唯名論は「普遍は名前にすぎず、実在するのは個物だけだ」と考える。
この対立は、科学や人権といった、私たちの世界の根幹に関わる問題に繋がっている。
【あなたへの問いかけ】
あなたは、SNSなどで使われる「〇〇な人」という“ラベル(普遍)”が、時に個人そのものよりも強く感じられることに、どんなことを思いますか?
さて、最後に、現代の哲学者がこの「存在」という問いに、どのように取り組んでいるのか、その最前線の一端を覗いてみましょう。
特に20世紀以降の英米圏では、哲学は「言語の分析」を通して、より厳密に問題の解明を目指すようになりました。
この言語分析の流れの中で、20世紀アメリカの最も重要な哲学者の一人、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワインは、存在論の問いの立て方そのものに、革命を起こしました。
彼は、古代から続く「何が存在するか?」という問いは、あまりにも曖昧で詩的だと考えました。
そして、もっと厳密に、論理的に存在について語るための、一つの基準を提案します。
それが、彼の有名なテーゼ、
「存在することは、変項の値であることだ(To be is to be the value of a variable)」
です。
暗号のようですよね。
安心してください。
まず、「変項」とは、数式でいう x や y のような「空欄」だと思ってください。
例えば、「x は犬である」という文があります。
このままでは、真か偽か分かりませんよね。
クラインの基準は、こうです。
「この x という空欄に、『ポチ』のような具体的な存在を代入することで、『ポチは犬である』という文が真になる。このように、私たちの“最良の科学理論”が、その存在を認めないと説明がつかないものだけを、私たちは『存在する』と語るべきだ」
という、非常にドライで強力な考え方なのです。
神話や個人の信念ではなく、私たちの知性の最良の成果である科学に、存在論の基準を委ねよう、というわけですね。
さらに現代では、存在論の探求はもう一段、上のレベルに進んでいます。
それは、「メタ存在論」と呼ばれる分野です。
「メタ」とは「~について」とか「高次の」という意味。
つまり、彼らは「何が存在するか?」と直接問うのではなく、
「『何が存在するか?』という問い自体は、そもそも有意味なのだろうか?」
と、問いそのものを問うのです。
ある哲学者は、実在論者と唯名論者の争いは、実は言葉の使い方が違うだけで、本当は何も争っていない「不毛な論争」かもしれない、と指摘します。
またある哲学者は、何が存在するかは、文脈や目的によって変わる相対的なものではないか、と考えます。
このように、哲学は、自らが立てた問いさえも疑いの対象とし、その意味や構造を問い直すことで、常に自己刷新を続けている、とてもダイナミックな営みなのです。
「こんな抽象的な議論が、何の役に立つんだ?」
そう思われる方もいるかもしれません。
しかし、驚くべきことに、この存在論の知見は、現代の最先端技術であるAI(人工知能)の開発を、根っこで支えています。
情報科学の分野に「オントロジー」と呼ばれる技術があります。
これは、特定の世界(例えば、医療や金融)に存在する様々な概念(「病気」「薬」「治療」など)と、それらの関係性(「薬は病気を治療する」など)を、コンピューターが処理しやすいように、体系的に定義する設計図のようなものです。
まさに、アリストテレスが試みたように、世界の存在者を分類し、体系化する作業ですよね。
哲学者が何千年とかけて磨き上げてきた「存在者を整理し、定義する」という知的なツールが、AIが世界の情報を効率的に理解するための、強力な基盤技術として応用されているのです。
哲学の思索は、決して机上の空論ではない。
その一つの、何よりの証拠と言えるでしょう。
【この章のポイント】
現代の分析哲学では、クワインが「科学理論が必要とするものだけが存在する」という厳密な基準を提案した。
メタ存在論は、さらに進んで「『何が存在するか?』という問い自体は有意味か?」と、問いそのものを問う。
存在論的な知の整理術は、情報科学における「オントロジー」として、現代のAI技術を支えている。
【あなたへの問いかけ】
あなたは、AIが書いた小説や描いた絵を「本物の作品」として「存在する」と認められますか?
【まとめ】「存在」を問うことで、あなたの見る世界はより深く、豊かになる
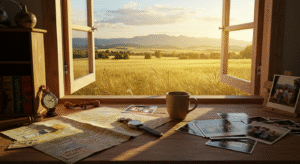
さて、古代ギリシアから現代のAI技術まで、時空を超えて「存在」をめぐる思索の広がりを見てきました。
最後に、この記事の核心となるポイントを、もう一度一緒に確認しておきましょう。
-
哲学の土台「存在論」とは?
「『存在する』とはどういうことか?」を問う、哲学のOS(土台)となる学問。 -
存在論が問う「2つの基本的な問い」
「何が(What)」存在するのか? そして「どのように(How)」存在するのか? -
古代ギリシア ― 「存在」という概念の誕生と大論争
パルメニデスが問いを立て、プラトン(理想主義)とアリストテレス(現実主義)が哲学の二大潮流を創った。 -
中世・近世 ― 存在の探求は「神」そして「私」へ
存在の根拠が、中世の「神」(トマス・アクィナス)から、近世の「考える私」(デカルト)へと大転換した。 -
近現代 ― 人間特有の「存在」と意味へのフォーカス
カントが理性の限界を示し、サルトルらが「人間存在(実存)」そのものを問うた。 -
普遍論争 ―「人間という性質」は本当に存在するのか?
「普遍は実在する(実在論)」か、「名前にすぎない(唯名論)」かをめぐる、哲学の根源的な対立。 -
現代の存在論 ― 「何が存在するか」をめぐる最前線の議論
クラインが科学的な基準を導入し、哲学の知はAI技術(オントロジー)にも応用されている。
ここまで読んでくださったあなたなら、もうお分かりかもしれません。
存在論には、そして哲学には、
数学の公式のような、誰もが納得する唯一絶対の「答え」というものは、おそらくありません。
しかし、それは哲学の欠点ではなく、むしろ最大の魅力なのだと、私は考えています。
「答え」を与えてくれるのが科学の役割だとしたら、
「豊かな問い」を与えてくれるのが哲学の役割です。
「なぜ?」と問うことを通して、私たちは初めて、普段「当たり前」だと思って見過ごしていた世界の不思議さ、奥深さに気づくことができます。
「存在とは何か?」という問いを、自分の中に持ち続けること自体が、当たり前の日常を、無限の発見に満ちた新鮮な世界へと変えてくれる。
その、新鮮な驚きこそが、哲学が私たちにくれる、最高の贈り物なのです。
もし、この記事を読んで、少しでも「哲学って、面白いかもしれない」と感じていただけたなら、これ以上嬉しいことはありません。
あなたの知的好奇心のレベルに合わせて、次の一歩となりそうないくつかの道しるべをご用意しました。
-
ステップ1(最初の一歩に)
-
NHK「100分de名著」シリーズ サルトル『実存主義とは何か』や、ハイデッガー『存在と時間』の回などが非常におすすめです。映像で専門家が語る言葉は、すっと心に入ってきますよ。
-
図解系の哲学入門書 書店で手に取り、パラパラとめくってみて「絵が好みだな」と感じるものが、あなたにとって最高の入門書です。
-
-
ステップ2(もう少し深く)
-
中山康雄『実存主義』(岩波新書) 今回のテーマ「実存」を、歴史の流れの中で非常にクリアに解説してくれます。
-
飯田隆『分析哲学入門』(ちくま新書) 現代の存在論に興味を持ったなら。少し歯ごたえがありますが、知的な興奮を味わえるはずです。
-
-
ステップ3(原典の世界へ)
-
プラトン『ソクラテスの弁明』 哲学が単なる理論ではなく、自らの生き方をかけた対話であることを、ドラマチックに体感できる最高の一冊です。
-
デカルト『方法序説』 近代的な「私」が、いかにして誕生したのか。その思索の軌跡を、あなた自身が追体験できます。
-
あなたの知的な探求が、これからも豊かで、実り多いものであることを、心から願っています。
このブログでは、今回のような哲学の知見もヒントにしながら、皆さんが自分にとっての「幸せ」や「豊かさ」とは何かを探求し、日常が少しでも気持ちが楽になるような様々な考え方を発信しています。もしよろしければ、他の記事も覗いてみてくださいね。
【こちらの記事も読まれています】



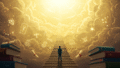
コメント