日々の判断に、確かな手応えが持てずに迷うことはないかな。この記事は、そんなあなたの中に、一本の確かな軸を築くためのヒントを渡すものだよ。
ここでは、トマス・アクィナスの思想の核心と、それを応用した、決断の質を高める4つの具体的な「思考の型」を紹介するね。
それは、700年以上も色褪せない、普遍的な考え方の道具。
少しだけ、その世界に触れてみないかい?
トマスの思想が、現代の「判断軸」になる理由

情報が多すぎて、何を選べばいいかわからなくなる。
会議で多様な意見が飛び交う中で、自分の意見に自信が持てなくなる。
仕事で答えのない問題に直面し、どう判断すればいいか立ち止まってしまう。
そういうこと、あるよね。
私たちの日常は、大小さまざまな決断の連続だよ。その一つひとつに、確かな手応えを持って臨めている人は、そう多くないのかもしれないね。その原因は、あなたの能力不足や知識不足というわけでは、きっとないんだ。
それは、場当たり的な情報処理ではなく、自分の中に一貫した「思考のOS」のようなものが、まだインストールされていないだけ、ということが多いように思う。
そして、そのOSとして、700年以上も前の哲学者の思想が、驚くほど有効に機能することがあるよ。
その哲学者の名は、トマス・アクィナス。
「なぜ、そんなに古い哲学が?」と、そう思われるのも無理はない。
なぜなら、彼の思想は特定の時代にしか通用しない知識ではなく、人間が物事の本質を考えるための、普遍的で体系的な「思考のアルゴリズム」そのものだからね。
時代が変わっても人間が悩むことの本質は、そう大きくは変わらないから。
この記事では、難解な哲学用語をただ解説するような、退屈なことはしないよ。あなたに提供したいのは、以下の2つだね。
トマス思想の核心的なエッセンス(要点)
それを、あなたの日常で明日から使える具体的な「4つの思考の型」
読み終える頃には、あなたの中に確かな「判断軸」を築くための、具体的な足がかりが、きっと一つは見つかっているはずだよ。
「哲学」という言葉に、どうか身構えないでね。
「自分の頭を整理するための、便利な道具を手に入れる」くらいの、実用的な気持ちで、リラックスして読み進めていただけたらと思う。
【この章のポイント】
現代社会の悩みの根源は、一貫した「思考のOS」が不在なことにある。
トマス・アクィナスの思想は、時代を超えて通用する普遍的な「思考のアルゴリズム」として機能する。
この記事では、彼の思想の要点と、日常で使える4つの具体的な「思考の型」を提供する。
トマスの思想を理解する前に。トマス・アクィナスとはどんな人物か?

彼の思想という、なかなか便利な道具に触れる前に、少しだけ。その作り手であるトマス・アクィナスという人物について、知っておこうか。
どんな人が、どんな時代に、何を考えていたのか。
その輪郭をぼんやりとでも知っておくと、思想そのものが、より立体的に、血の通ったものに見えてくるはずだから。
アリストテレス哲学と信仰を結んだ、当時の「革新家」
彼が生きた13世紀のヨーロッパというのは、キリスト教の教えが世界のすべてだった。人々の暮らしも、学問も、何もかもが「神」という絶対的な存在を前提に成り立っていた。
そういう、良くも悪くも、とても一色な時代だ。
そこへ、当時としては最先端であり、同時に少し危険な思想が、外からそろりと入ってきた。
それが、古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの哲学だよ。
アリストテレスの考え方は、ひと言でいえば、とてもドライだったね。
「神様がそう言っているから」ではなく、「自分の目で現実を観察し、筋道を立てて考える(理性)」ことを何よりも大切にしたんだ。
これは、当時の人々にとって、自分たちの信じる世界を根底からグラグラと揺るがしかねない、一種の「劇薬」のようなものだったわけだ。
当然ながら、多くの学者がこの“劇薬”を危険だと考え、遠ざけようとした。
でも、トマスは違った。
彼は、この危険な外来種とも言えるアリストテレス哲学を、在来のキリスト教という生態系の中に丁寧に取り込み、両方の長所を生かした、より強靭なハイブリッド種のようなものを創り出したのだ。
彼は、『信仰』と『理性』は対立するものではなく、真理に至るための異なる道だと考えた。
より具体的には、理性は世界の観察と論理によって真理を追求する自然の光であり、信仰は理性の届かないさらに深遠な真理を照らすより高い光(神の啓示)だと捉えたんだ。
この知的な誠実さと、常識に挑戦する静かな姿勢こそ、彼が単なる物知りな学者ではなく、「革新家」と呼ばれる理由なのだと、私は思うよ。
『神学大全』に学ぶ、「あらゆる問い」に答える体系的思考
彼の代表作に『神学大全』という、それはもう分厚い本がある。
「神学」という言葉を聞くと、少し身構えてしまうかもしれないね。だけど、その本質は、神様の話だけにとどまらない。
あれは、「当時の人々が抱くであろう、あらゆる問いに、一つの体系的な論理で答えようとした、壮大な試み」と言うのが、より実態に近いだろう。
そして面白いのは、その内容もさることながら、彼の「考え方の手順」そのものなんだ。彼はこの本の中で、一貫して次のようなスタイルを貫いている。
【問い】 まず、議論したいテーマを「〜は、〜か?」という、シンプルな問いの形で立てる。
【反論】 次に、その問いに対して予想される「いや、そうではないだろう」という反論や、世間一般の誤解を、あえて先にいくつか並べる。
【自説】 その上で、「しかし、私はこう考える」と、自身の見解を堂々と述べる。
【再反論】 最後に、STEP2で挙げた一つひとつの反論に対して、「この反論には、こう答えられる」と、丁寧に回答していく。
この思考のプロセス、どこかで見たことがないかな。
そう、これは現代の私たちが何かを考え、人に説明するときの「課題設定 → リスク分析 → 結論 → 質疑応答」という思考フレームワークの、ほとんど原型と言っていいものだよ。
700年以上も前に、これほど客観的で、誠実な思考の型が確立されていたというのは、少し驚きだね。
トマス・アクィナスという人は、ただ知識が豊富なだけでなく、その膨大な知識を整理し、体系化し、誰にでも分かるように論理的に説明する能力に、非常に長けた人物だった。
彼の思想そのものだけでなく、その考え方の「型」にも、私たちが学ぶべきヒントがたくさん詰まっているのだ。
【この章のポイント】
トマス・アクィナスは、常識に挑戦し、「信仰」と「理性」という対立するものを統合しようとした「革新家」だった。
彼の主著『神学大全』は、内容だけでなく、その論理的な「思考プロセス」自体が、現代の問題解決にも通じる強力なフレームワークである。
彼の思想を学ぶことは、その考え方の「型」を学ぶことでもある。
【要点解説】トマスの思想。世界を一つのシステムとして捉える

さて、ここからはいよいよ、トマスの思想の核心部分に、ゆっくりと入っていこうか。
彼の思想は、バラバラな知識の寄せ集めではないね。それは、しっかりとした「土台」の上に、合理的な「建築方法」で「柱」を立て、壮大な「屋根(ゴール)」を目指す、一つの家を建てるような、見事なシステムになっている。
この全体の設計図を理解すると、彼の思想がなぜ今もなお、私たちの「心の指針」として、ちゃんと機能するのか。
その理由が、きっと腑に落ちるはずだよ。
【土台】現実から始める、アリストテレス由来の思考法
まず、すべての「土台」となる考え方だね。
それは、師であるアリストテレスから受け継いだ「徹底した現実主義」だった。
哲学というと、どこか現実離れした、雲の上のような理想を語るイメージがあるかもしれない。実際、アリストテレスの師であるプラトンは、「この現実世界は、完璧な理想世界の影にすぎない」と考えた。
しかし、トマスが土台にしたのは、その逆のアプローチ。
「机の上で難しい理想を語る前に、まず目の前にある現実を、自分の五感でしっかりと観察することから始めようじゃないか」。
これが彼の、そしてアリストテレスの基本スタンスだった。
この姿勢は、現代の仕事の現場でよく言われる「ファクトベース思考」や「現場主義」の、まさに源流とも言えるものだね。
憶測や願望といった、フワフワしたものではなく、まず事実を冷静に見つめる。
このブレない土台があったからこそ、彼の壮大な思想体系は、絵に描いた餅ではない、確かな説得力を持つことになったのだろう。
【建築方法①】原因まで遡る「論理の階段」という考え方
堅固な土台の上に家を建てるための、一つ目の道具。
それが「論理」だ。
彼の論理的な思考を象徴するものに「神の存在証明」というものがある。これは少し堅い言葉に聞こえるけれど、何も宗教的な奇跡を語るものではないんだ。その本質は、もっとシンプルで、ずっと実践的なものだよ。
それは、「あらゆる結果には原因があるはずだ」という、ごく当たり前の信念のもと、物事の根源まで思考を遡っていく、一種の知的トレーニングのようなもの。
私はこれを「論理の階段」と呼んだりするね。
目の前の出来事に対して「なぜ?」と問い、その原因が見つかったら、さらにその原因に対して「なぜ?」と問いかける。
そうやって、一歩一歩、本質へと続く階段を静かに遡っていくイメージだ。
これは、優れた組織で用いられる「なぜを5回繰り返す」というあの問題解決手法と、考え方は全く同じだね。
【建築方法②】データとビジョンを繋ぐ「知のアーチ構造」
そして、二つ目の道具。これこそが、彼の思想を最も美しく、特徴的なものにしている部分だと、私は思う。
それが、「理性と信仰の調和」という考え方だったね。
当時の人々は、「理性(論理で考えること)」と「信仰(神の啓示による真理を信じること)」を、水と油のように、決して混じり合わないものだと考えていた。
しかし、トマスはそうは考えなかった。
彼は、「理性で分かることには、どうしても限界がある。その限界の、さらに先にある真理をそっと指し示してくれるのが信仰なのだ」と捉え、両者は互いに補い合う、大切なパートナーなのだと考えたのだ。
この関係は、古い石造りの橋などで見られる「アーチ構造」によく似ているね。
左右の石が互いに寄りかかり、支え合うことで、一つの強固な橋になる。それと同じなんだ。
そしてこの考え方は、不思議なことに、現代を生きる私たちの決断にも、そのまま当てはまるよ。
データやロジック(理性)を徹底的に分析し、行けるところまで行く。しかし、最後は自身の価値観や組織のビジョン(信仰に近いもの)を信じて、えいやっと一歩を踏み出す。
この両輪があって初めて、私たちは複雑な問題に対して、後悔のない決断を下せるのかもしれない。
【柱】人間の行動原則である「自然法」という内なる指針
さて、世界の捉え方(土台)と、考え方(建築方法)が固まったね。
次にトマスは、「では、人間はこの世界で、どう生きるべきか?」という、とても人間くさい問いに向き合う。この、人間倫理の部分が、彼の思想という家をどっしりと支える、太い「柱」になるね。
その答えが、「自然法」に従って生きる、ということだった。
「法」という言葉がついているけれど、これは国が定めた法律のことではないよ。もっと私たちの、そう、内側にあるものだ。ひと言でいえば、「人間がその本性として、より善く生きたいと願う、心の内側にある指針」のこと。
誰かに命令されなくても、「正直でありたい」「人を助けたい」「学び続けたい」と思う、あの自然な気持ち。
いわば、私たちの誰もが、心のどこかに持っている「良心」のようなもの。トマスは、この内なる声に従って生きることが、人間にとって最も自然で、正しい道なのだ、と考えた。
そして彼は、この「内なる指針(自然法)」に従って正しく生きるために必要な、具体的な心の技術が4つあると考えた。
それが「賢慮・正義・勇気・節制」という4つの徳(習慣)だ。
これについては、後の実践パートで、またゆっくり話そうか。
【屋根】人生の究極目標である「幸福」の本当の意味
土台があり、柱が立った。では、この家が目指す「屋根」、つまり私たちの人生の究極的なゴールは、一体何なのだろう。
トマスは、師であるアリストテレスと同じように、「この世界のあらゆるものには『究極的な目的(テロス)』がある」と考えた。
石が下に落ちるように、植物が太陽に向かって伸びるように、人間という存在にも、最終的に目指すべき究極の目的があるはずだ、と。
そして、それが「幸福」なのだ、と彼は考えたんだ。
ただし、ここで少し注意が必要だよ。彼が言う「幸福」とは、美味しいものを食べる、お金持ちになるといった、一時的な快楽や満足のことではない。
彼が定義した幸福とは、
「人間が持つ理性や善性といった素晴らしい能力を最大限に発揮し、世界の究極的な真理を認識している状態」を指す。
少し難しい表現だけど、現代の言葉で言うなら、心理学者のマズローが言った「自己実現」や、「自分のポテンシャル(可能性)を完全に開花させている状態」に、非常に近いものだね。
これこそが、私たちが目指すべき人生の「屋根」なのだ、と彼は言っているわけだ。
【この章のポイント】
トマスの思想は、
- 「現実主義(土台)」
- 「論理と価値観(建築方法)」
- 「善く生きる指針(柱)」
- 「幸福(屋根)」
という一つのシステムとして理解できる。
彼の思考法は、現代の「ファクトベース思考」や「なぜなぜ分析」にも通じる、極めて実践的なものである。
人生の究極目標は「幸福」だが、それは快楽ではなく、自分自身の可能性を最大限に開花させた「自己実現」に近い状態を指す。
【深掘り】トマスの思想の核心。「思考プロセス」そのものを型にする
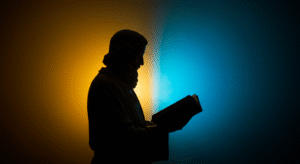
これまでの章で、私たちはトマスの思想という、なんとも壮大な「家の設計図」を見てきたね。
この章では、もう少しだけ、さらに一歩深く踏み込んでみようか。
その家を建てた“天才建築家”の「頭の中」、つまり、彼の思考プロセスそのものに、そっと光を当ててみたいと思う。
実は、彼の考え方の手順そのものが、現代の私たちが直面する、答えのない複雑な問題を解きほぐすための、非常に強力な「思考の型」になっているのだ。
『神学大全』に学ぶ、現代で通用する最強の問題解決フロー
彼の主著『神学大全』は、不思議なほどに、一貫した思考のフローに則って書かれているね。それは、次の4つのステップから成る。
STEP1:問いを立てる(提起)
STEP2:あらゆる反論を想定する(反証)
STEP3:自らの結論を述べる(仮説)
STEP4:反論に一つひとつ答える(検証)
一見すると、昔の学者の堅苦しい文章作法のように見えるかもしれない。
だけど、この4つのステップを現代の私たちの言葉に翻訳してみると、その本質が、極めて実践的な問題解決の技術であることが、すっと見えてくるよ。
STEP1:問いを立てる →「課題設定」の技術
「何が本当の問題なのか」「今、本当に議論すべき点はどこか」を正確に言語化する。これは、あらゆる仕事やプロジェクトの、静かな出発点だね。的確な問いを立てる能力は、いつの時代も、物事を前に進めるための本質的なスキルなのだろう。
STEP2:あらゆる反論を想定する →「クリティカルシンキング」そのもの
これこそが、彼の思考法の、なんというか、真骨頂だね。自分の意見に対して、あえて自分自身で、意地悪な視点からツッコミを入れてみる。そうすることで、自分の考えの穴や弱点を、事前に洗い出すんだ。これは、現代で言われる「リスク分析」にも通じる、とても誠実で客観的な態度だと思わないかい。
STEP3:自らの結論を述べる → 精度の高い「仮説構築」
あらゆる反論を想定し、それらを乗り越えられるだけの、どっしりと強固な「仮説」をここで提示する。単なる思いつきや願望ではないよ。厳しい自己批判に耐え抜いた、質の高い結論だね。
STEP4:反論に一つひとつ答える → 徹底した「妥当性検証」
そして最後に、自分の仮説がなぜ正しいのかを、想定されるすべての反論に答えながら証明していく。これは、プレゼンテーションの後の「質疑応答」で、あらゆる角度からの質問に的確に答えることで、聴衆の信頼をじんわりと勝ち取っていく、あのプロセスと全く同じだね。
どうだろう。
700年以上も前の思考法が、現代のリーダーたちが学ぶ思考法と、ここまで似ているというのは、面白いことだよね。
この思考の型が、なぜこれほど強力なのか。その理由は、たぶん3つあるよ。
【網羅性】 あらゆる反論を考慮するため、思考のヌケ・モレや見落としが、ぐっと減る。
【客観性】 一度、自分に反対の立場に立ってみることで、自分の思い込みや独善的な考え方から、ふっと抜け出すことができる。
【説得力】 すべての反論を乗り越えた結論であるため、その言葉には、自然と重みと説得力が宿る。
このように、トマスの思想は、その中身だけでなく、考え方のプロセス自体が、非常に実践的な「型」になっているのだ。
さて、次の章ではいよいよ、この強力な思想体系から導き出される、より日常のシーンで使いやすい、具体的な「4つの思考の型」を紹介するね。
【この章のポイント】
トマスの思想を生み出した「思考プロセス」そのものが、現代で通用する強力な問題解決の型である。
そのプロセスは「課題設定→リスク分析→仮説構築→妥当性検証」という、現代のクリティカルシンキングと酷似している。
この型を意識することで、思考の「網羅性」「客観性」「説得力」を飛躍的に高めることができる。
【実践】トマスの思想から生まれた、日常で使える「4つの思考の型」
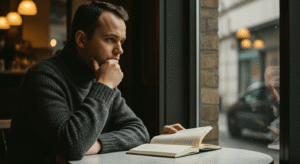
ここまでの章で、トマスの壮大な思想体系とその思考プロセスを、一緒に見てきた。
この最後の実践パートでは、その巨大な知性のエッセンスを、私たちの日常的な悩みを解決するために distillation(蒸留)し、すぐに使える4つの「思考の型」として紹介するね。
全部を覚える必要はないよ。
まずは「これなら、自分にもできそうかな」と思えるものを一つ見つけるくらいの、そんな気軽な気持ちで読んでみて。
思考の型① 決断の質を高める「四元徳チェック」
これは、思想のパートで少しだけ触れた、「自然法(内なる指針)」に従って生きるための、具体的な心の技術だね。
何か複雑な意思決定に直面したとき、この4つの視点から自分にそっと問いかけることで、思考のバランスを取り、決断の質を高めることができる。
【賢慮】(現実的な視点) その手段は、目的達成のために最も効果的で賢明と言えるだろうか?
【正義】(他者への配慮) その判断は、関わる人々(チーム、顧客、家族)に対して公正で誠実だろうか?
【勇気】(困難への挑戦) その選択は、面倒や対立を恐れた、安易な逃げになっていないだろうか?
【節制】(長期的な視点) その行動は、目先の感情や短期的な利益に、ふらっと流されていないだろうか?
実践の壁と対策
きっと、こう思われただろう。「緊急の判断を迫られている時に、こんなに悠長に考えてはいられない」と。
うん、その通りだね。まったくもって、その通り。
だから、現実的には二つの使い方を提案するよ。
一つは「ショートカット版」。
もし迷ったら、まず『それは、公正か?』という問い一つだけでも、自分に投げかけてみて。
これだけでも、自分本位な判断に陥るのを、すっと防いでくれるはずだ。
もう一つは「振り返り版」。
大きな判断を下した後で、この4つの視点で「あの時の決断は、どうだったかな」と静かにレビューするんだ。
そうすることで、次の意思決定の精度が、着実に上がっていくから。
思考の型② 自分の憲法を作る「パーソナルコア設定」
私たちは皆、心の中に「自然法」という善への指針を持っている、とトマスは考えたね。このワークは、その普遍的な指針を、あなただけの「個別の指針」として言葉にする試みだ。
いわば、あなただけの「個人憲法」を作るようなものだね。
-
STEP1:書き出す
次の3つの領域について、「自分が心から大切にしたいこと、守りたいこと」を、思いつくままに、ぽつりぽつりと書き出してみて。
-
自分自身に対して(例:心身の健康を損なわない、学び続ける)
-
大切な人々に対して(例:誠実である、相手の可能性を信じる)
-
社会や仕事に対して(例:ごまかしで成果を出さない、専門性で貢献する)
-
-
STEP2:絞り込む
書き出した中から、「もしこれを破ったら、自分自身を裏切ったと深く感じるだろう」と思うほど、自分にとって重要なものを、3つまで絞り込む。
-
STEP3:言語化する
絞り込んだ3つを、自分だけの「パーソナルコア(個人憲法)」として、短い言葉で表現してみよう。(例:「誠実」「成長」「貢献」など)
実践の壁と対策
「価値観が多すぎて、3つになんて、とても絞れない…」と感じるかもしれないね。でも、大丈夫。
完璧を目指さなくていいんだ。
これは一度決めたら変えられない、というような堅苦しいものではなくて、定期的に見直していく「OSのアップデート」のようなものだ。
まずは「ver1.0」を作るくらいの、ラフな気持ちで設定してみて。
この憲法が、あなたが判断に迷った時の、静かで、でも確かな心の指針(軸)になってくれるはずだよ。
思考の型③ 未来から逆算する「目的論プランニング」
これは、人生の究極目標である「幸福」から、現在を照らし出すという、トマスの「目的論」的な考え方を応用したものだ。キャリアや人生の大きな方向性を、ぼんやりとでも見出すのに役立つよ。
-
STEP1:【未来を描く】
「もし、お金、時間、スキル、他人の評価といった、あらゆる制約がなかったとしたら、10年後、どんな状態で、何をしている時に『最高の幸福』を感じるだろうか?」
この問いの答えを、できるだけ具体的に、情景が目に浮かぶくらい鮮明に書き出す。
-
STEP2:【中間地点を置く】
その10年後の未来を実現するために、「1年後には、どんな状態になっていたいか?」という、少し手前の中間目標(マイルストーン)を設定する。
-
STEP3:【今日の一歩を決める】
その1年後の状態になるために、「今週、具体的に始められる、ごくごく小さな第一歩は何か?」を、一つだけ決める。
実践の壁と対策
壮大な目標を立てても、モチベーションが続かず三日坊主で終わってしまう。これは、本当に、誰もが経験することだ。
続けるためのコツは、二つあるよ。
一つは、最初のステップを「5分で終わる作業」にまで、思い切って分解してしまうこと。
もう一つは、その小さな一歩を達成できたら、自分で自分のことを、ちゃんと褒めてあげることだね。
小さな成功体験の、あのじんわりとした温かい感覚。その積み重ねが、やがて大きな目標へと、あなたを運んでくれるはずだよ。
思考の型④ 完璧主義を捨てる「7割思考」
最後に紹介するのは、具体的なツールというより、心構えに近いものだね。
これは、理性の限界を認め、それを超えるものを信頼するという、トマスの成熟した知的態度に基づいている。
その心構えとは、
「複雑な問題に直面したら、7割まではデータや論理で徹底的に考え抜く。けれど、完璧な10割の答えを求めない。残りの3割は、自分の価値観や直感を信じて踏み出す、勇気の領域だ」
と、意識的に割り切ってみることだ。
実践の壁と対策
「論理で説明できない直感で決断するのは、やはり怖い」と感じるよね。その気持ち、よくわかる。
ただ、誤解しないでほしいのは、これは思考停止してヤマ勘で決める、ということとは全く違うということだ。
これは、7割の部分で「考え抜いた自分」を信頼するための、勇気を出す技術なんだ。
もし怖いと感じるなら、まずは今日のランチの店選びのような、失敗しても影響の少ない小さな決断から、この「7割思考」を試してみないかい?
そうやって、少しずつ自分の直感を信頼する練習をしていくのが、良いのかもしれないね。
【この章のポイント】
トマスの思想は、日常で使える4つの具体的な「思考の型」に応用できる。
四元徳チェック:決断の質を高めるための4つの視点。【賢慮】【正義】【勇気】【節制】
パーソナルコア設定:自分の「譲れない軸」を言語化する自己分析ワーク。
目的論プランニング:未来から逆算して、今やるべきことを見つける思考法。
7割思考:完璧主義を捨て、不確実性の中で前に進むための心構え。
まとめ トマスの思想を、あなたの確かな力にするために

ここまで、700年以上も前の哲学者、トマス・アクィナスの思想について、一緒に見てきたね。
彼の思想が、単なる難しい哲学ではなく、現代の私たちが直面する迷いや不安に対する、驚くほど実践的な「思考のシステム」であることが、少しでも伝わっていたら嬉しいよ。
彼の思想を、あの「家づくり」の比喩で振り返るなら、こうなるだろうか。
現実という土台の上に、論理と価値観という方法で、善く生きるための柱を立て、幸福という屋根を目指す。
そして、そのシステムから生まれた具体的な道具として、4つの「思考の型」を紹介したね。
決断の質を高める「四元徳チェック」
自分の憲法を作る「パーソナルコア設定」
未来から逆算する「目的論プランニング」
完璧主義を捨てる「7割思考」
ただ、正直に言っておくね。これらの型を知っただけで、明日から劇的に何かが変わる、というわけではないんだ。
これらの思考の型は、言ってみれば「思考の筋力トレーニング」のようなもの。
最初はぎこちなく、少し面倒に感じるのが当たり前だ。
だけど、不格好でも意識して使い続けることで、それはやがて、いちいち考えなくても自然に使える、あなた自身の「思考の筋肉」になっていくよ。
だから、どうか完璧にやろうとしないでね。
まずは、あなたが最も「しっくりきた」型を一つだけ、週に一度でも意識してみる。
それだけで、十分すぎるほどのスタートだ。
トマスの思想は、あなたに安易な答えを与えてくれるものではない。
しかし、あなたがあなた自身の頭で考え、複雑な世界の中で自分だけの答えを見つけ出すための、最も信頼できる「思考の指針」の一つだ。
この指針が、あなたのこれからの日々を、少しでも確かな、そして豊かなものにする一助となれば、これほど嬉しいことはない。
【この記事のポイント】
トマスの思想は、現代の悩みに応用できる、普遍的で体系的な「思考のシステム」である。
その思想の核心は、「現実」を土台に「論理と価値観」を用いて、「幸福」というゴールを目指す点にある。
彼の思想から生まれた「4つの思考の型」は、日常の意思決定や自己分析、目標設定に役立つ実践的なツールとなる。
これらの型は、意識して使い続ける「思考の筋トレ」によって、初めてあなた自身の確かな力になる。
このサイトでは、こうした古今東西の知恵をヒントにしながら、私たちがこの複雑な世界で、より「豊かに、幸せに生きる」ための考え方や、その具体的な方法について、これからも探求していくよ。
もしよろしければ、またふらりと立ち寄ってみてほしいな。
【こちらの記事も読まれています】



