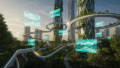なんだか毎日が同じように感じたり、人の言葉にいちいち心がざわついたり。
そんな、言葉にならない「モヤモヤ」を抱えていませんか。
この記事を読めば、あなたの「物の見方」が少しだけ変わり、日常のストレスで消耗することが減って、気持ちが楽になるはずです。
ここでは、難解な哲学を、誰でも今日から実践できる「3つの具体的な方法」として、わかりやすく解説しています。
悩みの本当の原因である、あなた自身の「解釈のクセ」にアプローチしていくので、きっと穏やかな変化のきっかけになりますよ。
よかったら、少しだけ覗いてみてください。
はじめに その日常の違和感、現象学という「新しい視点」で晴れるかも

その言葉にならない「モヤモヤ」、日常を変えるための大切なサイン
朝の満員電車で、窓に映る自分の顔がなんだか無表情だったり。
パソコンに向かってキーボードを叩きながら、ふと「私、このままでいいのかな」なんて考えが、胸をよぎったり。
夜、ベッドの中でSNSを開けば、きらきらして見える誰かの日常と、自分の変わらない毎日を、つい比べてしまったり…。
そんな時、胸のあたりにもわもわと広がる、言葉にならない「モヤモヤ」や、なんとも言えない違和感。
まるで自分だけが、色のない世界に取り残されてしまったような、そんな気持ちになること。
ありますよね。
でもね、その感覚は、決して悪いものではないんですよ。
むしろ、それはあなたの心が「もう、今までの物の見方では満足できないよ」と、そっと教えてくれている、とても大切なサインなんです。
変化の準備が整ったという、ちょっと喜ばしい合図のようなものなのかもしれません。
いつの時代も、人はふと、自分の世界の「当たり前」が色褪せて見える瞬間に立ち会うものです。
それは、魂が新しい景色を求めている、とても健やかな証拠なのだと、私は思います。
この記事が提供するもの あなたの「物の見方」を変える方法を伝えること
私たちの悩みの多くは、実は、起きた出来事そのものではなくて、
それをどう捉えるかという「解釈」から生まれている、
と言われています。
同じ出来事でも、ある人には「絶好のチャンス」に見えて、別の人には「最悪の事態」に見える。
その違いを生んでいるのが、私たち一人ひとりが持っている、独自の「物の見方」というわけです。
この記事でご紹介する「現象学」というのは、その「解釈」、つまりは「物の見方」そのものにアプローチするための、少し変わった、でもとてもパワフルな思考の道具なんです。
もちろん、人生が劇的に変わるような、派手なものではありません。
ですが、昨日と同じ通勤路の景色がほんの少しだけ新鮮に見えたり、人の言葉に心が大きく揺れにくくなったり。
そんな、穏やかで確かな変化を手に入れるための「方法」を、これから具体的にお渡ししていきますね。
いつの間にか曇ってしまっていた「心のメガネ」を、そっと拭いてあげるための特別な布のようなもの。
あるいは、少しピントがズレてぼやけていたカメラのフォーカスを、もう一度、今のあなたに合わせて静かに回してあげるための、ダイヤルのようなものだと考えてみてください。
【この章のポイント】
日常の「モヤモヤ」は、変化の準備が整った大切なサイン。
悩みの多くは「出来事」ではなく、あなたの「物の見方(解釈)」から生まれている。
この記事は、その「物の見方」にアプローチするための具体的な方法を提案します。
現象学とは?あなたの世界を「ありのまま」に見るための哲学
結論 現象学とはあなたの「無意識の色眼鏡」に気づくための思考法
現象学とは、一体なんなのか。
一言でいってしまえば、それは
「自分がどんな”色眼鏡”をかけて世界を見ているかに気づくための思考法」です。
少し、説明させてくださいね。
私たちはみんな、これまでの経験とか、周りの人から教わったことを通して、
「普通はこうだ」
「これは良いこと、これは悪いこと」
といった、自分だけの「色眼鏡」をかけて生きています。
これは、複雑な世界をてきぱきと理解するために、とても役立ってくれるものではあるんです。
ただ、時々その色眼鏡が、知らず知らずのうちに曇ってしまって。
現実をありのままに見えなくさせてしまうことが、どうもあるようなんですね。
例えば、そうですね…「雨の日」を考えてみましょうか。
「雨の日は気分がどんよりする」というのは、多くの人が持っている色眼鏡の一つかもしれません。
でも、一旦その色眼鏡を外して、「ただ、空から水滴が落ちている」という現象そのものに立ち返ってみると、どうでしょう。
窓をぽつぽつと打つ雨音が、なんだか心地よく聞こえたり。
道端の植物たちが、やけに生き生きして見えたり。
いつもとは違う、新しい発見があるかもしれませんよね。
こんなふうに、好き嫌いや善し悪しを判断する前の、まっさらな世界に一度触れてみようじゃないか、というのが現象学の基本的な考え方なんです。
現象学の創始者であるフッサールが生きた時代、科学は「心」でさえも、まるでモノのように客観的に分析しようとしていました。
フッサールはそれに「待った」をかけたのです。
「心が世界をどう体験しているか」という、この主観的で生き生きとした働きそのものを、ありのままに見つめ直そうとした。
それが現象学の始まりでした。彼の有名な合言葉「事象そのものへ」とは、
まさに
「レッテルを貼る前に、まず目の前の”それ自体”を、ありのままに見てみようよ」
という、とてもシンプルな呼びかけなのです。
中心的な考え方「判断中止(エポケー)」を世界一わかりやすく解説
この現象学の心臓部とも言えるのが、「判断中止(エポケー)」という考え方です。
「中止」なんて聞くと、なんだか強い力で無理やり止めるような、少し大変なイメージがあるかもしれません。
でも、本来はもっとずっと優しいニュアンスなんです。
「一旦、保留する」とか、「ちょっと横に置いておく」くらいの、とても穏やかなもの。
好き、嫌い。
正しい、間違っている。
私たちが日常で、本当に無意識に貼り付けている、そういったレッテル貼りを、ほんの少しだけお休みしてみる時間。
そう考えてみてください。
そして、この「判断中止」には、実はもう少しだけ深い意味があります。
それは、好き嫌いといった表面的な判断だけでなく、「目の前の世界は、自分とは関係なく、客観的にそこに存在している」という、私たちが息をするように信じている最も根本的な前提(哲学ではこれを”自然的態度“と呼びます)すら、一旦カッコに入れてみることなのです。
思考を単に横に置くのではなく、「そもそも私は、なぜ世界をこのように見ているのだろう?」と、
その前提そのものを問い直してみる。
それこそが、エポケーの持つ本当の力なんですね。
でも、まずはもっと気軽に、日常の小さな判断を「一旦、保留する」練習から始めてみましょう。
例えば、今あなたの目の前にあるスマートフォン。
私たちはそれを「便利な連絡手段」とか、時として「時間の無駄遣いのもと」なんて、すぐに判断してしまいます。
そうではなくて、練習として、ただその「ひんやりと滑らかな感触」や「画面が放つぼんやりとした光の色」だけを、まるで初めて見る不思議な物体のように、静かに味わってみる。
それが、「判断中止」のささやかな体験です。
【準備運動】まずはこれだけ。1分でできる「ただ、見る」という現象学の練習
理論は一旦さておき、まずは体で感じてみましょう。
これからご紹介するのは、現象学の「準備運動」です。
何かを深く理解することが目的ではなくて、ただ「ああ、こういう感覚か」と味わってもらうためのもの。
成功も失敗もありませんから、どうぞ気楽な気持ちで試してみてください。
【1分間「ただ、見る」練習】
-
対象を選ぶ
机の上のペンや消しゴム、マグカップなど、なんでも構いません。視界に入るものを一つだけ、決めます。
-
時間を計る
スマートフォンのタイマーを、1分間にセットしてみてください。 -
ただ、観察する
タイマーが始まったら、それが何であるかを一旦忘れ、ただその「形」や「色合い」、「光の当たり方」や「影の落ち方」だけを、言葉を使わずに目でじーっと“味わって”みてください。 -
それても大丈夫
途中で「今日の夕飯どうしようかな」なんて、他の考えがふと浮かんできたら、「あ、考えたな」と、それにそっと気づいてあげます。そしてまた、静かに対象に意識を戻す。それで大丈夫なんです。
いかがでしたか。
きっと、普段の1分がとても長く感じたことでしょう。
あるいは、いつも見ているはずの物に、意外な発見があったかもしれません。
どんな体験であっても、それで大成功です。
この「一旦立ち止まり、ただ一つのものに静かに向き合う」という経験こそが、この先、あなたの日常を豊かにしていくための、大切で、確かな第一歩になるのです。
【この章のポイント】
現象学は、科学が見過ごしがちな「主観的な体験」をありのままに見つめ直そうとした哲学。
「判断中止(エポケー)」とは、日常的な判断だけでなく「世界は客観的に存在する」という前提すら保留してみること。
まずは準備運動として、1分間だけ、身の回りのものを「ただ、見る」練習から始めてみましょう。
【実践編】日常が遊び場になる。悩み別「現象学の使い方」3つの方法
さあ、ここからはいよいよ実践編です。
「ワーク」や「トレーニング」なんて考えると、なんだか少しだけ気が重くなってしまうかもしれませんね。
なので、ここでは「日常を使った、ちょっとした実験」あるいは「自分の心を観察するゲーム」くらいの、もっと軽い気持ちで捉えてみてください。
あなたのいつもの日常が、新しい発見に満ちた「遊び場」に変わっていく。
そんな体験の始まりです。
【人間関係の疲れに】言葉のレッテルを剥がす「事実と解釈の分離」という使い方
人の言葉一つで、頭の中がぐるぐると考え事でいっぱいになってしまうこと、ありますよね。
そんな時、この『事実と解釈を分ける』という作業は、ごちゃごちゃになった思考を整理して、感情的になる前に「一呼吸おくためのスペース」を心の中に作ってくれる、とても頼りになる方法です。
「了解です。」
同僚から送られてきた、句点だけの短い返信。
それを見た瞬間、あなたの心に「ああ、何か怒らせてしまったんだ…」という考えが、もわもわと広がる…。
私たちは、日常のこんな些細な出来事で、心が大きく揺れ動いてしまうことがあります。
このワークは、そんな人間関係の疲れを少しだけ楽にするためのもの。
目的は、相手の言動という「事実」と、自分の心が無意識に作り出してしまった「解釈」を、意識的に切り離す練習です。
事件現場に残された「証拠(事実)」と、名探偵の「推理(解釈)」は、全くの別物ですよね。
私たちはつい、自分の推理を、まるで確定した事実かのように扱ってしまう癖があるのです。
【心のプロセスを図で見てみよう】
| 出来事(事実) | → | あなたの色眼鏡(解釈・思い込み) | → | 感情(モヤモヤ) |
| 例:「了解です。」という返信 | → | 「きっと怒っているに違いない」 | → | 不安・焦り |
この「色眼鏡」の存在に気づき、別のメガネをかけ直してみるのが、このワークの狙いというわけですね。
「事実と解釈」を分ける3ステップ
-
「モヤっとメモ」を作る
まず、心がざわついた出来事を、ノートやスマホのメモにありのまま書き出してみましょう。「〇〇さんに〜と言われて、悲しかった」というように、感情も一緒に書いてしまって大丈夫です。
-
「事実」と「解釈」に色分けする
次に、書き出した文章に、色ペンなどで印をつけていきます。-
事実 誰が見ても「そうだ」とわかる客観的なこと。(例:「〇〇さんが『了解です。』と返信した」)
-
解釈 自分の感情や憶測、思い込み。(例:「私は悲しかった」「きっと怒っているに違いない」)
-
-
「もしもBOX」を考える
最後に、事実だけを眺めながら、こう自問自答する「遊び」をしてみます。「もし、私の最初の解釈が、全くの間違いだとしたら。他にどんな可能性があり得るだろう?」
-
「ただ単に、すごく忙しかっただけかも?」
-
「スマホの調子が悪くて、それしか打てなかったのかも?」
-
「句点をつけるのが、その人のただの癖なのかも?」
-
このゲームの目的は、ポジティブな解釈を見つけることではありません。
「これだ!」という正解を探す必要もないのです。
ただ、自分の最初の解釈が、唯一絶対の真実ではなかった、と気づくこと。
あなたの心が作り出す物語は、一つである必要はない。
そう知るだけで、人の言葉に過剰に振り回されることが、少しずつ、本当に少しずつですが、減っていきますよ。
【日常の退屈さに】視点をズラして世界と遊ぶ「もしもゲーム」という現象学の方法
毎日通る道、毎日見るスマートフォンの画面、毎日会う人…。
いつからか、私たちの世界は「見慣れたもの」で埋め尽くされ、少しだけ色褪せて見えてしまうことがあります。
このゲームの目的は、凝り固まった「自分」という視点から心をふわりと解放し、世界に隠された無数の面白さを再発見すること。
いつもの日常を、あなただけのテーマパークに変えてしまう。
そんな、壮大な「ごっこ遊び」の始まりです。
【「もしもゲーム」のお題リスト】
-
『観光客ごっこ』
「もし、自分が初めてこの街に来た外国人観光客だったら?」という視点になって、いつもの通勤路を歩いてみてください。コンビニの商品棚や、駅の案内表示、道端のマンホールの蓋まで、すべてが興味深い観察対象に見えてくるかもしれません。
-
『カメラマンごっこ』
「もし、自分が世界的な写真家だったら?」という気持ちで、日常の風景を眺めてみましょう。壁のシミやアスファルトのひび割れ、木漏れ日の光と影のコントラストなど、「これは作品になる」と感じる美しい瞬間を探してみるのです。
-
『虫さんぽ』
たまには、視点をぐっと下げてみましょう。「もし、自分が小さなアリだったら?」と想像しながら、公園を散歩してみる。
普段は気にも留めない石ころが巨大な岩に見えたり、タンポポが太陽の塔のように見えたり、世界が全く違うスケールで立ち現れてくるはずです。
このゲームに、正解や不正解はありません。
「こんなことして、何の意味があるんだろう?」なんて考え始めたら、思考の罠にはまっているサイン。
むしろ、少しバカバカしいと感じるくらいが、ちょうどいいのです。
世界がつまらないのではありません。
ただ、私たちの見方が、少しだけ凝り固まってしまっているだけ。
この「もしも」という小さな問いかけは、そんな心のストレッチのようなもの。
そして、あらゆる発明や芸術も、最初はこうした「もしも」から始まったことを、心のどこかで覚えておいてくださいね。
【頭の中の混乱に】思考を止め五感を研ぎ澄ます「感覚フォーカス」という使い方
夜、ベッドに入ってから頭の中のスイッチがオフにできず、同じ考えがぐるぐる回り続けてしまう…。
本当に、疲れてしまいますよね。
そんな時、この『ただ、何かを眺める』という単純な行為は、その思考のボリュームを、ほんの少しだけ下げてくれるような働きをします。
一旦、脳をリセットするような、そんな感覚に近いかもしれません。
この方法は、意識のスポットライトを、頭の中のざわめき(思考)から、あなたの身体(感覚)へと、そっと移してあげるためのものです。
思考は、過去や未来へと自由にタイムトラベルできる、少しやんちゃな旅人のようなもの。
一方、感覚は、常に「今、この瞬間」にしか存在できない、とても実直な案内人です。
道に迷ってしまった時は、この実直な案内人の声に、静かに耳を澄ませてみるのが一番ですよ。
【「いつでも、どこでも」できる実践リスト】
-
お茶を飲む時
最初のひと口だけでいいのです。カップを持つ手の温かさ、鼻に抜ける香り、舌の上に広がる温度と味わい。
その感覚だけに、全神経を集中させてみてください。
-
手を洗う時
水の冷たさや、石鹸の泡のなめらかな感触、タオルが肌に触れる感覚。普段は無意識に行っている行為の一つひとつを、丁寧に味わってみましょう。
-
歩く時
スマートフォンをポケットにしまい、30秒だけで構いません。風が頬をなでる感覚、地面を踏みしめる足の裏の感覚、遠くから聞こえてくる車の音。
ただ、それを感じてみるのです。
もし、実践の途中で考え事を始めてしまっても全然OK。
「あ、思考の旅が始まっていたな」と、それに気づいてあげるだけで十分です。
そしてまた、そっと、あなたの身体という「今」に戻ってきてあげる。
その優しい繰り返しが、何よりも素晴らしい練習なのですから。
【この章のポイント】
人間関係の疲れには、ノートを使って「事実」と「解釈」を分けてみる。
日常の退屈さには、「もしも〜だったら?」と視点を変えて遊んでみる。
頭の中の混乱には、思考から離れ、お茶を飲むなどの「身体の感覚」に集中してみる。
【少し深い話】なぜ私たちは、現象学が示す「当たり前の世界」から抜け出せないのか
ここまでの実践編、お疲れさまでした。
ここからは少しだけ、視点を変えてみましょうか。
そもそも、なぜ私たちは「思い込み」や「当たり前」といった、自分だけの物の見方に、これほどまでに強く囚われてしまうんでしょうね。
その理由を少しだけ深く知ることで、自分自身に対する見方が変わり、心がもう少し、楽になるかもしれません。
(筆者の視点)人間が「思い込み」を好む理由
不思議だと思いませんか。
私たちは時に、目の前にあるはずの真実よりも、慣れ親しんだ「思い込み」の方を、かたくなに信じて、なかなか手放そうとしないのです。
思うに、思い込みというのは、人間がこの複雑で、時に予測不可能な世界を生き抜くために編み出した、一種の「心の安全基地」のようなものなのでしょう。
「こういう時は、こうすればいい」
「あの人は、きっとこういう人だ」。
そうやって世界を瞬時に判断し、分類することで、私たちは大きな混乱なく、安心して日常を送ることができている。
それは、私たちの祖先から脈々と受け継がれてきた、生きるための立派な知恵なのだと思います。
ただ、問題は、その安全基地が、いつしか自分を縛る「快適な牢獄」になってしまうことがある、
ということ。
世界は変わり、あなた自身も日々、少しずつ経験を重ねて変化していく。
その中で、かつては自分を確かに守ってくれたその壁が、新しい景色を見るのを妨げてしまうことがあるんですね。
あなたが感じている日常のモヤモヤは、あなたの心が、その壁の存在にうっすらと気づき始めた、とても大切な証拠なのです。
だから、現象学は「その壁を、今すぐ壊してしまいなさい」なんて、そんな乱暴なことは言いません。
ただ、「少しの間だけ、ドアを開けて、外の新鮮な空気を吸ってみませんか」と、優しくあなたを誘うだけ。
それは、自分の安全基地を完全に捨てることではありません。
むしろ、これまで自分を守ってくれたその存在に感謝しつつ、もう一度、世界と新鮮な関係を結び直すための、ささやかな儀式のようなもの。
私は、そう考えています。
SNS時代の日常で「自分の感覚」を取り戻すという、現象学の重要な役割
特に、私たちが生きる現代において、この「思い込み」の問題は、少し形を変えて現れてきているように感じます。
スマートフォンを開けば、他人の「楽しかった!」「美味しかった!」という、鮮やかに加工された「解釈済みの世界」が、洪水のように私たちの目に流れ込んできますよね。
その結果、何が起きるか。
私たちはいつしか、自分の内側からじんわりと湧き上がる純粋な体験
…例えば「ただ、夕日が綺麗だと感じた」という、誰にも評価されない名もなき感覚よりも、
他人から「いいね」という承認を得られた解釈の方に、より価値があるかのように錯覚してしまうのです。
それは、自分だけの「感覚」という、人生の豊かさの源泉を、いつの間にか他人の手に明け渡してしまっているようなものかもしれません。
現象学の「判断中止」は、この「いいね」がつく前の、誰にも評価される前の、あなただけの純粋な感覚の世界に立ち返るための、強力なトレーニングになります。
誰かの解釈ではない、あなたの身体で感じたこと。
それこそが、あなたの人生における唯一無二の「一次情報」であり、誰にも奪うことのできない、豊かさの源泉なのだと。
現象学は、その当たり前で、でもつい忘れがちな事実を、そっと、でも力強く思い出させてくれるのです。
注意点 現象学という哲学の道具に「振り回されない」ための大切な心構え
ただ、最後に一つだけ、大切な注意点をお伝えさせてください。
どんなに優れた道具も、使い方を誤れば、自分を傷つけてしまうことがあります。
現象学も、その例外ではないのです。
現象学に傾倒しすぎた結果、陥ってしまう可能性のある罠。
それは、
「観察者としての自分」に閉じこもってしまうことです。
あらゆることを「判断中止」しているうちに、現実の出来事に感情移入できなくなり、まるで他人事のように、自分の人生をただぼんやりと眺めているだけになってしまう…。
喜びも、悲しみも、どこか遠い世界の出来事のように感じられる。
「考えすぎて、動けないし、感じられない」という状態ですね。
これを避けるために、どうか覚えておいてください。
大切なのは、現象学は人生から「判断」をなくすための哲学ではない、ということです。
むしろ、これまで無意識に、自動的に下していた判断を、より丁寧に、納得感をもって下せるようになるために、一旦立ち止まるための知恵なのです。
私たちは、航海の途中で港に立ち寄り、船を整備し、心の指針となる羅針盤を確認しますよね。
判断中止とは、その「心の港」に、ちょっとだけ立ち寄る時間のようなもの。
ずっと港に留まるために、私たちは生きているわけではないのですから。
十分に休息をとり、自分の現在地を確認したら、また新しい航海へと、安心して出発していいのですよ。
【この章のポイント】
「思い込み」は、世界を生き抜くための「安全基地」だが、時に自分を縛る「牢獄」にもなる。
SNS時代だからこそ、他人の解釈に惑わされず、自分の純粋な「感覚」を取り戻すことが重要。
現象学は、判断をなくすためではなく、より良い判断のために「一旦立ち止まる」ための知恵。
【深掘り】現象学の理解がグッと深まる、他の哲学・心理学との関係性
ここまでの話で、現象学がどのようなものか、少しずつ体感していただけたかもしれませんね。
この章では、あなたが既に知っているかもしれない他の考え方と現象学を比べることで、その輪郭をよりはっきりとさせていきたいと思います。
少しだけ専門的な話も入りますが、あなたの知的好奇心を満たす、面白い発見がきっとあるはずですよ。
アドラー心理学「課題の分離」との決定的な違いとは?
人間関係の悩みを軽くする、という点で、アドラー心理学の「課題の分離」を思い浮かべた方もいるかもしれません。
うんうん、確かに、どちらも私たちの心を楽にしてくれる素晴らしい知恵ですが、アプローチする「深さ」が少しだけ違うんですね。
まず、「課題の分離」とは、とてもシンプルに言えば、これは「自分の課題」、そしてそれは「相手の課題」と、心の中に境界線を引くことです。
「相手が自分のことをどう思うか」は相手の課題であって、自分にはコントロールできない。
だから、そこに踏み込みすぎず、自分の課題に集中しましょう、と考える方法です。
これは、人間関係のごちゃごちゃを整理する上で、非常に強力な考え方だと思います。
一方、現象学は、その「境界線を引く」という判断すら、一旦保留にしてみます。
そして、もっと手前の地点に立ち返り、「そもそも私は、この状況をなぜ”人間関係の問題”だと捉えているんだろう?」と、自分がその状況全体に貼り付けている意味そのものに、静かに光を当てるのです。
もし、人間関係を「もつれた糸」に例えるなら、こんな風に言えるかもしれません。
-
課題の分離は、自分の糸と相手の糸を丁寧に見分け、「これは自分の糸、これは相手の糸」と、糸を分類しようとする試みです。
-
現象学は、「そもそも、なぜ私はこれを”もつれている”と感じるのだろう?」と、その糸を見つめる自分の「視線」そのものに気づこうとする試みなのです。
どちらが優れているという話ではありません。
状況に応じて使い分けることで、私たちの心は、より自由になれるはずです。
マインドフルネスとの共通点「判断しない」がもたらす心の静けさ
もし、これまでの実践編を試す中で、「なんだか、これはマインドフルネスに似ているな」と感じたなら、その感覚はとても鋭い!
実際、近年注目されているマインドフルネスは、現象学の哲学的な思想と、とても近い場所にいる親戚のようなもの、と言えるでしょう。
両者をつなぐ最も重要なキーワードが、
「ノンジャッジメンタル(non-judgmental)な態度」です。
日本語にすれば、「判断をしない態度」となりますね。
良い・悪い、好き・嫌いといった評価や判断を挟まずに、ただ、今ここで起きていることを、ありのままに観察する。
その態度が、両者の共通する核心部分です。
哲学者の鷲田清一氏は、私たちは常に何かを「仕事モード」や「親モード」といった特定の「モード」で世界を見ている、といった趣旨の議論を展開しています。
マインドフルネスや現象学の実践は、そうした特定のモードに無意識に囚われている自分自身に気づき、そこからふっと自由になるための、貴重な時間を与えてくれるのです。(参考:鷲田清一『「聴く」ことの力―臨床哲学試論』)
次々と湧き上がる思考や感情の嵐に巻き込まれてしまうのではなくて、それを静かに眺めることができる「心の安全な場所」。
両者が目指すのは、そうした穏やかな境地を、私たちの日常の中に見出すこと、と言えるでしょう。
【専門家の知見】心理学が解き明かす「脱中心化」という現象学の効果
そして、現象学がもたらす心の変化は、ただの気休めや精神論ではありません。
実は、現代の臨床心理学によっても、その効果が科学的に裏付けられ始めているんです。
そのキーワードとなるのが、「脱中心化(Decentering)」という考え方です。
これは少し専門的な言葉ですが、簡単に言えば、
「自分の思考や感情を『自分そのもの』と一体化させるのではなく、『ただ心に浮かんだ、一時的な現象』として客観的に眺められるようになること」
を指します。
例えるなら、こういう感覚に近いかもしれません。
これまでは、自分が映画の登場人物としてスクリーンの中で一喜一憂していた。
それが、ふと客席に座って、「ああ、今スクリーンでは、こういうストーリーが展開しているんだな」と、少しだけ距離を置いて映画を観られるようになる感覚です。
「判断中止(エポケー)」の実践は、まさにこの「脱中心化」の能力を、私たちの心の中に育むための、最高のトレーニングなんですね。
自分のネガティブな解釈を「絶対的な真実だ」と見なすのをやめ、「ああ、今、自分はこんな風に解釈しているな」と、ただ眺めてみる。
この心の動きそのものが、脱中心化に他なりません。
特に、マインドフルネス認知療法(MBCT)などの分野では、この「脱中心化」がうつ病の再発予防に有効であるという研究成果が数多く報告されています。
何百年も前に生まれた古い哲学の知恵が、今、科学の言葉で、その正しさを改めて証明され始めている。
なんだか、とても興味深いことだと思いませんか。
【この章のポイント】
アドラー心理学が「境界線を引く」のに対し、現象学は「なぜそう見るのか」と視線そのものに気づこうとする。
マインドフルネスとの共通点は「判断しない態度」。どちらも心の静けさを目指す。
現象学の効果は心理学の「脱中心化」という概念で説明でき、科学的にも裏付けられている。
【Q&A】現象学と歩むあなたの「ちょっとしたつまずき」に寄り添います
ここまで読み進めてくださったあなたなら、もしかしたら早速、日常の中でいくつかの実践を試してくれているかもしれませんね。
そして、実践してみたからこそ生まれる、新しい疑問や「これでいいのかな?」という小さな不安も、きっとあることでしょう。
この章では、そんなあなたの「ちょっとしたつまずき」に、一つひとつ丁寧に寄り添っていきたいと思います。
Q1. すぐに「好き・嫌い」と判断してしまいますが、ダメでしょうか?
その感覚、素晴らしい気づきです。
そして、その答えは、全く「ダメ」ではありません。
むしろ、それはあなたが現象学をきちんと実践できている、何よりの証拠なのですよ。
少し意外に聞こえるかもしれませんね。
現象学の目的は、「判断」という心の働きを、この世からゼロにすることではないのです。
私たちは、朝起きてから夜眠るまで、息をするように何かを判断し続けています。
好き嫌いのない人間になるのが、ゴールではありませんから。
大切なのは、「あ、今わたしは”好き”と判断したな」とか、「無意識に”ダメだ”とレッテルを貼ったな」と、
その、判断している自分自身に、ほんの一瞬でも気づくことなのです。
空に雲が浮かんでくるのは、ごく自然なことですよね。
私たちの心に浮かぶ判断や感情も、それと全く同じ。
雲一つない完璧な青空を、無理に目指す必要はありません。
ただ、「あ、雲が出てきたな」と、その雲の存在に気づいて、静かに眺めてあげる。
その優しい眼差しこそが、現象学的な態度そのものなのです。
ですから、もし「また判断してしまった…」と自分を責めそうになったら、その代わりに、「お、また気づけたじゃないか、自分」と、心の中で軽くガッツポーズでもしてみてください。
それだけで、あなたの練習は、もう100点満点です。
Q2. フッサールなどの哲学書を読まずに、この方法を実践できますか?
はい、全く問題ありません。
というより、むしろ、今はまだ哲学書を読まずに始めることを、私は強くお勧めします。
なぜなら、現象学は、頭で理解する難しい学問である前に、何よりもまず、あなたの体と心で「体験」する、とても個人的な実践だからです。
それは、水泳の教科書を何十冊も完璧に読み込むよりも、一度でいいから、そっと水の中に入ってみる方が、水というものが何であるかがわかるのと、少し似ていますね。
この記事でご紹介している様々な方法は、難解な哲学理論の広大な海の中から、誰もがすぐに味わえる「美味しいエッセンス」だけを、丁寧に取り出してきたようなものです。
ですから、まずはこのエッセンスを、あなたの日常の中で、じっくりと味わってみてください。
そして、もし実践を続ける中で、心の奥から「この不思議な感覚の、もっと奥にある源流には、一体何があるのだろう?」という知的な好奇心が湧いてきた時。
その時こそが、分厚い哲学書を手に取る、絶好のタイミングです。
でもまあ、知識だけなら今の時代、ネットで調べれば出てきますからね。
どんな方法でもOK!
きっとその時には、難解に見える言葉の奥にある宝物を、あなた自身の体験と照らし合わせながら、一つひとつ発見していくことができるはずですよ。
Q3. 現象学の効果を実感できるまで、どれくらいの期間が必要ですか?
これも、とても大切な質問ですね。
「効果」をどう定義するかにもよりますが、もし「あ、少しだけ世界の見え方が変わったかも」という、ささやかな変化のことを指すのであれば、その答えは「この記事を読んだ、5分後にでも訪れる可能性があります」となります。
現象学の効果には、大きく分けて二つの種類がある、と私は考えています。
一つは、「瞬間の効果」です。
例えば、先ほどご紹介した「感覚フォーカス法」を試した後の、頭の中がすーっと静になる、あの感覚。
これは、実践すればすぐに味わえる、即時的な効果と言えるでしょう。
そしてもう一つが、「蓄積の効果」です。
より大きな変化、例えば、人間関係で悩む時間が明らかに減ったり、自分の感情の波に簡単に飲み込まれにくくなったり、といった変化は、日々のささやかな実践の「蓄積」によって、数週間から数ヶ月という時間をかけて、ゆっくりと、しかし確実に現れてきます。
それは、庭に花の種をまく作業に、少し似ているかもしれません。
すぐに立派な花が咲くわけではありません。
でも、毎日少しずつ、忘れずに水をやり続けていれば、ある晴れた日の朝、ふと、地面から可憐な芽が顔を出していることに気づく。
現象学の実践とは、そんな風に、自分の心に毎日優しく水をあげ続けるような行為なのです。
ですから、どうか焦らないでくださいね。
何かを「達成」することよりも、日常の中に「ちょっと立ち止まって、自分の心と世界に耳を澄ます時間」を持つ。
その習慣自体が、もうすでに、あなたの人生を静かに、豊かにしてくれているのですから。
【この章のポイント】
判断してしまう自分に気づけたら、それで100点満点。判断をゼロにするのが目的ではない。
哲学書は読まなくて大丈夫。まずは自分の体と心で「体験」することが何よりも大切。
効果には「瞬間の効果」と「蓄積の効果」がある。結果を焦らず、続けること自体を楽しんでみて。
まとめ 明日からの日常が”少しだけ”違って見える、現象学という哲学のはじめの一歩

現象学とは、「日常への優しい眼差し」そのもの
現象学とは結局のところ、フッサールがどうだとか、判断中止がどうだとか、そういった難しい哲学用語の集合体ではないのです。
それはただ、自分の心と、目の前の世界に対して、ほんの少しだけ丁寧で、優しい眼差しを向けてみよう、という、とてもシンプルで、温かい呼びかけのようなもの。
私たちは今日、そのためのいくつかの練習をしてきましたね。
好き嫌いをすぐに判断してしまう自分に気づき、「そうかそうか」と、ただそうっと見守ってあげること。
見慣れた通勤路の中に、隠された面白さを見つけようと、少しだけ遊んでみること。
一杯のお茶がもたらしてくれる、ささやかな温かさに、心を澄ませてみること。
その一つひとつが、他の誰でもない、あなたからあなたの日常に向けられた、「優しい眼差し」そのものなのです。
そして、どうか忘れないでください。
この眼差しは、誰かから新しく与えられるものではありません。
この記事を読む前から、ずっと、ずっとあなたの心の中にあったものです。
私たちはただ、そのかけがえのない存在を思い出すための、小さなきっかけをご一緒したに過ぎないのですから。
最後に提案 あなたの「当たり前リスト」を作るという、最高の現象学の使い方
さて、最後に一つだけ。
あなたのこれからの人生にとって、きっと静かな宝物になるであろう「遊び」を、提案してもよろしいでしょうか。
それは、「あなたの当たり前リスト」を作ってみる、というものです。
やり方は、とても簡単です。
ノートの新しいページを開いて、一番上に、こう書いてみてください。
「私が”当たり前”だと思っていること」
そして、思いつくままに、自由に書き出してみるのです。
難しく考える必要は、全くありません。
-
「毎朝、同じ時間に目が覚めること」
-
「蛇口をひねれば、水が出ること」
-
「コンビニで、いつでも好きなものが買えること」
-
「空が、青いこと」
-
「あの人は、きっと私のことをこう思っているだろう、ということ」
…いかがでしょうか。
このリストに書き出されたものこそ、あなたが今、無意識にかけている「色眼鏡」の正体であり、あなたがこれまで学んできた「判断中止」を試してみるべき、格好の対象です。
それに気づき、自分の手で書き出し、客観的にリストとして眺めてみるという行為。
それこそが、この記事でお伝えしてきた中で、最もシンプルで、そして最もパワフルな現象学の使い方なのです。
そのリストは、今のあなたの世界を形作っている、一枚の、大切な設計図のようなものです。
そして、一度その設計図を、自分の目で静かに眺めてみることができたなら。
私たちはもう、その設計図の言いなりになる必要はありません。
どの線を、ほんの少しだけ書き換えてみるか。
どの部分に、今までとは違う新しい色を塗ってみるか。
その選択は、いつだって、あなたの自由です。
あなたの明日が、昨日とはほんの少しだけ、違って見えることを。
心の底から、願っています。
【こちらの記事も読まれています】

【この章のポイント】
現象学の本質は、難しい理論ではなく「日常への優しい眼差し」を向けること。
最後の実践として、自分が「当たり前」だと思っていることをリストアップしてみよう。
そのリストに気づくことこそが、自分の世界を自由に描き変えていく、はじめの一歩となる。
【大切なお知らせ】
この記事は、哲学的な考え方を日常に活かすためのヒントを提供するものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。
心の不調が長く続く場合や、深刻な悩みを抱えている場合は、決して一人で抱え込まず、専門の医療機関やカウンセリングにご相談ください。
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。
このブログでは、こうした「物の見方」を変えることを通して、日常を少しでも豊かにしたり、幸せに繋がるための様々な考え方を、これからも探求していきます。
もしご興味があれば、他の記事も覗いてみていただけると、とても嬉しいです。