「何のために頑張ってるんだろう…」
ふと心が虚しくなる、あの、どうしようもなくしんどい気持ち。
しんどいですよね。
この記事を読めば、その虚しさが、明日を少しだけ楽にする「力」に変わる、その確かなきっかけが掴めるはずです。
ここでは、虚しさの正体である「ニヒリズム」を敵と見なさず、むしろ味方につけてしまうための、具体的で、すぐに試せる「3つの思考の道具」を、誰にでも分かるように解説します。
難しい哲学の知恵を、あなたの日常で使えるように優しく紐解いていきます。
一緒に、その虚しさと上手に付き合っていく方法を、見つけにいきましょう。
あなたの虚無感の正体は?現代社会に広がる「ニヒリズム」の基本

「ニヒリズム(虚無主義)」とは何か?【虚無主義との違いを3分で解説】
「どうせ意味ないし」
「頑張ったって、ねぇ…」
そんな風に、ふとした瞬間に心がすーっと冷めてしまう感覚。その感覚の正体、それが「ニヒリズム(虚無主義)」と呼ばれる考え方かもしれません。
なんだか難しそうな響きですけど、その核心は、実はとてもシンプルなんです。
一言でいうと、
「絶対的な“物差し”や“みんなが信じる正解”が、この世界にはもう無いんじゃない?」
という、少し乾いた考え方のことです。
昔の時代には、多くの人が信じる「神様」であるとか「お国のため」みたいな、絶対的な価値がありました。
それが、人生の大きな道しるべになっていたんですね。
でも、時代が進むにつれて、そうした大きな指針が少しずつ揺らいでいった。
哲学者のニーチェという人が「神は死んだ」と言ったのは、まさにそういう時代の空気の変化を告げる言葉でした。
彼が生きた19世紀のヨーロッパでは、産業革命や科学の発展によって、それまで人々を固く結びつけていた宗教や伝統の力が、急速に揺らぎ始めていました。
そんな時代の大きな変化を、彼は敏感に感じ取っていたのです。
みんなが信じていた大きな物語が終わってしまって、
一人ひとりが
「…で、何を信じて生きていけばいいの?」
と、だだっ広い野原にぽつんと立たされている。
あぁ、この感覚、現代に生きる私たちの状況に、なんだかとても近い気がしませんか。
で、よく似た言葉に「厭世主義」ってのがあるんですが、これらは少しだけニュアンスが違うんです。
| 名称 | 特徴 |
|
ニヒリズム(虚無主義) |
「絶対的な価値はないよね」という、結構ニュートラルな認識・思想。 |
| 厭世主義 | この世は苦しいことばっかりだから「関わりたくないな…」という、世の中に対する“態度”。 |
見ての通り、ニヒリズム(虚無主義)って、必ずしも絶望とイコールじゃないんですよね。
それはむしろ、「古い地図がもう使えなくなったらしい」という、ただの事実認識。
だからこそ、新しい地図を自分で描けるっていう“始まりの可能性”も秘めた、意外とフラットな地点なんです。
あなたはどっち?諦めの「受動的ニヒリズム」と可能性の「能動的ニヒリズム」
その「絶対的な価値がない」という、だだっ広いフラットな地点から、私たちはどっちへ向かうんでしょうか。
そこにはね、大きく分けて二つの道があるんです。
一つは、「受動的ニヒリズム」の道。
これは、「どうせ何をやっても無意味だ」って、ただ立ち尽くして、無気力や諦めに心をゆだねてしまう状態のことですね。
何を見ても心が動かず、新しいことを始める気力も湧いてこない。
世界がまるで、ざらざらした質感の、古いモノクロ映画のように見えてしまう。
多くの人が「ニヒリズム(虚無主義)」と聞いてイメージするのは、たぶん、こっちの状態でしょう。
うん、しんどいですよね。
そして、もう一つが「能動的ニヒリズム」の道です。
これは、「絶対的な価値がない? 最高じゃないか!」って、その状況をむしろ面白がっちゃうような、ちょっと力強い生き方です。
古い建物が全部なくなった焼け野原を見て絶望するんじゃなくて、「よーし、ここにどんな新しい街を建ててやろうかな」ってワクワクするような感覚。
伝わりますかね。
誰かが決めた正解がないからこそ、自分の「好き」とか「心地いい」を基準にして、全く新しい価値を自分で創り出していける。
それが、能動的ニヒリズムが秘めている、すごい可能性なんです。
今のあなたは、どちらの道に、心が少しだけ傾いている感じがしますか。
もし、「あぁ、自分は完全に受動的だ…」と感じたとしても、全く心配いりません。
というか、ほとんどの人が、まずそこから始まりますから。
この記事は、その場所から、もう一つの道へとふらっと散歩に出てみるための、一枚の地図のようなものです。
一緒に、のんびりいきましょう。
【この章のポイント】
ニヒリズムとは「絶対的な物差しがない」という考え方で、現代ではごく自然な感覚なんです。
それは単なる絶望じゃなく、「新しい始まり」の可能性も秘めています。
ニヒリズムには、無気力に陥る「受動的」な道と、新たな価値を創る「能動的」な道の二つがあるんですね。
なぜ虚しい?現代人がニヒリズムに陥る3つの構造的な原因

さて、前の章でニヒリズム(虚無主義)っていうものの輪郭が、なんとなく見えてきましたかね。
じゃあ次に、もう一歩だけ、深く掘り下げてみたいと思うんです。
それは、「…なんで、私たちはこんなに虚しい気持ちになりやすいんだろう?」っていう、とても素朴な問いです。
実はその原因って、あなたの心の中だけにあるわけじゃないんですよ。
むしろ、私たちが毎日、当たり前のように吸い込んでいるこの社会の「空気」そのものに、深く、ふかーく、関係しているんです。
「あぁ、なんだ、私のせいだけじゃなかったのか」
原因が分かると、漠然とした不安の正体がはっきりして、それだけで少しだけ、気持ちが楽になるはずです。
一緒に、その空気の正体を覗いてみましょうか。
原因① 情報が多すぎて「自分の正解」が選べない【価値観の多様化】
昔はね、人生にはある程度の「モデルルート」みたいなものがあったんです。
良い学校を出て、安定した会社に入って、素敵な家庭を築く…。
それが多くの人にとっての「幸せ」の、分かりやすい形でした。
でも、現代はどうでしょう。
生き方は、それこそ星の数ほどあって、何が「正解」かなんて、もう誰にも分かりません。
一見すると、これは素晴らしい「自由」ですよね。
でも、その裏側で、私たちは「常に、自分で、正解を選び続けなきゃいけない」っていう、見えないプレッシャーに、ずーっと晒されているんです。
心理学に「決定麻痺」っていう言葉があるんですけど、
これは、
選択肢が多すぎると、人はかえって何も選べなくなって、選んだ後の満足度まで下がっちゃう、
っていう現象のことなんです。
なんか、贅沢な悩みなんですけどね。
どの道もキラキラして見えるし、同時に、どの道も不安だらけに見える。
うんうん唸って考えあぐねた結果、「…あーもう、どうでもいいや」って、全部放り出したくなっちゃう。
これこそが、豊かさの中で生まれる現代的な虚無感の、一つの大きな原因なんですね。
これは、あなたの気のせいなんかじゃありません。
例えば、内閣府の「国民生活に関する世論調査」を見ても、社会が物質的に豊かになったからといって、人々の生活満足度がずっと上がり続けているわけではない、ということが示されています。
私たちはまるで、
豪華すぎる料理がずらーっと並んだビュッフェで、お皿を持ったまま「どれを取るのが一番コスパいいかな…」なんて考え続けて、結局何も食べられずにお腹を空かせている。
そんな、ちょっと笑えない状況にいるのかもしれません。
原因② SNSがもたらす「相対的な不幸感」と承認欲求の罠
朝、目が覚めて、最初に手に取るものって、何ですか?
もしそれがスマートフォンなら、きっと無意識に、青い鳥とか、カラフルなカメラのアイコンを開いているんじゃないでしょうか。
SNSは、世界中の人々と繋がれる、本当に便利なものです。
でも、その本質を別の角度から見てみると、
「世界中の人々の“人生で最も輝いているキラキラした瞬間”を、24時間、強制的に浴び続ける装置」
とも言えるんです。
友人の結婚報告。
同僚の海外旅行。
誰かの、ものすごい成功体験…。
私たちはそこで、他人の人生の、きらびやかな「予告編」ばかりを、延々と見せられている。
そして、自分の、特に何も起きない日常という「本編」とを、無意識のうちに、いちいち比べてしまう。
もちろん、頭では分かってるんですよ。
みんな、良いところだけを切り取って、上手に見せてるんだって。
でも、心って、そんなに器用じゃないんですよね。
毎日毎日、そんな光のシャワーを浴び続けていれば、自分の人生がなんだか、色あせて見えてくるのも、…あぁ、無理はないことですよね。
総務省の調査なんかを見ても、多くの人がSNSから精神的な疲れ、いわゆる「SNS疲れ」を感じている、というデータがあります。
SNSの「いいね」は、まるで心の栄養ドリンクみたいです。
ぽちっと押されると、一瞬で承認欲求が満たされて、シャキッと元気になる。
でも、その効果は驚くほど短くて、すぐにまた次の「いいね」が欲しくなってしまう。
この、喉が渇いて塩水を飲むような果てしないループが、私たちの心を静かに、確実にすり減らして、深い虚無感へと繋がっていくんです。
原因③ 結果ばかりを求められ「今」を味わえない効率主義の浸透
「タイパ(タイムパフォーマンス)」とか、「生産性」とか、そういう言葉を、もう聞かない日はないですよね。
私たちはいつの間にか、あらゆる行動に「目的」とか「意味」とかを、求めるようになっていないでしょうか。
読書は「知識を得るため」。
散歩は「健康のため」。
友達と会うことさえ「有益な情報を得るため」。
何かの「ため」じゃなくて、
ただ、それ自体を楽しむっていう、純粋な時間が、どんどん私たちの生活から失われていく。
まるで、人生そのものが、一つひとつチェックして消していくべき「タスクリスト」になってしまっているかのよう…
もちろん、目的を持つことは大切ですよ。
でもね、そればかりを追い求めていると、そこに至るまでの道のりが、全部ただの「作業」になっちゃうんです。
そして、もしその目的が達成できなかったり、そもそも目的自体を見失ったりした時に、
「…今までやってきたことって、全部、無駄だったじゃん」
という、ものすごく強烈な虚無感に、どーんと突き落とされることになる。
本当はね、
目的のない時間、一見すると「無駄」に見える時間にこそ、私たちの心が本当に求めている豊かさって、隠れているのかもしれないんです。
友達と、本当に中身のない話をして、お腹を抱えて笑い合う時間。
ただぼーっと、窓の外をだらだらと流れていく雲を眺める時間。
そういう時間を取り戻すことが、この効率主義の社会で虚しさを感じずに生きていくために、実は、ものすごく大切なことなんじゃないかなって、私は思うんです。
【この章のポイント】
あなたの虚しさは、個人的な弱さというより、現代社会の構造的な問題が原因であることが多いんです。
多すぎる情報と選択肢が、私たちを「決められない…」という決定麻痺に陥らせます。
SNSは、他人のキラキラした部分との比較で、「相対的な不幸感」を生み出しやすい構造なんですね。
効率主義は、「今、ここ」を味わう喜びを奪って、目的を見失った時の虚無感を大きくしてしまいます。
【ニヒリズム(虚無主義)対策の第一歩】焦らないで。まずはその虚無感を観察することから

さて、ここまでニヒリズムの正体とその原因について、一緒に見てきました。
「なるほど、原因は分かった。じゃあ、すぐに何とかしなきゃ!」
もしあなたが今、そう感じているのだとしたら、その真面目さと前向きな気持ちは、本当に素晴らしいものです。
でも、ちょっとだけ、待ってください。
深い虚無感の霧の中にいる時、いちばん、やってはいけないこと。
それは、
無理やり「ポジティブにならなきゃ!」って、自分の心に鞭を打つことなんです。
この章では、具体的な解決策に進む前に、とてもとても大切な「助走」について、お話しさせてください。
それは、まず今の自分の心の状態を、「そっか、今、そう感じてるんだね」って、静かに認めてあげるというステップです。
無理に元気になろうとしないで。その虚無感はあなたの一部
「前向きにならなきゃ」
「やる気を出さなきゃ」
そう思えば思うほど、逆に心がずーんと鉛みたいに重くなって、指一本動かせなくなる。
そんな経験、ありませんか。
もうね、本当に、無理に元気になろうとしなくていいんです。
あなたが今感じているその虚無感とか、無気力感とか、そういうものって、決して「悪者」なんかじゃないんですよ。
それは、あなたの心が
「ごめん、今、ちょっとバッテリー切れなんだ。少しだけ、休ませてくれないかな」
って送っている大切なサイン。
ほら、身体が風邪をひいたら、温かくして休みますよね。
それと全く同じです。
心が疲れている時に本当に必要なのは、根性とか気合いとかじゃなくて、まず何よりも「休養」なんです。
今のあなたの心は、いわば「冬」の季節を迎えているのかもしれません。
冬の木々って、無理に葉っぱを茂らせたり、綺麗な花を咲かせたりはしませんよね。
ただ静かに葉を落として、土の中でじーっと根っこを休ませて、春のためのエネルギーを、静かに、静かに蓄えている。
あなたの心も、今はそれでいいんです。
その虚無感を、無理に玄関から追い出そうとしないでください。
まるでお客さんのように、
「あぁ、いらっしゃい。どうぞ、お茶でも飲んで、ゆっくりしていってくださいな」
って、心の中にそっと席を譲ってあげてみてください。
敵だと思っていたものを、ただ「そういうものかぁ」と、ぼんやり眺められるようになった時、不思議と、心は少しだけ、楽になるものですから。
【簡単ワーク】心を整理する「ジャーナリング」で気持ちを書き出す方法
「休む」と言っても、ただじーっとしていると、かえって頭の中で、ぐるぐると同じことばかり考えてしまって、もっと辛くなる…。
うん、そういうことも、ありますよね。
そんな時に、とても効果的な、ちょっとした方法があるんです。
何か壮大なことを始める必要は、全くありません。
ただ、ペンと紙、あるいはスマートフォンのメモ帳アプリを用意するだけ。
たった5分でできる、心のストレッチみたいなものです。
それは、「ジャーナリング」と呼ばれる方法です。
難しく考える必要は、これっぽっちもありません。
「頭の中にある、ごちゃごちゃした感情や思考を、良いとか悪いとか一切ジャッジしないで、ただそのまま外に書き出すこと」です。
やり方は、本当に、びっくりするくらい簡単です。
【5分でできる、心の換気ワーク】
まず、スマートフォンのタイマーを5分にセットします。
そして、「今、自分、何を感じてるかな?」って、心の中で優しく問いかけてみてください。
あとは、タイマーが鳴るまで、頭に浮かんできたことを何も考えずに、ひたすら、だらだらと書き出すだけです。
誤字脱字、文法の正しさ、話の筋道なんて、一切気にしない。
例えば、こんな感じです。
「あー、だるい。なんかもう、だるいな。なんでこんなにやる気でないんだろ。そういえば、昨日のドラマの続きが気になる。お腹すいたな~。でも何か作るのも面倒やな~。ていうか、あの時あんなこと言わなきゃよかったかな…。あ、もう5分か」
本当に、こんな感じでいいんです。
このワークの目的は、問題を解決することじゃありません。
一番の目的は、「自分の心を“見える化”してあげること」。
心の中だけで抱えていると、もやもやっとして実態のなかった感情が、文字として外に出てくる。
それだけで、私たちは自分の気持ちを、少しだけ「他人事」みたいに客観的に眺められるようになって、不思議と気持ちがスッキリするものです。
まるで、淀んだ空気がずっしりとこもった部屋の窓を、ほんの少しだけ開けて、新鮮な空気に入れ替えてあげるような、そんな感覚です。
もし、ほんの少しでも気持ちが動いたら、ぜひ、騙されたと思って試してみてください。
【この章のポイント】
虚無感を感じている時、無理に元気になろうとする必要は、本当にありません。
ネガティブな感情は「敵」じゃなくて、心が休息を求めている、正直な「サイン」なんです。
まず自分の感情をありのまま認めてあげる「受容」が、回復への、とても大切な第一歩になります。
頭の中がごちゃごちゃしたら、5分間のジャーナリングで、気持ちを外に書き出してみるのがおすすめです。
【実践編】ニヒリズム(虚無主義)を「力」に変える3つの思考の道具
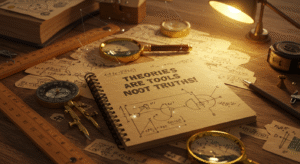
さて、前の章で自分の気持ちと静かに向き合う準備が整ったところで、いよいよここからは、あなたの日常を、ほんの少しだけ変えていくための、具体的な「思考の道具」の使い方についてお話ししていきますね。
これから紹介するのは、難しい精神論や、「気合いだ!」みたいな根性論ではありません。
あなたの毎日の生活の中で、「あ、あの道具、ちょっと使ってみようかな」って、気軽に、それこそ鼻歌まじりにでも試せる、3つの実践的なツールです。
お守りのように、心のポケットにそっと忍ばせておいてください。
この道具箱を手にすれば、虚無感という、あの得体の知れない感情は、いつしかあなたが普通に使いこなせる、便利な道具の一つになっているはずですから。
道具①「壮大な意味」を捨て、「小さな手触り」を集める習慣
私たちはね、つい「人生の意味」とか「生きる目的」とか、あまりに壮大で、答えの出ない問いを自分に課してしまいがちなんです。
で、その壮大な答えが見つからないから、「あぁ、自分はダメだ…」って、動けなくなってしまう。
だから、一度、その大きすぎる問いを、脇にそっと置いてみませんか。
代わりに、もっと小さな、手で触れられるような確かな“実感”。
この記事ではそれを「手触り」と呼びたいんですけど、その「手触り」を、日々の中で、宝物みたいに集めてみる。そんなことを、提案したいんです。
「手触り」っていうのは、誰かに褒められるためでも、何かを達成するためでもありません。
ただ自分自身が、心の内側で感じる、ささやかで、でも確かな充足感のことです。
例えば、そうですねぇ…こんなことです。
-
仕事で 「今日のこの資料のフォント、誰にも気づかれないだろうけど、自分的には完璧に揃えられたな」という、自分だけの、静かな満足感。
-
家事で 「ぴっかぴかに磨いた蛇口から、つるん、と水が流れるのを見て、なんだか気持ちがいいな」という、あの、すーっとする感覚。
-
食事で 「今日の卵焼き、奇跡的に完璧な半熟にできた!」という、食卓での、小さなガッツポーズ。
ほら、どれも本当に、他の人から見たら「だから何?」って言われそうな、些細なことですよね。
でも、こういう「手触り」こそが、私たちの、ともすればぐらつきがちな日常を、確かに支えてくれる錨(いかり)になるんです。
【今日からできる「小さな手触り」集め】
朝、一杯のコーヒーを淹れたら、飲む前に、その湯気の香りを3回、いつもより深く、ふーっと吸い込んでみる。
通勤の時に、ほんの数分だけイヤホンを外して、街のざわめきや、頬をなでる風の感覚に、意識を向けてみる。
夜、ベッドに入ったら、手足にかかっている布団の、あの、なんとも言えない重みや柔らかさを、30秒間だけ、じーっと味わってみる。
道具②「当たり前」を疑うための“ニヒリズム・フィルター”活用術
「どうせ意味なんてない」って感じてしまう、あなたの、その少しだけ冷めた視点。
実はそれ、使い方次第では、あなたをがんじがらめにしている鎖から解き放つ、強力な武器になるんです。
ここで紹介するのが、2つ目の道具、「ニヒリズム・フィルター」です。
これは、世の中の「当たり前」とか「常識」とか、あるいはSNSでキラキラ流れてくる情報に対して、
「…で、それって、本当に“私”にとって価値があることなの?」
と、一度ふっと立ち止まって問い直すための、便利な色メガネみたいなものだと考えてみてください。
私たちは毎日、まるで大量のスパムメールみたいに、社会からの「こうあるべき!」っていう価値観を、無意識に受信してしまっています。
ニヒリズム・フィルターは、それらのメールを、自分にとって本当に重要かどうか、自動で「迷惑フォルダ」に振り分けてくれる、とっても優秀なセキュリティソフトなんです。
使い方は簡単です。
何かにもやもやしたり、じりじりと焦りを感じたりした時に、自分にこんな質問を、そっと投げかけてみるだけです。
【心を自由にする4つの魔法の質問】
Q1:それって、「誰か」のため? それとも「私」のため?(見栄とか、世間体とかで、やろうとしてないかな?)
Q2:もし、誰にもSNSで報告しなくても、私、それ、やりたい?(他人の「いいね」が、目的になってないかな?)
Q3:それを失ったら、本当に、私の人生、終わっちゃう?(失うことを、怖がりすぎてないかな?)
Q4:もし明日死ぬとしたら、私、本当にそのことで悩んでる?(自分にとって、それ、本質的なことかな?)
これらの質問を自分に投げかけてみると、
「…あれ? なんだ、自分がこだわってたことって、実は、大したことじゃなかったんだな」
と、心の力が、ふっと抜ける瞬間があるはずです。
これは、いわば「価値観の断捨離」。
自分にとって不要な、重たい荷物を降ろして、本当に大切なものだけを置くための、心のスペースを作ってあげる。
そのための、とっても便利な道具です。
道具③ 思考の沼から抜け出すための“身体アンカー”という対策
虚しさがどっと襲ってくると、頭の中で同じ考えが、ぐるぐる、ぐるぐると回り続けて、抜け出せなくなることはありませんか。
それは、「思考の沼」にはまっている、ちょっと危険なサインです。
この沼から抜け出そうと、頭の中でもがけばもがくほど、私たちはさらに深く、ずぶずぶと沈んでいくだけ。
なぜなら、思考で思考を止めようとするのは、火に油を注ぐようなものだからです。
そんな時に使うのが、3つ目の道具「身体アンカー」です。
アンカーとは、船を港に繋ぎとめておく、あの重たい「錨」のことですね。
思考の嵐に飲み込まれそうになった時、意識を「身体」という、今ここにある確かな現実に強制的に繋ぎとめることで、心の漂流を防ぐための道具です。
使い方は、いつでも、どこでも、誰にも気づかれずにできますよ。
【いつでも使える“3つの身体アンカー”】
手のひらアンカー
両手の指を、息を吸いながら「ぎゅーっ」と、ありったけの力で握りしめます。そして、息をふーっと吐きながら、じわーっと開いていく。
その筋肉の緊張と、だんだん緩んでいく感覚だけに、すべての意識を集中させてみてください。一杯の水アンカー
コップ一杯の水を、ただ、ゆっくりと飲みます。そして、その水が口の中に入ってきて、喉を通り、胃にぽちゃんと落ちていくまでの、その冷たい感覚を、心の中で実況中継するように、ただ感じてみてください。
一点集中アンカー
部屋の中にある、何かどうでもいいもの(壁のシミ、時計の秒針、観葉植物の葉っぱ一枚とか)を一つだけ決めます。そして、30秒間、ただ、それだけを、まばたきも忘れるくらい、じーっと観察し続けてみてください。
ポイントは、
「思考」から「感覚」へと、意識のチャンネルを、強制的に、えいっ!と切り替えることです。
心がどんなにざわざわと荒れていても、確かな身体の感覚に意識を向けることで、私たちは思考の沼からすっと抜け出し、再び「今、ここ」という、穏やかな岸辺に戻ってくることができるのです。
【この章のポイント】
「人生の意味」みたいな壮大な問いじゃなく、日常の「小さな手触り」を集めることに、集中してみましょう。
ニヒリズムを「当たり前」を疑う便利なフィルターとして使って、自分にとって不要な価値観を手放しちゃいましょう。
頭の中がぐるぐるし始めたら、「身体アンカー」を使って、意識を「今、ここ」の身体の感覚に戻してあげましょうね。
【光と影】ニヒリズムとの付き合い方で変わる、あなたの未来

ここまで、ニヒリズムと向き合うための、具体的な道具をいくつか見てきましたね。
もしかしたらあなたは、心のどこかで
「…でも、結構、面倒だな」
「本当に、こんなことで何かが変わるのかな」
なんて、感じているかもしれません。
ええ、ええ、その気持ちも、よーく分かります。
だからこの章では、少しだけ、未来の話をさせてください。
あなたが今感じている、そのニヒリズムという、なんとも言えない、色のない感覚。
それを放置して、ずるずると心の奥底に居座らせてしまった場合の未来(影)と、先ほどの道具を手に、サーフィンのようにうまく乗りこなせるようになった場合の未来(光)。
その二つの道を、ほんの少しだけ覗いてみることで、
「あぁ、だから今、向き合う価値があるのか」
って、きっと心から、腑に落ちるはずです。
ただ、あなたが、どちらの未来の空気を吸ってみたいか。
その意志を、そっと確かめるための問いかけです。
「影」放置されたニヒリズムが行き着く「冷笑」と「孤立」という末路
ニヒリズムはね、ただ心の中にあるだけなら、それほど悪いものではないんです。
でも、その感覚に心を完全に支配されて、どっぷりと浸かりきってしまうと、少し厄介な二つの状態に行き着くことがあります。
一つは、「冷笑(シニシズム)」です。
これは、何かにキラキラと情熱を注いでいる人を見ては「…どうせ無駄なのにね」と心の中でフッと鼻で笑ったり、感動的な映画を観ても「はいはい、お涙頂戴ね」と、素直に心を動かせなくなったりする状態のこと。
世界から、じわじわと色が失われていって、すべてが退屈なモノクロームに見えてしまう。
そして何より辛いのは、そんな風にしか物事を感じられなくなってしまった自分自身のことを、心のどこかで、ものすごく嫌いになってしまうことなんです。
そしてもう一つが、「孤立」です。
冷笑的な態度は、必ず、人間関係にも、ぽつんと暗い影を落とします。
他人の喜びや悲しみに心から共感できず、会話がどこか、つるつると上滑りしているように感じる。
「どうせ誰も、本当の私なんて理解してくれないし」と、いつの間にか心のシャッターをガラガラと下ろし、人と深く関わることを諦めてしまう。
その結果、たとえ大勢の輪の中にいても、決して埋まることのない、ひんやりとした孤独感を、常に抱え続けることになります。
まるで、
安全だけど、とても分厚いガラスケースの中から、外の賑やかで温かい世界を、ただ、ぼんやりと眺めているだけの人。
そんな感じです。
確かに、ガラスケースの中にいれば、傷つくことはないかもしれません。
でも、そのケースの中には、人の肌の温もりも、美味しいご飯の湯気も、決して届くことはないのです。
もちろん、誰もがこうなるわけじゃありませんよ。
ただ、今いる場所から、ゆるやかに続いている道の一つとして、知っておくことは、きっと大切です。
そうすれば、私たちは、意識して、「あ、こっちの道はやめておこう」って、別の道を選ぶことができますからね。
光 ニヒリズムを乗り越えた先にある「本当の自由」とクリアな視界
では、逆の道はどうでしょう。
もしあなたが、ニヒリズムという、あの、ざわざわとした嵐のような感情をうまく乗りこなし、その静かな中心、つまり「台風の目」に、すっとたどり着けたなら。
そこには、驚くほど穏やかで、澄み切った、気持ちのいい景色が広がっています。
まず手に入るのは、「本当の自由」です。
これは、「何でも好き勝手にできる」っていう、子どもみたいな自由じゃありません。
そうではなくて、「何にも、縛られずにいられる」という、もっと心の深い部分での、しなやかな自由です。
-
世間の誰かが決めた「これが幸せですよ」っていう、窮屈なテンプレートに、自分を無理やり、ぎゅうぎゅうと押し込む必要がなくなります。
-
SNSで誰が海外旅行に行っていようと、誰が大きな成功を収めようと、「へえ、すごいねぇ。でも、私は私のペースで、のんびりいこうかな」と、心の中心が、全く、びくともしなくなります。
そして、もう一つ手に入るのが、「クリアな視界」です。
一度、すべての価値を「それ、本当に?」って疑うニヒリズムのフィルターを通過したあなたの目は、以前よりもずっと、物事の本質を、すーっと見通せるようになっています。
-
世の中の流行りとか、人々が一時的にわーっと熱狂している物事を、一歩引いた場所から、「ふむふむ」と冷静に眺められるようになります。
-
そして、自分にとって本当に、本当に大切にしたいものと、実はどうでもよかったものが、驚くほどはっきりと、くっきりと、区別できるようになる。
これは、人生の“解像度”が、ぐぐっと上がる感覚、と言えるかもしれません。
ニヒリズムという、あの暗くて長いトンネルは、実は、この気持ちのいい場所に、ちゃんと通じていたんです。
そして、一度手に入れたその自由と視界は、もう誰にも奪われることのない、あなただけの、かけがえのない財産になるのです。
【この章のポイント】
ニヒリズムに心を支配されると、世界を斜めに見る「冷笑」とか、他者と共感できない「孤立」に行き着いてしまう可能性があります。
一方で、ニヒリズムを乗り越えた先には、他人の価値観に縛られない「本当の自由」が待っています。
物事の本質を見抜いて、自分にとって大切なものがクリアに分かる「クリアな視界」も手に入るんですね。
ニヒリズムの荒波を越えた巨人たち。哲学に学ぶ「生きるヒント」
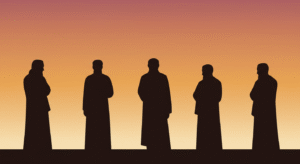
あなたが今感じている、その、どうしようもなく虚しい気持ち。
実はそれって、ここ10年や20年で急に出てきた、新しい種類の悩みなんかじゃないんです。
人類の長ーい歴史の中で、たくさんの、頭が良くて感受性の強い人たちが、あなたと全く同じように「…意味って、なんだろう」と、うんうん唸りながら悩み、格闘してきました。
ここでは、その荒波の中を、自分なりのスタイルで泳ぎ抜いて、私たちに「こんな泳ぎ方もあるよ」って、ヒントを残してくれた、3人の先人たちの知恵を、少しだけ借りてみましょうか。
難しい哲学の話をするつもりは、毛頭ありません。
彼らの言葉は、あなたの日常の悩みを、そっと横から照らしてくれる、温かいランプの光みたいなものですから。
ニーチェの教え「超人」のように、自分の価値基準で主体的に生きる
フリードリヒ・ニーチェ。
彼は、「ニヒリズム」という言葉を世に広めて、その危険性を、誰よりも早く私たちに「おい、大変な時代になるぞ!」って、教えてくれた、預言者のような哲学者です。
彼のメッセージを、とても、とても乱暴に要約するなら、こんな感じでしょうか。
「『神は死んだ(=みんなが信じる絶対的な価値基準は、もうないぞ)』。ならば、いつまでも失われたものをメソメソと嘆くのはやめて、お前自身が、全く新しい価値を創造する『超人』になれ!」
…いや、「超人」って言われても、って感じですよね。
なんだかマッチョで、自分とは全く関係のない、遠い存在に聞こえます。
でもね、ニーチェの言う「超人」っていうのは、空を飛んだり、ビルを軽々と持ち上げたりする人のことじゃないんです。
単に自分の『好き』を追求するだけでなく、人生の苦悩や困難も受け入れ、それを力に変えていく『意志の力』によって、自己を超越していく存在。
彼は、人生という名の、真っ白で、だだっ広いキャンバスを前に、「ふーん、誰かの絵の真似なんて、まっぴらごめんだね。私は、私の絵を描くよ」と、静かに、でもきっぱりと宣言する画家のような生き方を、私たちに求めたんです。
もちろん、言うのは簡単です。
でも、その、誰にも媚びない、凛とした姿勢は、他人の評価に疲れ果てた私たちの心を、強く、強く、揺さぶるものがありますよね。
あなたにとって、誰に何と言われようとも「うん、これが私の価値なんだ」と、胸を張れるもの。
それは、一体なんでしょうか。
その小さな答えの種を、心の中で、そっと探してみる。
それが、ニーチェからの、最初の問いかけです。
【ニーチェの核心的な概念:「権力への意志」】
カミュの教え「不条理」な日々に、ささやかに“反抗”し続ける
アルベール・カミュ。
彼は、人生が、そもそも持っている「無意味さ」みたいなものを、誰よりもクールな目で、じーっと真正面から見つめて、それでもなお、その中に、なんとか希望を見出そうとした、とても誠実な哲学者でした。
彼の主著『シーシュポスの神話』には、その考えが詰まっています。
彼の思想を、一言で表すなら、こうです。
「人生は、私たちが『意味を教えてくれ!』って叫んでも、しーんとして、決して答えてはくれない『不条理』なものだ。…でも、その無意味さを、まるごと理解した上で、それでもなお、目の前のことに誠実に向き合い続けること。それ自体が、人間だけにできる、最も尊い“反抗”なんだ」
無意味さ問いに対する唯一の誠実な答えが、この世界に意味を求めず、ただ生き続けること、カミュが言うところの「不条理」への『反抗』なのです。
この考えを象徴するのが、彼が語った「シーシュポスの神話」です。
シーシュポスっていう男が、神々から罰として、巨大な岩を、えっちらおっちらと山頂まで運び、運び終えた瞬間に、岩がゴロゴロと転がり落ちる、という、永遠に終わらない苦役を課される話。
無意味な、全く報われない労働。カミュは、このシーシュポスの姿を、私たちの「意味のない繰り返しに見える日常」に、そっと重ね合わせました。
毎日、同じような仕事をして、同じような家事をこなす。
「…これ、一体、何のためにやってるんだっけ?」って。
でも、カミュは言うんです。
「山頂に向かうシーシュポスは、幸福なのだ」と。
なぜなら、彼は自分の運命が無意味であることを、誰よりも知り尽くした上で、その運命に対して
「それでも私は、この岩を、私のやり方で運び続けてやる」
と、静かに、でも確かに、意志的に向き合っているからです。
あなたの仕事が、世界を直接変えるような、派手なものではなくても、全く構いません。
その無意味に見える日々のタスクの中に、
自分だけの小さな矜持や、「昨日の自分より、少しだけ上手くやってやろう」っていう工夫を見出すこと。
それこそが、カミュの言う、静かで、でも、とても偉大な「反抗」なのです。
それは、雨が降っているっていう変えられない現実を前に、ふてくされて家に閉じこもるんじゃなくて、お気に入りの傘をぱっと広げて、あえて水たまりをぴょんと飛び越えてみるような、ささやかな遊び心にも、似ている気がします。
【カミュのの核心的な概念:「不条理」】
フランクルの教え 人生からの問いに「応答する」ことで意味を見出す
最後に紹介するのは、哲学者ではありません。
ナチスの強制収容所という、人間の尊厳が、もうこれ以上ないっていうくらい踏みにじられる場所を、奇跡的に生き延びた心理学者、ヴィクトール・フランクルの言葉です。
その壮絶な体験は、世界的ベストセラーである『夜と霧』に、静かに、しかし圧倒的な迫力で記されています。
彼のメッセージの核心は、これまでの二人とは、また少し違う、驚くべき視点の転換にあります。
「『人生の意味とは、一体何ですか?』と、我々が人生に問いかけるのは、そもそも、お門違いなのだ。むしろ、人生の方が、常に我々に『お前は、このどうしようもない状況で、どう生きるつもりだ?』と、問いかけてきている。私たちの使命は、その問いに、自分の行動をもって、誠実に“応答”することだ」
フランクルは、どんな状況でも奪うことのできない人間の最後の自由、すなわち、避けられない苦悩に対する「態度」を選択することに、人生の意味を見出しました。
意味は、どこか遠い未来に探しにいくものじゃない。
それは、あなたの目の前の状況の中に、常に見出されるのを、じっと待っている。
フランクルは、そう言います。
そして彼は、私たちが意味を見出すことができる、具体的な道を3つ、示してくれました。
-
何かを創造すること(仕事や、趣味の創作活動など)
-
何かを体験すること(自然の美しさに、はっと息をのんだり、誰かを深く愛したりすること)
-
態度を決定すること(避けられない苦悩に対して、自分が、どういう態度で向き合うかを選ぶこと)
特に、特に重要なのが、3つ目の「態度」です。
どんなに絶望的な状況に置かれても、それに対して自分がどういう態度を取るかという、その、心の最後の自由だけは、誰にも、何にも、奪うことはできない。
人生は、台本のない即興劇の舞台みたいなものなのかもしれません。
次から次へと、予期せぬ状況(人生からの問い)が、ぽんぽんと投げかけられます。
それに対してどう振る舞い、どんなセリフを言うか。
その一つひとつの、あなたらしい「応答」の積み重ねが、やがて、振り返った時に
「あぁ、これが私の人生だったんだな」
って思えるような、かけがえのない意味を、形作っていくのです。
【フランクルの核心的な概念:「態度」】
【この章のポイント】
ニーチェは、他人の物差しじゃなく、自分自身の価値基準で、主体的に生きることを教えてくれます。
カミュは、無意味に見える日常の中に、ささやかな「反抗」や、自分なりの工夫を見出すことの尊さを伝えています。
フランクルは、人生の意味は探すものじゃなくて、目の前の状況への、誠実な「応答」の中に見出されるものだと、示してくれています。
【コラム】歴史が語る、「壮大な意味」よりも大切なこと

ここまで、ニヒリズムと向き合うための、いろんな知恵を見てきましたね。
少しだけ、ここで、休憩しませんか。
肩の力を抜いて、温かいお茶でも飲みながら、聞いてほしい話があるんです。
それは、
「私たちって、一体いつから『人生の壮大な意味』なんていう、そんなに難しくて、壮大な宿題を、自分に課すようになっちゃったんでしょうかね」
っていう、とても素朴な疑問です。
少しだけ、時間旅行をするような気持ちで、歴史という、大きな、大きな鏡を、一緒に覗いてみませんか。
何世代にもわたって、巨大なピラミッドを、こつこつと築き上げた古代エジプトの人々。
彼らは、一人ひとり、自分のテントの中で「…私の人生の意味とは」なんて、深刻に悩んだでしょうか。
あるいは、見知らぬ海の向こうを目指して、小さな木の船に乗り込んだ、大航海時代の船乗りたちは、どうでしょう。
もちろん、彼らにも、私たちと同じように、たくさんの悩みや、苦しみはあったはずです。
でも、その悩みの「質」は、もしかしたら、少しだけ違っていたのかもしれません。
歴史を、ずーっと、ずーっと遡って見てみると、かつての多くの人々は、もっと具体的で、自分の手が届く範囲のものに、支えられて生きていたように思うんです。
生まれた村の共同体とか、家族との強い絆とか、先祖代々受け継いできた仕事とか、あるいは、心の底から信じられる神様とか…。
彼らの人生は、良くも悪くも、そういう大きなものの中に、すっぽりと、温かく包まれていたんですね。
ところが、近代になると、私たちは、そうした「当たり前」の共同体から、少しずつ解放されて、「個人」として、自由になりました。
これは、人間が手にした、本当に素晴らしい権利です。
でも、その、あまりにも広すぎる自由には、一つだけ、重たい代償が伴いました。
それは、
「自分の人生の意味は、自分自身で、ゼロから見つけなければならない」
という、見えない宿題です。
そして、その宿題は、いつしか、「それが見つけられない者は、価値がない人間だ」という、静かで、でも、とても強力な呪いにもなってしまったのかもしれません。
私たちはまるで、広大な砂漠の真ん中で「地平線の先にあるという、幻のオアシスを探してきなさい」と言われた旅人。
どこにあるかも分からないオアシスを探し続けることに疲れ果てて、すぐ自分の足元に、こんこんと湧いている、命を繋ぐための小さな泉の存在を、うっかり見過ごしてしまっている。
歴史という、気の遠くなるような、壮大な時間の流れが、本当に、本当に私たちに伝えていることって、何でしょう。
それは、教科書に載っているような、英雄や天才たちの、キラキラした功績だけではないはずです。
むしろ、歴史の大部分を、黙々と創ってきたのは、名前も残っていない、普通の人々です。
彼らが、日々の中で、大切にしてきたもの。
それはきっと、「壮大な意味」よりも、もっと素朴で、ざらざらしていて、でも、温かいものだったはずです。
-
汗水たらして、へとへとになるまで働いた後、誰かと一緒に囲む、食卓の、あの湯気の温かさ。
-
沈んでいく夕焼けの、息をのむような美しさに、ふと、心を奪われる、あの瞬間。
-
自分の作ったものが、顔も知らない誰かの、ささやかな喜びにつながっているという、じんわりとした実感。
-
大切な人が、ただ隣で、くすくすと笑っている、何気ない声。
歴史という、壮大な、壮大な物語は、結局のところ、そうした
意味をいちいち問うまでもない、確かな瞬間の、無数の積み重ね
で、できているんです。
だから、もし、あなたが今、「人生の意味が見つからない」と、深く、深く悩んでいるのだとしたら、私は、心の底から、こう伝えたい。
壮大な意味なんて、見つからなくても、全く、全く、問題ありません。
むしろ、その、あまりにも難しすぎる探求を、一度、ふっとやめてみた時に初めて、あなたの足元に、キラキラと輝く無数の宝物が、最初からずっと、落ちていたことに、気づけるのかもしれませんから。
【この章のポイント】
「人生の意味」を個人で探求するようになったのって、歴史的に見れば、実は、比較的新しい悩みなんです。
かつての多くの人々は、共同体や家族との絆みたいな、もっと身近なものに支えられていました。
歴史が本当に伝えているのは、壮大な意味よりも、日々の、ささやかで、でも確かな瞬間の大切さなんですね。
虚無感の先へ。ニヒリズムから始める「自分だけの指針」の育て方

【要約】この記事で伝えたかった、ニヒリズムとの上手な付き合い方
最後に、この記事で私がいちばん、あなたの心に残したかったことを、もう一度だけ、シンプルにまとめておきたいと思います。
【結論から言うと…】
あなたが時々感じる、あの虚無感(ニヒリズム)は、決して敵なんかじゃありません。
それは、「自分だけの、本当の価値って何だろう?」って考え始めるための、とても重要で、静かな“始まりの合図”なんです。
【なぜなら…】
絶対的な正解がどこにもなくなった現代において、私たちは、社会や他人から「これがいいよ」って与えられた、借り物の価値観じゃなくて、自分自身の手で、自分だけの「心の指針」を、こつこつと創り出していく必要があるからです。
【例えば…】
そのための具体的な道具として、この記事では
「小さな手触りを集める」
「ニヒリズム・フィルターを使う」
「身体アンカーに繋がる」という、明日から、いえ、今日からでも使える3つの、ささやかな方法をご紹介しました。
【だから、もう一度結論です】
もし、また、ふと虚無感に襲われた時は、絶望する必要なんて、これっぽっちもありません。
むしろ、「あぁ、古い地図が使えなくなったんだな。じゃあ、そろそろ、新しい地図を描き始めるチャンスが来たってことか」と、静かに、そう考えてみてください。
壊れてしまったコンパスを前に、ただ途方に暮れるのではなく、夜空の星を読み、頬をなでる風の匂いを感じて、自分だけの力で、次の一歩を踏み出すべき道を見つけ出していく。
ニヒリズムとの上手な付き合い方っていうのは、そういう、少しだけたくましくて、そして、とても創造的な営みなのかもしれませんね。
最後に あなたの「最初の一歩」は、壮大な目標じゃなくていい
さて、この記事を読んで、「よし、やるぞ!」と、あまり、力強く意気込む必要は、全くありません。
むしろ、お願いです。
どうか、頑張ろうとしないでください。
変わりたい、と強く思う、その真摯な気持ちは、本当に尊いものです。
でも、心が疲れている時に、さらに無理をしてアクセルを踏み込むと、エンストしてしまうことをよく知っていますよね。
だから、あなたの「最初の一歩」いや、「0.1歩」は、他の誰の目にも見えないくらい、本当に、本当に、ささやかなものでいいのです。
もしよかったら、この記事を閉じた後、まず、たった一つだけ、試してみてはくれませんか。
今日の夕食を、いつもより3口だけ、ゆっくり、ゆっくりと味わってみる。
できればテレビやスマートフォンを少しだけ遠くに置いて、ただ、その食べ物が持つ味や、食感や、じんわりとした温かさだけに、静かに、意識を向けてみる。
それだけで、いいのです。本当に、それだけで、もう十分すぎるほどです。
あるいは、
今日の帰り道、少しだけ、ほんの少しだけ顔を上げて、夜空にぽっかりと浮かぶ月を探してみる。
その静かな光は、私たちに「人生の意味とは!」なんて、壮大なことを語りかけてはきません。
でも、それはただ、それだけで、どうしようもなく美しい。
その小さな、言葉にならない実感が、今のあなたには、何よりの力になるはずです。
壮大な人生の意味なんてものは、明日すぐに見つかるものではありません。
多分、一生かかっても、見つからないかもしれない。
でも、そうした
小さな「実感」や、ざらりとした「手触り」を、一日ひとつ、まるで宝物のように、丁寧に、丁寧に拾い集めていくこと。
その、気の遠くなるような積み重ねが、やて、あなただけの、誰にも奪うことのできない、確かな「心の指針」となって、これからの未来の道を、静かに、でも確かに、照らしてくれるはずです。
あなたのこれからの日々が、虚無の荒野を超える、豊かで、穏やかなものでありますように。
【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、このように、日々の生活が少し楽になったり、豊かになったりするような「考え方」を、これからも色々な角度から探求していきます。
少しだけ「豊かさ」や「幸せ」について考えてみたいな、という気持ちが湧いてきたら、ぜひ他の記事も、散歩するような気分で覗いてみてくださいね。


