毎日同じことの繰り返し…。
ふと、自分の人生が色褪せて見えることはありませんか?
大丈夫。
大げさな変化を起こす必要なんて、全くないんです。
この記事では、「目的」という大きな言葉から一旦離れて、いつもの日常に隠れた「小さな喜び」を見つけるための、簡単な視点をご紹介します。
読み終える頃には、壮大な目的を探すのをやめ、足元にある幸せに気づき、心から楽しめるようになっていますよ。
なぜ、生きる目的が見つからないのか?【苦しみの正体】

あなたが「目的が見つからない」と苦しんでしまうのは、決して、あなたのせいではないんです。
まずは、その苦しみの正体がどこから来るのかを、一緒に、客観的に知ることから始めましょう。
原因がわかると、それだけで少し、気持ちが楽になるはずですから。
「目的」「夢」「やりたいこと」…言葉の呪いがあなたを縛っている
「あなたの、人生の目的は何ですか?」
…なんて、改まって聞かれると、まるで壮大なスピーチでも求められているようで、急に息苦しくなりませんか?
私だけでしょうか、なんだかすごく構えてしまうんですよね。
私たちは、いつの間にか無意識のうちに、言葉に序列をつけてしまっているのかもしれません。
-
目的 人生を懸けるような、最も高尚なもの。
-
夢 目的ほどではないけれど、実現すべき大きな目標。
-
やりたいこと もっと日常的で、少し個人的な願望。
こんな風に、「目的」という言葉を、あまりにも神聖で、手の届かない特別な場所に置いてしまっている。
これこそが、私たちの行動を縛る「思考の呪い」の正体です。
人によってはこの「目的」と「夢」が逆の人もいるでしょう。
例えば、「ただ、絵を描いている時間が好き」なだけなのに、
「画家になる、という立派な”目的”がなければ、本気で始めてはいけない気がする…」
と感じてしまう。
「ただ、人の話を聞くのが得意」なだけなのに、
「カウンセラーになる、という明確な”夢”がなければ、その能力を活かしてはいけない気がする…」
と思ってしまう。
心当たり、ありませんか?
この呪いを解くための、はじめの一歩。
それは、一旦「目的」という大きな言葉を、そっと脇に置いてみることです。
そして、その代わりに、
「これをしていると、少しだけ気分がいいな」
「つい、時間を忘れてしまうな」
といった、あなた自身の身体や感覚が教えてくれる、ささやかな「心地よさ」を、新しい心の指針にしてみる。
誰かに評価されるためでもなく、何かの役に立つからでもない。
ただ、自分が「そう感じる」から。
それだけで、もう十分すぎるくらい、立派な理由になるんですよ。
【専門的分析】社会が「目的を持て」と囁く3つの理由
あなたが「目的を持たなきゃ!」と焦ってしまうのは、あなたが怠け者だからでも、意識が低いからでもありません。
むしろ、あなたが、社会の声に真摯に耳を傾けている、とても誠実な証拠なのです。
では、なぜ私たちの社会は、これほどまでに「目的を持て!」と囁きかけてくるのでしょうか。
それには、はっきりとした3つの理由があるんです。
【理由1 SNSによる「人生の劇場化」】
他人の成功、旅行、記念日…。
キラキラと編集された「ハイライト」だけが、私たちのスマートフォンには絶え間なく流れ込んできます。
これを、私は「人生の劇場化」みたいに呼んでいます。
私たちは、観客として他人の華やかな舞台を毎日見せられるうちに、いつの間にかこう思い込んでしまうのです。
「自分も、何か壮大な目的という脚本を持った、舞台の上の『主役』でなければならない」
と。
でも、忘れないでください。
あなたが見ているのは、あくまで編集されたハイライト。その裏にある無数の地味な日常や、うまくいかない時間は、決して映し出されることはないのです。
【理由2 キャリア神話の崩壊と「コンパスなき航海」の強制】
かつては、「良い大学に入り、良い会社に就職する」といった、社会が用意してくれた、ある程度の成功モデルがありました。
しかし、今は違います。
生き方も働き方も、無数に枝分かれしました。
この状況は、まるで
「コンパスも海図も渡されずに、大海原の真ん中に一人で放り出された状態」
に似ています。
「どの航路を選ぶも自由だ」という言葉は、聞こえはいいかもしれません。
でもその裏側では、
「どの島に漂着しようと、その結果は全て船長であるあなたの自己責任だ」
という、強烈なプレッシャーが働いています。
だからこそ、私たちは
「絶対に失敗しないための、唯一絶対の目的地(=目的)」
を、必死に探そうとしてしまうのです。
【理由3 哲学の祖アリストテレスの「壮大な誤解」】
少しだけ、昔の話をさせてください。
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、「テロス(telos)」という言葉を使いました。
これが「目的」と訳されることが多いのですが、実は少しニュアンスが違うんです。
彼が言いたかったのは、
「あらゆる物事には、そのものが最もよく機能する『本質』がある(例:ナイフの本質は”よく切れること”)」
ということ。
決して、「個人は社会的成功という目標を達成すべきだ」なんて、一言も言っていないんですね。
しかし、この「テロス」という考え方が、近代の資本主義や個人主義と結びつく過程で、いつの間にか
「個人は、社会的成功という目的を達成してこそ価値がある」
という思想に“誤訳”されてしまった。
この壮大な誤解が、2000年以上の時を経て、私たちの無意識に深く根付いてしまっているのです。
どうでしょう。
こうして見てみると、「目的が見つからない」というあなたの悩みは、個人の問題というより、極めて現代的な社会構造が生み出した「時代の空気」のようなものだ、という気がしてきませんか?
【この章のポイント】
「目的」という言葉の重圧が、私たちの行動を縛る「思考の呪い」になっている。
「目的を持て」というプレッシャーは、SNSの普及や社会構造の変化が生み出したもので、あなたのせいではない。
まずは「自分はダメだ」という自己否定を手放すことが、何よりも大切な第一歩。
【逆転の発想】「目的がない」は欠陥じゃない。人生の”余白”が持つ本当の価値

前の章で、目的が持てないのは「あなたのせいではない」というお話をしました。
ここからは、もう一歩、前に進んでみたいと思います。
もし、「目的がない」という今の状態が、単にマイナスやゼロなのではなく、むしろ、
これからの人生を豊かにするための「積極的なプラス」の状態だとしたら…?
そう言われても、すぐには信じられないかもしれませんね。
でも、大丈夫。
「目的がない」からこそ見えてくる、新しい景色の話を、これから少しだけさせてください。
答えを急がない勇気。「ネガティブ・ケイパビリティ」が創造性を生む心理学
「早く答えを出さなくちゃ」
「白黒ハッキリさせないと、なんだか気持ちが悪い」
私たちは、わからない状態にいること自体を“悪”だと考えがちです。
その焦る気持ち、本当によく分かります。
しかし、心理学や精神医学の世界では、
その
「わからない状態に、あえて留まり続ける力」
にこそ、大きな価値があると考えられているのです。
これを専門的には「ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)」と呼びます。
日本語にすると、「不確かさに耐える力」とでも言いましょうか。
答えが出ない宙ぶらりんな状態に、慌てて浅い結論に飛びつかず、じっと向き合い続ける能力のことです。
なんだか、少し難しい言葉に聞こえますよね。
私はこれを、「心の熟成期間」のようなものだと考えています。
美味しい果物やワインが、時間をかけてゆっくりと糖度や深みを増していくように。
私たちの心も、答えが出ないモヤモヤとした期間があるからこそ、浅い思考では辿り着けないような、深い洞察や、本当にしっくりくる感覚が、静かに醸成されていく。
そう思いませんか?
すぐに転職先を決めずに、一度じっくり自分と向き合う時間を持ったからこそ、本当に自分に合う仕事が見つかった。
特に目的もなく、ただ好きで続けていた趣味が、何年も経ってから、思いがけない形で誰かの役に立った。
きっと、あなたにも似たような経験があるはずです。
目的を無理に設定しない「余白」の時間は、決して無駄な空白期間ではありません。
それは、あなたの心が、より深く、より豊かに熟していくための、とても大切な時間なのです。
【もっと深く知りたいあなたへ】
この「ネガティブ・ケイパビリティ」という考え方に興味を持たれた方は、精神科医である帚木蓬生氏の著書を手に取ってみることをお勧めします。
私たちの社会が見失いがちな、大切な視点に気づかされるはずです。
ニーチェに学ぶ、未来のためじゃない「”今”この瞬間」を最高に肯定する方法
「いつか幸せになるために、今は我慢しよう」
「この目標を達成したら、きっと素晴らしい人生が待っているはずだ」
私たちはつい、未来の輝きのために、“今”という時間を犠牲にしがちです。
でも、哲学者のニーチェは、そんな生き方に、力強く「待った!」をかけました。
彼は、私たちにこんな問いを投げかけます。
少しだけ、想像してみてください。
もし、この退屈な会議も、気まずい会話も、感動した映画のワンシーンも、あなたが今経験している全てのことが、全く同じように、この先無限に、永遠に繰り返されるとしたら…。
あなたは、この人生に、心から「然り(しかり)!」と言えるだろうか?
これは「永劫回帰(えいごうかいき)」と呼ばれる、彼の有名な思想です。
少し難解に聞こえるかもしれませんが、
私はこれを
「人生の究極のリトマス試験紙」みたいに思っています。
この問いを心に持つと、私たちの行動基準が、ガラリと変わるんです。
「この行動は、未来の目的達成に役立つだろうか?」
という視点から、
「”今”この瞬間が、もう一度繰り返されても構わないと思えるほど、自分にとって価値があるだろうか?」
という視点へ。
大げさな話ではありません。
例えば、「給料のために仕方なくやる仕事」の中に、
「このデータ整理の作業、パズルみたいで地味に楽しいんだよな」
と思える瞬間を見つけること。
「痩せるために嫌々やる運動」ではなく、
「ああ、体を動かすこと自体が、純粋に気持ちいいな」
と感じる瞬間を大切にすること。
そんな、日常の中に隠れている「目的を超えた充足感」に、光を当てる作業です。
壮大な目的が見つからなくても、このリトマス試験紙を心のポケットに持っているだけで、日々の小さな選択が変わっていく。
そして、その選択の積み重ねが、いつの間にかあなたの人生の質感を、より温かく、豊かなものに変えていってくれるはずです。
【もっと深く知りたいあなたへ】
ニーチェの思想に触れてみたい方は、まずは彼の主著である『ツァラトゥストラはかく語りき』の、分かりやすい解説書から手に取ってみるのがおすすめです。
きっと、あなたの価値観を揺さぶる言葉に出会えるでしょう。
データが証明。世界幸福度報告書が示す「目的達成」以外の幸せのカタチ
「理屈はわかるけど、やっぱり大きな目標を達成している人の方が、幸せそうに見える…」
そんな風に感じてしまうあなたの心に、最後に一つ、客観的なデータをご紹介させてください。
国連の関連組織が毎年発表している「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」というものがあります。
これは、世界中の人々の幸福度を様々な角度から調査した、非常に信頼性の高いデータです。
この報告書によると、人々の幸福度を測るための重要な指標として、経済的な豊かさ(一人当たりGDP)の他に、以下のような項目が挙げられています。
| 幸福度を測る6つの指標(一部抜粋) |
|
|
|
|
|
ここで注目したいのは、
「何かを達成したか」という項目は、どこにも入っていない
ということです。
むしろ、データが示しているのは、
いつでも自分の道を選び直せるという「選択の自由」や、
多様な生き方を認め合える「寛容さ」、
そして困った時には誰かに頼れるという「安心感」
…そういった要素の方が、人の幸福に大きく関わっている、という事実です。
私は、これらの指標が示す幸せのあり方を、「人生の”風通し”の良さ」と呼んでいます。
一つの山頂だけを目指して、息を切らしながら登り続ける、息苦しい登山のような人生観。
それだけが、幸せの形ではないのかもしれません。
いつでもルートを変更でき、道に迷えば「助けて」と言え、様々なペースで歩く人たちとお互いを認め合える。
そんな、風通しの良いハイキングのような生き方。
「何かを成し遂げる」という縦軸の価値観だけでなく、
そんな「誰かと繋がり、自由に生きる」という横軸の価値観も、私たちの幸せにとって、同じくらい
…いえ、もしかしたらそれ以上に、大切なものなのかもしれません。
【この章のポイント】
「目的がない」時間は、心が熟成するための大切な「余白」であり、無駄ではない。
未来の目的のためだけでなく、「”今”この瞬間」の充足感を大切にする視点を持つ。
世界的なデータも、「目的達成」以外の要素(選択の自由や他者との繋がり)が幸福に重要であることを示している。
人生が少し楽になる。「迷ったまま」進むための3つの哲学的解決策

ここまで、目的がなくても大丈夫な理由を、色々な角度からお話ししてきました。
きっと、あなたの心の中にある焦りや自己否定も、少しずつ和らいできたのではないかと思います。
この章では、いよいよ
「では、具体的にどうすればいいのか?」
という、最も大切な部分に入っていきます。
これからご紹介するのは、哲学の世界で古くから伝えられてきた、心を整えるための知恵です。
でも、決して難しいことではありません。
「解決策」なんて少し大げさな言葉を使いましたが、実際には、明日から、いえ、この記事を読みながらでもすぐに試せる、
ごくシンプルで、具体的な心の習慣です。
ゲーム感覚で、気軽に試してみてくださいね。
解決策①【現象学】「良い/悪い」の評価をやめる。ただ、世界を味わう練習
私たちの頭の中には、まるで小さな裁判官が住んでいるようです。
「この時間の使い方は、有益だったか?」
「今の発言は、正しかっただろうか?」
「この選択は、良いことか、悪いことか?」
四六時中、自分の行動や感情に、
- 良い
- 悪い
- 正しい
- 間違い
の判決を下し続ける…。
正直、これって、ものすごく疲れることですよね。
この思考の癖こそが、私たちの心をすり減らす大きな原因になっているんです。
そこで、まず試していただきたいのが、哲学の「判断中止(エポケー)」という考え方です。
難しそうに聞こえますが、要は「思考のお休みスイッチ」のようなもの。
全ての物事に対して、無意識に貼っている
「良い/悪い」
「意味がある/ない」
といったレッテルを、意識的に“一旦停止”してみる、という心の技術です。
一番わかりやすいのが、五感を使う練習です。
もしよろしければ、一緒にやってみませんか?
【五感を解放する3分間ワーク】
準備 いつも飲んでいるコーヒーでも、お茶でも、一杯の水でも構いません。何か飲み物を用意してみてください。
眺める(視覚) まずは評価せず、ただカップの色や形、湯気の揺らめき、液体の透明度を、20秒ほど静かに「眺め」ます。
香る(嗅覚) 次に香りを「分析」するのではなく、ただ胸いっぱいに吸い込み、その香りが鼻を通っていく感覚だけを意識します。
触れる・聴く(触覚・聴覚) カップを持った時の温かさや冷たさ、指先の感触。静かな部屋で聞こえる、衣擦れの音や、遠くの車の音に、そっと耳を澄ませてみてください。
味わう(味覚) 「美味しいかどうか」を考える前に、液体が舌に触れた瞬間の質感、喉を通っていく感覚を、ただ心の中で実況中継するように感じてみます。
どうでしょう。
ほんの数分ですが、頭の中の裁判官が、少しだけ静かになったような気がしませんか?
私はこのワークを、凝り固まった体をほぐす「ストレッチ」のようなものだと思っています。
思考にも癖や凝りがあるんです。
このワークは、常に緊張している「評価する思考」を優しく緩め、
普段は眠っている「感じる感覚」を呼び覚ますための、
誰にでもできる「心のストレッチ」なのです。
これを日常のふとした瞬間に取り入れるだけで、不要な自己批判が減り、何気ない日常の中に隠れていた、たくさんの「心地よさ」を再発見できるようになりますよ。
解決策②【ストア派】不安の9割を手放す。「変えられること」だけに集中する技術
将来のこと、他人の評価、変えられない過去…。
よくよく考えてみると、私たちの悩みのほとんどは、考えても仕方のない
「自分ではどうにもならないこと」
で出来ている、なんてことはないでしょうか。
どうにもならないことを、どうにかしようとすればするほど、心は消耗し、無力感に苛まれてしまいます。
そんな時に絶大な効果を発揮するのが、古代ローマのストア派哲学が提唱した、極めて強力な思考法、「コントロールの二分法」です。
やり方は、驚くほどシンプル。
人生で起こる全ての出来事を、たった2つの箱に、仕分けていくだけです。
-
箱① 自分にはコントロール”できない”こと
-
箱② 自分にコントロール”できる”こと
もしよかったら、今、紙とペンを用意して、あなたの悩みをこの2つの箱に仕分けてみてください。
【心の仕分けワークシート】
まず、紙の真ん中に一本、縦線を引きます。
左側に「コントロールできないこと」を書き出します。
(例)上司の機嫌、景気の動向、他人の噂話、過去の失敗、天候…
右側に「コントロールできること」を書き出します。
(例)今日の自分の行動、言葉遣い、物事の受け止め方、寝る時間、誰に会うか…
書き終えたら、左側をじっと眺めて、心の中でこう宣言します。
「これは、私の管轄外だ」と。
そして、右側に書かれたことだけに、あなたの貴重なエネルギーと時間を集中させると、静かに決意するのです。
このワークは、他人の車や天候に文句を言う「助手席」から、自分のハンドルをしっかりと握る「運転席」に意識を戻すためのもの、と考えると分かりやすいかもしれません。
私たちは、天候を変えることはできません。
でも、傘を持っていくか、どの道を通るか、車内でどんな音楽を聴くかは、自分で決められます。
その「自分で決められる」という感覚を取り戻すことこそが、無力感から抜け出すための、最も確実な鍵なのです。
この思考法を習慣にするだけで、あなたの漠然とした不安は、その9割が自然と消えていくはずです。
そして、自分が本当に力を注ぐべきことが明確になり、日々の生活に、確かな手応えと穏やかな自信が生まれてくることを、お約束します。
解決策③【プラグマティズム】”正解探し”から”お試し”へ。暮らしの小さな実験のススメ
「何かを始めたいけど、何が正解かわからなくて、結局動けない」
「失敗するのが怖くて、最初の一歩がどうしても踏み出せない」
完璧な答えを探しているうちに、何もできなくなってしまう…。
真面目な人ほど、この「分析麻痺」という罠に陥りやすいものです。
そんなあなたに、アメリカで生まれた「プラグマティズム」という、とても実践的な哲学の考え方をお贈りします。
その教えは、たった一言。
「まず、やってみよう。その結果が、あなただけの答えを教えてくれる」
頭の中でこねくり回している「机上の空論」よりも、実際に行動して得られる「生きた経験」の方を、何よりも重視する考え方です。
この考え方を、日常に取り入れるための合言葉。
それは、「暮らしの科学者になる」です。
| 【これまでの考え方(正解探し)】 | 【これからの考え方(小さな実験)】 |
| 「人生の選択」は、重くて怖い | 「日々の実験」は、軽くて楽しい |
| 「失敗」は、絶対に避けたいもの | 「データ収集」は、次に活かせる財産 |
| 「正解」は、行動する前に知りたい | 「自分なりの答え」は、行動した後に見つかる |
どうでしょう。
少しだけ、行動へのハードルが下がったような気がしませんか?
ぜひ、あなただけの一冊の「実験ノート」を用意してみてください。
そして、日常の中でふと浮かんだ、ささやかな「もし~したら?」を記録していくのです。
-
仮説① もし、通勤中に一駅だけ音楽を聴かずに、街の音に耳を澄ませたら、何か発見があるかもしれない。
-
実験① 実際にやってみる。
-
結果と考察 車の音は思ったよりうるさかった。でも、公園の近くで鳥の声が聞こえて、少しだけ気持ちが和んだ。次は、週末の朝に公園で試してみよう。
この、試行錯誤の繰り返しこそが、あなただけの「心地よいことリスト」を、少しずつ作り上げていってくれます。
よく、「目的は探すものだ」と言われます。
でも、私は少し違う考えを持っています。
目的は、探すものではなく、「育つ」ものなのではないでしょうか。
様々な種類の種(小さな実験)を、自分の心の畑に蒔き続ける。
どの種が、いつ、どんな芽を出すかは、誰にもわからない。
でも、水をやり、光を当て続けるうちに、いつの間にか自分でも予期しなかった、あなたらしい「目的」という名の芽が、ひょっこりと顔を出している。
だから、今は焦って探さなくていいんです。
日常を、あなただけの「実験場」という、ワクワクする舞台に変えてみませんか?
そのプロセスを楽しむこと自体が、人生を豊かにする、全く新しい方法なのですから。
【この章のポイント】
日常の小さな瞬間に「評価」せず「ただ味わう」練習をすると、心の疲れが減っていく。
悩み事を「変えられること」と「変えられないこと」に仕分けるだけで、不安の9割は手放せる。
「正解探し」をやめ、日常を「小さな実験」の場に変えることで、行動へのハードルが劇的に下がる。
心がざわつく夜に読む。哲学の賢人たちとの対話 Q&A
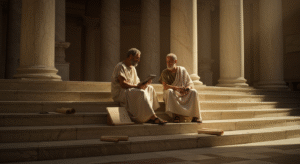
ここまでご紹介した考え方や習慣を試しても、やっぱり、ふとした瞬間に心がざわついてしまう夜もあるかもしれません。
長年の思考の癖は、そんなに簡単には消えないものですから。
「頭では分かっているんだけど、どうしても感情がついていかない…」
あなたの心の中に浮かぶであろう、正直な疑問。
それに、歴史上の偉大な賢人たちが、そっと寄り添い、答えてくれます。
Q. 目的を持って輝く人が羨ましく、劣等感で辛くなります。
A. その感情、本当に苦しいですよね。
SNSを開けば目に入る、誰かの華やかな成功譚。
それに比べて、自分の日常はなんて地味で、平凡なんだろう…。
心が、ちくっと痛むような、あの感覚。
それはあなたが弱いからではなく、あまりにも人間的で、自然な感情です。
だから、そんな風に感じてしまう自分を、どうか責ないであげてください。
なぜ、私たちはこんなにも苦しくなってしまうのか。
それは、私たちが無意識のうちに「他人の『ハイライト動画』と、自分の『メイキング映像』を比べている」からなんです。
編集され、最高に輝いている一瞬と、カットされていない、うまくいかない時間も含めた自分の全ての過程。
それを比べてしまえば、落ち込んでしまうのは、むしろ当然のことですよね。
ここで、フランスの哲学者アランの、こんな言葉に耳を傾けてみませんか。
「幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ」
原因と結果が、まるで逆転していますよね。
この視点を、今回のあなたの悩みに応用してみましょう。
つまり、
「目的を達成したから輝くのではなく、”今”この瞬間を楽しんでいるから、その姿が輝いて見える」
ということです。
私たちが本当に羨ましいと感じているのは、その人が手に入れた「結果」そのものではありません。
その人が、何かに夢中になり、没頭している、その「”今”を生きる姿」に、心を奪われているのです。
だとしたら、私たちが目指すべきは、他人と同じ「輝き」を手に入れることではないはずです。
比べる物差しを、少しだけ変えてみませんか。
「あの人と比べて、自分はどうか」という物差しから、
「昨日の自分より、今日のコーヒーを少しだけ深く味わえたか」
「先週の自分より、今日の散歩で新しい発見があったか」
という、あなただけの「充足度」を測る物差しへ。
比べる相手は、他人ではありません。
ほんの少し前の、自分自身だけで、もう十分なんですよ。
Q. 何も成し遂げないまま、人生が終わりそうで焦ります。
A. 時間だけが、まるで砂時計の砂のように、サラサラとこぼれ落ちていく。
なのに、自分の人生の物語は、まだ一行も始まっていないような気がする…。
その、出口のないトンネルにいるような焦燥感。
特に、真面目で、誠実な人ほど、この「空虚感」に苛まれてしまうものです。
この焦りの根っこには、おそらく、こんな無意識の思い込みがあるのではないでしょうか。
「人生の意味とは、歴史に名を残すような『大きな何かを成し遂げること』である」
と。
でも、本当にそうなのでしょうか。
ここで、強制収容所という、想像を絶する極限状態を生き抜いた精神科医、ヴィクトール・フランクルの言葉に、静かに耳を澄ませてみたいと思います。
彼は、人生の意味について、こう語りました。
人生の意味とは、私たちが人生に問いかけるものではない。
むしろ、人生の方が、私たちに問いかけてくるものなのだ、と。
私たちの役割は、その、日々投げかけられる小さな問いかけに、誠実に「応答」していくこと。
ただ、それだけなのだと。
その「問いかけ」とは、決して、何か大きなことを成し遂げろ、というような大げさなものではありません。
目の前で疲れている家族の話を、今日は遮らずに、最後まで優しく聞けるだろうか?
誰も見ていない、この退屈な作業に、ほんの少しだけ、丁寧さを加えてみることはできるだろうか?
道端で困っている人に、見て見ぬふりをせず、声をかける勇気はあるだろうか?
…そんな、日常の中に無数に散りばめられた、ささやかな問いかけです。
あなたは、「何かを成し遂げる」ために、ここにいるのではありません。
「日々の小さな問いかけに、誠実に応答し続ける」ために、ここにいるのです。
そして、その誠実な応答の一つひとつが、誰にも真似することのできない、あなただけの、尊い意味の物語を、静かに、しかし確実に、紡いでいってくれる。
フランクルの言葉は、私たちにそう教えてくれているように、私には思えるのです。
【もっと深く知りたいあなたへ】
ヴィクトール・フランクルの思想の原点に触れたい方は、ぜひ一度『夜と霧 新版』(みすず書房)を読んでみてください。
短い本ですが、きっと、あなたの人生の見え方が変わるはずです。
【まとめ】さあ、「探す」のをやめて、「歩き出す」時がきた

私たちは一緒に、「目的」という言葉の呪縛から心を解き放ち、目的のない「余白」が持つ本当の価値を知り、そして、日常の中で実際に使える3つの心の道具を、手に入れてきました。
もう、あなたは、何も探さなくていいんです。
「目的を探す」という行為は、常に「本当の人生は、ここではないどこかにある」と言っているのと同じこと。
それは、今の自分と、今のこの日常の価値を、無意識のうちに否定してしまうことに繋がります。
でも、本当は、そうではありません。
あなたの足元に、全ての豊かさは、すでにあるのですから。
何か大きな決意をする必要は、全くありません。
ただ、もしよろしければ、一つだけ、ご自身に約束をしてみてはいかがでしょうか。
「今日、帰り道に、いつもは通らない路地を一本だけ曲がってみる」
結果なんて、どうでもいいんです。
何かを発見できなくても、もちろん構いません。
その、目的のない一歩。
その、ほんの少しの寄り道こそが、あなたの新しい人生の、本当の始まりになるはずです。
目的とは、探すものではなく、あなたが歩いた後に、いつの間にかできている、愛おしい轍(わだち)のようなもの。
焦らず、比べず、あなただけの、今日の散歩を、どうぞ心から楽しんでください。
心から、応援しています。
【この章のポイント】
-
他人と比べて辛い時は、「結果」ではなく「”今”への没頭」に目を向け、比べる相手を「過去の自分」に切り替える。
-
人生の意味とは「成し遂げる」ものではなく、日々の小さな「問いかけに応答する」積み重ねの中に見出される。
-
もう「探す」必要はない。ただ、目的のない「はじめの一歩」を踏み出すことから、全ては始まっていく。
【こちらの記事も読まれています】

【このブログについて】
このブログでは、「心」や「哲学」をテーマに、日々の暮らしが少しだけ豊かになるような考え方のヒントを発信しています。
私たちの願いは、あなたがあなた自身の力で、「自分にとっての幸せとは何か?」を探求していく、そのささやかなお手伝いをすることです。
もし、今回の記事があなたの心に少しでも響くものがあったなら、きっと他の記事もお役に立てるかもしれません。
豊かさや幸せについて、さらに深く考察した記事もありますので、お時間のある時にでも、また散歩のついでに、立ち寄ってみてくださいね。


