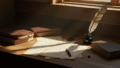【導入】もし、人生のあらゆる決断に「幸福のものさし」があったなら
この記事では、一見難しそうなベンサムの思想を、あなたの日常で使える「思考の型」へと完全に作り変えました。
まったく新しい視点を古い哲学から、具体的な解決策を丁寧に抽出してお伝えしていくよ。
200年前の知恵が、なぜ今のあなたの悩みに効くのか。それは、彼の考えが人間の「幸福」という、私たちの心のど真ん中を貫くテーマに基づいているから。
さあ、その古くて新しい心の道具を、一緒にあなたの武器に変えていきましょう。
これから話すのは、分厚い本に書いてある難しい言葉の暗記じゃないんだ。
もっとシンプルで、ある意味では、すごくドライな考え方の話。
あなたの日常に、そっと寄り添うか、一つの思考の道具の話だよ。
【前半】思想の全体像を、わかりやすく理解する

【ベンサムの思想の要点】功利主義とは?幸福を「天秤」にかける思考法
結論から言おうか。 ベンサムが考えた功利主義とは、
「関係者みんなの“うれしい”とか”楽しい”とか”幸せ”の合計が、一番大きくなる選択こそが正しい」と考える、いわば「幸福の天秤」。
こんな感じのイメージなんだ。
あなたの喜びも、私の喜びも、そこにいる誰かさんの喜びも。 偉いとか、貧しいとか、そういうの一切関係なく、ぜんぶ等しく一つの天秤に載せてみる。
そして、社会全体で見たときに、一番どっしりと“うれしい”の方に傾く選択肢はどれだろう、と。 冷静に、ただひたすら冷静に、それだけを探す。 これだけ、功利主義の基本的な考え方は。
皆のハッピーポイントが多い方が「良い」という考え方だね。
どうして彼は、人の心なんていう、ふわふわして掴みどころのないものを、社会の基準にしよう、なんて考えたんだろうね。
ジェレミ・ベンサムが生きた18世紀のイギリスは、産業革命の真っ只中。 古い街並みが壊され、新しい工場がもくもくと煙を上げる。そんな、社会全体が大きく揺れ動いていた時代だったね。
古いしきたりや、どう考えても不公平な法律が、まだ当たり前のように残っていて、そのせいで、たくさんの人が息苦しさを感じていた。
彼は、優れた法学者でありながら、社会を本気で良くしたいと願う、情熱的な改革家でもあったよ。 彼の目には、当時の社会が、まるでバグだらけでぎこちなく動く、複雑な機械みたいに見えていたのかもしれない。
「どうして、一部の人の都合や、遠い昔の迷信みたいなもので、こんなに多くの人が苦しまなきゃいけないんだ?」
その、じりじりとした義憤が、彼の出発点。
そして、そのバグを直すために、彼は誰の目にも明らかな「客観的なものさし」を探したんだ。
それが、人間であるなら誰もが、心の奥底に持っているはずの「気持ちよさを求め、痛みを避けたい」という、ごく自然な感情だったんだよ。
ここで、少しだけ専門的な話を。
ベンサムの思想は「最大多数の最大幸福」という言葉で知られているけど、実はこの言葉を最初に使ったのは、フランシス・ハチソンという別の哲学者だと言われているんだ。
ベンサムも初期にはこの言葉を使っていたけど、後に
「“最大多数”を優先するあまり、全体の幸福の“総量”を最大化するという目的からずれてしまうかもしれない」
と考え、より厳密な「最大幸福原理」という表現の方を好むようになったんだね。
この記事では、彼の意図を汲んで、「全体の幸福の総量」という視点で話を進めていくよ。
幸福を測る7つのものさし【快楽計算】とは?
さて、幸福を天秤にかける、と言っても、どうやって測ればいいんだろうね。
そこでベンサムが考え出したのが、「快楽計算」。
いわば、幸福という、もやもやしたものを分析するためのツールだね。
あ、誤解しないでほしいんだけど、彼が目指したのは、人々を計算ずくの冷たい人間にすることじゃなかった。
むしろ、これまで一部の権力者のあいまいな判断や都合で決められていた社会のルールを、誰もが納得できる透明な基準で作り直したかったんだ。
ベンサムは、快楽の種類には本質的な優劣はなく、知的な喜びも、美味しいものを食べる喜びも、すべて同じ尺度で量的に測定できると考えたんだ。 そのために、以下の7つの基準(ものさし)を考えたんだよ。
- ① 強度 (Intensity):その快楽は、どれくらい「うわぁ!」ってなるか。
- ② 持続性 (Duration):その快楽は、どれくらい長く続くか。
- ③ 確実性 (Certainty):その快楽は、どれくらい確実に手に入るか。
- ④ 遠近性 (Propinquity):その快楽は、どれくらいすぐ手に入るか。
- ⑤ 生産性 (Fecundity):その快楽は、次の快楽を生み出すか。
- ⑥ 純粋性 (Purity):その快楽は、後から面倒なことを連れてこないか。
- ⑦ 範囲 (Extent):その快楽は、どれくらい多くの人に影響を与えるか。
鋭い疑問だね。
ここで注意したいのは、ベンサムが言う「純粋性」や「生産性」は、快楽そのものの“質”ではない、ということ。
これらは、ある快楽が、結果としてもたらす長期的な影響(例えば、飲みすぎた次の日の頭痛という“苦痛”が混じっていないか)を考慮するための、あくまで量的な計算の一部なんだよ。
彼の考えの根底には、あくまで「快楽は快楽であり、種類によって価値は変わらない」という、徹底した平等主義があったんだね。
【後半】思想を、日常で使える「思考の型」に応用する

【人生の決断】ベンサムの思想を応用する「未来予測シート」の使い方
さて、ここからは、この少し変わった思想を、あなたの日常で使える、具体的な「思考の型」へと応用していこうか。
生きていれば、どうしたって、どっちの道に進めばいいのか分からなくなる時がある。 そんな、人生の岐路に、ふと立ちすくんでしまった時のために。
ベンサムの考え方を応用した「未来予測シート」というものを紹介するよ。
これは、あなたの迷いの霧を晴らし、より「ああ、これで良かったんだ」と納得感のある決断を後押しするための、特別なフレームワークだよ。
▼未来予測シート
なぜ、わざわざこんなシートが有効なのか。
それは、頭の中の漠然とした不安や期待を、一度「書き出す」ことで、自分から切り離して、客観的に眺められるようになるからだよ。
ざわざわと騒ぐ感情的な自分と、腕を組んで冷静に見ている自分。 その両方と、ゆっくり相談しながら、未来の輪郭をなぞっていく。そんな作業なんだね。
多くの人が一度は悩むであろう、「転職」を例に考えてみようか。(あくまで”例”です)
どうだろう。
このシートは、どちらの未来が「より幸福か」を教えてくれる魔法の水晶玉ではないよ。
どちらの未来が、より「あなたらしい幸福の形か」を、あなた自身が知るための、一枚の鏡なんだね。
ここで、とても、とても大切な注意点を、一つだけ伝えておくよ。
もし、このシートでの計算結果が、あなたの心の奥底からの声と、逆のことを示していたら、どうする?
結論から言えば、その心の声を、決して無視してはいけない。
ベンサムの思考法は、あくまで幸福の「量」を測るツールだ。 あなたにとっての「誇り」とか「夢」とか「愛情」といった、数値化なんて到底できない、あなただけの「譲れない価値」までは、保証してくれないんだ。
最後は、あなた自身の心の指針を、信じてあげてね。
論理と感情、その両方と、丁寧に対話した末の決断こそが、きっとあなたを、より納得感のある未来へと、そっと導いてくれるはずだから。
【人間関係】ベンサムの思想で対立を乗り越える「相手の天秤」の想像術
さて、もう一つの応用編だ。
次は、他者との関わりについて、考えてみようか。
なぜ、私たちはすれ違うんだろうね。 その根源的な理由は、たぶん、お互いが「自分の天秤」に載っているもの(自分自身の利益や感情)しか、見えなくなってしまっているからだよ。
ここで、ベンサムの思想が、役に立つ。
対立して、心がカッと熱くなった時こそ、一度ぐっとこらえて、こう想像してみるんだ。
「相手の天秤には、今、どんな “うれしい” と “かなしい” が、載っているんだろう?」
これが、ベンサムの思想を人間関係に応用するための、シンプルで、でも、極めて強力な第一歩。 私はこれを、ひそかに「相手の天秤の想像術」と呼んでいるよ。
相手の天秤を想像できたら、次が、最も重要なステップだね。
「正しさ」のぶつけ合いは、結局のところ、どちらかが我慢して、二人の幸福の総量をじりじりと減らすだけの、不毛な消耗戦だ。 目指すべきゴールは、そこじゃない。
新しいゴールを設定しようか。
それは、
『私の天秤』と『相手の天秤』、その両方が、どうすれば一番“うれしい”に傾くだろうか?
という、共通の問いを、二人の間に、そっと置くことだね。
「どっちが正しいか」ではなく、「二人の幸福を、どうやったら増やせるか」。
この小さな思考の転換が、あなたの人間関係を、きっと、より温かく、豊かなものにしてくれるはずだよ。
【補論】思想の「光と影」を知り、思考を深める
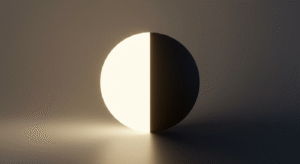
【深掘り分析】ベンサムの功利主義が批判される3つの問題点
さてと。
ここまで、ベンサムの思想がいかに強力で、便利な道具であるかを見てきたね。
だけど、ここからは、この道具が、その鋭さゆえに持ってしまう「影」。つまり、その危険性についてだ。
「全体の幸福」という言葉。
これは、一見すると、誰も反論できないような、きらきらした響きを持っているよね。 だけど、その大きな光が、時として、たった一人の尊厳や、数では到底測れない、ざらついた手触りのある大切なものを見えなくしてしまうことがある。
この問いを考える上で、どうしても避けては通れない、有名な思考実験がある。
「トロッコ問題」だ。
線路を、一台のトロッコが猛スピードで暴走している。その先には、5人の作業員がいる。このままでは、5人は、確実に死んでしまう。あなたの手元には、線路の切り替えレバーがある。レバーを引けば、トロッコは別の線路に進み、5人は助かる。だけど、その先の線路にも、一人の作業員がいる。あなたがレバーを引けば、その一人は、確実に死ぬ。
純粋な功利主義の「幸福の天秤」にかければ、答えは、驚くほど、あっさりと出てしまう。
「5人の命」と「1人の命」。天秤は、迷いなく、「5人」の方に傾く。
功利主義による結論は、「ためらわず、レバーを引くべきだ」となるわけだ。
でも、あなたの心は、本当にそれを、何の曇りもなく「正しい」と、納得できるだろうか。
全体の幸福量を最大化するという目的は、時として「個人の権利」や「人間の尊厳」といった、数では測れない原則と、激しく衝突してしまうんだね。
この、どこかぞっとするような計算が、現実の世界で、しかも、大きな会社の、静かな会議室で実際に行われたのが「フォード・ピント事件」だ。
1970年代、フォード社は、自社の車「ピント」に、追突されると燃料タンクが破裂しやすいという欠陥があることに気づいていた。 彼らは、ここで、一つの冷徹な計算を行ったんだ。
- 「全車両をリコールして修理する費用」
- 「欠陥を放置した場合に予測される死傷者への賠償金」
その二つを天秤にかけ、計算上、「修理費用」の方が高いと判断した彼らは、人々の安全よりも企業の利益を優先し、欠陥を放置するという決断を下したんだよ。
この事件が私たちに突きつけるのは、根源的な問いだ。
「そもそも、人の命や安全、人間の尊厳に値段をつけて、他の利益と平気で比較計算すること自体が、根本的に、何かが間違っているのではないか?」
最後の問題点は、功利主義の内部から生まれた、魂の叫びともいえるような批判だよ。
それを唱えたのは、誰あろう、ベンサムの一番弟子、ジョン・スチュアート・ミルだった。
師であるベンサムが快楽の「量」のみを問題にしたのに対し、ミルは、快楽には明確に「質」の違いがあるはずだ、と主張したんだね。 そして、その信念を、彼は、こんな有名な言葉で表現したんだ。
満足した豚であるより、不満足な人間であるほうが良い。 満足した愚か者であるより、不満足なソクラテスであるほうが良い。
ミルが言いたかったのは、たぶん、こういうことだよ。
たとえ、低俗で感覚的な快楽に、ただただ満たされて「満足」して生きる豚がいたとしても。 私たち人間は、時に悩み、時に苦しみながらも(つまり、不満足であっても)、知性を働かせ、より高い精神性を求める生き方の方が、ずっと尊いのだ、と。
ベンサムが幸福の「広さ」を示したとすれば、ミルは幸福の「高さ」を示したんだね。
【現代への問い】ベンサムの思想はAIと監視社会を予見していた?
古い哲学の話は、もうお腹いっぱいだ、と思ったかもしれない。
だけど、本当に、ぞっとするほど恐ろしいのは、ここからだよ。
ベンサムが夢想し、そして批判された世界は、今、あなたのポケットの中にあるそのスマートフォンで、静かに、でも確実に、現実のものとなりつつあるんだから。
ベンサムは、功利主義的な社会を、効率的に実現するための具体的な建築物として、「パノプティコン」という、一望監視が可能な、円形の刑務所を構想した。
この建物の巧妙なところは、中央の監視塔から、全ての囚人の独房が、まるっと見える。その一方、囚人からは、監視塔の様子が、よく見えない。
つまり、囚人は「常に、誰かに監視されているかもしれない」という意識を、自分の内側に取り込んで、監視者が、たとえ居眠りしていても、自ら規律正しい振る舞いをするようになる、という仕組みだね。
さて、この話。
何かに、とてもよく似ていると思わない?
そう、現代のSNS空間だ。
私たちは、他者の評価(いいね、コメント、フォロワー数)を、常に、ちらちらと意識しながら、時に「ウケの良い自分」を演出し、投稿する言葉や写真を選んでいく。
かつての囚人は、分厚いコンクリートの壁に囲われていた。 現代の私たちは、自ら進んで「見られる」ことで、目に見えない、透明な壁の中に、囚われているのかもしれない。
最後に、あなた自身が、その当事者となる問いを投げかけたいと思う。
それは、自動運転AIが、どうしても避けられない事故に直面した時、一体、誰の命を優先するように、プログラムされるべきか、という問題だよ。
あなたが乗る、一台の自動運転車。
ブレーキが故障し、このままでは、前を横断している5人の歩行者に、突っ込んでしまう。
AIに残された、たった一つの選択肢は、急ハンドルを切り、道路脇の壁に激突すること。
そうすれば、5人の歩行者は助かる。
でも、乗っている、あなた一人が、犠牲になる。
もし、このAIが、純粋な功利主義でプログラムされていたら、どうなるだろう。
答えは、もう、お分かりだね。
AIは「5人を救う」ために、一瞬の迷いもなく、壁への激突を選び、あなたを犠牲にするだろう。
この問いに、まだ、世界の誰も、答えを出せずにいる。
それは、この問いが「どのプログラムが正しいか」という、技術的な問題ではなく、
「私たち人間は、何を、最も大切にすべきか」
という、哲学そのものを、真正面から、私たちに問うているからなんだ。
【さらなる思考】功利の怪物という問い
ここまで読んでくれたあなたなら、もう一つ、面白い思考実験に付き合ってほしい。
ベンサムの功利主義を、さらに深く揺さぶる「功利の怪物」という考え方があるんだ。
もしも、あなたが感じる幸福の「100倍」も大きな幸福を感じられる存在がいたとしたら?
社会全体の幸福を最大化するためには、全ての富や食料を、その一体の「怪物」に集中させるのが正しい、ということになってしまう。 たとえ、周りのみんなが、飢えて不幸になったとしても、だ。
これは、
「全体の幸福の合計値さえ大きければ、その分配の仕方はどうでもいいのか?」
という、功利主義の、ぞっとするような弱点を突いたものだね。
これもまた、絶対的な答えのない問いだ。
ただ、私たちが「幸福」を考えるとき、その「総量」だけでなく、その「配り方」にも、心を配る必要があるのだということ。
そのことを、この少し奇妙な怪物は、静かに教えてくれているのかもしれない。
まとめ ベンサムの思想を手に、あなたはどんな「幸福」をデザインするか?

ふぅ。ずいぶんと、長い道のりだったね。
私たちは、ジェレミ・ベンサムという、二百年以上も前の一人の思想家が遺した、「幸福の天秤」という、少し変わった道具を手に取った。
まず、前半で、その道具の基本的な仕組みを学んだ。
功利主義が「関係者みんなの幸福の総量を最大化する」という、シンプルで画期的な考え方であること。そして、「快楽計算」というツールで、もやもやとした感情を「見える化」できること。
次に、後半では、その道具を、あなたの日常という、現実の舞台で使ってみた。
「未来予測シート」で、人生の大きな決断の霧を晴らし、「相手の天秤の想像術」で、人間関係のもつれを、そっと解きほぐす視点も手に入れたね。
そして最後に、この道具が持つ、まばゆい光と、その裏側にある、深く暗い影の両方を、じっと見つめてきた。
結局のところ、ベンサムの思想から、私たちが学ぶべき最も大切なことは、何だったんだろう。
それは、あらゆる場面で完璧な答えを出してくれる、魔法の計算式そのものでは、きっとない。
この思想の、本当の価値。
それは、
私たちの視野を、どうしても凝り固まりがちな「自分」という、ちっぽけな世界から、「自分を含む、より多くの人々」へと、ぐいっと強制的に広げてくれる点にある。
そう、私は思うよ。
独りよがりな正義や、狭い思い込みから、私たちを自由にしてくれる。
その点にこそ、価値がある。
自分の選択が、自分の、ほんのささいな行動が、巡り巡って、どこかの誰かの天秤を、ほんの少しでも「うれしい」に傾けられるかもしれない。
あるいは、知らず知らずのうちに、「かなしい」の方に、重りを乗せてしまっているのかもしれない。 その想像力を、常に、心の片隅で働かせ続ける姿勢。
それこそが、彼が私たちに本当に遺したかった、一番大切な心の指針なのかもしれないね。
私はあなたに、一つの、強力な思考の道具を手渡した。 この道具は、使い方次第で、より多くの人を幸せにするための、温かい設計図を描くこともできれば、冷徹な計算で、誰かを傷つけるための、たい凶器にもなり得る。
どう使うかは、これからを生きる、あなた自身にかかっているんだ。
なにも、難しく考える必要はないよ。
まずは今晩にでも、あなたがした小さな選択が、誰かの天秤を、ほんの少しでも“うれしい”に傾けられたか、思い出してみることからはじめてはどうだろう。
コンビニの店員さんに、ひとこと「ありがとう」を、ちゃんと言えたか。家族の話を、昨日より、少しだけ長く聞けたか。 そんな、本当に、ささやかなことでいいんだ。
ベンサムは、幸福を測るための一つの方法を、私たちに示した。
でも、あなたの幸福が、一体、どんな質感で、どんな温かさで、どんな形でできているかまでは、教えてはくれないんだ。
だから、最後に、こう問いかけたい。
その道具を手に、あなたは、あなた自身の、そして、あなたの周りの世界のために、どんな「幸福」を、これからデザインしていく?
【こちらの記事も読まれています】

このブログでは、こんなふうに、少しだけ変わった視点から「豊かさ」や「幸せ」について考えるための、様々なヒントを研究しているよ。
もし、もう少しだけ、思考の散歩にお付き合いいただけるなら、他の記事も覗いてみてくれるとうれしいな。