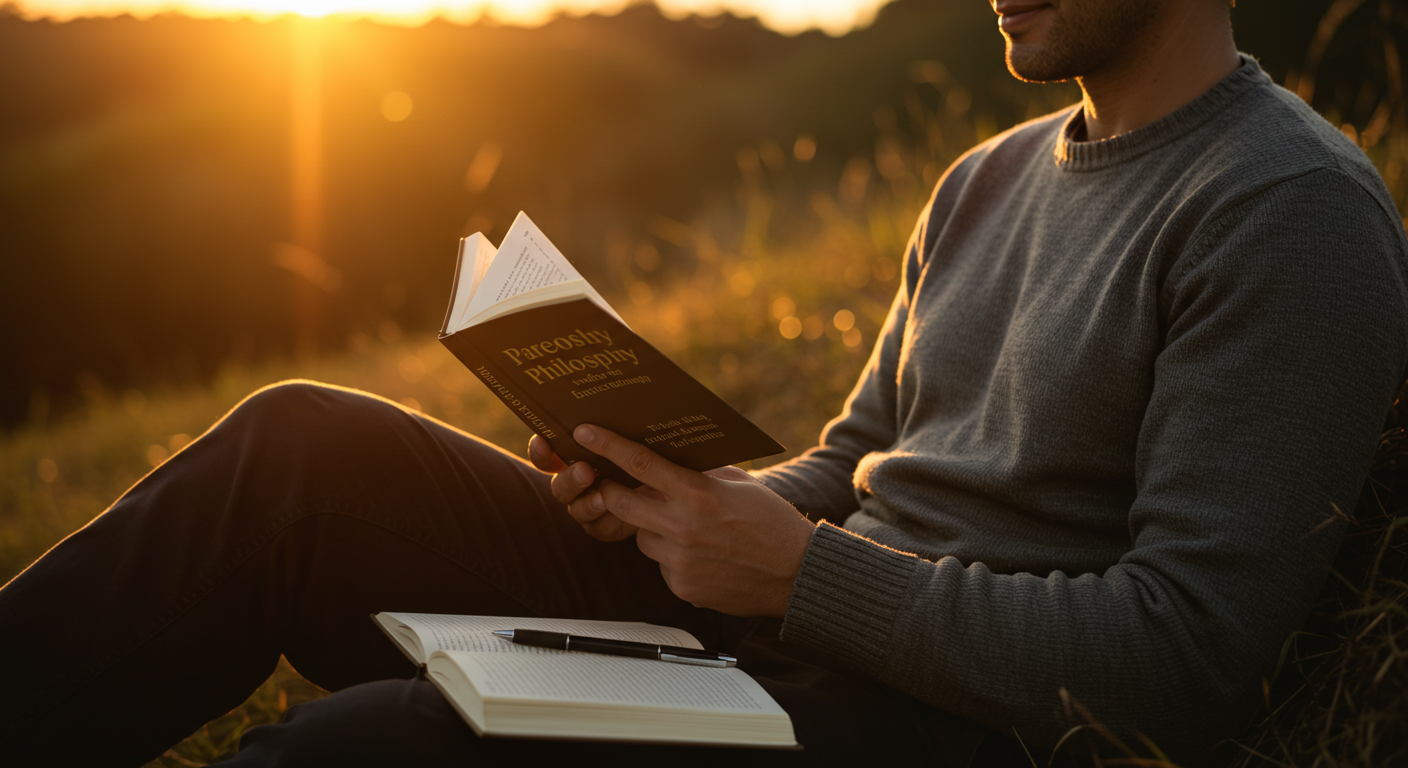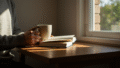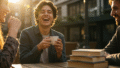「頑張っているのに、なぜか心が満たされない…」
そんな漠然とした悩みを抱えていませんか?
この記事を最後まで読めば、もう他人の価値観に振り回されることなく、あなただけの「幸せの基準」をその手に見つけることができます。
そのために、哲学を「思考の道具」として、
①社会の思い込みから自由になる方法、
②自分の本心を探るための対話法、
③日常に豊かさを発見する観察法まで、
具体的なステップを網羅的に解説しますね。
これらは、何千年もの間、多くの賢人たちが考え抜いてきた、信頼できる人類の知恵です。
頑張っているのに、なぜか心が満たされないあなたへ
SNSを開けば、誰かの「幸せ」と比べてしまう…。
一日中パソコンと向き合って、あぁ、疲れた…。
やっとの思いで重い体をソファに「ずしん」と沈めた夜。部屋のしんとした空気感が、かえって心の中のざわめきを大きくさせる。
そんな時、ありますよね。
つい、手の中のスマートフォンに吸い寄せられて、習慣でSNSを開いてしまうこと。
指先で画面をなぞれば、流れてくるのは友人たちの、まぶしいくらいの投稿。
海外での休暇、素敵なパートナーとの記念日、仕事での大きな成功…。
ふむ。
みんな、それぞれの場所でちゃんと輝いているように見える。
それに比べて、自分の一日はどうだったかな、なんて。
代わり映えのしない、いつもと同じ景色。
頭のどこかでは、ちゃんと分かってるんです。
「人と比べても、意味なんかないよ」って。
でも、胸の奥が、チクっと痛む。
自分だけが、なんだか取り残されていくような、あの感覚。
あぁ、これって本当に、しんどいですよね。
「私だって、毎日ちゃんと頑張っているはずなのに…」
そんな言葉にならないため息が、静かな部屋に、ぽつりと落ちる。
それはね、あなたが弱いからとかじゃあありません。
むしろ、自分の人生にとても真面目に、誠実に向き合っているからこそ生まれてくる感情なんじゃないかな、と。
私は、そう思うのです。
実は「幸せ探し」には“罠”がある
まず、一番に知っておいてほしいことがあります。
その、どうしようもない虚しさは、あなたの努力不足とか、能力のせいじゃない。
…たぶんね。私はそう思いたい。
じゃあ、その正体は一体何なのか。
実は、今の社会には、私たちが気づかないうちにハマってしまう、巧妙な「幸せ探しの“罠”」が、いくつも仕掛けられているようなのです。
それは、いつの間にか私たちの心に刷り込まれた「こうあるべき」という理想像かもしれない。
あるいは、手に入れても手に入れても、なぜか満たされない人間の脳の仕組み、そのものかもしれない。
この「罠」の存在に気づかないまま、ただがむしゃらに走り続けても、心が満たされないのは、ある意味で当然のことなんですね。
でも、大丈夫。
この記事で、その「罠」の正体を、これから一緒に、一つひとつ、ゆっくり解き明かしていきましょう。
この記事は「答え」は教えません。一生使える「自分だけの幸せ」を見つける“道具”を渡します
先に正直にお伝えしておくと、「こうすれば絶対に幸せになれる!」という、魔法のような簡単な答えはありません!
なぜなら、本当の幸せって、一人ひとり形が違う、完全なオーダーメイド品みたいなものだから。
誰かから与えられた既製品じゃ、心の本当に深いところまでは、なかなか満たされないものなんですね。
その代わりに、この記事があなたにお渡ししたいのは、あなた自身が「自分だけの幸せ」を、ちゃんと自分の手で見つけ出していくための「思考の“道具箱”」です。
そして、その道具こそが、数千年もの間、たくさんの賢い人たちが
「よく生きるって、どういうことだろう?」
と、うんうん唸りながら考え抜いてきた知恵の結晶。
そう、「哲学」なのです。
…なんだか、難しそうに聞こえましたか?
ここでは哲学を、小難しい学問としてではなく、日常を少し豊かにしてくれる、驚くほど実践的な思考ツールとして、丁寧にご紹介しますからね。
この記事を読み終える頃には、あなたはその道具を手に、漠然とした不安の霧の中から、自分だけの道を照らすための、確かな一歩を踏み出せるようになっているはずです。
【この章のポイント】
人と比べて感じる虚しさは、あなたが真面目に生きている証拠です。
その苦しみの原因は、あなた個人ではなく、社会に潜む「幸せ探しの罠」にあるかもしれません。
この記事は「答え」ではなく、哲学という「自分だけの幸せ」を見つけるための実践的な道具を提供します。
なぜ、幸せ探しはこんなにも苦しいのか?現代人が陥る3つの「心の罠」
前の章で、あなたの苦しみは「罠」のせいかもしれない、なんて話をしました。
ここでは、その「罠」の具体的な正体を、三つ、じっくりと見ていきましょう。
あなたが感じている、あの、言葉にならない「生きづらさ」の輪郭が、きっと、すぅっと見えてくるはずですから。
罠① いつの間にか刷り込まれた「幸せのテンプレート」という幻想
良い大学、安定した会社、ある程度の年齢で結婚して、都心に家を持つ…。
んー、なんでしょうね。
私たちは、いつからこれを「誰もが目指すべき幸せ」だと、思うようになったんでしょうか。
こういう画一的な幸福のイメージを、ここでは「幸せのテンプレート」と呼ぶことにします。
これは、テレビや広告、あるいは身近な人々の言葉を通じて、私たちが子どもの頃から、まるで空気を吸うように、無意識に心に刷り込んできたもの。
この「テンプレート」の厄介なところ。
それは、まるで「既製品の服」みたいなものだ、っていう点なんです。
一人ひとり、体つきも、肌の色も、好きなテイストも違うのに、
「今シーズンはこの服が流行りですから!」
って、全員に同じ服を着せようとする。
そりゃあ、当然、サイズが合わなくて窮屈だったり、自分には似合わなくて、なんだか惨めな気持ちになったりする人が出てきますよね。
もしあなたが、世間一般で「幸せ」とされているものに、どこか息苦しさや、「ん?なんか違うな…」という違和感を覚えているのなら。
それは、あなたの感性が鈍いからじゃありません。
むしろ、自分に合わない服をちゃんと「合わないよ」と感じられる、とても繊細で、正直な心を持っている証拠なんだと、私は思います。
罠② 手に入れても満されない脳の仕組み「快楽の踏み車」
念願だったプロジェクトを成功させた。
ずっと欲しかった、あのバッグを手に入れた。
目標だった貯金額に、やっと届いた。
あの瞬間の、胸が「ふわっ」と高鳴るような喜びは、確かにあったはず。
なのに…。
驚くほどすぐに、その感覚は日常に溶けて薄れていって、気づけばまた「何かが足りない」って感じてしまう。
あぁ、こういう経験、あなたにもありませんか。
実はこれ、人間の脳にもともと備わっている、「仕様」みたいなものらしいのです。
心理学の世界では、この現象を「ヘドニック・トレッドミル(快楽の踏み車)」と呼びます。
うん、なんだか難しい名前ですよね。
要するに、
「人間は、良いことにも悪いことにも、びっくりするくらいすぐに慣れちゃう。だから、幸福度って、結局は元の安定したレベルに、自然と戻ってきちゃうんだよ」
っていう、心の性質のこと。
なぜ、こんな切ない仕組みになっているのか。
一説には、人類が現状に「あー、満足」ってならずに、常により良い環境を目指して、ここまで生き延びてくるために必要だった機能だ、と言われています。
だから、あなたが何かを達成しても、すぐに満たされなくなるのは、贅沢になったからじゃなくて、ごく正常に、あなたの脳が働いている証拠とも言えるんですね。
ただ…そう。
この「踏み車」の存在を知らないままだと、私たちは永遠に満たされない渇望を、ただただ追いかけ続けることになってしまうのです。
罠③SNSが加速させる、終わりなき「他人との比較」地獄
そして、現代。
先の二つの罠を、とんでもない勢いで増幅させているのが、ご存知「SNS」です。
ちょっとだけ、冷静になって考えてみてください。
SNSに投稿されるのって、その人の人生の「ハイライト」を、すごく上手に切り取って、きらきらに編集したものですよね。
誰も、わざわざ自分の失敗談や、ベッドから出られない日曜の午後、みたいな舞台裏を切り取って見せたりはしません。
…それなのに。
私たちは無意識のうちに、
自分の「舞台裏を含む、ぐちゃぐちゃな24時間」と、
他人の「輝かしいハイライト集」を、
いとも簡単に見比べてしまう。
考えてみれば、こんなに不公平で自分が不利になるだけのゲーム、ありませんよね。
SNSは、常に魅力的な「幸せのテンプレート」(罠①)を私たちの目の前にぶら下げ続ける。
そして、他人のハイライトを見て「自分も、もっともっと手に入れなくちゃ」と、
「快楽の踏み車」(罠②)を必死に回させ、
永遠に自分を肯定できない「比較地獄」(罠③)に、私たちを閉じ込めてしまうのです。
…と、ここまで聞いて、なんだか、どっと疲れてしまったかもしれませんね。
でも、これらの罠の正体を知った今、あなたはもう、ただ翻弄されるだけの無力な存在じゃありません。
次の章から、これらの罠から抜け出し、あなたの心を本当に自由にするための具体的な「道具」を、一つずつ、一緒に手に入れていきましょう。
【この章のポイント】
私たちは、社会が作った画一的な「幸せのテンプレート」に、知らず知らずのうちに縛られています。
何かを手に入れてもすぐに慣れてしまうのは、「ヘドニック・トレッドミル」という、脳の正常な仕組みです。
SNSは、自分の「舞台裏」と他人の「ハイライト」を無意識に比較させてしまう、現代特有の罠なのです。
【第1部 解放】もう比べない。社会の「思い込み」から心を自由にする3つの哲学思考
さて、あなたの心を縛っていた「罠」の正体が、少しずつ見えてきましたね。
ここからは、いよいよその罠から、ひらりとかわすための、具体的で強力な「思考の道具」を手に入れていきましょう。
何千年も前に生きていた賢い人たちの言葉が、不思議なくらい、今の私たちの心に「すっ」と染み渡るはずです。
ストア派哲学「変えられない悩み」から解放される“コントロール二分法”
上司の、あの理不尽な機嫌。
SNSで目にした、心ないコメント。
あぁ、どうしてあんなことを…と悔やんでしまう、過ぎ去った過去の失敗。
私たちの心を、まるで嵐のようにかき乱す悩みの多くは、よーく考えてみれば、自分では「どうにもできないこと」ばかりだったりします。
ここで、一つ目の道具です。
古代ギリシャのストア派哲学が教えてくれる、
「コントロール二分法」
これは、世の中の出来事をたった二つに分けるシンプルな思考法です。
名前はちょっと硬いですが、中身は驚くほどシンプルですよ。
それは、
世の中の全てのことを「自分にコントロールできること」と「できないこと」の、たった二つに分けて考える
というもの。
-
コントロールできないこと(=考えても仕方がない。そっと手放してOKなこと)
-
他人の評価や感情、過去と未来、景気や天気とか、そういうの全部。
-
-
コントロールできること(=自分のエネルギーを注ぐべき、唯一のこと)
-
自分の考え方や物事の解釈、今日の行動、何を選んで、どう反応するか。
-
そう。
私たちの苦しみのほとんどは、コントロールできないことを、必死になってコントロールしようとすることで生まれるんですね。
この仕分け作業を、頭の片隅に置いておくだけで、無駄な悩みから解放されて、本当に大切なことだけに、自分のエネルギーを注げるようになります。
【例えば、こう使う!】
上司に理不尽に怒られて、心が「どんより」した時。
「怒られた」という事実は、もうコントロールできません。
でも、「この経験から何を学ぶか」「単なる虫の居所が悪かっただけ、と解釈して、さっさと忘れるか」は、100%、あなたがコントロールできる領域です。
【うまくいかなくても、大丈夫】
分かっていても、つい悩んでしまうのが、人間ってもんですよね。
だから、完璧にできなくて当たり前。
「あ、今、自分には変えられないことで、また悩んでるな」と、ただ“気づける”だけで、もう100点満点。
その気づきの回数が、少しずつ増えていくだけで、あなたの心は、確実に軽くなっていきますよ。
エピクロスの哲学「ないもの」より「あるもの」に目を向ける“心の平穏術”
「友人の、あの新しい車、いいなぁ…」
「もっと広い家に住めたら、幸せなのに…」
私たちの心は、放っておくとすぐに「自分にないもの」を探し出して、それと今の自分を比べては、勝手に不満を感じるようにできています。
あぁ、本当に、厄介な癖ですよね。
ここで、二つ目の道具です。
哲学者エピクロスが目指した、最高の幸せ。
「アタラクシア(心の平穏)」という考え方。
彼は、刺激的な快楽をどんどん「足し算」していくんじゃなくて、苦痛や不安といった、心の中の余計なものを「引き算」していくことこそ、真の幸福だと考えました。
つまり、幸せになるために、何か特別なものを、外から「手に入れる」必要はない、っていうこと。
むしろ、「健康な体」「安全な寝床」「話せる友人」「温かい食事」…。
そう、失って初めて、その途方もない価値に気づくような、「当たり前」に、意識的に、そっと目を向けてみる。
日常に、すでに満ちている豊かさを、再発見するのです。
【例えば、こう使う!】
SNSで友人の豪華な旅行の写真を見て、心が「ざわっ」とした時。
すぐにスマートフォンを伏せて、部屋の窓を、少しだけ開けてみてください。
頬をなでる風の感触や、遠くで聞こえる電車の音に、意識を向ける。
派手さはないけれど、確かに「今、ここにある心地よさ」を、ただ静かに、深く味わうのです。
【うまくいかなくても、大丈夫】
物欲が湧くのは、ごく自然な感情。
それを無理に消そうとする必要なんてありません。
「欲しいなぁ」という気持ちを、うんうん、と認めつつ、「でも、それがなくても、今の私は十分に満たされているな」と、心の中で、そっと付け加えてみる。
それだけで、心の天秤は、少しずつ、平穏の方へと傾いていきます。
アリストテレスの哲学「結果」ではなく「プロセス」が輝き出す“幸福論”
「目標を達成することこそ、全てだ」
「失敗した人生なんて、無価値だ」
私たちは、知らず知らずのうちに、そんな結果至上主義に、心を蝕まれてしまいがちです。
でも、その考え方は、日々の挑戦をためらわせ、仕事や学びを、単なる「苦行」に変えてしまいますよね。
ここで、三つ目の道具。
哲学の巨人アリストテレスが教えてくれる、幸福観そのものを、ガラリとひっくり返すような視点です。
彼は、幸福(エウダイモニア)を、ゴールした瞬間の感情や状態ではなく、「活動」そのものだと考えました。
もっと言うと、
「自分の持つ優れた能力や美徳を、生き生きと発揮している活動」のこと。
そう!
これ!
つまり、
幸福を「山頂からの、あの絶景(結果)」だけでなく、一歩一歩、自分の足で風景を味わい、呼吸を整え、時には困難な岩場を乗り越えていく、あの登山そのもの(プロセス)にこそ、幸福の本質がある、と。
アリストテレスは、そう教えてくれているのです。
【例えば、こう使う!】
仕事で思うような成果が出ず、無力感で、肩が「がっくり」落ちた時。
「結果は、ダメだったかもしれない。」
「でも、このプロジェクトを通じて『粘り強く調べ抜く力』を発揮できたじゃないか」
「難しい交渉の中で、最後まで『誠実さ』を、自分は貫けたじゃないか」
というように。
結果と、自分自身の価値を、ちゃんと切り離して、プロセスの中にあった輝きを、見つけてあげるのです。
【うまくいかなくても、大丈夫】
毎日、自分の能力を100%フルパワーで発揮するなんて、不可能。
大切なのは、「今日の仕事で、自分の強みを、ほんの1%でも使えたかな?」と、少しだけ意識を向けてみること。
その小さな自己認識の積み重ねが、結果に一喜一憂しない、どっしりとした、安定した充実感へと繋がっていきますから。
【この章のポイント】
悩みを「コントロールできること」と「できないこと」に分け、できることに、そっと集中しましょう。(ストア派)
「ないもの」を追いかけるのを少し休んで、「すでにあるもの」に目を向け、心の平穏を大切にしましょう。(エピクロス)
「結果」だけじゃなく、自分の能力を発揮している「プロセス」そのものにこそ、幸福はあるのです。(アリストテレス)
【第2部:探求】ぼんやりした本心を探る。自分だけの「心の指針」を見つける3つの対話法
社会という名の「外」からの、あの、ざわざわしたノイズが、少しだけ静かになったところで。
今度は、あなた自身の「内」なる声に、じっくりと、耳を澄ませてみましょうか。
他人の物差しじゃなく、自分の物差し。
これからのあなたの人生を、ちゃんと支えてくれる、あなただけの「心の指針」を見つけ出すための、三つの、自分との対話の時間です。
ソクラテスの問答法「なぜ?」を繰り返し、自分の本当の願いを“発掘”する
「もっとお金が欲しいなぁ」
「キャリアアップしたいな」
「自由な時間が欲しい…」
私たちは、いろいろなことを望んでいるようで、その実、自分が「本当に、心の底から」何を望んでいるのかを、案外知らないもの。
ここで一つ目の道具は、哲学の祖ソクラテスが使っていた
「問答法(もんどうほう)」です。
やり方は、びっくりするくらいシンプル。
自分の心に、ぽっかり浮かんだ願望に対して、「それって、なんで?」と、まるで小さな子どものように、何度も、何度も、問いを重ねていくだけ。
彼の「自分は、何も知らないんだよ(無知の知)」という、あの謙虚な姿勢を真似て、自分の心を探求してみましょう。
例えばね。
多くの人が感じる「もっと自由な時間が欲しい」という願いを、一緒に、ちょっと掘り下げてみませんか?
-
問1 なぜ、自由な時間が欲しいのですか?
-
答え1 うーん…好きなことをして、のんびり過ごしたいから、かな。
-
-
問2 なぜ、好きなことをしてのんびり過ごしたいのですか?
-
答え2 そうすれば、心が満たされるって、感じるから。
-
-
問3 なぜ、心が満たされたいのですか?
-
答え3 普段、仕事とか、やるべきことに追われて、なんだか心が、すり減ってる感じがするから…。
-
-
問4 なぜ、心がすり減ってしまうのですか?
-
答え4 いつも、周りの人の期待に応えようって、気を張り詰めてるから、かもしれないな。
-
-
問5 なぜ、周りの期待に応えようとするのですか?
-
答え5 …そうしないと、自分の価値を、認めてもらえないような気が、するから。
-
どうでしょうか。
「自由な時間が欲しい」という、表面的な願いの、ずーっと奥底に。
「他人の評価に左右されずに、ありのままの自分の価値を、ちゃんと自分で認めたい」
という、より深く、切実な、魂の叫びみたいなものが眠っていたことに、気づきます。
そう、これ!
これが、あなたの「心の指針」の、とても大切な一部分なのです。
【実践ワークシート あなたの願いを発掘する「なぜなぜ5回」】
ぜひ、あなたも試してみてください。
答えに詰まっても、大丈夫。
それが、今のあなたの心です。
あなたが今、漠然と望んでいることは、何ですか?
答え:______________________
↓ なぜ?
答え:______________________
↓ なぜ?
答え:______________________
↓ なぜ?
答え:______________________
↓ なぜ?
【あなたが、本当に求めているもの】:______________________
ニーチェの永劫回帰 「この人生を繰り返したいか?」究極の思考実験
人生は、選択の連続です。
「あっちの道と、こっちの道…どっちを選ぶべきなんだろう」
後悔を恐れるあまり、動けなくなってしまうことも、ありますよね。
そんな時、あなたの本心を、容赦なく、的確に炙り出す、二つ目の道具があります。
哲学者ニーチェが提唱した、
「永劫回帰(えいごうかいき)」
という、少し風変わりで、でも、とてつもなく強力な思考実験です。
少しだけ、目を閉じて、想像してみてください。
ある日、悪魔があなたの元に、すっと現れて、こう告げます。
「お前の今のこの人生。その最高の喜びも、そして、あの耐え難いほどの苦しみも、何もかも全てを、全く同じ順序で、無限に、永遠に、繰り返すことになるのだ」と。
…さあ、この運命を前にして、あなたはどう感じるでしょうか。
絶望して、その場に崩れ落ちるでしょうか。
それとも、「それこそが、我が望みだ!」と、悪魔に向かって叫ぶでしょうか。
この思考実験の目的は、
「この選択をした自分の人生を、心の底から肯定して、何度でも、何度でも、引き受けられるか?」
と、自分の魂に、問い質すことにあります。
もし、「これを無限に繰り返すのは、もう、ごめんだ」と、心が悲鳴をあげるなら。
その選択は、世間体や、一時的な快楽に、ただ流されているだけなのかもしれません。
逆に、「この苦しみさえも、この人生に不可欠な一部として、何度でも受け入れよう」と、腹の底から思えるなら。
それこそが、あなたの「心の指針」が、確かに指し示す、本当に進むべき道なのです。
これは、転職や結婚といった大きな決断だけでなく、「なんだか退屈だな」と感じる、今日一日をどう生きるか、という問いにも繋がります。
「この何気ない一日も、もう一度、何度でも繰り返したいと思えるほど、深く、愛おしく、味わい尽くせないだろうか?」と。
【実践ワーク】あなたの「心の指針」発見チャート
最後の道具は、ここまでのような深い思索が、少し苦手だな、と感じる方でも、ゲーム感覚で、楽しく取り組めるツールです。
あなたの、あの、ぼんやりとした本心を「見える化」して、客観的に、そっと眺めてみましょう。
やり方は、とても簡単。
STEP1
まず、下のリストの中から、あなたが「これは、自分の人生にとって、絶対に譲れないなぁ」と感じる言葉を、あまり深く考えずに、直感で、5つ選んでみてください。
| □ 自由 | □ 安定 | □ 成長 | □ 貢献 |
| □ 家族 | □ 健康 | □ 冒険 | □ 創造 |
| □ 誠実 | □ 知性 | □ 富 | □ 権力 |
| □ 平穏 | □ 刺激 | □ 友情 | □ 美 |
| □ 伝統 | □ 革新 | □ 秩序 | □ 情熱 |
STEP2
次に、選び出した5つの言葉に、あなたの中で、最も大切なものから1位から5位まで、順位をつけてみましょう。
1位:________________
2位:________________
3位:________________
4位:________________
5位:________________
さて、いかがでしたか。
このトップ5が、現時点での、あなたの「心の指針」です。
これに、正解も不正解もありません。
これが、今のあなたにとっての「真実」なのです。
一度、このランキングと、現在のあなたの「時間の使い方」や「お金の使い方」を、ぼんやりと比べてみてください。
もし、そこに大きなズレがあるとしたら、それこそがあなたの感じている、あのモヤモヤの正体なのかもしれませんね。
ちなみに、この価値観ランキングは、あなたの成長や環境の変化とともに、少しずつ変わっていきます。
だから、ぜひ、半年に一度くらい、自分の心と対話する良いきっかけとして、このワークを試してみてくださいね。
【この章のポイント】
自分の願望に「なぜ?」を繰り返すことで、奥に隠された、本当の願いが見えてきます。(ソクラテス)
「この人生を、無限に繰り返したいか?」と問うことで、自分の選択が、魂に沿っているかを確認できます。(ニーチェ)
価値観リストを使って、自分の「心の指針」を、客観的に、そっと見える化してみましょう。
【深掘り分析】幸福に優劣はない。自分だけの「幸せのポートフォリオ」を構築する技術
さて、ここまでの探求で、あなたは自分だけの「心の指針」という、とても大切なコンパスを手に入れましたね。
この章では、少しだけ視点を空高く上げて、より戦略的に、あなたの人生全体の幸福をデザインしていくための、応用の思考法をご紹介します。
これは、他のどこにも書かれていない、この記事だけの、ちょっと特別な視点かもしれません。
あなたはどの配分?幸福の3タイプ「達成」「平穏」「超越」を知る
一言で「幸せ」と言っても、その中身は、実に様々ですよね。
険しい山を登りきった時の、あの「やった!」っていう喜びもあれば、麓の陽だまりで、静かに本を読む時の、あの「ふぅ…」っていう喜びもあるように。
これまでの哲学者の考え方をヒントに、ここでは幸福を、シンプルに3つのタイプに分けて、整理してみましょうか。
| 幸福のタイプ | こんな感じ | キーワード |
| ① 達成の幸福 | ゲームでレベルアップする時の、あの高揚感。できなかったことができるようになる喜び。 | 成長、成功、自己実現 |
| ② 平穏の幸福 | 猫が日向ぼっこしている時の、あの安心感。嵐が過ぎ去った後の、静かな朝のような穏やかさ。 | 安心、健康、調和、感謝 |
| ③ 超越の幸福 | 映画の主人公が、最大の挫折を乗り越えて、より強く、優しくなっていく、あの感動。 | 挑戦、克己、変容 |
いかがでしょうか。
今のあなたは、この3つのうち、どの幸福を、最も強く求めていると感じますか?
ちなみに私は2番。平穏の幸福。
あるいは、どの幸福が、今の自分には、一番欠けているなぁ、と感じるでしょうか。
ここで、大切なのは、「どれが一番優れている」という話ではない、ということです。
むしろ、これらは資産運用における「株式」や「債券」みたいなもの。
これらを、どういうバランスで組み合わせ、自分だけの「幸せのポートフォリオ」を構築していくか。
その視点こそが、これからのあなたの人生を、より深く、豊かにしてくれるのです。
【独自視点】人生のステージで最適解は変わる。20代と40代の幸福戦略
では、そのポートフォリオの最適な配分は、一生ずっと同じなのでしょうか。
…そんなこと、ありませんよね。
私たちの人生のステージによって、求める幸福の形は、まるで生き物のように、しなやかに変化していきます。
-
20代〜30代前半(キャリア形成期)
スキルアップや自己実現を目指す「達成の幸福」の比重が、ぐんぐん高まりがちな時期。それは、本当に素晴らしいこと。
でも、それだけに偏ると、心が「ぷつん」と燃え尽きてしまうことも。
意識的に「平穏の幸福」(趣味や、友人との、どうでもいい話で笑う時間)を組み込むことが、長く、楽しく走り続けるための秘訣になります。
-
30代後半〜40代(安定・成熟期)
家庭や社会的な責任が増してきて、穏やかな日常を守る「平穏の幸福」の価値が、じんわりと、でも確かに高まってくる時期かもしれません。一方で、日常のマンネリ化を防ぐために、新しい学びや、今までやったことのない役割への挑戦、といった「超越の幸福」を、スパイスのように少しだけ加えることが、人生の彩りを保つ鍵になります。
-
50代以降(統合期)
これまでの人生経験を振り返り、乗り越えてきた困難に、深い意味を見出す「超越の幸福」や、穏やかな日常を、ただただ愛おしむ「平穏の幸福」の重要性が、より増してくるかもしれませんね。
大切なのは、これが正解だ、と決めつけることじゃありません。
「今の自分は、どんなバランスを求めているんだろう?」と、定期的に自分のポートフォリオを、そっと見直し、今の自分にとって、一番心地よい配分へと、意識的に「リバランス(再調整)」していく。
その主体的な姿勢そのものが、豊かな人生に繋がっていくのです。
要注意!「この幸せだけ」に偏る危険性とは?燃え尽きと停滞のサイン
「バランスが重要ですよ」とは言っても、私たちは、つい、一つの価値観に偏りがちです。
その先に、どんな落とし穴が待っているのか、少しだけ知っておくことも、きっと、あなたの役に立つはずです。
-
「達成」に偏りすぎると…
-
危険性 燃え尽き症候群(バーンアウト)、成功への依存、人間関係の軽視、敗北への極端な恐怖。
-
心のサイン 「休むことに、なぜか罪悪感がある」「勝つこと以外に、価値を感じられない」
-
-
「平穏」に偏りすぎると…
-
危険性 挑戦を避けることによる停滞、成長の機会損失、変化への対応力の低下、退屈。
-
心のサイン 「面倒なことは、なるべく避けたい」「最近、心が動くような出来事がないなぁ」
-
-
「超越」に偏りすぎると…
-
危険性 不必要な苦労の美化(苦労ジャンキー)、過度な自己犠牲、現実離れした理想主義。
-
心のサイン 「楽をしてるのは、なんだか悪いことだ」「もっと苦労しないと、成長できない」
-
実は、現代のポジティブ心理学でも「PERMAモデル」という理論で、
幸福が
「ポジティブ感情」
「没頭」
「良好な人間関係」
「意味・意義」
「達成感」
といった、多様な要素から成り立っていることが示されています。
哲学者の、あの深い直感と、現代科学の知見が、ここで見事に、ぴたりと一致しているのは、とても興味深いことですよね。
もし、あなたが何かに偏っている、と感じても、どうか自分を責めないでください。
それは、あなたが今、何かを一生懸命に頑張っている、素晴らしい証拠でもあるのですから。
問題なのは、その偏りに「無自覚でいること」。
このポートフォリオという視点を持って、客観的に、今の自分を「ふむふむ」と眺めてみること。
それだけで、あなたはもう、より賢明な人生の舵取りができるようになっているはずです。
【この章のポイント】
幸福には、大きく分けて「達成」「平穏」「超越」の3タイプがあり、どれも等しく大切です。
これらを資産運用のように組み合わせる「幸せのポートフォリオ」という視点を、持ってみましょう。
人生のステージに合わせて、ポートフォリオの配分を、意識的に「リバランス」していくことが、とても重要です。
【第3部:実践】日常は宝物になる。ありふれた日々に「豊かさ」を発見する心のトレーニング
ここまでの探求で、あなたの頭の中は、新しい考え方や視点で、きっといっぱいになっていることでしょう。
ここからは、少しだけ、趣向を変えて。
その思考を、あなたの五感や身体にまで、じんわりと落とし込んでいく、具体的な心のトレーニングの時間です。
幸せを、どこか遠くに「探す」のをやめて、「今、ここ」にある日常を、深く、深く、「味わう」ための。
誰にでもできる、簡単なレッスンを、一緒に始めましょうか。
いつもの日常が輝き出す現象学の思考法「エポケー(判断中止)」
「毎日、同じことの繰り返しで、なんだか世界が、色褪せて見える…」
いつからか、私たちは日常を「自動運転」で、ただやり過ごすようになってしまいました。
通勤の道のりも、毎朝のコーヒーの味も、ほとんど意識にのぼることなんて、ありませんよね。
そんな、マンネリ化した日常に、鮮やかな色彩を取り戻すための、ちょっと変わった道具があります。
それが、哲学者フッサールが提唱した「エポケー(判断中止)」です。
難しそうな名前ですけど、やることは、たった一つ。
それは、
「これは、いつもの〇〇だ」っていう、心の中の“ラベル貼り”を、一旦、やめてみること。
例えばね。
毎朝、なんとなく口にしている、あの一杯のコーヒーでこのトレーニングを試してみましょう。
-
STEP1 まず、「これは、いつもの苦いコーヒーだ」という、頭の中の思考や判断を、心の中で、そっと横に置きます。
-
STEP2 そして、まるで、生まれて初めてコーヒーという液体に出会ったかのように、五感をぜんぶ使って、それを「体験」してみるのです。
| 五感 | こんなふうに、味わってみる |
| 視覚 | 湯気が、ゆらゆらと立ち上る様子は?カップの中の黒色は、どんな深みがある?光は、どう「きらり」と反射している? |
| 嗅覚 | 鼻を近づけてみる。香ばしさ、酸味、甘さ…どんな香りが、ふわっと、複雑に混じり合っている? |
| 触覚 | カップから、手のひらに伝わる、じんわりとした温かさは?陶器の、つるりとした感触は? |
| 味覚 | 一口含んで、すぐに飲み込まず、舌の上で、ころがしてみる。苦味、酸味、コク、そして後味は、どう変化していく? |
どうでしょうか。
「いつものコーヒー」という、たった一枚のラベルを剥がしてみるだけで、そこには、驚くほど豊かで、複雑な世界が、広がっていたことに気づくはずです。
この「心のラベル剥がし」は、コーヒーだけじゃありません。
通勤途中の、道端に咲く小さな花、いつも聞いている音楽、家族の、ふとした表情。
あらゆるものに応用できます。
「知っているつもり」になって、見過ごしていた世界のディテールに、ふと気づき始めた時。
あなたの、あの退屈だった日常は、無限の発見に満ちた、宝物の山へと、変わっていくでしょう。
1分で思考の暴走を止める。禅に学ぶ「マインドフルネス」入門
ベッドに入っても、頭の中は、終わらなかった仕事の反省会や、明日の会議への心配事で、ぐるぐる、ぐるぐる…。
私たちの心って、本当に、しょっちゅう「過去」や「未来」に飛んでいって、「今、この瞬間」に、いてくれませんよね。
この“心の不在”こそが、私たちの不安やストレスの、大きな原因になっているのです。
そんな、思考にハイジャックされた心を取り戻すための、とても強力なトレーニングが、禅の思想などをルーツに持つ「マインドフルネス」です。
これはね、よく誤解されがちですが、「無になろう」と、頑張ることじゃないんです。
そうじゃなくて、
思考の暴走に「あ、またやってるな」と“気づいて”あげて、意識を「今、ここ」に、優しく、そっと連れ戻してあげる、心の筋力トレーニングみたいなもの。
一番簡単な「1分間呼吸法」を試してみましょう。
-
椅子に座るか、楽な姿勢で立って、軽く背筋を伸ばします。
-
そっと目を閉じて、自分の意識を、ただ「鼻先」にだけ、集中させます。
-
空気が、鼻を「すーっ」と通り、体に入ってくる感覚と、体から「ふーっ」と出ていく感覚を、ただ静かに、実況中継するように、観察します。
-
きっと、すぐに別の考えが、ぽっかり浮かんできます。「今日の夕飯、どうしようかな…」とか。それが、ごく普通。その時が、一番のポイントです。その考え事を「ダメだ!」と追い払うんじゃなくて、「あ、今、考え事をしていたな」と、ただ優しく、気づいてあげるのです。
-
そして、また、そっと、意識を鼻先の呼吸の感覚へと、戻してあげます。
そう!
この「逸れる→気づく→戻す」の繰り返しこそが、マインドフルネスの本質なんです。
思考の暴走に、ただ気づけるだけで、あなたはもう、思考の「奴隷」から、思考の「観察者」へと、変わることができるのですから。
もし、不安で頭がいっぱいになってしまった時の緊急避難テクニックとしては、
「今、自分の周りにある『青いもの』を3つ探す」とか、
「今、聞こえている音を2つ、心の中で挙げてみる」といった、五感を使うワークも、びっくりするくらい効果的ですよ。
【この章のポイント】
日常の物事への「いつもの〇〇だ」というラベル貼りをやめて、五感で、じっくり再体験してみましょう。(エポケー)
思考の暴走に「あ、またやってるな」と気づき、意識を「今、この瞬間」の呼吸や感覚に、優しく戻す練習をしてみましょう。(マインドフルネス)
幸せは、どこか遠くに探すものではなく、「今、ここ」にある日常の中に「発見」し、「味わう」ものです。
【応用編】「自分だけの幸せ」から「誰かと分かち合う豊かさ」へ
ここまでの道のりで、あなたは、自分だけの「心の指針」という、かけがえのないコンパスを手に入れましたね。
そして、日常を深く味わうための、心のトレーニングも、積んできました。
それは、何物にも代えがたい、あなただけの、大切な財産です。
…でも、もし。
その財産を、自分一人だけで、ずーっと抱えているとしたら…。
この最後の章では、あなたの視点を「私」という個人から、「私たち」へと広げて、より深く、より持続可能な幸福の扉を、一緒に開いていきましょう。
【ハーバード大学の研究】幸福な人生の最大の秘訣は「良い人間関係」だった
少しだけ、想像してみてください。
もし、あなたが自分にとっての幸せを、完璧に見つけ出したとして。
無人島で、たった一人、それを満喫しているとしたら。
その幸せは、どれほどの意味を、持つのでしょうか。
「それはそれで悪くはない。」って思う人も当然いるでしょう。いて当然です。
でも…なんかね。
私たちは、一人では、本当に満たされることができないようにできているのかもしれません。
そして、そのことを、哲学だけじゃなく、現代の科学もまた、極めて強力な証拠をもって、私たちに示してくれています。
アメリカのハーバード大学に、「グラント・スタディ」という、とても有名な研究があります。
これは、724人の男性の人生を、彼らがまだ青年だった頃から、老年期に至るまで、75年以上、今もなお続く、おそらく史上最も長期にわたる幸福の研究です。
研究者たちは、彼らの仕事、家庭生活、健康状態など、人生のあらゆるデータを集め続け、たった一つの問いの答えを、探し続けました。
「一体、何が、人を幸福で、健康にするのか?」と。
富でしょうか。
名声でしょうか。
それとも、身を粉にして働くことでしょうか。
75年という、途方もない歳月を経て、この研究が導き出した答えは、驚くほどシンプルで、ただ一つでした。
研究の4代目責任者であるロバート・ウォールディンガー教授は、ある有名な講演で、こう語っています。
「私たちを幸福で、健康にするものは、富でも、名声でも、懸命に働くことですら、ありませんでした。それは、『良い人間関係』です。…これに、尽きるのです」
研究によれば、50歳の時点で、人間関係に最も満足していた人々が、80歳になった時に、最も健康だったそうです。
大切なのは、友人の「数」ではなく、関係の「質」であることも、分かっています。
哲学が、私たちに自分自身の内面を、深く、深く見つめるよう促すとすれば、科学は私たちに「外」、つまり他者とのあの温かい繋がりへと、目を向けるよう力強く、示しているのです。
アドラー心理学が教える究極の幸福「共同体感覚」とは?
では、「良い人間関係」とは、具体的に、どのような心の状態を指すのでしょうか。
そのヒントをくれるのが、
「嫌われる勇気」で一躍有名になった、アルフレッド・アドラーの心理学です。
彼は
「人間のあらゆる悩みは、対人関係の悩みである」
と、ばっさりと断言し、その解決策、そして、幸福のゴールとして「共同体感覚」という考え方を、提唱しました。
うん、なんだか難しそうに聞こえますよね。
でも、大丈夫。
分解してみると、とても自然で、温かい心のあり方なんです。
-
① 自己受容
-
まずは、「ありのままの自分」を、良い点も、ちょっとダメな点も含めて、100点満点として、まるっと受け入れること。そう!これは、私たちが第2部で探求してきた「心の指針」を見つけるプロセス、そのものです。
-
-
② 他者信頼
-
次に、他者を、自分と競争する「敵」ではなく、共に歩む「仲間」だと、無条件に、信じてみること。裏切られる可能性を恐れるんじゃなくて、まず、こちらから、そっと信じる勇気を持つことです。
-
-
③ 他者貢献
-
そして最後に、その「仲間のために、自分は、何ができるだろうか?」と考え、貢献している、という“主観的な感覚”を持つこと。
-
アドラーは、人は、この「他者貢献感」を持てた時にのみ、自らの価値を、じんわりと実感し、対人関係の悩みから解放され、深い幸福を感じることができる、と考えました。
つまり、
幸福とは、誰かから「もらう」ものではなくて、他者に、何かを「与える」ことで、結果として、自分の心が、ぽかぽかと満たされていく、
という、逆転の発想なのです。
ここで、とても大切なのは、貢献とは、自己犠牲のことじゃない、ということです。
客観的に見て「すごいこと」をする必要も、全くありません。
重要なのは、ただ「自分は、誰かの役に立っているなぁ」と、主観的に、あなたが感じられること。
それだけで、私たちの心は、ちゃんと満たされるように、できているのです。
今日からできる、小さな「貢献」のはじめ方リスト
「貢献」なんて言われると、なんだか、すごく大げさに聞こえてしまいますよね。
でも、本当に、大丈夫。
世界を変えるような、大それたことである必要は、全くありませんから。
あなたの日常には、小さな「貢献」の機会が、きらきらした宝物のように、たくさん散らばっています。
-
コンビニの店員さんに、いつもより少しだけ、丁寧な声で「ありがとうございます」と、伝えてみる。
-
家族やパートナーの話を、スマートフォンを置いて、ただ静かに、うんうん、と最後まで聞いてみる。
-
同僚が、なんだか忙しそうにしていたら、「何か、手伝えること、ありますか?」と、そっと一声かけてみる。
-
SNSで、誰かの批判的な意見に反応する代わりに、素敵な投稿に、心からの「いいね!」や、肯定的なコメントを送ってみる。
-
電車の中で、周りを、ふと見渡し、席を必要としていそうな人に、すっと立って、譲ってみる。
-
誰も見ていなくても、会社の給湯室や、マンションの共有スペースを、ほんの少しだけ、綺麗にしてみる。
これらの行動のポイントは、「見返りを、求めないこと」。
ただ、あなたの心からの「与えたい」という、ささやかな気持ちに従って、行動を起こしてみる。
その行動自体が、驚くほどあなたの心を温かく満たしてくれることに、きっと気づくはずです。
まるで「幸せの貯金」みたい。
一つ一つの行動は、小さくても、それは確実に、あなたの心に、温かい幸福感を、こつこつと積み立てていきます。
そして、気づいた頃には、あなたの周りの世界も、以前より、ほんの少しだけ、優しいものに、変わって見えるかもしれませんよ。
【この章のポイント】
科学的な研究によれば、人生における幸福の、最大の決定要因は「良い人間関係」です。
幸福とは「他者に貢献しているなぁ」という、主観的な感覚を持つことで、深く、じんわりと実感できます。(アドラー心理学)
日常の中の、ささやかな「小さな貢献」を意識することが、自分と、あなたの周りの世界を、豊かにしていきます。
まとめ 哲学は幸せの「地図」ではない。自分だけの道を歩むための「コンパス」だ

社会が作った「幸せのテンプレート」という、あの、幻の地図をまず手放すことから始めましたね。
そして、ストア派やアリストテレスといった、古代の賢い人たちから、心を自由にするための「思考の道具」を、一つ、また一つと、受け取りました。
次に、ソクラテスやニーチェに導かれ、自分自身の心の、ずーっと奥深くへと潜っていき、「心の指針」という自分だけのコンパスを、見つけ出しました。
そのコンパスを手に、ありふれた日常に隠された豊かさを、深く味わうための「心のトレーニング」を積み、最後にはその道が、他者という温かい光へと繋がり、共に歩む喜びこそが究極の幸福であることも知りました。
…この記事が、あなたに、本当に渡したかったもの。
それは、どこかに隠された宝の場所を示す「幸せの地図」では、ありません。
なぜなら、そんな、万人共通の宝の地図なんて、世界のどこにも、存在しないからです。
私たちが手に入れたのは、もっと、ずっと素晴らしいもの。
それは、どんな道なき道を進む時も、嵐の中で方角を見失いそうになった時も、常に「あなたにとっての幸せ」を、静かに、でも確かに、指し示してくれる。
あなただけの「心の指針(コンパス)」です。
地図を頼りにする歩みは、ゴールに辿り着くことだけが、目的になってしまいます。
でも、コンパスを持つ人の歩みは、違います。
道中の、名もなき花に心を動かされ、心惹かれる脇道に、ふらりと逸れることを楽しみ、時には道に迷うことさえも自分だけのかけがえのない経験として、まるごと肯定することができる。
そう。
幸せとは、どこかにあるゴールに、辿り着くことではありません。
自分だけのコンパスを手に、自分らしい道のりを、一歩、また一歩と、深く、愛おしく味わいながら、ただ歩んでいく。そのプロセス、そのものなのです。
もうあなたは、誰かの価値観に心を揺さぶられる必要はありません。
焦る必要も、他人をむやみに羨む必要も、ありません。
あなたの手には、もう、確かなコンパスがありますから。
もし、これから先、少しでも迷うことがあったなら。
どうか、一度ふぅっと息を吐いて、立ち止まってみてください。
そして、その針が指し示すあなたの心のあの静かな声に、そっと耳を澄ませてみてくださいね。
完璧な道のりなんて、ありません。
どうか、間違うことを恐れずに。
あなたらしい、世界でたった一つの探求を心から楽しんでください。
…さて。
もし、よろしければこの記事を閉じたら、まずスマートフォンをそっと机に置いてみませんか。
そして、窓の外の空の色をただ30秒だけ何も考えずに、ぼーっと眺めてみる。
雲は、どんな形でどんな風に流れているでしょう。
それが、あなたの新しい探求の静かで美しい、始まりの合図です。
【こちらの記事も読まれています】

【この記事のポイント】
幸せとは、誰かが作った「地図」を見て目指すゴールではなく、自分だけの「コンパス(心の指針)」を頼りに歩む、プロセスそのものです。
哲学とは、そのコンパスを手に入れ、使いこなすための、一生使える、実践的な「思考の道具」です。
自分を知り、世界を深く味わい、そして誰かと繋がること。その探求の全てが、あなたの人生を、豊かにしてくれます。
【さいごに】
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
このブログでは、今回のような哲学的な視点だけでなく、心理学や様々な考え方をもとに、「豊かさや、幸せになる方法」について、日々研究し、発信しています。もし、もう少しだけ、心の探求を続けてみたいと感じたら、ぜひ、他の記事も覗いてみてください。あなたの日常が、昨日より少しだけ、豊かになるヒントが、見つかるかもしれません。
【参考文献リスト】
【哲学】
ストア派の思想
エピクテトス『エンケイリディオン』(日本語訳:鹿野 忠義 訳、岩波文庫など)
マルクス・アウレリウス『自省録』(日本語訳:神谷 美恵子 訳、岩波文庫など)
セネカ『幸福な人生について』(日本語訳:茂手木 元蔵 訳、岩波文庫など)
エピクロス主義
エピクロス『主要教説』
アリストテレスの幸福論
アリストテレス『ニコマコス倫理学』(日本語訳:高田 三郎 訳、岩波文庫など)
ニーチェの永劫回帰
フリードリヒ・ニーチェ『悦ばしき知恵』(日本語訳:手塚 富雄 訳、岩波文庫など)
アドラー心理学
アルフレッド・アドラー『個人心理学講義』(日本語訳:岸見 一郎 訳、アルテなど)
アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学』(日本語訳:岸見 一郎 訳、ベストセラーズなど)
【心理学・科学】
ヘドニック・トレッドミル
フィリップ・ブリックマン, ダニエル・T.キャンベル『Hedonic Relativism and Planning the Good Society』(1971年)
グラント・スタディ(ハーバード成人発達研究)
ロバート・ウォールディンガー, マーク・シュルツ『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』(日本語訳:児島 修 訳、辰巳出版)
PERMAモデル
マーティン・セリグマン『ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”と“楽観主義”のサイエンス』(日本語訳:小林 裕子 訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)